
「夜中に汗びっしょりで目が覚める…」「更年期の始まりなのかな?」と不安になる方は少なくありません。寝汗は更年期の典型的な症状のひとつですが、生活習慣やストレス、病気が関わっている場合もあります。
本記事では、更年期による寝汗の特徴や見極めポイントをわかりやすく解説し、日常でできる対策から市販薬・漢方の活用方法、受診の目安まで幅広くご紹介します。つらい寝汗を少しでもラクにしたい方は、ぜひ参考にしてください。
「寝汗がひどい…」と感じたら、更年期の可能性も
夜中にパジャマやシーツがぐっしょり濡れるほどの寝汗…。
「風邪でもないのに、どうして?」と不安になる方も多いはずです。実は、更年期の時期には寝汗が増えることがよくあります。
更年期とは、女性ホルモンの分泌が急激に変化する時期のこと。このホルモンバランスの乱れが、体温調整や自律神経の働きに影響し、寝ている間にも汗が大量に出てしまうのです。
寝汗が毎晩続く場合や、日常生活に支障をきたすほど辛いときは、更年期による症状の一つと考えてみましょう。
更年期に寝汗が増えるのはなぜ?
更年期の女性は、卵巣機能の低下により エストロゲン(女性ホルモン) が大きく減少します。
エストロゲンは体温を安定させる役割を持っているため、分泌が少なくなると体温調節がうまくいかなくなり、寝ている間でも突然「カーッ」とのぼせたり、急に汗が噴き出たりすることがあります。
特に夜は体が休息モードに入るため、自律神経のバランスが乱れやすく、結果として「寝汗」として現れるのです。
対策のポイント
-
就寝前はカフェインやアルコールを控える(体温が乱れやすい)
-
寝室を涼しく保ち、通気性の良い寝具を使う
-
寝る前に深呼吸やストレッチをしてリラックスする
ホルモンバランスの変化と自律神経の関係
更年期の寝汗を語るうえで外せないのが、 ホルモンと自律神経の密接な関係 です。
エストロゲンが減少すると、自律神経(交感神経と副交感神経)の切り替えがスムーズにいかなくなります。
その結果、体温を下げるはずのタイミングで交感神経が優位になり、余計に汗が出てしまうのです。
さらにストレスや不眠が重なると、自律神経の乱れは悪化し、寝汗がひどくなる悪循環に…。
自律神経を整えるセルフケア
-
規則正しい生活(就寝・起床時間を揃える)
-
軽い有酸素運動(ウォーキング・ヨガなど)で血流改善
-
ぬるめのお風呂でリラックス(副交感神経を優位にする)
-
必要に応じて婦人科でのホルモン補充療法(HRT)や漢方相談
「寝汗がひどい=すぐ病気」とは限りませんが、更年期特有の体のサインであることは多いです。
日常の工夫とあわせて、無理せず医療機関を頼ることも安心につながります。
命の母A はこちら🔻
こんな症状があれば“更年期のサイン”かも

寝汗は更年期のサインのひとつですが、それだけで判断するのは難しいものです。
更年期には、女性ホルモンの急激な変化によって体や心にさまざまな不調が現れるため、寝汗とあわせて他の症状が出ていないか確認することが大切です。
寝汗と一緒に出やすい更年期特有の症状
更年期の寝汗と同時に現れやすい代表的な症状には、次のようなものがあります。
-
ホットフラッシュ(顔のほてり・急な発汗)
→ 日中でも突然カーッと暑くなり、大量の汗をかくことがある。 -
動悸・息切れ
→ 自律神経の乱れにより、安静時でも心臓がドキドキする。 -
不眠・眠りの浅さ
→ 夜中に何度も目が覚める、入眠しにくいなどの睡眠障害。 -
気分の落ち込み・イライラ
→ ホルモン変動による精神的な揺らぎが増える。 -
冷えとほてりの両方を感じる
→ 血流や自律神経の調整が乱れ、寒暖差をうまく調節できない。
寝汗単独よりも、こうした症状が組み合わさって出てくる場合、更年期による影響が強いと考えられます。
チェックリスト|日常生活で気づくサイン
次のチェックリストにいくつ当てはまるか確認してみましょう。
✅ 夜中に寝汗で目が覚めることが多い
✅ 顔や首に突然ほてりを感じる
✅ 以前より寝つきが悪くなった
✅ ちょっとしたことでイライラする
✅ 気分が落ち込みやすくなった
✅ 動悸やめまいを感じることがある
✅ 手足の冷えやしびれを感じやすい
✅ 以前より疲れが取れにくい
3つ以上当てはまる場合は、更年期症状の可能性が高いといえます。
自己判断で不安を抱え込むのではなく、婦人科や内科で相談すると安心です。
寝汗が出る理由は更年期以外にもある
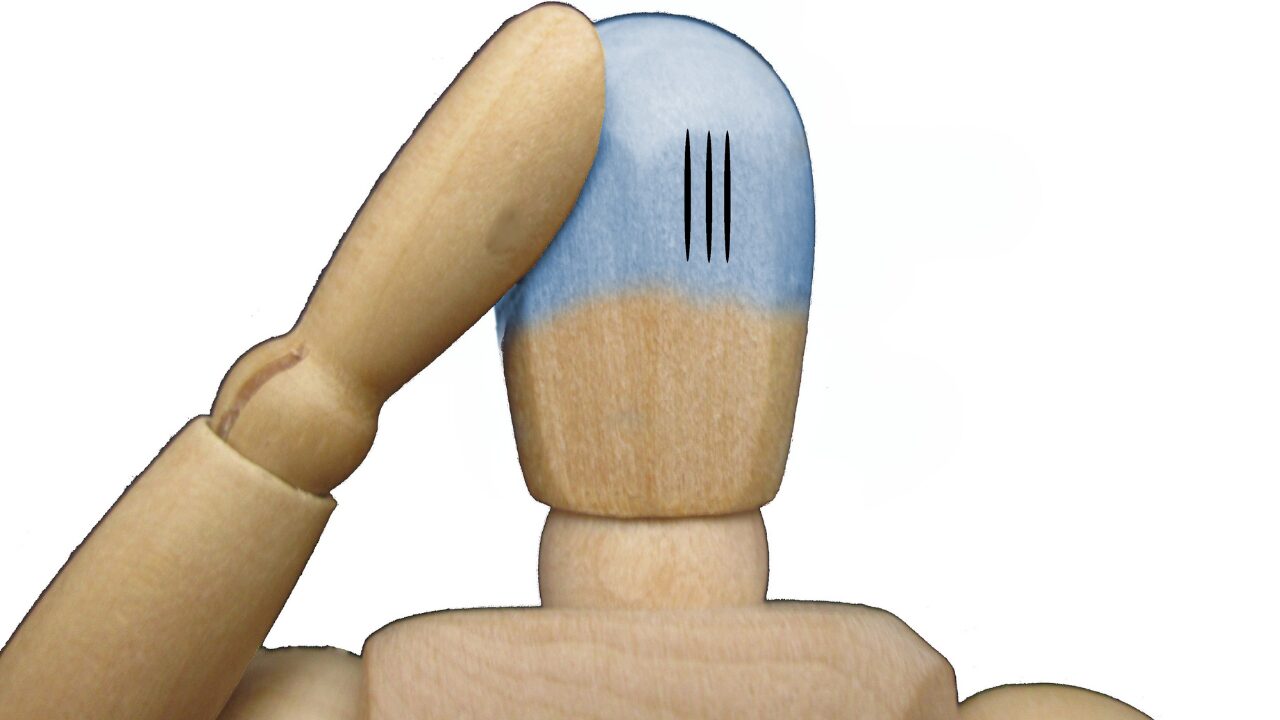
「更年期だからかな?」と思っていても、寝汗にはさまざまな原因があります。
ホルモンの影響だけでなく、生活習慣やストレス、さらには病気や薬の副作用などが関わっている場合もあります。原因を幅広く知っておくことで、適切に対処できるようになります。
生活習慣やストレスによる寝汗
-
寝室環境の影響
暑すぎる室温、厚手の布団や通気性の悪いパジャマは寝汗を増やす大きな要因です。 -
飲酒・カフェイン摂取
アルコールやコーヒーは血管を広げたり自律神経を刺激したりするため、寝ている間の発汗が増えることがあります。 -
精神的ストレス
ストレスや不安が強いと交感神経が優位になり、夜間でも汗をかきやすくなります。
👉 セルフ対策
-
室温は夏は25℃前後、冬は18℃前後を目安に調整
-
通気性の良い寝具・パジャマを選ぶ
-
就寝前の飲酒やカフェインは控える
-
深呼吸やストレッチでリラックスしてから眠る
感染症や病気が原因となるケース
寝汗が頻繁に起こるとき、体の異常が隠れている場合もあります。
-
感染症
結核やHIV、慢性の感染症では夜間に大量の寝汗が出ることがあります。 -
甲状腺の病気
甲状腺機能亢進症では代謝が過剰になり、発汗・動悸・体重減少が起こりやすくなります。 -
糖尿病や自律神経の異常
血糖値の変動や神経の乱れで寝汗が増えることも。 -
がん・悪性リンパ腫
強い寝汗とともに体重減少や発熱がある場合は、早急な受診が必要です。
👉 セルフ対策というより医療機関の受診が必須。
「寝汗が毎晩続く」「発熱・体重減少・倦怠感がある」場合は、早めに内科を受診しましょう。
市販薬・サプリの影響による寝汗
薬やサプリの副作用として寝汗が出るケースもあります。
-
抗うつ薬や精神安定剤:発汗作用が副作用として現れることがある
-
解熱鎮痛薬:発汗を促す働きがある場合がある
-
ダイエット系サプリや代謝促進サプリ:交感神経を刺激し、発汗を増やすことがある
👉 セルフ対策
-
服用中の薬の添付文書を確認する
-
気になる場合は自己判断で中止せず、必ず医師や薬剤師に相談する
ポイントまとめ
寝汗は「更年期だけ」とは限りません。
生活習慣の見直し → 改善しない → 医療機関へ相談 という流れを意識することが安心につながります。
更年期の寝汗をラクにする対処法

寝汗が更年期に起因している可能性が高いなら、原因を補いながら無理のない対策を組み合わせていくのがポイントです。以下の観点で対策を整理しました。
生活習慣の見直し(食事・睡眠・ストレスケア)
食事の工夫
-
バランス良く、体を冷やしすぎない食材中心に
夏野菜や冷たい飲み物ばかりでなく、根菜・良質なタンパク質(魚・大豆製品など)・良好な脂質(ナッツ、青魚、オリーブ油など)を意識して。 -
発汗を促す刺激物を控える
辛味・香辛料・過度のカフェイン・アルコールは寝汗を誘発しやすいため、夕方以降は控えるように。 -
水分補給を適度に
乾燥を防ぎつつ、水分過多による代謝促進までは行かないよう、常温の水や白湯を中心に。
睡眠・就寝前の習慣
-
一定の睡眠リズムを保つ
起床・就寝時間をできるだけ毎日揃えることで自律神経の安定化をはかる。 -
寝る前のリラックス習慣
ぬるめのお風呂(38〜40℃程度)、軽いストレッチ、深呼吸、アロマ(副交感神経を優位にする香りを選ぶ)など。 -
ブルーライトや強刺激の排除
就寝直前のスマホ・PC視聴は控え、穏やかな読書や穏やかな音楽などに切り替えると、交感神経のオンを下げやすくなる。
ストレスケア
-
軽い運動・有酸素運動
散歩、ヨガ、ゆったりした体操などを日中に取り入れ、自律神経のバランスを整える。 -
マインドフルネス・瞑想・呼吸法
短時間でも「今ここ」に意識を向ける時間を作ると、自律神経のゆらぎを落ち着かせやすくなる。 -
趣味・気分転換
好きなことに没頭したり、自然に触れたり、人との会話や笑いの時間を持ったりすることも重要。
寝具・寝室環境の工夫で快適に
寝汗を少しでも軽くするためには、寝具・寝室環境を整えることが直接的に効きます。
-
通気性・吸湿性に優れた寝具
綿、リネン、竹繊維(バンブー)などの素材。湿気を逃がしやすい敷布団やマットレス、パッドを重ねすぎない構成に。 -
パジャマの選び方
透けにくく、速乾性・通気性のある綿や混紡素材(例:綿+モダールなど)が望ましい。ウール混なども、湿度コントロールに向く素材であれば選択肢。 -
寝室の温湿度管理
夏は25℃前後、湿度50〜60%前後を目安。扇風機・エアコン・除湿器などを併用する。 -
空気循環を促す工夫
扇風機で壁や天井を循環させる、絨毯を減らす、カーテンを遮光かつ通気性の良いものに替えるなど。 -
枕・掛け布団の調整
枕も通気性・高さを見直して、首周りに熱や湿気がこもらないように。夏はタオルケット・ガーゼケットなどを試す。
市販薬・漢方・サプリの活用方法
更年期の寝汗対策として、補助的に市販薬・漢方・サプリを取り入れる人も多いですが、以下のポイントを押さえましょう。
選択の際の注意点
-
個々の体質・症状に合わせて選ぶ(「ほてり型」「不眠型」「神経過敏型」など)
-
他の持病・併用薬との相互作用を確認
-
継続的に使用するなら、効果と副作用をモニタリング
-
医師・薬剤師に相談してから始める
国産〜国内で流通している例(参考)
以下は日本国内で市販されている例ですが、あくまで参考例であり個人の使用可否は医療専門家と確認してください。
-
ツムラ漢方 加味逍遙散 エキス顆粒
更年期の不安感、肩こり、ほてり・のぼせなど複数の症状が混在するタイプで使われることが多い。
リンク -
クラシエ 漢方 加味逍遙散 料エキス顆粒
同じく加味逍遙散処方を含むクラシエ製品。複合的な更年期症状の改善を目的とする。
リンク -
クラシエ 漢方 桂枝茯苓丸 料エキス錠
体質に応じて使われる漢方処方のひとつ。
リンク
また、漢方の定番処方としては 加味逍遙散、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散 等が「婦人科三大処方」として挙げられ、症状や体力・体質に応じて使われています。
他、サプリ系ではホルモンに類似成分を含むものやハーブ系(ブラックコホシュ、イソフラボンなど)が市販されていますが、症状を悪化させるリスクもあるため、これらは慎重な判断が必要です。
病院を受診すべきタイミング
セルフケアを続けても改善が見られない、あるいは以下のような兆候があれば、早めに医療機関を受診することが重要です。
-
寝汗が毎晩続き、日常生活に支障をきたす
-
発熱、体重減少、倦怠感などが伴う
-
息切れ・胸痛・動悸が強く出る
-
夜間の発汗が膵臓・内分泌疾患・感染症に起因する可能性が疑われる
-
他の更年期症状(不正出血、骨粗しょう症リスク、記憶力低下など)も強く現れている
-
漢方や市販薬を開始したものの、副作用や体調悪化の疑いがある
婦人科、内科、ホルモン内分泌科などが受診先の候補になります。ホルモン補充療法(HRT)や更年期専門治療に対応している施設を選べると安心です。
まとめ|「いつもと違う寝汗」は、体からの大切なサイン

寝汗は単なる暑さや一時的なストレスだけでなく、更年期や病気のサインであることもあります。
「いつもと違う」と感じるときこそ、体が発しているメッセージに耳を傾けることが大切です。
自己判断せず、早めの相談が安心
寝汗が長引いたり、他の症状を伴ってつらさが増している場合は、自己判断で放置せずに医師へ相談しましょう。
婦人科・内科・更年期外来などで相談すれば、検査や治療、生活改善のアドバイスを受けられます。
特に更年期世代は、「年齢のせい」と思い込んで我慢してしまう方も少なくありません。
しかし、早めに相談することで「原因の特定」と「適切なケア」が可能になり、安心して日常を送れるようになります。
日常の工夫で「つらい寝汗」を和らげよう
医療のサポートと並行して、日常の工夫で寝汗の負担を減らすこともできます。
-
寝室環境を整える(温湿度管理・通気性のよい寝具)
-
食生活を見直す(カフェイン・アルコールを控え、栄養バランスを意識)
-
睡眠リズムとストレスケア(規則正しい生活・リラックス習慣を取り入れる)
-
必要に応じて市販薬や漢方を活用(医師・薬剤師に相談したうえで)
こうした小さな工夫の積み重ねが、寝汗の不快感を和らげ、心身の安定につながります。
✅ 寝汗は「不快なもの」ではありますが、見方を変えれば 体からの大切なお知らせ です。
不安なときは早めに相談し、無理なくできる工夫を取り入れながら、更年期を前向きに乗り越えていきましょう。
汗をかいても快適に眠れる寝具はこちら🔻
【快眠タイムズ】 ![]()


