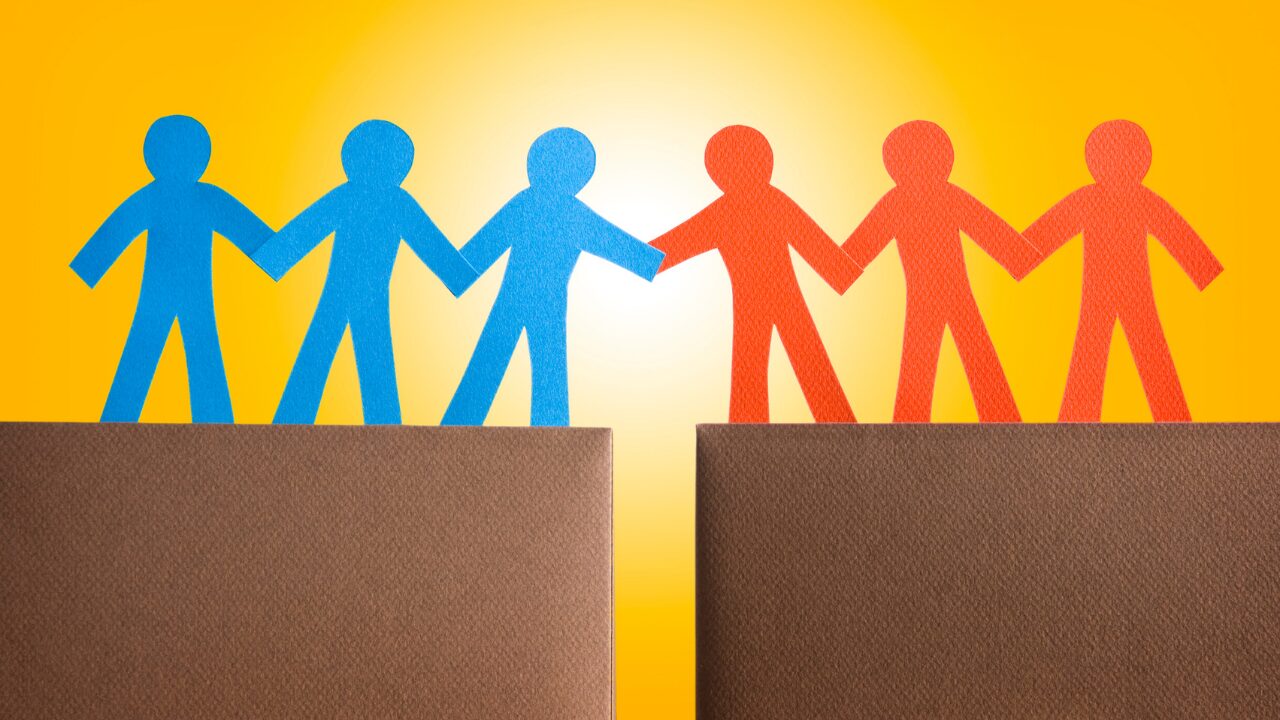
SNSや動画文化の発達によって、世界中の若者たちが日々新しい言葉を生み出しています。
英語圏で話題の「rizz」や「delulu」、日本で定着した「エモい」「チル」など──これらのスラングは、単なる流行ではなく世代の価値観やカルチャーを映す“鏡”です。
この記事では、海外と日本の若者スラングを比較しながら、その意味・使い方・背景にある文化の違いをわかりやすく解説。
「今どきの言葉がわからない…」という人も、「海外のスラングを使いこなしたい!」という人も、これを読めば“ことばのトレンド”の裏にある世界が見えてきます。
若者スラング、なぜ注目されているの?
近年、「スラング(俗語)」は単なる“流行語”を超え、時代の価値観や文化を映す鏡として注目を集めています。
特にSNSや動画配信を中心とするZ世代の間では、スラングが自己表現や共感の合図として使われることが増えています。
なぜここまで若者語が話題になるのか――その背景を3つの視点から紐解いてみましょう。
SNSと動画文化が生んだ“スラングの拡散力”
かつての流行語はテレビや雑誌が中心でしたが、今やSNSと動画文化が言葉の発信源です。
TikTokやInstagram、YouTubeなどでは、短い動画やコメント欄でスラングが次々と誕生し、ハッシュタグやミームによって瞬時に世界中へ拡散します。
たとえば、英語圏で生まれた「rizz(=魅力、モテる力)」や「slay(=最高、完璧にこなす)」といった言葉は、TikTokで爆発的に広まり、日本語圏のユーザーも自然に使うようになりました。
つまりスラングは、**“国境を越える言葉のトレンド”**となりつつあるのです。
また、SNSのアルゴリズムによって似た感性の人同士がつながりやすくなり、共通言語としてのスラングがコミュニティ内で定着するのも特徴です。
言葉に表れるZ世代の価値観とコミュニティ感
スラングの背景には、Z世代ならではの価値観が深く関わっています。
彼らは「誰かと同じ」であることよりも、**“自分らしさ”や“共感できるノリ”**を大切にします。
たとえば、海外では「delulu(delusional=妄想的の略)」という言葉が、推し活などで「夢を見てるけど幸せ」な状態を表すポジティブな意味に変化。
日本でも「チル(=落ち着く)」や「エモい(=感情が動かされる)」といったスラングが人気なのは、感情をストレートに共有したいという世代特有の心理が反映されています。
また、スラングは単なる言葉遊びではなく、**“同じ空気を感じ取れる仲間の証”**でもあります。
同じスラングを使うことで「同世代」「同じコミュニティ」に属している感覚を得られるのです。
スラングは“トレンド”ではなく“文化の反映”
スラングは一見くだけた言葉ですが、実は時代や社会の動きを最も敏感に映す表現でもあります。
「かわいい」「やばい」「ガチ」など、もともと特定の意味だった言葉が文脈によって新しい感情表現に進化しているのもその証拠。
海外では「woke(=社会意識の高い)」が政治・文化の文脈で使われ、日本では「尊い」「しんどい」といった感情語が拡張的に使われています。
これらは単なる流行ではなく、時代の価値観が言葉に姿を変えたものと言えるでしょう。
つまり、若者スラングとは「今を生きる人たちの心の動き」そのものであり、文化や世代を読み解く重要な手がかりなのです。
✍️まとめポイント
-
SNSの拡散力がスラングの寿命を短くも早くもしている
-
スラングにはZ世代の「共感・感情共有」文化が色濃く出る
-
言葉の変化は“時代の感情”を映すカルチャー現象
海外スラング編|注目の10語と意味・使い方

SNSを中心に、海外のスラングは世界中へと瞬く間に広がっています。
特にTikTokやX(旧Twitter)、YouTubeのコメント欄では、短くインパクトのある言葉が好まれ、感情表現や共感のツールとして使われています。
ここでは、今注目されている海外スラング10語をピックアップし、意味・使い方・背景をまとめました。
🔤海外スラング10選|意味・使い方・背景
| 単語 | 意味 | 使い方・例文 | 背景・ニュアンス |
|---|---|---|---|
| rizz | 魅力・惹きつける力(主に恋愛面) | He’s got mad rizz!(彼、めっちゃモテる!) | “charisma”の略。恋愛・ナンパ文脈でZ世代が多用。 |
| delulu | 妄想的・理想を見すぎ | She’s so delulu about her crush.(彼女、推しに夢見すぎ) | “delusional”の略。推し活文化からポジティブに転用。 |
| slay | カッコいい・完璧に決まってる | You slayed that outfit!(その服、最高!) | 元はLGBTQ+カルチャー由来。今は称賛の意味で広く使用。 |
| based | 自分の意見を貫く・本音で生きてる | That’s so based.(それマジで正しい) | 元々は政治・ネットスラング。現在は“芯がある”ポジティブ語。 |
| no cap | 嘘じゃない・本気 | I’m serious, no cap.(ガチだよ、嘘じゃない) | “cap=嘘”の逆語。正直さを表すZ世代の定番。 |
| it’s giving~ | ~っぽい雰囲気・ vibe がある | It’s giving main character.(主人公感ある!) | TikTok発祥。ファッションや自己表現を褒める時に使用。 |
| mid | 微妙・普通 | That movie was mid.(その映画、まあまあだった) | “middle”の略。ネガでも淡々とした評価語。 |
| ghosting | 連絡を突然無視する | He ghosted me after two dates.(2回目のデート後に音信不通になった) | 恋愛・人間関係用語。SNS文化の副作用的現象。 |
| simp | 惚れすぎな人・尽くしすぎ男子 | He’s such a simp for her.(彼、彼女にゾッコンすぎ) | 皮肉半分・愛情半分の表現。Z世代では軽口的に使用。 |
| core | ~っぽい世界観・スタイル | Cottagecore / Y2Kcoreなど | ファッションやサブカルチャーを象徴する接尾語。 |
“rizz” や “delulu” に見るZ世代の恋愛観
「rizz」や「delulu」といった恋愛系スラングは、Z世代の恋の価値観を象徴しています。
“rizz”は「モテる=自分らしさと自信を持つこと」という新しい魅力の定義。
“delulu”は、推し活や恋愛での「妄想」を否定せず、“楽しむ姿勢”としてポジティブに使われます。
つまりZ世代にとって恋愛は、
「現実的でありながら、理想を楽しむ」
というバランスが大切。
SNS上での恋愛観共有が、スラングの形で可視化されているのです。
“based”“cap”など共感・本音を表す言葉
“based”“no cap”などのスラングは、本音で生きること・嘘をつかないことを重視するZ世代の姿勢を反映しています。
「正直に言ってもいい」「自分の意見を持つのがカッコいい」という風潮が、SNS時代の新しい“誠実さ”の象徴になっています。
特に“based”は、「流行や圧力に流されず自分を貫く人」へのリスペクトを表す言葉。
“no cap”は「ガチで」「本気で」というリアルトーンを加える言葉で、コメントやメッセージでの共感サインとして定着しています。
海外スラングがSNSを通じて広まる仕組み
海外スラングが世界に広まる背景には、SNSのアルゴリズムとカルチャーの相互作用があります。
TikTokやXでは、同じ音源・ハッシュタグ・ミーム(ネタ動画)を通して共通の表現が急速に拡散。
一つのスラングが数日でグローバル化することも珍しくありません。
さらに、インフルエンサーや海外アーティストの発信力も大きな要因。
たとえば“rizz”はYouTuber Kai Cenatの発言から流行し、“slay”はドラァグクイーン文化からポップカルチャーに広がりました。
このようにスラングは、**ネット文化・音楽・ファッションが交差する“言葉のトレンド”**として進化しています。
✍️まとめポイント
-
“rizz”や“delulu”は恋愛観・推し文化の象徴
-
“based”“no cap”は本音や誠実さを重視する価値観の表れ
-
SNSの拡散力とミーム文化がスラングの寿命と広がりを決める
日本スラング編|注目の10語と意味・使い方

日本のスラング(若者語)は、SNSや日常会話の中で日々進化しています。
特にTikTok・Instagram・X(旧Twitter)などでは、短くて共感を呼ぶ言葉が次々と生まれ、誰かが口にした“ノリ”が一気にトレンド化。
ここでは、今注目されている日本のスラング10語をピックアップし、意味・使い方・背景を整理します。
🇯🇵日本スラング10選|意味・使い方・背景
| 単語 | 意味 | 使い方・例文 | 背景・ニュアンス |
|---|---|---|---|
| それな | 同意・共感のサイン | 「今日めっちゃ寒いね」「それな!」 | 相づちの定番。会話の“共感力”を高める。 |
| エモい | 感情が揺さぶられる・懐かしい | 「この曲、マジでエモい」 | “emotional”の略。情緒やノスタルジーを含む感覚語。 |
| ガチ勢 | 本気で取り組む人・熱狂的ファン | 「彼は筋トレガチ勢」 | “ガチ=真剣”+勢。趣味文化とSNSの融合語。 |
| チル | 落ち着く・まったりする | 「今日は家でチルする」 | 英語“chill”由来。ストレス社会の“癒し”価値観。 |
| やばたにえん | 「やばい」をコミカルにした言葉 | 「テスト全然できん、やばたにえん」 | ネットミーム発祥。語感重視のユーモアスラング。 |
| きゅんです | 胸がときめく・かわいい | 「この仕草、きゅんです♡」 | TikTok発祥。恋愛や推し文化の象徴。 |
| ぴえん/ぱおん | 悲しい・切ない感情 | 「宿題終わらない…ぴえん」 | 擬音的感情語。SNSの“感情表現スタンプ”化。 |
| バズる | 急速に拡散される | 「この動画、めっちゃバズってる」 | SNS文化の象徴。情報の広がりを表す現代語。 |
| 尊い | 推しへの強い愛情・感動 | 「このツーショット尊すぎる」 | オタク文化発祥。神聖・感情的な称賛語。 |
| 量産型 | 同じ系統のファッションや人を指す | 「あの子、量産型女子っぽい」 | ファッション文化語。共感と皮肉の両面あり。 |
「それな」「エモい」「ガチ勢」など定番ワードの進化
これらのスラングは、もはや「若者語」ではなく**“現代語”として定着した存在です。
「それな」は一言で“共感”を表せる万能フレーズであり、SNS上ではスタンプのように使われます。
「エモい」は、単なる“感動”を超えて、「懐かしさ」「切なさ」「空気感」など日本独特の情緒を含む言葉**として発展しました。
また、「ガチ勢」は“本気で楽しむ人”へのリスペクト表現として、オタク文化や趣味コミュニティで自然に使われています。
これらの言葉に共通しているのは、感情や温度感を共有する機能。
日本のスラングは、意味の正確さよりも**「相手と気持ちをそろえる」**ことを目的に使われる傾向があります。
SNS発の新語「チル」「やばたにえん」などの系譜
SNS時代のスラングは、テンポの良さとノリの良さが命。
「チル」「やばたにえん」「きゅんです」「ぴえん」などは、リズムや語感の楽しさが重視されています。
たとえば「チル」は英語“chill”を日本流にアレンジした言葉で、「まったり」「癒される」など穏やかな自己肯定感を表現するワードとして人気に。
一方「やばたにえん」は、意味というより音の遊びで広がった“ネタスラング”であり、Z世代のユーモアセンスを象徴しています。
これらのスラングは、TikTokやYouTube Shortsなどの短尺動画でフレーズ+表情+動きとセットで使われることで拡散。
言葉単体ではなく、“コンテンツ体験”として広まるのが今の潮流です。
日本のスラングが“やさしさ”や“ノリ”を重視する理由
海外スラングが「自己主張」や「個性」を表すのに対し、
日本のスラングは**“空気を読むコミュニケーション”の延長線上**にあります。
たとえば、「それな」「ぴえん」「チル」などは、相手を否定せず、やわらかく共感を伝える表現。
強い主張よりも、“共感・連帯・ノリ”を重視する文化的背景が見えてきます。
また、現代の若者はSNSを通じて他人との距離感を敏感に感じ取る世代。
スラングを使うことで、「私も同じ気持ちだよ」「一緒に笑いたい」というやさしい同調のサインを送っているのです。
この“言葉のやさしさ”こそが、日本スラングの最大の特徴といえるでしょう。
✍️まとめポイント
-
「それな」「エモい」などの定番語は“感情共有”の文化を象徴
-
SNS発スラングは語感・ノリ・テンポ重視で進化
-
日本のスラングは“やさしい共感”を中心に発展している
海外スラングと日本スラングの違い&共通点
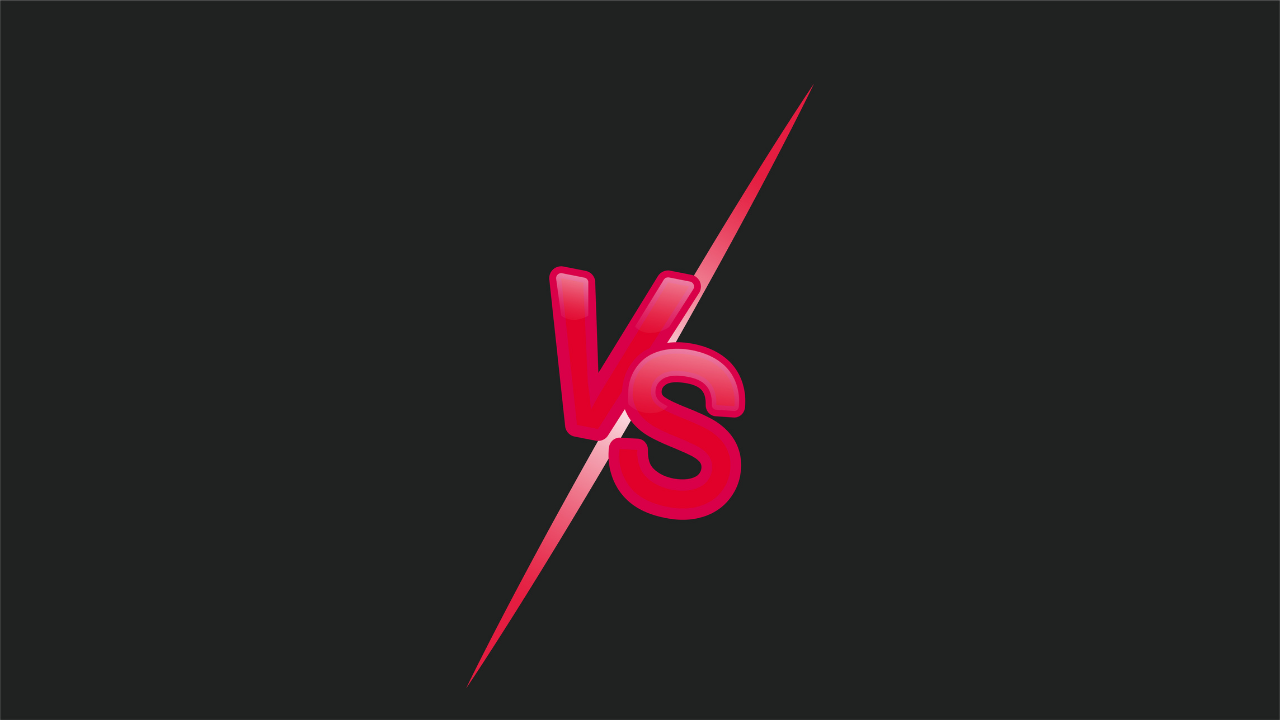
スラングはどの国にも存在し、時代や文化を映す“鏡”のような言葉です。日本・アメリカ・韓国など、それぞれのスラングを比べると、言葉の背景にはその国の「人間関係の距離感」や「価値観の違い」がはっきり表れています。ここでは、海外と日本のスラングの違い・共通点を通して、言葉の裏にあるカルチャーを読み解いていきましょう。
文化の違いが生む“ノリ”の違い(直接 vs 間接)
英語圏のスラングは、「ストレートで勢いがある」表現が多いのが特徴です。
たとえば「lit(最高に盛り上がってる)」「savage(容赦ない・かっこいい)」など、感情を直接的に伝える言葉が好まれます。
一方、日本のスラングは「やんわり」「空気を読む」ニュアンスが重視される傾向にあります。
「それな」「ワンチャン」「微妙」など、明言を避けつつも共感や温度感を伝える表現が多いのが特徴。
つまり、英語圏のスラング=主張のツール、日本のスラング=共感のツールという構図が見えてきます。
どちらも「仲間内の共感」を生むツール
文化的な違いはあっても、スラングの本質はどの国でも同じ。
それは「仲間とのつながり」を生むための言葉であるということです。
英語の「bro(兄弟・仲間)」「fam(家族のような仲間)」、
日本語の「リア友」「ガチ勢」など、いずれも“内輪感”を共有するために使われます。
つまり、スラングは**「外」と「内」を分けるコミュニケーションの境界線**でもあり、使いこなすことで同世代や同文化圏での一体感を感じられるのです。
言葉から見える日米・韓国カルチャーの今
スラングのトレンドを追うと、それぞれの国の“今”が見えてきます。
-
アメリカ:ポジティブで自信を持つ表現(例:「slay」「fire」)が主流。SNS映え文化の象徴。
-
韓国:可愛さ・共感重視の表現(例:「존예(超かわいい)」「킹받다(ムカつくけど笑える)」)が多く、エンタメ発の影響が強い。
-
日本:感情をやわらかく伝える曖昧さと、ネタっぽいノリ(例:「草」「ぴえん」「尊い」)が共存。
このように、スラングは国ごとの価値観や感情表現の違いを映し出す“文化のバロメーター”。
単なる流行語として消費するのではなく、その背景にある“人間らしさ”を感じ取ると、言葉の奥行きがぐっと深まります。
若者スラングの使い方|SNS・リアル会話での注意点

スラングは、使いこなせば会話をぐっと親しみやすく、軽やかにしてくれる便利な言葉です。
しかし一方で、使う場面や相手を誤ると「空気が読めていない」「無理してる」と思われるリスクも。
SNSでもリアルでも、スラングを“自然に”使うには距離感と文脈の見極めが重要です。ここでは、若者スラングを使うときのマナーやコツを具体的に見ていきましょう。
スラングは「使う場面」と「相手」を選ぶのがマナー
スラングはカジュアルな言葉のため、公的な場面や目上の人との会話では控えるのが基本。
たとえば「ガチで無理」「それな〜」といったフレーズは、同世代との日常会話やSNS投稿では自然ですが、ビジネスメールや公式の場では不適切に見えることもあります。
また、相手がその言葉を理解しているかどうかも大切なポイント。
世代や地域によって意味が伝わらないことも多いため、相手の反応を見ながら使うようにしましょう。
スラングは「仲間内限定の共通言語」であることを忘れずに。
言葉の背景を知らずに使う“痛い使い方”とは?
流行っているからといって、意味をよく知らずにスラングを使うのはNG。
たとえば「エモい」を「かわいい」だけの意味で使ったり、「ガチ勢」を単に“本気な人”と混同したりすると、文脈のズレで“ちょっと痛い”印象を与えてしまうこともあります。
スラングにはそれぞれ**文化的背景や使う人たちの“ノリ”**があります。
意味だけでなく「どんな気持ちで」「どんな場面で」使われているかを理解してこそ、本当の使いこなしにつながります。
うまく取り入れるコツ=“雰囲気”を真似しすぎないこと
スラングを自然に使うコツは、「無理して若者っぽく見せようとしない」こと。
文末や語調をムリに合わせると、不自然さや違和感が出やすくなります。
たとえば、無理に「〇〇すぎて草」「ガチでそれな」などを多用すると、相手との温度差が生まれることも。
大切なのは、言葉を“自分の言葉”として消化してから使うことです。
SNSでは投稿の雰囲気や自分のキャラクターに合う範囲で取り入れ、リアル会話では相手との関係性に合わせて調整を。
スラングを“媚びるための言葉”ではなく、“距離を近づける言葉”として使えたとき、それはもう立派なコミュニケーションスキルです。
まとめ|若者スラングはカルチャーを知る入口!

スラングは単なる「流行り言葉」ではなく、時代のムードや価値観を映し出す鏡。
どんな言葉が流行っているかを知ることで、今の若者たちが何を感じ、何を大切にしているのかが見えてきます。
言葉の変化を追うことは、すなわちカルチャーを理解する第一歩でもあるのです。
言葉を通じて見える「時代の空気」
「エモい」「チル」「尊い」などの言葉には、現代の若者たちが求める“穏やかさ”や“共感”がにじんでいます。
一方で「rizz」や「based」など海外発のスラングには、自己肯定や率直な表現を重んじる文化が表れています。
つまり、スラングを分析すると、その時代の空気──
・どんな人が“カッコいい”とされているか
・どんな感情が共有されているか
・どんな価値観が支持されているか
といった、社会全体の温度感が見えてくるのです。
スラングを理解する=世代や文化を理解すること
スラングを学ぶことは、若者文化への「翻訳」を手に入れるようなもの。
言葉の背景をたどれば、SNS文化・推し文化・ジェンダー観など、さまざまな社会現象が結びついていることに気づきます。
たとえば「バズる」はネット時代の拡散性を、「推し活」は個人の情熱や共感の形を象徴しています。
スラングを知ることで、世代の境界を越えてコミュニケーションの理解が深まるのです。
使いこなすより“感じ取る”姿勢が大切
スラングを完全に使いこなす必要はありません。
むしろ大切なのは、「この言葉にはこんな気持ちがこもっているんだ」と感じ取る柔軟さです。
流行語はすぐに入れ替わりますが、そこに込められた思いや背景は普遍的。
「今の若者はこう感じているんだな」という理解の視点を持てば、世代を超えて会話が広がり、より深いコミュニケーションが生まれます。
スラングを知ることは、“ことばの流行”を追うことではなく、“人の感性”を学ぶこと。
それが、現代を生きるうえでの一番のカルチャーリテラシーと言えるでしょう。
リアルな英語の9割は海外ドラマで学べる!はこちら🔻


