
SNSやチャットで飛び交う「略語」や「スラング」。
「意味が分からないけど、みんな使っている…」そんな経験はありませんか?
特にZ世代を中心に広まる短縮言葉や造語は、日常会話やネット上でのやり取りをスピーディーかつユーモラスに彩ります。
本記事では、【保存版】として SNSで流行中の略語・スラングを一覧化。意味や由来はもちろん、正しい使い方や注意点まで徹底解説します。
最新の流行を先取りしたい方も、会話についていきたい方も、このページを読めばスラングの世界が一気に分かります!
SNSで広がる略語・造語スラングとは?
SNSやチャットアプリを中心に、若者の間で次々と生まれているのが「略語」や「造語スラング」です。
「ありがとう」→「あり」、「了解」→「り」などのように、短縮して手軽に使えるものから、「エモい」「それな」「草」など独特のニュアンスを含むものまで幅広く存在します。
これらの言葉は単なる省略ではなく、仲間内での共通言語として機能したり、感情を一言で表現できたりする便利さがあります。そのためZ世代を中心に爆発的に広がり、今やSNSを使う上で欠かせない文化のひとつとなっています。
Z世代を中心に流行する「言葉遊び」
スラングの多くは、Z世代(1990年代後半〜2010年代生まれ)の若者たちによって発信され、TikTokやX(旧Twitter)、InstagramなどのSNSを通じて拡散しています。
彼らがスラングを使う理由には、以下のような特徴があります。
-
入力や会話を短縮して効率化したい
-
仲間同士だけが理解できる“秘密の言葉”感覚を楽しみたい
-
新しい言葉を使うことでトレンドに乗っているアピールができる
つまり、略語や造語スラングは単なる「省略」ではなく、遊び心や自己表現の一部として使われているのです。
略語・造語が使われるシーン(SNS・チャット・日常会話)
これらのスラングはSNSだけでなく、日常のちょっとした会話やLINEなどのチャットでも多用されています。
-
SNS投稿やコメント
例:「今日のライブまじ神」「それな」「エモすぎ」 -
友達同士のチャット
例:「明日集合な」「おけ」「り」 -
日常会話の口頭表現
例:「この曲ガチでバズってる」「それ、草」
このように、SNSを起点に広まったスラングが、リアルな会話にも浸透していくケースがほとんどです。特にZ世代では、自然な感覚で略語を取り入れており、SNS=辞典代わりの発信源になっているといえます。
【2025年最新版】よく使われる略語・スラング一覧【五十音順】

SNSで日常的に見かける略語やスラングを、五十音順に整理しました。由来や意味を理解しておくと、投稿やコメントを読むときにスムーズです。
あ行のスラング
-
あざまる(水産)
「ありがとう」をかわいく崩した言葉。主に若者同士の軽い感謝で使われる。
例:「手伝ってくれてあざまる!」 -
ありよりのあり
「すごくアリ!」「めっちゃいい!」という強調。肯定感を示すときに使う。
例:「その服ありよりのあり!」 -
エモい
「emotional(感情的な)」が由来。感動・懐かしさ・雰囲気があるなど幅広く使われる。
例:「この曲、青春思い出してエモい」
か行のスラング
-
ガチ勢
本気で取り組む人。ゲーム・趣味などで「真剣な人」を指す。
例:「彼はカメラのガチ勢」 -
神ってる/神
「最高!」「すごすぎる!」という褒め言葉。
例:「このライブ神だった!」 -
草
(笑)を表すネットスラング。「wwww」が草に見えることから。
例:「それ草生える」
さ行のスラング
-
それな
「同意」「めっちゃわかる」という意味。相槌として便利。
例:「今日寒すぎない?」「それな!」 -
尊い
「推しや好きな存在が崇高すぎて言葉にできない」気持ちを表現。
例:「推しの笑顔が尊すぎる」 -
しんどい(良い意味)
感情が揺さぶられて耐えられない時に「最高すぎてしんどい」とポジティブにも使う。
た行のスラング
-
大草原
「草(爆笑)」をさらに強調した表現。
例:「その写真大草原すぎる」 -
チルい
「chill」から。落ち着く、リラックスできる雰囲気。
例:「このカフェまじチルい」 -
天才かよ
褒め言葉としてカジュアルに使われる。
例:「その発想、天才かよ!」
な行〜わ行のスラング
-
ぬん
特に意味はなく、ゆるい挨拶や語尾に使う。
例:「おはぬん」 -
バズる
SNSで爆発的に拡散されること。
例:「この動画バズった!」 -
ワンチャン
「one chance」から。「もしかしたら」「可能性がある」という意味。
例:「明日ワンチャン行けるかも」 -
了解→り
「りょ」からさらに省略。最短の承諾表現。
例:「10分後に集合ね」「り」
✅ この一覧を読めば、SNSでよく見かける言葉の意味をすぐ理解でき、会話や投稿をスムーズに楽しめます。
略語・スラングの元ネタを解説!
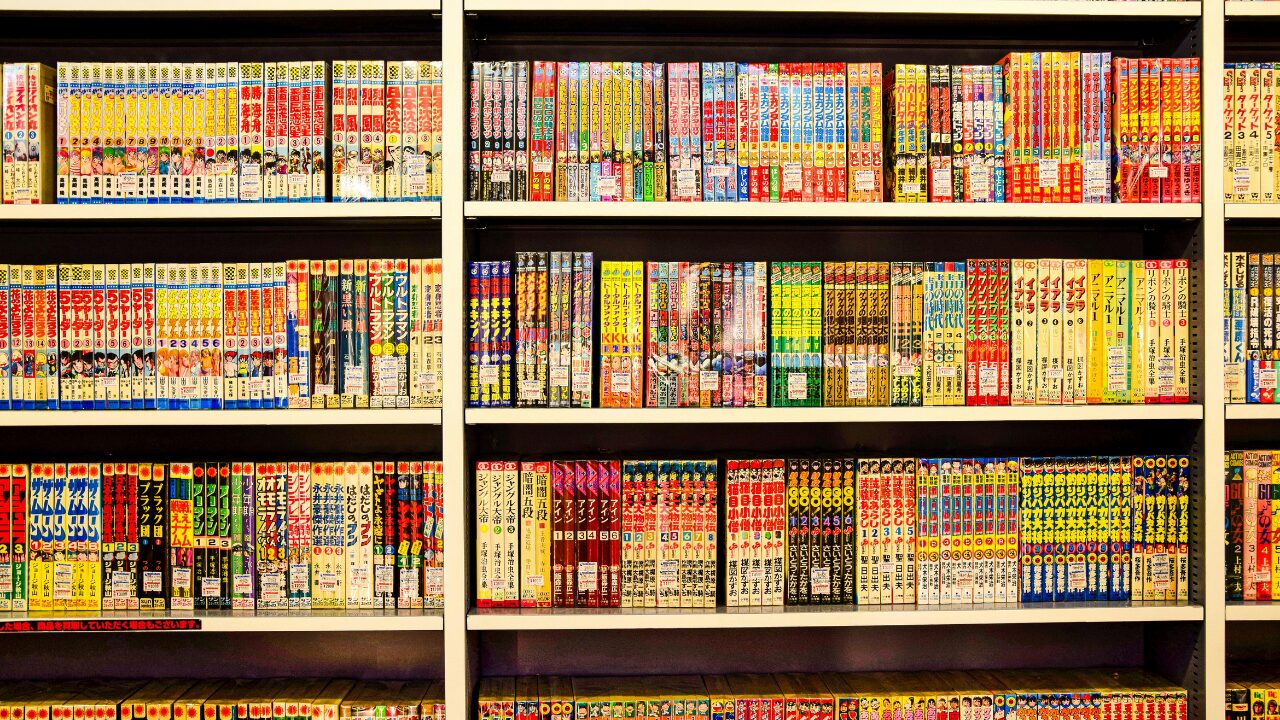
SNSでよく目にする略語や造語スラングは、実は「発祥の場所」がはっきりしているものが多いです。ネット掲示板や動画サイトから広まったものもあれば、芸能人・インフルエンサーの発言、さらにはアニメやゲームといったカルチャーから誕生したものもあります。
ここでは代表的な“元ネタ”ごとに解説していきます。
ネット発祥の流行語
インターネット掲示板(2ちゃんねる/5ちゃんねる)やSNS(Twitter→X、ニコニコ動画)で生まれたスラングは数多く、今でも定着して使われています。
-
草:「wwww(笑)」が草に見えることから → 現在では「笑った」の定番表現。
-
乙(おつ):「お疲れさま」の略。掲示板文化から広まり、今では日常会話でも使われる。
-
バズる:SNSで一気に拡散すること。広告業界にも取り入れられるほど普及。
👉 ネット発祥のスラングは「タイピングの効率化」や「文字遊び」から始まることが多いのが特徴です。
芸能人・インフルエンサー発の言葉
テレビやYouTube、TikTokなどで人気のタレントやインフルエンサーが口にした言葉が、そのまま流行語になるケースも多いです。
-
あざまる水産:お笑い芸人やYouTuberが広めた「ありがとう」を崩した言葉。かわいくて真似しやすいため定着。
-
○○しか勝たん:推し活文化で使われる言葉。「この人が一番」「最高!」の意味。アイドルファン発祥だがSNS全般で使用。
-
きゅんです:TikTok動画から流行。指でハートを作りながら「胸がときめく」様子を表現。
👉 インフルエンサー発のスラングは「動画やSNSの拡散力」で一気に広がりやすく、数か月で全国区の言葉になることもあります。
アニメ・ゲーム・漫画から生まれたスラング
オタク文化から生まれた言葉もSNSで広まり、一般層にまで浸透しています。
-
尊い:もともと二次元キャラやアイドルに対する強い愛情表現から。「尊死(とおとし)」などの派生もあり。
-
無双する:ゲーム用語「敵を圧倒する」から転じて、現実のシーンでも「圧勝する」の意味に。
-
チート:ゲームでの不正行為が由来。「能力が桁外れに高い」キャラや人にも使われる。
👉 アニメ・ゲーム発祥のスラングは「ファンコミュニティ」内で使われていたものが、SNSを通じて日常語に近づいたケースが多いです。
✅ このようにスラングの背景を知ることで、「なぜその言葉が生まれたのか」「どんな場面で使うのが正しいのか」がわかり、誤解や浮いた使い方を避けられます。
SNSアイコン+アカウント名ステッカーはこちら🔻
略語・スラングの正しい使い方と注意点

SNSやチャットで気軽に使われている略語・スラングですが、誰にでも通じるわけではありません。便利な半面、誤解を招いたり「TPOに合わない」と思われたりするリスクもあります。ここでは、スラングを上手に使うためのポイントと注意点を整理します。
場面に応じた使い分け
スラングは「仲の良い友達同士」「SNSでの軽いやりとり」など、カジュアルな場面で使うのが基本です。
-
OKな場面:SNS投稿、DM、友達とのチャット、オタ活仲間との会話
-
注意が必要な場面:学校や職場でのフォーマルなやり取り、公的な文書、年上や目上の人への会話
例えば「了解」を「り」だけで返すのは、同世代の友人には通じても、目上の人には失礼に映る可能性があります。「誰とどんな場面で話しているか」を意識することが重要です。
誤解されやすい言葉に注意
スラングには「使う人によって解釈が分かれる言葉」もあります。意味を知らない人に使うと、思わぬ誤解を招くことも。
-
草:「笑った」の意味だが、相手によっては「バカにされている?」と感じられることがある。
-
しんどい:ポジティブな「尊い!」の意味で使っても、「体調不良?」と受け取られるケースも。
-
ワンチャン:「一発逆転できる可能性」→人によっては軽率なニュアンスに聞こえる場合がある。
👉 新しいスラングは「通じない人も多い」という前提で、相手の理解度を考えて使うのが安全です。
大人世代・ビジネスシーンでは避けるべき表現
スラングは若者文化に根ざしているため、ビジネスメールや職場の会話、親世代とのやりとりでは基本NGです。
-
「おけまる」「あざまる」 → フランクすぎて不真面目に見える
-
「バズる」「チート」 → 一般的に浸透していても、目上の人には伝わらない場合がある
-
「それな」「了解→り」 → 略しすぎて礼儀を欠く印象を与える
フォーマルな場面では、略語を使わず 正しい日本語をしっかり表現することが信頼につながる という意識が必要です。
✅ スラングは便利で楽しい表現ですが、「場面を選んで使う」ことが最大のマナー。特に、SNSと現実の会話の境目を意識すると、誤解やトラブルを防ぐことができます。
【ジャンル別】スラングの分類まとめ
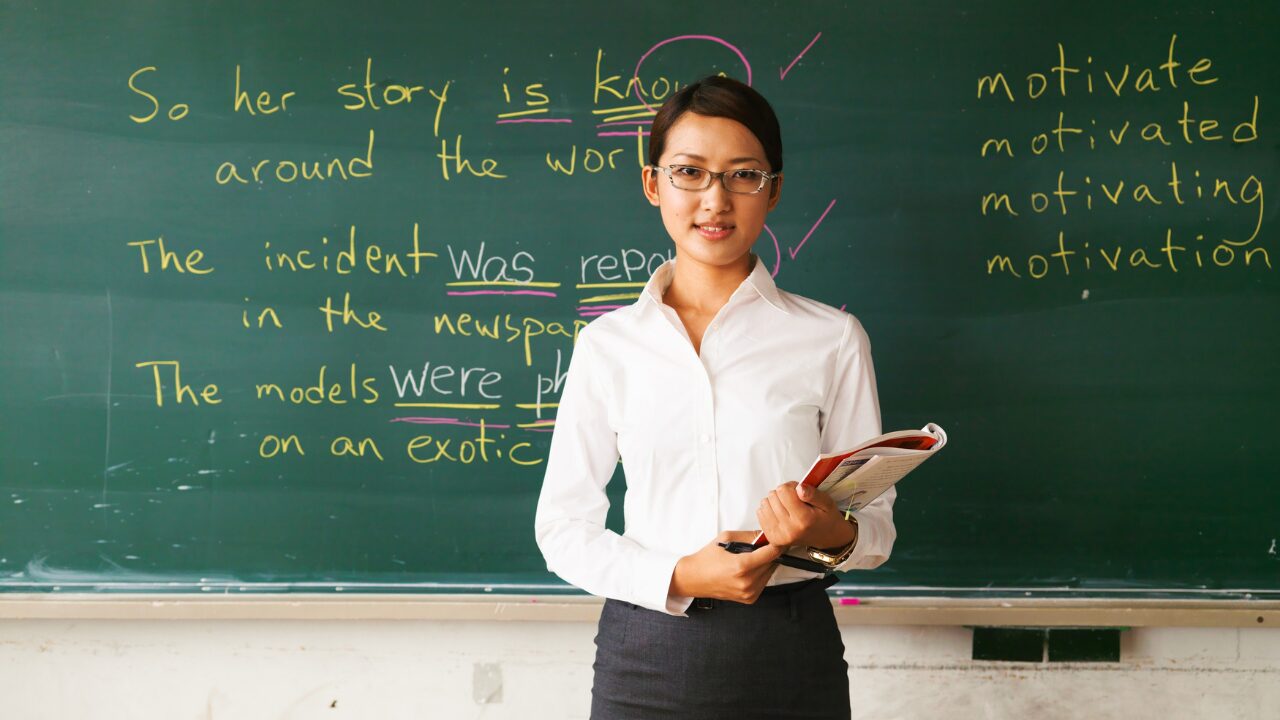
スラングは発祥や使われる場面によって、いくつかのジャンルに分けることができます。同じ「略語」でも、日常会話でよく使うものと、オタク文化やネット特有のものでは雰囲気やニュアンスがまったく異なります。ここでは代表的な分類を紹介します。
日常会話系
友達同士のLINEやSNSで自然に使われる、最も身近なスラングです。短縮形が多く、効率的にやり取りするために生まれました。
-
おけ/り/りょ:「了解」「OK」を簡略化した返事
-
あざまる:「ありがとう」をかわいく言い換えた表現
-
だる絡み:めんどうな絡み方、しつこいコミュニケーション
👉 若者の普段の会話に自然に溶け込みやすく、Z世代の「共通語」ともいえます。
恋愛・人間関係系
「推し活」や恋愛シーンでよく使われるスラング。感情を短く表現できるため、共感を得やすいのが特徴です。
-
尊い:好きな存在が崇高すぎて感情が爆発する様子
-
きゅんです:ときめいたときの表現(TikTok発祥)
-
○○しか勝たん:「推しが最強」「この人が一番」という意味
👉 恋愛感情や友情を表すだけでなく、アイドルやアニメキャラへの熱い気持ちを伝えるときにも使われます。
エンタメ・オタク文化系
アニメ・漫画・ゲームから広まった言葉が中心。ファン同士の共通言語として機能し、SNSでの“拡散力”も高いジャンルです。
-
チート:ゲームでの不正行為が由来。「能力が異常に高い」の意味
-
無双する:ゲーム用語。「圧倒的に勝つ」こと
-
ガチ勢:趣味に本気で取り組む人を指す
👉 オタク文化で生まれた言葉が一般層にも広がり、「誰でも使える便利ワード」として定着しているのが特徴です。
ネット文化・ミーム系
インターネット掲示板やSNSから誕生し、拡散によって広まったスラング。ネタ感が強く、ユーモアや笑いを共有するために使われます。
-
草/大草原:(笑)を意味するネットスラング
-
バズる:投稿や動画が爆発的に拡散されること
-
秒で〜:「すぐに」という意味のネット表現
👉 ネット発のスラングは「ネタ」「ジョーク」として楽しむ文化が強く、若者同士のコミュニケーションに欠かせません。
✅ このようにジャンルで整理すると、スラングは「ただの略語」ではなく、感情表現・仲間意識・ユーモアの道具として使われていることがわかります。
なぜ略語・スラングは流行るのか?

SNSや日常会話で飛び交うスラングや略語は、なぜこれほど浸透するのでしょうか。そこには 便利さ・仲間意識・拡散力 の3つの要素が関係しています。
短くて便利だから
現代のコミュニケーションは、LINEやX(旧Twitter)などの短文文化に強く影響されています。
長い言葉をそのまま使うよりも、短く省略した表現のほうがスピーディで使いやすいため、自然と略語やスラングが好まれるのです。
例えば「了解」→「りょ」、「お疲れさま」→「おつ」など、日常のやりとりを効率化する表現は瞬く間に定着します。
仲間意識を生む「合言葉」的な役割
スラングは単なる省略ではなく、**同じ文化や価値観を共有する仲間同士の“合言葉”**として機能します。
特定のコミュニティでしか通じない言葉を使うことで、
-
「自分は仲間の一員だ」
-
「この場に馴染んでいる」
という安心感や連帯感が生まれます。
これは若者文化だけでなく、鉄道オタクやアニメファンなどの専門的な趣味コミュニティでもよく見られる現象です。
SNSの拡散力で一気に広まる
昔はスラングが広まるのに時間がかかりましたが、今はSNSの登場で状況が一変しました。
TikTokやXで一度流行語が投稿されると、短期間で爆発的に拡散され、多くの人が真似して使うようになります。
また、動画やミーム画像とセットで広がるため、意味が直感的に理解されやすく、さらに定着スピードが加速します。
✅ 略語やスラングが流行る背景には、「便利さ+仲間意識+拡散力」という3つの要素が組み合わさっているのです。
知っておきたい!もう古い・使わなくなったスラング

スラングや流行語は常に生まれては消え、まるで「旬の食べ物」のように寿命が短いのが特徴です。ここでは、かつて人気だったけれど今ではほとんど耳にしなくなった言葉や、その背景を解説します。
平成・令和初期に流行したスラング
平成後期から令和初期にかけては、SNSの普及とともに多くのスラングが爆発的に広がりました。
例えば、
-
「チョベリバ(超ベリー・バッド)」や「MK5(マジでキレる5秒前)」などの 平成ギャル語
-
「卍(まんじ)」「あげみざわ」などの 高校生を中心に広まった若者言葉
-
「ガチ勢」「エモい」などの オタク文化・ネットスラング由来の言葉
これらは一時代を象徴する表現として使われましたが、現在では新しい言葉に置き換えられつつあります。
今はほとんど見かけない言葉たち
スラングの中には、一世を風靡したにもかかわらず、今ではほとんど耳にしないものもあります。
たとえば、
-
「ヤバタニエン」
-
「ワンチャン」
-
「それなー!」(強い共感の表現)
-
「とりま」(とりあえず、まぁ)
一部はまだ使われますが、全盛期のような勢いはなく、若い世代からすると「古い」と感じられるケースが多いです。
「死語化」するスピードが早い理由
スラングが急速に廃れる理由のひとつは、SNSでの拡散力の高さです。
一気に広まり、短期間で社会全体に浸透する反面、同じくらいの速さで「飽きられる」傾向があります。
また、若者文化の特性として「前の世代が使っていた言葉をあえて使わない」という心理もあり、スラングは次々と新しいものに更新されていきます。
結果として、かつての流行語は数年も経てば「死語」と呼ばれてしまうのです。
✅ スラングはその時代を映す「文化の鏡」でもあります。あえて古い言葉を振り返ることで、世代ごとの価値観や流行の移り変わりが見えてきます。
まとめ|略語・造語スラングを知ってSNSをもっと楽しもう!

スラングや略語はただの「言葉遊び」ではなく、時代ごとのトレンドや若者文化を映す鏡のような存在です。意味や背景を知るだけでも、SNSや日常会話の見え方がグッと変わり、情報をより深く楽しめるようになります。
新しいスラングを知る=流行を先取りできる
SNS発の新語は、流行やカルチャーを先取りするためのヒントにもなります。
「最近よく見かけるけど意味が分からない」という言葉を押さえておくことで、
-
投稿やコメントの内容が理解しやすくなる
-
若い世代との会話にスムーズに入れる
-
ネタやユーモアの幅が広がる
といったメリットがあります。
特にマーケティングや教育など人との接点が多い仕事をしている人にとっては、スラングを知っておくことが大きな武器になります。
無理に使わなくても「理解」しておくことが大事
ただし、スラングは必ずしも自分で使う必要はありません。
むしろ、世代や立場によっては使うことで「浮いてしまう」こともあります。
大事なのは、意味を理解しておくこと。
理解していれば、相手の意図を正しく汲み取り、コミュニケーションをスムーズにできます。
「知っているけどあえて使わない」という選択も、大人ならではの賢い付き合い方です。
✅ スラングは常に変化していくもの。
これからも新しい言葉が次々と生まれてきますが、焦らず楽しみながら取り入れていくことで、SNSや日常のコミュニケーションがもっと豊かになります。
高速連打 自動タップ機はこちら🔻


