
「自分のいびきで目が覚める…」そんな経験はありませんか?実はいびきは、単なる睡眠中の音ではなく、睡眠の質の低下や病気のサインである可能性もあります。特に睡眠時無呼吸症候群などを放置すると、日中の強い眠気や生活習慣病のリスクにつながることも。
この記事では、医師監修のもと、いびきの原因をセルフチェックする方法や、生活習慣・寝具の工夫、医療機関での改善法までをわかりやすく解説します。
自分のいびきで目が覚めるのは異常?
いびきは多くの人に見られる現象ですが、自分のいびきで目が覚める場合は注意が必要です。通常のいびきであれば、本人は気づかずに眠り続けることがほとんど。にもかかわらず目が覚めてしまうということは、呼吸が一時的に止まったり、強い振動で睡眠が分断されている可能性があるからです。
いびきで起きる人に多い状況とは
自分のいびきで目覚める人には、いくつか共通の状況があります。
-
呼吸が一時的に止まり、苦しくて目が覚める
睡眠時無呼吸症候群の典型的な症状で、日中の強い眠気や集中力低下につながります。 -
大きな音や振動で睡眠が分断される
特に横向きから仰向けに寝返りを打った時など、気道が狭まり強いいびきをかくと、自分のいびきで驚いて起きることがあります。 -
寝室環境や体調が影響している
鼻づまり、飲酒後、疲労がたまっているときなどにいびきが悪化し、睡眠を妨げるほど強くなる場合があります。
普通のいびきと異常ないびきの違い
「ただのいびき」と「病気が隠れているいびき」を区別することが大切です。
普通のいびき
-
疲れた日や飲酒後だけに出る
-
体調が良ければいびきが減る
-
自分では気づかないことが多い
異常ないびき(要注意)
-
毎晩のように大きないびきをかく
-
自分のいびきで頻繁に目が覚める
-
無呼吸・呼吸の途切れが同居人に指摘される
-
朝起きても疲労感が強い、日中に強い眠気がある
こうした異常ないびきが続く場合は、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性があります。放置すると高血圧・動脈硬化・心疾患リスクの上昇にもつながるため、早めに医療機関で相談することが大切です。
いびきで起きるのは病気のサイン?

自分のいびきで目が覚めるのは、単なる疲れや一時的な体調不良によることもありますが、病気のサインである可能性も否定できません。特に「無呼吸」「日中の眠気」「慢性的な疲労」が重なる場合は要注意です。
睡眠時無呼吸症候群の可能性
最も代表的なのが 睡眠時無呼吸症候群(SAS) です。
-
就寝中に気道が塞がり、呼吸が10秒以上止まる
-
無呼吸が繰り返されることで、体内の酸素不足が起こる
-
睡眠が浅くなり、いびきや呼吸の途切れで目が覚めてしまう
この状態が続くと、高血圧・心筋梗塞・脳卒中など生活習慣病のリスクが上昇します。自分のいびきで頻繁に起きる人は、早めに医療機関での検査を検討すべきです。
生活習慣や体質が原因のケース
いびきで目が覚めても、必ずしも病気とは限りません。以下のような要因で、一時的にいびきが強くなっている場合もあります。
-
体重増加(肥満):首回りに脂肪がつき気道が狭くなる
-
飲酒・喫煙:筋肉が弛緩し、いびきが出やすくなる
-
鼻づまりやアレルギー:呼吸がしづらく口呼吸になりやすい
-
仰向け寝:舌が喉に落ち込み気道を塞ぎやすい
-
加齢や体質:喉の筋肉が衰えて気道が狭まりやすい
この場合は、生活習慣の見直しや寝姿勢の工夫で改善することも可能です。
病院に相談すべきタイミング
以下のような症状がある場合は、自己判断せずに医療機関(耳鼻咽喉科・睡眠外来など)に相談しましょう。
-
自分のいびきで何度も起きる
-
家族から「無呼吸」や「呼吸が止まっている」と指摘される
-
日中に強い眠気・集中力低下がある
-
朝起きても疲労感や頭痛が残る
-
高血圧や糖尿病など生活習慣病を持っている
特に 「無呼吸の指摘」+「強い日中の眠気」 がある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高く、放置は危険です。
自分の睡眠の質をチェックしてみよう
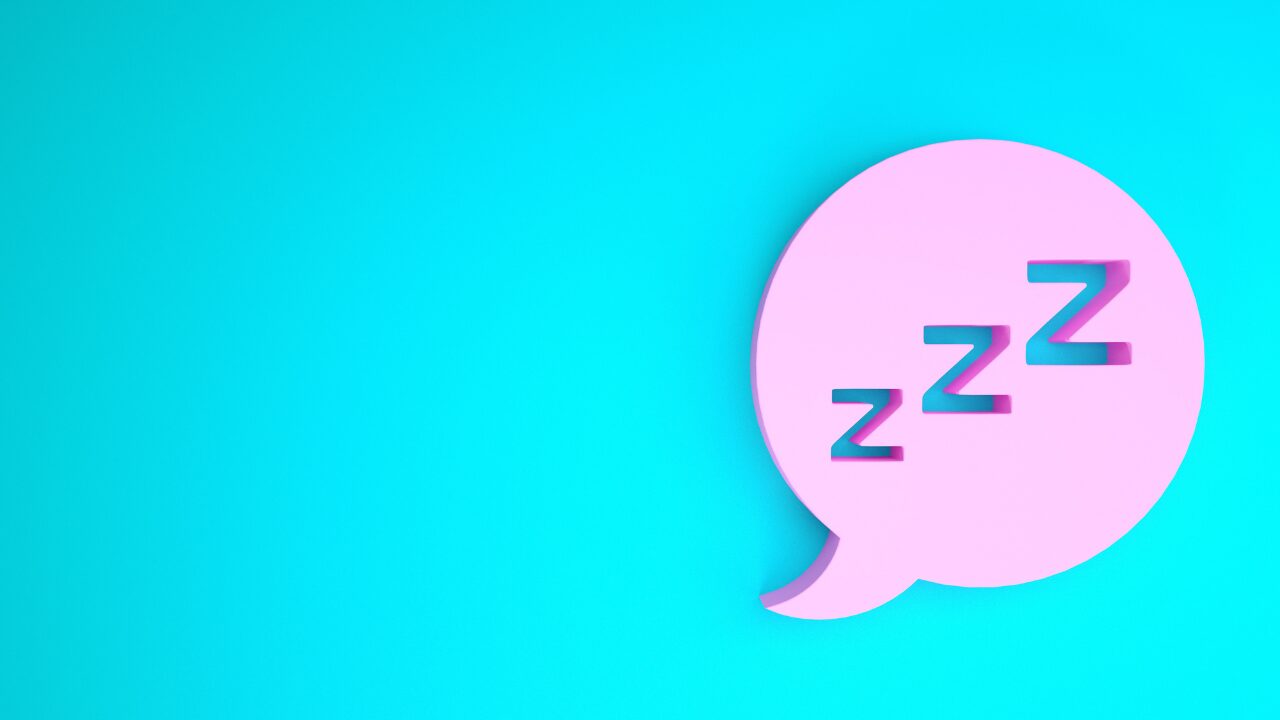
「寝ているはずなのに疲れが取れない」「いびきで目覚めることが多い」──こうした悩みを抱えている人は、まず自分の睡眠の質をチェックしてみましょう。睡眠不足や病気のサインを早めに察知することで、改善や予防につなげられます。
セルフチェックリスト|睡眠の質を見極めるポイント
以下の項目にいくつ当てはまるか確認してみてください。3つ以上該当する場合は、睡眠の質が低下している可能性があります。
-
寝ても寝ても朝スッキリ起きられない
-
夜中に何度も目が覚める、またはいびきで起きる
-
家族やパートナーから「呼吸が止まっていた」と指摘された
-
日中の眠気が強く、仕事や勉強に集中できない
-
週末に長時間寝ても疲れが取れない
-
起床時に頭痛やだるさがある
-
就寝前の飲酒やスマホ使用が習慣になっている
👉 このリストはあくまで目安ですが、複数当てはまる場合は生活習慣の改善、または専門医での相談を検討しましょう。
眠気・疲労感・集中力低下はSOSサイン
質の高い睡眠がとれていないと、身体だけでなく心にも影響が出ます。
-
日中の強い眠気:睡眠不足や無呼吸により深い眠りが妨げられている可能性
-
疲労感の持続:睡眠の回復効果が十分に得られていないサイン
-
集中力や記憶力の低下:脳の休養不足による影響
こうした状態を「一時的な疲れ」と放置すると、仕事や学業のパフォーマンス低下だけでなく、生活習慣病やメンタル不調につながるリスクもあります。
もし毎日の生活に支障を感じるほど続いている場合は、医療機関での相談や睡眠検査を受けることが重要です。
いびきを改善するための対策法

いびきで目が覚めてしまう、あるいはいびきそのものが大きくて日常生活に支障を来しかねない人は、根本的な対策を行うことが重要です。ただし、「これだけで必ず治る」という万能策は存在しないため、段階的・組み合わせ的に取り組むことを念頭に置きましょう。
生活習慣の見直し(寝姿勢・体重・飲酒・喫煙)
まず取り掛かりやすく、効果を期待できるのが生活習慣の改善です。
| 改善項目 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 寝姿勢の工夫 | 仰向け寝だと舌や軟口蓋が後方へ落ち込みやすいため、横向き寝を基本とする。抱き枕を併用して寝返りしづらくする。 | 気道が物理的に閉じにくくなる。いびき軽減につながる。 |
| 体重管理 | 特に首回り・顎周りに脂肪がつくと気道が狭まりやすい。食事・運動で適正体重を維持する。 | 呼吸器系への負荷を下げ、いびき発生を抑えやすくなる。 |
| 飲酒・就寝前のアルコール | アルコールは咽頭筋を弛緩させ、いびきの原因になりやすい。就寝3時間以上前には摂取を控える。 | 筋肉の緩みが減り、いびき量・頻度を抑えやすくなる。 |
| 喫煙の見直し | 喫煙による気道刺激・炎症で粘膜が腫れ、空気の通り道が狭くなる可能性。可能であれば禁煙を検討。 | 気道の炎症・むくみを軽減し、呼吸の通りを改善する。 |
| 規則的な睡眠習慣 | 毎日ほぼ同じ時間に寝起きをする、睡眠時間を確保する。深い睡眠を取りやすくする。 | 睡眠の質が安定し、バランスの良い呼吸制御が促される。 |
これらは「ゼロコストまたは低コストでできる改善策」として、まず実践を促すことが多いです。
寝具や寝室環境を整える工夫
生活習慣に加えて、「寝る環境」を整えることで気道が閉じにくい状態をサポートします。
-
枕の見直し
高すぎたり低すぎたり、柔らかすぎたり硬すぎたりする枕は首が変な角度で曲がり、気道を圧迫しやすくなります。自分の肩幅や仰向け/横向きポジションに合った適切な高さ・硬さの枕を選ぶことが重要です。 -
抱き枕・クッション活用
横向き寝を維持しやすくするよう、抱き枕を抱えて寝たり、背中側にクッションを置いたりすると寝返りで仰向けに戻る回数を抑えられます。 -
室内湿度と空気質
乾燥や埃・アレルギー物質は鼻腔・気道に炎症を引き起こしやすく、鼻詰まり→口呼吸→いびきの悪循環を招きます。加湿器や空気清浄機を活用し、湿度 40〜60 % 程度を維持するよう心がけましょう。 -
就寝前の環境コントロール
寝る1時間前からスマホや強い光を避け、リラックスする時間にする。カフェインの摂取も就寝6時間前までに抑える。部屋の明るさ・騒音対策も併せて。 -
寝具の清潔・アレルギー対策
布団・枕カバーをこまめに洗濯し、ダニ・ホコリを減らす。アレルギー性鼻炎を持つ人は、アレルゲンを抑える寝具(防ダニカバーなど)を使うと良いでしょう。
グッズや医療機関を活用する方法
生活習慣・環境改善だけでは十分効果が出ない人、重度ないびきや無呼吸の疑いがある人は、補助的なグッズまたは医療的アプローチを検討します。
グッズ(市販・補助器具)
以下は日本で入手できる/紹介されているいびき対策グッズの例です。効果には個人差があるため、使う前に適合性や安全性を確認する必要があります。
-
小林製薬 ナイトミン 鼻呼吸テープ
口呼吸を防ぎ、鼻呼吸を促すテープ。就寝中口が開きやすい人向け。
リンク -
いびきマウスピース
装着型のマウスピース。下顎を前方に保つことで気道閉塞を予防。
リンク -
ZQuiet(マウスピース)
アメリカ発の顎保持型マウスピース。気道を確保する目的で使われる。
リンク -
Snoreeze(いびきマウスピース)
英国ブランドのマウスピース製品。
リンク -
日進医療器 鼻呼吸テープ
鼻呼吸を補助するテープ型グッズ。
リンク -
そのほか、ノーズクリップ(鼻腔拡張器)、ナステント(鼻腔に挿入する柔軟管型デバイス)、いびき防止マスク・フェイスサポータータイプなどがあります。
使うときの注意点・コツ
-
初回は短時間で試し、異物感や痛みがないか確認する
-
継続使用前に歯科医や耳鼻科医に相談する
-
マウスピース使用時は口腔・歯の状態に注意(顎関節などに負担がかからないよう)
-
グッズだけで改善できない重症例では無理せず医療機関を併用
医療機関・専門診療の活用
-
睡眠外来/いびき専門クリニック
ポリソムノグラフィー(睡眠時呼吸検査)や簡易検査を行い、無呼吸症候群の有無を診断。 -
耳鼻咽喉科
鼻中隔弯曲、鼻炎、扁桃肥大など、呼吸路に構造的な問題がないかを調べる。 -
歯科(顎口腔領域)
マウスピース(口腔内装具・スリープスプリント等)を歯科医の管理下で作成・調整する。 -
CPAP(持続陽圧呼吸療法)
中等度〜重度の睡眠時無呼吸症候群には、CPAP治療が標準的治療として用いられることが多い。 -
外科手術
気道が構造的に狭いケース(軟口蓋肥大、扁桃肥大、鼻中隔湾曲など)では手術的介入が検討されることもある。 -
定期フォローとモニタリング
治療後も定期的に症状観察を続け、改善が見られなければ別の治療法を検討。
補足・注意事項
-
上記の対策法はあくまで 予防・軽症改善向けのアプローチ です。
-
いびきだけでなく 無呼吸、日中の強い眠気、起床時の頭痛 などが同時にある場合は、まず医療機関で原因を精査することが優先です。
-
グッズ使用中に 違和感・口腔痛・顎関節痛 が出た場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
まとめ|いびきで起きる人は放置NG!まずは睡眠の質チェックから

小さな改善が大きな変化につながる
いびきは「ただの寝相のクセ」ではなく、体のSOSサインである場合もあります。寝姿勢の工夫、生活習慣の見直し、寝具の改善など、身近なことから始めるだけでも症状が軽減するケースは少なくありません。小さな改善を積み重ねることで、熟睡できる環境をつくり、翌日のパフォーマンス向上にもつながります。
気になる場合は専門医に相談を
生活習慣を見直してもいびきが続く場合や、呼吸が止まるような症状がある場合は「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。放置すると高血圧や心疾患リスクの増大につながるため、早めに耳鼻科や睡眠専門クリニックを受診することが大切です。セルフチェックと生活改善を起点にしつつ、必要に応じて医療機関を頼ることで、安心して眠れる毎日を取り戻しましょう。


