
はじめに
発熱は、体がウイルスや細菌と戦っているサインであり、自然な防御反応のひとつです。必ずしも「すぐに熱を下げること」が正しいとは限りませんが、38度を超える高熱や強い倦怠感があると、つらさから早く解熱したいと感じる人も多いでしょう。
一方で、解熱剤の使い方を誤ると、症状を悪化させたり副作用のリスクを高めたりする可能性があります。特に子どもや高齢者、持病のある方では注意が必要です。
この記事では、
-
発熱が起こる原因
-
自宅でできる基本的な対処法
-
解熱剤を使うべき適切なタイミング
-
解熱剤の正しい使い方と注意点
-
医療機関を受診すべきケース
について、医療的な観点も踏まえてわかりやすく解説します。正しい知識を身につけることで、発熱時にも落ち着いて対応でき、不要な不安や間違った対処を避けることができます。
1. 発熱の原因とは?
体温が上がる仕組みと意味
発熱は、体がウイルスや細菌などの異物(病原体)と戦うために起こる自然な反応です。体内に病原体が侵入すると、免疫細胞が「発熱物質(サイトカインなど)」を放出し、脳の視床下部にある体温調節中枢に働きかけます。その結果、体温が上昇し、病原体が増殖しにくい環境を作り出します。つまり、発熱は体を守るための防御システムなのです。
風邪・インフルエンザ・感染症など主な原因
発熱の原因はさまざまですが、代表的なものは次の通りです。
-
風邪やインフルエンザ:最も一般的で、ウイルス感染による発熱。咳・鼻水・喉の痛みなどの症状を伴うことが多い。
-
細菌感染症:扁桃炎、肺炎、中耳炎、尿路感染症など。高熱が出やすく、抗菌薬が必要になる場合もある。
-
子どもの突発性発疹:突然の高熱のあと、解熱とともに発疹が出る。
-
その他の炎症性疾患や免疫反応:リウマチ、薬剤アレルギーなどでも発熱が起こる。
発熱の背景には「感染症」が多いものの、必ずしも全てが感染症とは限らない点も理解しておきましょう。
発熱=悪いことではない理由
多くの人は「熱が出た=悪いこと」と考えがちですが、発熱は必ずしも悪者ではありません。体温が上がることで:
-
免疫細胞の働きが活発になる
-
ウイルスや細菌の増殖が抑えられる
-
体が病原体を排除しやすくなる
といったメリットがあります。したがって、熱を無理に下げることが必ずしも正解ではないのです。重要なのは「体のつらさを和らげながら、適切に回復をサポートすること」です。
2. 発熱時にまずやるべき基本的な対処法

発熱したときに大切なのは、むやみに解熱剤を使うことよりも、まず 体に負担をかけない環境を整えること です。ここでは自宅でできる基本的な対処法を紹介します。
水分補給と安静が最優先
発熱時は汗や呼吸で体内の水分が失われやすく、脱水症状に陥るリスクが高まります。水や麦茶、経口補水液(ORS)などを少しずつ、こまめに摂取しましょう。カフェインやアルコールは利尿作用があるため避けるのが無難です。
また、免疫機能が病原体と戦うためには休養が不可欠です。無理をせず横になり、十分な睡眠と安静を心がけましょう。
室温・湿度の調整
発熱中は体温調節がうまく働かないことがあります。室温は 20〜25℃前後 を目安にし、暑すぎたり寒すぎたりしないように調整しましょう。加湿器や濡れタオルを利用して 湿度を50〜60% に保つと、呼吸が楽になり回復を助けます。
着るもの・冷やし方の工夫
厚着をしすぎると体に熱がこもり、逆に悪化することがあります。発熱時は 通気性のよい衣類 に着替え、汗をかいたらこまめに取り替えましょう。
また、熱がつらいときには 脇の下・首・足の付け根 など太い血管が通る場所を冷やすと、体温を効率的に下げる効果があります。ただし、寒気が強いときは無理に冷やさず、体を温めることを優先してください。
食事の取り方のポイント
発熱時は消化機能が低下するため、無理に食べる必要はありません。食欲がある場合は、おかゆ・うどん・スープ など消化の良い食事を選びましょう。ビタミンやミネラルを含む果物や野菜スープもおすすめです。食欲がないときは水分補給を優先し、回復してから少しずつ食事を再開すれば大丈夫です。
3. 解熱剤を使うべきタイミングとは?
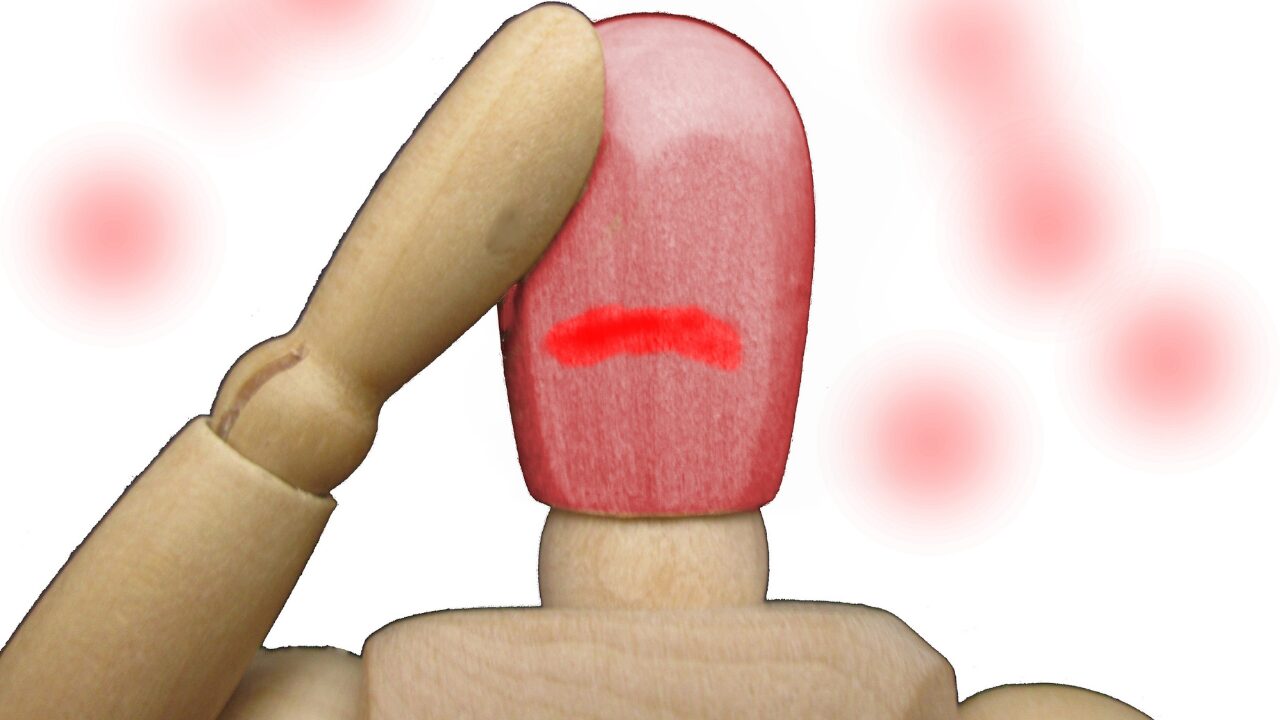
解熱剤は「熱があるからすぐ飲む薬」ではありません。基本的には、体が病原体と戦うのをサポートするために使うもので、体温の数字だけで判断せず、つらさの程度や年齢によって使用の目安が変わります。
何度以上で使うべき?
-
一般的に 38.5℃前後 がひとつの目安とされます。
-
ただし、熱が高くても元気に過ごせていれば必ずしも解熱剤は不要です。
-
逆に、37〜38℃程度でも強い頭痛や関節痛でつらい場合には、解熱剤を使用して構いません。
つまり「体温の高さ」よりも「本人のつらさ」を基準に判断することが大切です。
子どもと大人で違う基準
-
大人の場合
-
38.5℃以上、あるいは体のだるさ・頭痛・関節痛が強いときに使用するのが一般的です。
-
-
子どもの場合
-
39℃前後を目安にすることが多いですが、体温よりも「機嫌が悪い」「水分が取れない」「眠れない」といった状態が重視されます。
-
生後3か月未満の乳児が38℃以上の発熱をした場合は、解熱剤を使う前に必ず医療機関を受診してください。
-
つらさを和らげるための目安
解熱剤の目的は「熱を完全に下げること」ではなく、症状をやわらげて休養や水分補給をしやすくすることです。
-
食事や水分が取れない
-
寝られないほどの不快感がある
-
強い頭痛や悪寒で休めない
こうした場合には、体温が何度であっても解熱剤を使う意義があります。
エスエス製薬 イブAはこちら🔻
4. 解熱剤の正しい使い方

解熱剤は発熱時のつらさを和らげるために役立ちますが、誤った使い方をすると副作用や思わぬ健康被害につながることがあります。ここでは代表的な解熱剤の種類と安全に使うためのポイントを解説します。
よく使われる解熱剤の種類
-
アセトアミノフェン
-
子どもから大人まで幅広く使える安全性の高い解熱鎮痛薬。
-
胃腸への負担が少なく、妊婦にも比較的使いやすいとされる。
-
-
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
-
イブプロフェン、ロキソプロフェン などが代表的。
-
炎症や痛みを抑える効果が高いが、胃粘膜への刺激や腎機能への影響があるため注意が必要。
-
用量・用法の守り方
-
医師や薬の添付文書に記載された 容量・間隔を必ず守る こと。
-
決められた量を超えて服用しても効果が強まるわけではなく、副作用のリスクだけが高まる。
-
薬の効果が切れる前に焦って追加で服用しない。
併用してはいけない薬
-
複数の解熱剤の重複(例:市販薬と処方薬の飲み合わせ)は過剰投与の原因に。
-
NSAIDsどうしを組み合わせると、胃腸障害や腎障害のリスクが高まる。
-
アルコールとの併用は肝臓への負担が増すため避ける。
-
既に他の薬を服用中の人は、必ず医師や薬剤師に相談すること。
子ども・高齢者の場合の注意点
-
子ども
-
体重に応じた投与量が決まっているため、必ず医師・薬剤師の指示に従う。
-
アスピリンはライ症候群の危険があるため、子どもには使用禁止。
-
-
高齢者
-
腎機能や肝機能が低下していることが多く、副作用が出やすい。
-
少量でも強く作用する場合があるため、自己判断せずに医師の指導を受ける。
-
ムヒのこども解熱鎮痛顆粒はこちら🔻
5. 解熱剤使用時の注意点

解熱剤は正しく使えばつらい症状を和らげてくれる一方、誤った使い方をすると体に負担をかけてしまうことがあります。ここでは使用時に特に気をつけたいポイントを解説します。
無理に熱を下げすぎない
発熱は体がウイルスや細菌と戦うための防御反応です。体温を無理に下げすぎると、かえって免疫の働きを妨げる可能性があります。解熱剤は「平熱に戻すため」ではなく、つらさを和らげて休養や水分補給をしやすくするために使うのが基本です。
過剰服用によるリスク
「熱が下がらないから」と短時間で何度も服用したり、複数の解熱剤を併用したりすると、肝臓や腎臓への負担、胃腸障害などを引き起こす危険があります。必ず 用量・服用間隔を守る ことが大切です。
体温の上がり下がりに一喜一憂しない
解熱剤を飲んでも、数時間で再び体温が上がることは珍しくありません。体は病原体と戦っているため、自然な経過と考えてよい場合が多いです。体温計の数字だけで判断せず、本人の体調や表情、食欲や水分摂取の様子を重視しましょう。
アレルギーや副作用の可能性
-
皮膚の発疹、かゆみ、呼吸困難 などが出た場合はアレルギー反応の可能性があります。すぐに服用を中止し、医療機関へ相談してください。
-
NSAIDsでは 胃痛や胃出血 のリスク、アセトアミノフェンでは 肝機能障害 のリスクが知られています。持病や体質によって副作用の出やすさは異なるため、初めて服用する薬は特に注意が必要です。
6. こんなときは医療機関へ

発熱は多くの場合、風邪や一時的な感染症などで自然に回復しますが、中には 早急な受診が必要なケース もあります。次のような症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診しましょう。
高熱が続くとき
-
38.5℃以上の高熱が 2〜3日以上続く
-
解熱剤を使ってもすぐに熱が戻る、またはほとんど下がらない
-
強い寒気や悪寒を繰り返す
こうした場合は、肺炎や尿路感染症など重い細菌感染症の可能性もあるため注意が必要です。
意識がもうろうとしているとき
-
受け答えがおかしい、反応が鈍い
-
強い倦怠感で起き上がれない
-
けいれんが起こる
このような場合は、ただの発熱ではなく脳炎や重度の感染症など、緊急性の高い状態の可能性があります。
乳幼児・高齢者・持病持ちの発熱
-
乳幼児(特に生後3か月未満) の発熱は、体力が少なく重症化しやすいため必ず受診が必要です。
-
高齢者 は免疫力が低下しており、肺炎や敗血症に進行するリスクがあります。
-
糖尿病・心疾患・腎疾患などの持病がある人 は発熱で病状が悪化する可能性があるため、早めに医師の診察を受けましょう。
発疹や強い頭痛・吐き気を伴うとき
-
発疹が体に広がっている
-
強い頭痛や嘔吐がある
-
首が硬直して動かせない
これらは髄膜炎や重度の感染症の兆候である可能性があり、早急な医療対応が必要です。
👉 発熱時は「数字」よりも「症状の重さ」で受診を判断することが大切です。上記のようなケースでは自己判断せず、速やかに医療機関を受診してください。
まとめ|発熱時の正しい対処と安心のためのポイント

発熱は体がウイルスや細菌と戦うための自然な防御反応であり、必ずしも無理に下げる必要はありません。大切なのは「焦らず、正しく対応すること」です。
-
体を休める・水分補給を徹底する:解熱剤だけに頼らず、体力の回復をサポートしましょう。
-
解熱剤は正しく使用する:用量を守り、必要なときにのみ使用することが安全につながります。
-
危険なサインを見逃さない:高熱が続く、意識がもうろうとする、乳幼児や高齢者の発熱などは、迷わず医療機関へ。
正しい知識を持つことで、不要な不安を減らし、発熱と上手に向き合えます。判断に迷うときは、自己判断せずに早めに医師の診察を受けることが安心への近道です。
熱さまシート 大人用 冷えピタはこちら🔻


