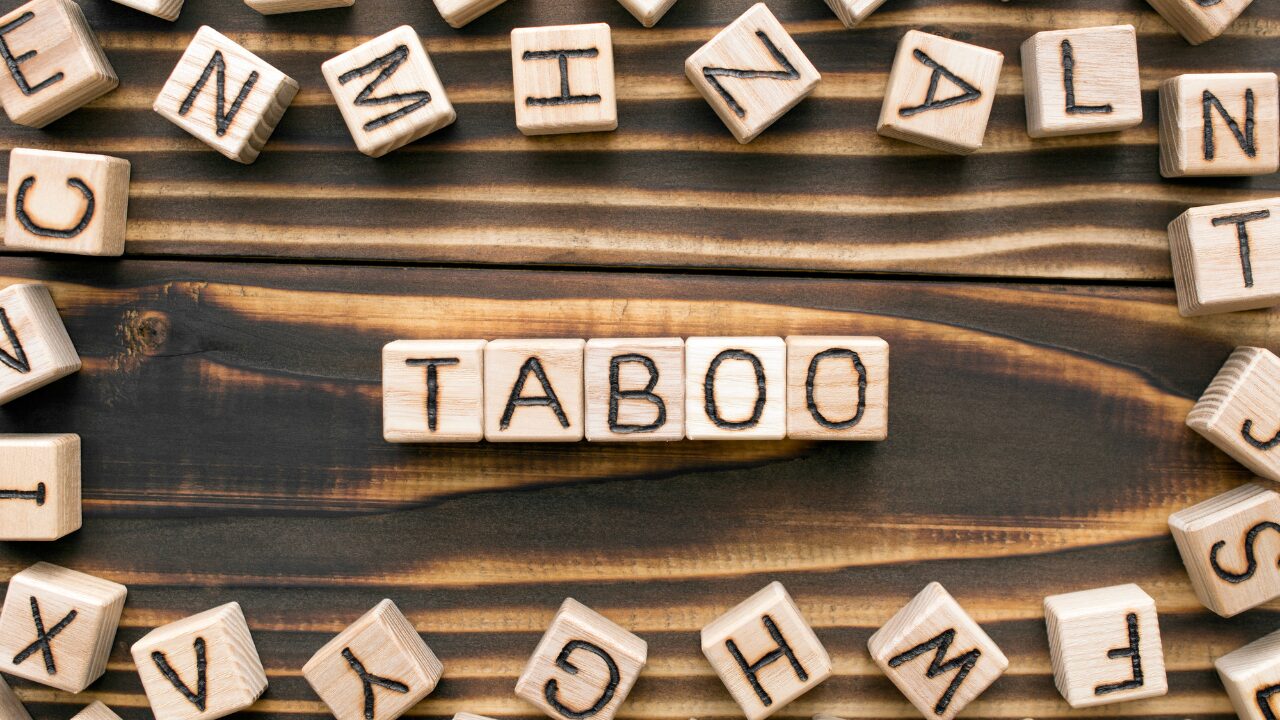
日本ではごく普通で美しい名前なのに、
海外では“変な意味”や“スラング”として誤解されてしまうことがあるのをご存じですか?
グローバル化が進む今、子どもの名づけやビジネスネームを考えるうえで、
「海外でどう受け取られるか」を意識するのは大切なポイントです。
この記事では、
海外で“変な意味”に聞こえてしまう日本の名前の実例や、
誤解される理由・避けるためのチェック法・それでも使いたいときの工夫まで、
国際社会で浮かない名づけのヒントをわかりやすく解説します。
知らなかった!日本では普通でも「海外ではNG」な名前がある理由
日本ではごく自然で美しい響きの名前でも、海外ではまったく違う意味に受け取られることがあります。
その原因は、文化や言語の違い、そして発音の偶然の一致によるもの。ここでは、なぜそんな「名前ギャップ」が生まれるのかを詳しく見ていきましょう。
文化や言語の違いで“偶然かぶる”意味がある
言葉はその国の文化や歴史の中で育まれるもの。
そのため、日本語ではポジティブな意味でも、他言語では全く異なるニュアンスを持つ場合があります。
たとえば、日本では女の子の名前として人気の「Nana(ナナ)」。
しかし英語圏では「おばあちゃん」を意味するスラングでもあり、海外では少し年配のイメージを持たれることもあります。
また、「Mio(ミオ)」という可愛らしい名前も、スペイン語では「mío=“私のもの”」という意味を持つため、恋人同士の呼びかけのように誤解されることもあります。
つまり、文化や言語の違いによって、「普通の名前」が海外では“別の意味”を連想させるのです。
発音・スペルが外国語の“スラング”になるケースも
もうひとつの理由が、発音やスペルが海外のスラング(俗語)と偶然一致してしまうことです。
例えば、「Rina(リナ)」は英語圏では問題ありませんが、スペイン語圏では「rina(リーナ)」が「ケンカ」や「争い」を意味する言葉として使われます。
また、「Kumi(クミ)」という名前は、英語圏のスラングで“下品な言葉”に近い発音になると指摘されることも。
このように、アルファベット表記にしたときの響きや読み方が、現地の俗語や侮辱語と重なることがあるのです。
名づけの段階では気づかなくても、海外で呼ばれた瞬間に「笑われた」「驚かれた」といった経験をする人も少なくありません。
海外在住者や留学生が困った実例も
実際に、海外在住の日本人が名前で苦労したケースはたくさんあります。
たとえば、海外留学中の女性が「Sari(サリ)」という名前を名乗ったところ、英語圏では「Sorry(ソーリー)」に聞こえてしまい、毎回「謝ってるの?」と笑われたという話があります。
また、ビジネスの場で「Maki(マキ)」という名前が「Monkey(モンキー)」に聞こえると言われた…という実例も。
こうしたトラブルは本人のせいではなく、“音の偶然”による誤解。
ですが、日常的に呼ばれる名前だからこそ、本人にとっては大きなストレスになることもあります。
国際化が進む今の時代、名前の響きや意味が海外でどう受け取られるかを意識することは、決して特別なことではありません。
「海外ではどう聞こえるのか?」を少し調べておくだけで、未来のトラブルを防ぐことができます。
実例でチェック!海外で「変な意味」になる日本の名前10選

ここでは実際に、海外で“思わぬ意味”を持ってしまう日本の名前を紹介します。
日本ではごく普通でも、海外では「笑われた」「気まずくなった」なんてことも。
国や言語によって、どんなふうに意味が変わるのかを見てみましょう。
① アメリカ・英語圏で誤解される名前
(例:Nana=スラングで「おばあちゃん」)
英語圏では、日本語の響きがスラングや日常表現に似ていることで誤解されるケースが多くあります。
たとえば、日本では可愛らしい印象の「Nana(ナナ)」。
しかし英語では「grandma(おばあちゃん)」の親しみ表現として“Nana”が使われるため、
「おばあちゃん?」と笑われたり、「変わった名前だね」と言われることがあるのです。
また、「May(メイ)」は英語の助動詞“may(〜かもしれない)”と同じスペルで、
文法的な意味として受け取られることもあります。
さらに、「Noa(ノア)」は英語では男性名(旧約聖書のノア)として使われるため、
性別を誤解されることも少なくありません。
このように、英語圏では“意味がある単語”と重なると、
ネイティブにとって違和感を持たれやすくなります。
② フランス・イタリアで笑われる名前
(例:Mika=「醜い」に近い発音)
ヨーロッパの言語では、日本語の響きが別の単語に似てしまうことが原因で、
意図せず「ネガティブな印象」になることがあります。
例えば、フランス語では「Mika(ミカ)」という音が“moche(モッシュ:醜い)”や
“micca(ミッカ:イタリア語で“まったく~ない”の意)”と似て聞こえるため、
人によってはネタにされることも。
また、「Saki(サキ)」という名前は、イタリア語では「sacchi(サッキ:袋)」を連想させ、
日常単語として軽く扱われてしまうことがあります。
さらに、「Rina(リナ)」はスペイン語では“riña(争い・けんか)”に近い発音で、
「ちょっと印象が強すぎる名前」と受け取られることもあるようです。
つまり、ヨーロッパでは響きの偶然一致で意味が変わるケースが多いのです。
③ 中国・韓国で意味が変わってしまう名前
アジア圏でも、発音や漢字の使い方の違いで“別の意味”になることがあります。
例えば、「Ai(アイ)」という名前。
日本では「愛」「藍」などポジティブな意味ですが、
中国語の発音では“哀(āi)=悲しい”を連想させる場合もあります。
また、「Mana(マナ)」は韓国語の「만아(マナ)」という言葉に似ており、
意味合いが異なることで不自然に聞こえることも。
「Kou(コウ)」も、発音によっては中国語で「狗(gǒu=犬)」に近く聞こえ、
現地では“軽い笑い”の対象になることがあるそうです。
漢字文化圏でも、同じ文字でも読み方・意味が異なるため、
海外生活を想定するなら音と意味の両方を確認するのが安心です。
④ 海外SNSでネタにされた日本の名前事例
近年は、TikTokやX(旧Twitter)などで、
「日本の名前が海外でどんなふうに聞こえるか」という投稿が話題になることも。
たとえば、
-
「Mio」が英語の“me, oh!”に聞こえて“自分を呼んでるみたい”と笑われた
-
「Sari」が“Sorry(ごめんね)”に聞こえて、会話が誤解された
-
「Kumi」が一部スラングと発音が似ているとSNSで拡散された
など、意図せず“ネタ化”されるケースも増えています。
こうした事例は笑い話で済むこともありますが、
中には本人がショックを受けて名前を省略したり、英語名を使うようになった人も。
SNS時代では、名前が世界中で共有されるリスクもあるため注意が必要です。
オプションコラム:
コラム:「外国人に変な笑い方をされた名前」SNSで話題になった例まとめ
実際に海外在住者や留学生のあいだでは、
「最初は笑われてショックだったけど、意味を知って笑い話にできた」
という声も多く見られます。
例として、
-
「Nana」→ “おばあちゃん” と呼ばれて最初は驚いたが、今では“親しみのあだ名”として受け入れている
-
「Mio」→ 英語圏の友人に意味を説明して“Cute name!”と褒められた
-
「Kumi」→ 英語圏では避けるニックネームを考えて対応
といったように、理解と工夫でポジティブに変えられるケースも。
名前の意味が違っても、「その背景を説明できること」自体が国際交流のきっかけになるのです。
なぜそんなことに?海外で“変な意味”に聞こえる理由

日本では美しく響く名前でも、外国語の音や意味と“偶然かぶる”ことで、まったく違う印象になることがあります。
これは決して悪意ではなく、言語の「音」「文化」「感情表現」の違いによるものです。
ここでは、なぜ日本の名前が海外で“変な意味”に聞こえてしまうのか、その仕組みを解説します。
音(発音)がスラングや俗語と似ているから
最も多い理由が、発音が現地のスラング(俗語)や日常語と似てしまうというものです。
たとえば、
-
「Kumi(クミ)」は英語の発音では一部の卑語に近く聞こえる
-
「Sari(サリ)」は英語の“Sorry(ごめんね)”に似て誤解される
-
「Rina(リナ)」はスペイン語の“riña(争い)”に近い発音
このように、名前そのものは日本語では美しい意味を持っていても、
外国語の発音体系に置き換えたときに“別の単語”と重なってしまうことがあるのです。
スラングは国や世代によっても意味が変わるため、
「昔は問題なかったけど、今はSNSで違う意味に使われている」
というケースも珍しくありません。
国際化が進む今は、Urban Dictionary(スラング辞典)などで事前チェックしておくと安心です。
ローマ字表記にしたときに誤読されやすい
次に多いのが、ローマ字表記にしたときの「読み間違い」です。
日本語では「まお」「なお」「れお」など、母音が多い柔らかい音の名前が人気ですが、
ローマ字にすると “Mao”“Nao”“Reo” などと書かれ、
英語圏ではまったく別の読み方をされることがあります。
たとえば、
-
「Nao」は英語話者に“Now(今)”と聞こえることがある
-
「Reo」は“Leo(レオ)”や“Ryo(リョウ)”と混同されやすい
-
「Mao」は“猫(Mao=中国語)”を連想させる
また、名前をアルファベットにしたとき、大文字・小文字の並びで別の単語に見えてしまうことも。
(例:「Misaki」→ “mi saki”と分けて読むとスペイン語風に聞こえる)
国際的に使う機会がある人は、英語圏での読み方・発音動画をチェックしておくとよいでしょう。
「かわいい響き」が海外では下ネタになることも
日本では「響きがかわいい」「女の子らしい」と人気の名前が、
海外では“性的なニュアンス”を含むスラングに似ているケースもあります。
たとえば、
-
「Puri(プリ)」や「Mimi(ミミ)」など、擬音的で可愛らしい名前は、
英語やフランス語で“ボディパーツ”や“子どもっぽい言い回し”を連想させることがある -
「Koko(ココ)」は英語圏では“Coco=スラング的な愛称”として使われることがあり、
文脈によってはからかわれる場合も
つまり、「かわいい響き」は日本語では褒め言葉でも、
海外では子どもっぽい・ふざけた印象を持たれることがあるのです。
ただし、全てがNGというわけではありません。
「Coco Chanel」や「Mimi Rogers」など、有名人の名前として定着している例もあるため、
大切なのは「意味を理解したうえで選ぶ」こと。
名前を決める際は、“響きのかわいさ”と“海外での印象”のバランスを取ることがポイントです。
まとめポイント
海外での誤解は、言語の違いによる“偶然”がほとんど。
けれど、その偶然を事前に知っておくことで、トラブルや誤解を避け、世界でも愛される名前を選ぶことができます。
名づけの最終チェックには、「発音・意味・表記」の3点を確認しておくのが理想です。
避けるためにできる!名づけ前の「海外チェック法」
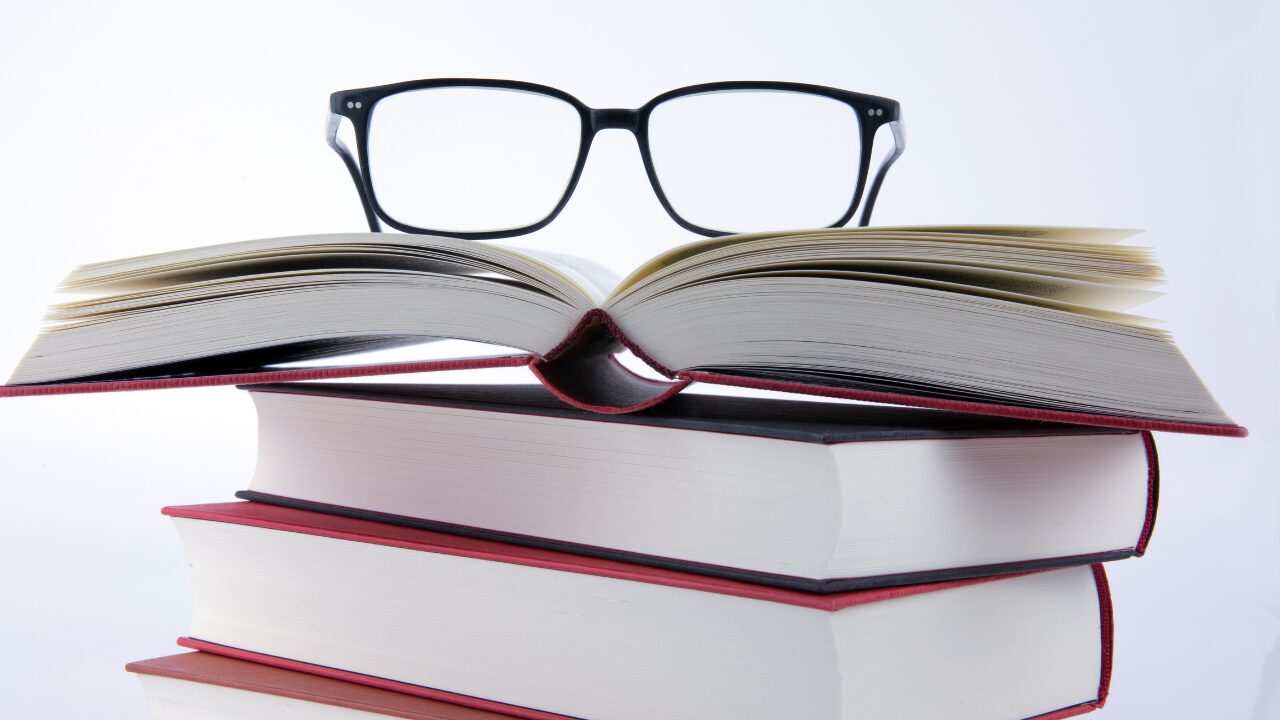
「海外ではどう聞こえるのか」を気にせず名づけをすると、
後になって“思わぬ意味”や“誤解”に気づいて後悔するケースも。
しかし、最近ではオンラインツールやSNSを使えば、自分で簡単に海外チェックができるようになっています。
ここでは、名づけの段階でやっておきたい具体的な確認方法を紹介します。
① Google翻訳・Urban Dictionaryで意味を調べる
まず基本となるのが、翻訳ツールやスラング辞典で意味を調べること。
Google翻訳では、名前を英語・フランス語・スペイン語などに入力して、どんな単語として認識されるかを確認します。
ただし、スラングや俗語は通常の辞書に出てこない場合もあるため、
英語圏の若者が使うネット辞典「Urban Dictionary(アーバンディクショナリー)」を活用するのがおすすめです。
例:
-
“Mika” → “Mean girl(意地悪な子)”といった意味が出てくることも
-
“Kumi” → 一部地域で卑語的ニュアンスが登録されている場合も
これらを確認することで、意図せぬ意味や発音の問題を早めに発見できます。
また、他の言語(スペイン語・中国語など)でも検索しておくと、より安心です。
② SNS検索(X・Instagram)で現地の反応を確認
翻訳ツールで意味を確認したら、次はSNS上で実際に使われている例を調べるのが効果的です。
X(旧Twitter)やInstagramの検索バーに「#名前」「”Name”」などを入力してみましょう。
英語やフランス語、スペイン語のタグを使うと、現地ユーザーの投稿が見られます。
たとえば、
-
「#Mio」で検索すると「飲料ブランド名(Mio Drink)」がヒットする
-
「#Nana」で「Grandma(おばあちゃん)」の写真が多数表示される
など、現地でどんな意味や印象で使われているかがリアルにわかります。
SNSはネイティブの感覚を知るのに最も便利なツール。
数分の検索で、「この名前は避けた方がいいかも」と判断できるケースもあります。
③ 海外在住者や外国人の意見を聞く
ツールやSNSだけでなく、実際に現地感覚を持つ人に聞くのもとても有効です。
たとえば、
-
海外在住の日本人ママ・パパに相談する(SNSや掲示板などで)
-
オンライン英会話や外国人の友人に名前を聞かせて反応をチェックする
このとき、「この名前を聞いたとき、何をイメージする?」と素直に聞くのがポイント。
意図せず“笑われる響き”や“スラングとのかぶり”を指摘してもらえることがあります。
実際、国際結婚家庭や海外在住者の間では、子どもの名前の“ダブルチェック”が常識化しています。
リアルな声を聞くことで、名づけに自信を持てるはずです。
④ 将来のグローバル展開(留学・海外勤務)を想定して考える
名づけは一生もの。
だからこそ、将来その名前が海外でどのように受け取られるかを視野に入れることが大切です。
特に最近は、
-
留学やワーキングホリデー
-
海外就職
-
国際結婚や外国企業との交流
など、グローバルな環境で活躍する日本人が増えています。
もしお子さんが将来、海外で名乗る可能性があるなら、
発音がしやすい・誤解されにくい名前を選ぶのがおすすめ。
例:
-
「Riku」→ “Rick(リック)”として自然に発音されやすい
-
「Ami」→ “Amy”や“Emmy”と同じ響きで親しみやすい
このように、“国際的に通用する名前”は将来の選択肢を広げる意味でも有利です。
“かわいさ”だけでなく、“世界でどう響くか”という視点を持っておくと安心です。
まとめポイント
海外チェックは、わずか数分のリサーチでできる“名づけの保険”。
Google翻訳・SNS・外国人の意見を組み合わせれば、世界で通じる名前を自信を持って選べます。
時代はすでにグローバル。名づけも「世界目線」で考える時代です。
それでも使いたい!海外でも通用させるコツ
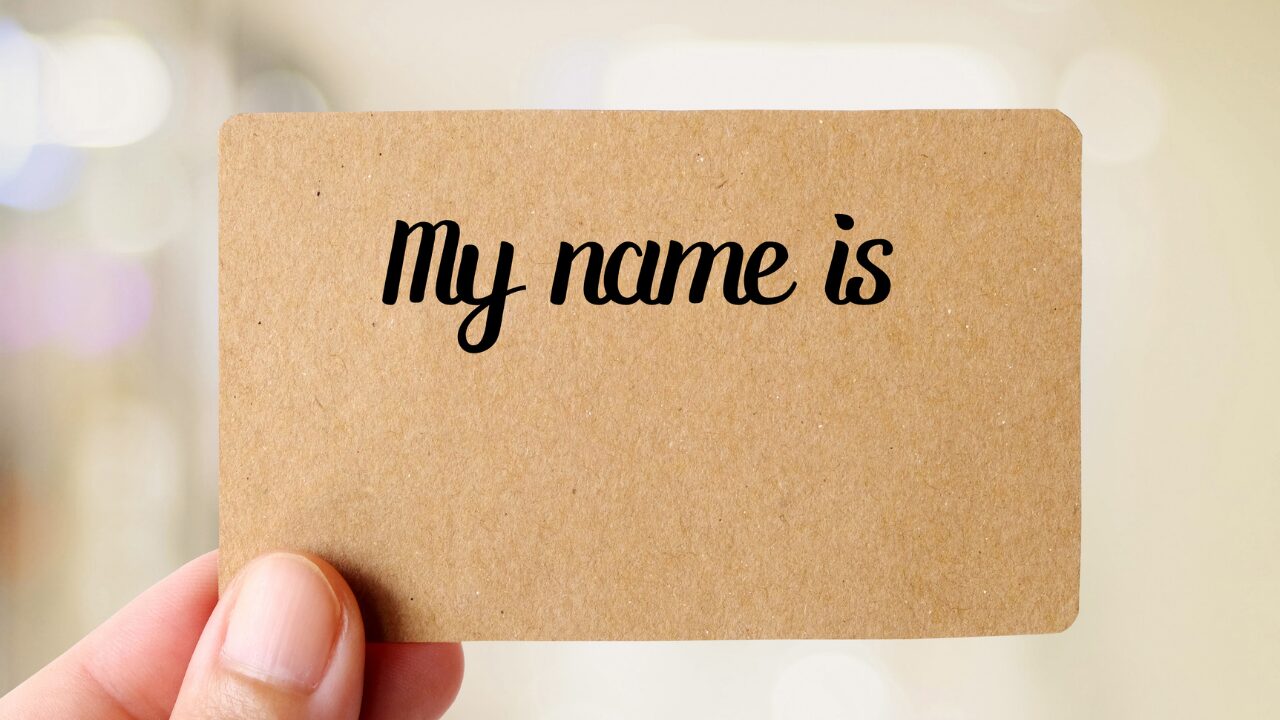
海外で誤解されやすい名前でも、「少しの工夫」で印象を変えることは可能です。
英語圏・ヨーロッパ・アジアなど、多様な文化の中でも親しまれるようにするには、
“響き・表記・意味”の3つを意識することが大切です。
英語表記やニックネームを工夫する
たとえば「Nana」という名前は英語では“おばあちゃん”の意味になりますが、
「Nanae」や「Nanami」といった正式名を使うことで印象を変えることができます。
また、「Yuki(ユキ)」のように“雪”を意味する日本語でも、
英語では男性名“Yuki=You key”と聞こえることもあるため、
「Yukie」「Yukinari」など少し長くして響きを変えるのもおすすめです。
ビジネスやSNSで使う際には、
-
「Mika → Mica(ミカ)」など綴りを少し変える
-
「Haruka → Haru」と短縮する
-
「Satoshi → Sato」と呼びやすくする
など、柔軟にアレンジして発音しやすくするのがコツです。
国際的に似た響きの“ポジティブな言葉”に寄せる
海外で通じやすい名前には、「ポジティブな印象を持つ響き」が共通しています。
たとえば:
-
「Ren」:英語圏では“蓮”と同時に“Renn(勇敢)”という響きに近く、好印象
-
「Kai」:ハワイ語で“海”を意味し、世界的にも人気のユニセックスネーム
-
「Sora」:スペイン語や英語では“空”を連想し、覚えやすく親しまれやすい
このように、“意味が美しい”かつ“国際的に心地よい発音”の名前を選ぶと、
海外でも自然に受け入れられます。
「日本らしさ」を活かした名づけにする
あえて日本的な美しさを強調するのも、ひとつの戦略です。
海外では「日本らしい響き」「和の意味」が魅力的に映ることがあります。
たとえば:
-
「Sakura(桜)」=春や自然の象徴として世界的に人気
-
「Hana(花)」=シンプルで発音しやすく、“花”のイメージが好印象
-
「Riku」「Aoi」「Noa」なども、ミニマルでグローバルな響きが支持されています
つまり、“日本での意味が美しく、かつ発音しやすい名前”は
国際社会でも“オリジナリティ”として通用するのです。
コラム:海外でも人気の日本人の名前ランキング
世界のSNSや留学データで人気の日本人名TOP3は以下の通り。
| 順位 | 名前 | 人気の理由 |
|---|---|---|
| 1位 | Sakura | 「桜=日本らしさの象徴」で覚えやすい |
| 2位 | Ren | 男女問わず使える、短く響きが良い |
| 3位 | Kai | ハワイ語・北欧語でも意味を持ち、国際的に好印象 |
海外で通じる名前=「意味・響き・発音の3拍子」がそろったもの。
名づけの段階で“世界の目”を意識することが、これからの時代のスタンダードです。
まとめ|「国際社会で浮かない名前」はこれからの常識

かつては「日本だけで使う名前」でも問題ありませんでしたが、
いまやSNS・留学・海外ビジネスなど、
誰もが“国際的な場”に立つ可能性のある時代です。
名前は一度つけたら一生付き合うもの。
だからこそ、“日本では素敵でも海外では誤解される”ような名前は、
名づけの段階でしっかりチェックしておくことが大切です。
名前は“世界でも自分を表す名刺”になる時代
いまの子どもたちは、将来SNSやオンラインを通じて
世界中の人とつながる可能性を持っています。
そのとき、自分の名前がどう発音され、どんな意味で受け取られるかは、
第一印象を左右する大きな要素になります。
「覚えやすく、誇りを持てる名前」は、
グローバル社会での“自分のブランド”のような存在です。
響きと意味、どちらも大切に選ぼう
日本語では美しい響きの名前でも、
海外では思わぬ意味やスラングと重なることがあります。
しかし、逆に「Ren(レン)」「Hana(ハナ)」などのように、
日本らしさ×国際的な響きを両立した名前もたくさんあります。
名づけでは、
-
日本語としての由来・意味の美しさ
-
海外での発音・イメージの良さ
の両方を意識することで、よりバランスの取れた名前を選ぶことができます。
知っておくことで、後悔しない名づけができる
「海外で変な意味になるかもしれない」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、
事前に知っておくことが最大の対策です。
Google翻訳やSNS検索、実際に外国人の意見を聞くなど、
少しのリサーチで“誤解されない名前”を選ぶことができます。
そして何より、
意味を理解し、意図を込めて名づけた名前は、
どこの国に行っても自信を持って名乗れる“世界で通用する名前”になります。
まとめポイント
名前は「国際社会でも自分を表す顔」
響きと意味の両面からチェックするのが新常識
情報を知っておけば、後悔しない名づけができる
これからの名づけトレンドは、
「日本らしさ × グローバル適応力」を意識すること。
世界のどこでも愛される名前を目指して、
あなたらしい“意味のある名づけ”をしていきましょう。


