
お腹がゴロゴロ鳴るのに、なかなかスッキリ出ない…。そんな“もどかしい”状態に悩んでいませんか?
実はこの症状、単なる便秘とは限りません。腸の動きが乱れたり、ガスが溜まっていたり、さらにはストレスが原因で腸の働きが低下しているケースもあります。
この記事では、医師監修のもと「お腹がゴロゴロするのに出ない」原因を徹底解説。腸内環境の整え方から、ストレスによる“腸の不調”をやわらげる具体的な改善法まで、今日からできる対策をご紹介します。
「お腹がゴロゴロするけど出ない」のはなぜ?
「お腹がゴロゴロ鳴っているのに、便が出ない…」という状況は、腸の働きが低下していたり、ガスが溜まっていたりするサインかもしれません。
音がしている=腸が動いている証拠ではありますが、“動きの質”が悪いと、排便までうまくつながらないことがあります。
腸が動いているのに便が出ない理由
お腹の「ゴロゴロ音」は、腸のぜん動運動によって内容物や空気が移動している音です。
しかし、腸の動きが不規則だったり、緊張してけいれん気味になっていると、**排便に必要なリズムが乱れて“動いているのに出ない”**状態になります。
とくに、
-
食生活の乱れ(脂っこいもの・糖質過多)
-
水分不足
-
睡眠不足やストレス
などが重なると、腸の蠕動が弱まり、便がうまく肛門方向へ進まなくなります。
💡対策ポイント
-
朝起きたら常温の水をコップ1杯飲む(腸のスイッチを入れる)
-
朝食を抜かない(胃腸反射で自然な便意を促す)
-
冷えを防ぐ(腹部を温めると腸の動きが活発に)
「ガスが溜まっている」「腸がけいれんしている」などの可能性
ゴロゴロ音の正体は、腸内ガスであることも多いです。
悪玉菌が増えると、未消化物が発酵してガスが多く発生し、それが腸内に滞ることで「ゴロゴロ」「張る」「出そうで出ない」といった違和感を感じます。
また、腸がストレスや冷えなどでけいれん状態になると、腸が部分的に収縮し、内容物やガスがスムーズに通らなくなります。
これも「お腹が鳴るけど出ない」典型的なパターンです。
💡対策ポイント
-
食物繊維を摂るときは「水溶性+不溶性」をバランスよく
(例:納豆+野菜スープなど) -
発酵食品(ヨーグルト・味噌・キムチなど)を毎日少しずつ
-
ガスが溜まって苦しい時は、軽く体をひねるストレッチでガス抜き
便秘や過敏性腸症候群(IBS)との関係
「お腹がゴロゴロするのに出ない」状態が続く人の中には、**便秘型や混合型の過敏性腸症候群(IBS)**が隠れているケースもあります。
IBSでは、ストレスや自律神経の乱れで腸が過敏になり、
-
腹部の違和感
-
ガスが多い
-
出ないのにトイレに行きたくなる
などの症状が起こります。
単なる一時的な便秘と違い、「精神的ストレス」や「緊張」でも腸が反応するのが特徴です。
💡対策ポイント
-
「出ない」ときに無理にいきまない(腸に負担)
-
腹式呼吸でリラックスしながらトイレに座る
-
ストレスが強いと感じる場合は、専門医に相談を
まとめ
お腹が鳴っているのに出ないのは、腸がサインを出している状態です。
腸を責めるよりも、「整える」視点で生活を見直すことが改善への第一歩。
次の章では、腸内環境を立て直すための食事・生活習慣を詳しく見ていきましょう。
腸内環境が乱れるとどうなる?
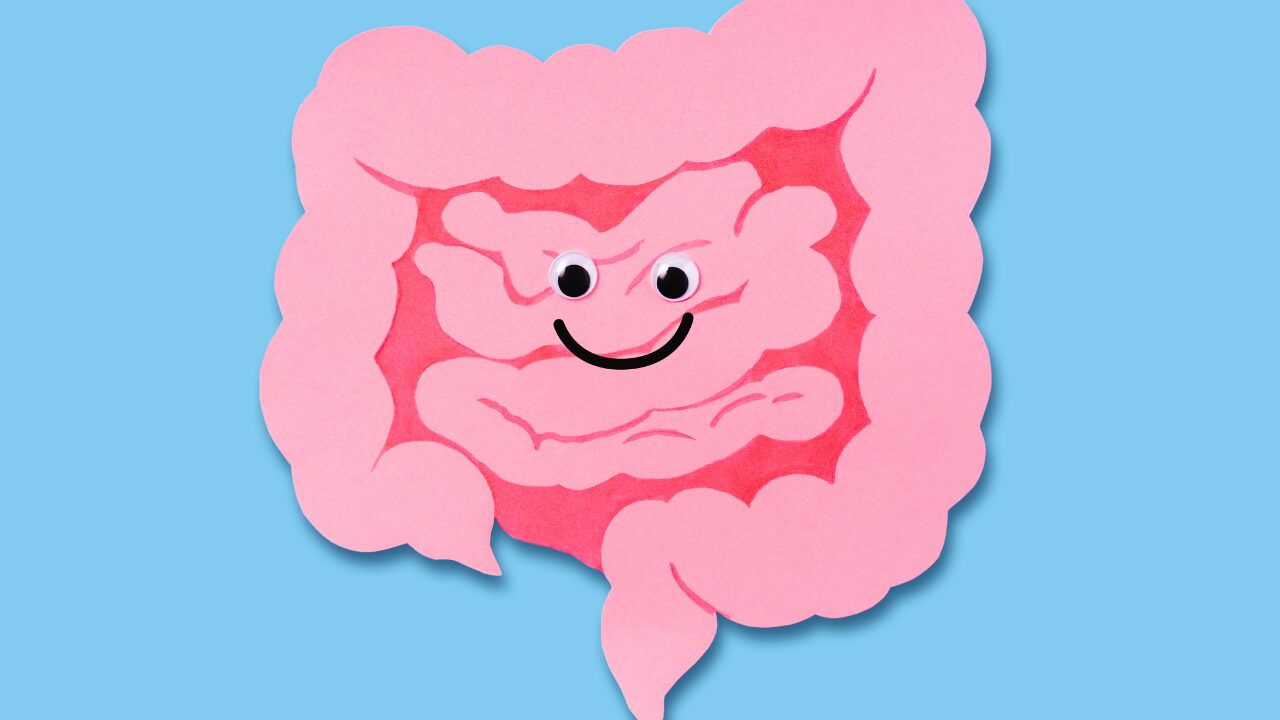
腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、心身の健康に深く関わっています。
腸内環境が乱れると、ガスが溜まりやすくなったり、排便リズムが乱れたりと、“出ないのにお腹が鳴る”不快な状態を引き起こします。
ここでは、腸内のバランスが崩れたときに起こる主な変化と、その対策を紹介します。
悪玉菌が優位になると“ガス過多”に
腸の中には、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3種類の菌がバランスを保っています。
しかし、脂っこい食事や甘いものの摂りすぎ、ストレスなどが続くと、悪玉菌が増えてしまいます。
悪玉菌が優勢になると、食べ物がうまく消化されずに発酵・腐敗が進み、ガスが多く発生します。これが「お腹がゴロゴロ」「張る」「ガスっぽい」と感じる原因です。
💡対策ポイント
-
善玉菌を増やす発酵食品を毎日摂る
(ヨーグルト、納豆、ぬか漬け、キムチなど) -
悪玉菌のエサになる動物性脂肪や糖質を控える
(揚げ物・菓子類・ジャンクフードなど) -
朝食後に軽く歩くことで腸の動きを刺激し、ガスの滞留を防ぐ
腸内フローラのバランスが乱れると排便リズムも崩れる
腸内には、約1000種類以上・100兆個もの細菌が棲みついています。これらが花畑のように群れを成している様子から「腸内フローラ」と呼ばれます。
このフローラのバランスが乱れると、腸のぜん動運動や便の水分調整がうまくいかなくなり、排便リズムが不安定になります。
便が硬くなったり、ガスが多くてスッキリ出ない状態が続くと、腸内に老廃物がたまり、さらに悪循環に。
特に女性はホルモンバランスの影響もあり、腸内環境が変化しやすいといわれています。
💡対策ポイント
-
水溶性食物繊維+発酵食品の組み合わせ
→ 例:オートミール+ヨーグルト、味噌汁+わかめ -
こまめな水分補給(1日1.5〜2L目安)で便を柔らかく保つ
-
朝・夜の「腸リズム」を一定にする(寝る時間・起きる時間を固定)
食生活や睡眠不足が腸の動きを鈍らせる
腸は自律神経の影響を強く受ける臓器です。
夜更かしや睡眠不足が続くと、交感神経が優位になり、腸の動きがストップしやすくなるため、朝の便意が起きにくくなります。
また、朝食を抜く生活や不規則な食事も腸のリズムを乱し、排便リズムが崩れる原因になります。
💡対策ポイント
-
夜は12時前に就寝、朝は同じ時間に起きるリズムを維持
-
夕食は寝る3時間前までに済ませる(腸の負担を軽減)
-
ストレスを和らげるリラックスタイムを作る(深呼吸・入浴・アロマなど)
まとめ
腸内環境の乱れは、“ガスが出ない・便が出ない”といった不調の根本原因です。
ポイントは、「腸内細菌を育てる」生活習慣をコツコツ続けること。
腸を整えることで、自然とお腹のゴロゴロや張りも改善していきます。
次の章では、ストレスが腸の動きをどう左右するのか、“腸脳相関”の仕組みを詳しく見ていきましょう。
ストレスと腸の関係|“腸脳相関”って?

お腹の調子が悪いと気分も落ち込み、反対にストレスが溜まると腸の動きが乱れる――。
そんな経験、ありませんか?
実はこれ、「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」と呼ばれる密接なつながりによるものです。
腸と脳は神経とホルモンを通じて常に情報をやり取りしており、ストレスの影響が腸にダイレクトに表れることがわかっています。
ストレスが自律神経を乱し、腸の働きに影響
人はストレスを感じると、無意識のうちに**交感神経(緊張モード)**が優位になります。
すると、腸の動きをコントロールする自律神経のバランスが崩れ、腸のぜん動運動がうまく働かなくなります。
結果、
-
腸の動きが弱くなり、便秘に
-
腸が過剰に反応して、下痢に
-
腹部の張り・ガス・ゴロゴロ音が増える
といったトラブルが起こります。
💡対策ポイント
-
深呼吸を1日数回意識的に行う(交感神経→副交感神経に切り替わる)
-
寝る前のスマホ・PCを控える(自律神経を鎮める)
-
「湯船につかる」時間を毎日10分でも確保(血流と腸の動きを促進)
「脳が緊張すると腸も緊張する」腸脳相関のメカニズム
腸は“第二の脳”とも呼ばれ、**脳と同じ神経伝達物質(セロトニンなど)**を多く持っています。
ストレスや不安を感じると、脳が「危険」と判断して腸に信号を送り、腸も緊張状態に。
その結果、腸の運動リズムが乱れ、ゴロゴロ・張り・腹痛が起こりやすくなるのです。
特に、ストレスを我慢しがちな人や、常に頭の中が忙しい人は、腸の緊張も続いてしまう傾向があります。
💡対策ポイント
-
「リラックスできる習慣」を意識的に持つ
(アロマ・音楽・軽いストレッチなど) -
腸マッサージや腹式呼吸で“腸の緊張”をゆるめる
-
セロトニンを増やす食事を意識(バナナ、発酵食品、魚など)
ストレス性の便秘・下痢を繰り返す人も
「お腹がゴロゴロするのに出ない」「下痢と便秘を交互に繰り返す」――
こうした症状が続く場合は、**ストレス性の過敏性腸症候群(IBS)**の可能性もあります。
これは、ストレスによって腸が過敏に反応し、便通やガスのコントロールが難しくなる状態です。
日常生活の中でストレスを避けることは難しいですが、“ストレスを感じたときにどう整えるか”を知っておくことが改善への第一歩です。
💡対策ポイント
-
「無理に出そうとしない」習慣をつける(トイレで焦らない)
-
腸にやさしい食事を心がける(温かいスープ・消化の良い食材)
-
ストレス管理を意識する(紙に気持ちを書く・深呼吸する)
💬もし症状が長期間続く場合は、消化器内科を受診し、腸の働きやストレス状態を専門的にチェックしてもらいましょう。
まとめ
腸は、あなたの「心の状態」をそのまま映す鏡。
ストレスを感じると脳が緊張し、腸も同じように固まってしまいます。
だからこそ、腸のケア=心のケア。
深呼吸やリラックス習慣を取り入れることで、ゴロゴロするお腹も、気持ちも少しずつ落ち着いていきます。
バンホーテンの腸活ココアはこちら🔻
「出ない…」を解消するためにできること

「お腹がゴロゴロ鳴っているのに出ない…」という状態を改善するには、
薬に頼る前に、腸のリズムを“自然に整える”生活習慣を身につけることが大切です。
腸は毎日少しずつ刺激を与えることで、徐々に本来の働きを取り戻します。
ここでは、今日からできるシンプルな3つの習慣を紹介します。
朝一杯の水+軽いストレッチで腸を目覚めさせる
朝は、腸が最も活発に動き出す時間帯。
起きてすぐに常温またはぬるめの水をコップ1杯飲むことで、胃腸が刺激され、「腸のスイッチ」が入ります。
さらに、軽いストレッチや深呼吸を組み合わせると、腸のぜん動運動が促進され、自然な便意が起こりやすくなります。
💡対策ポイント
-
寝起きに「コップ1杯(200ml)の水」をゆっくり飲む
-
腹部をひねるストレッチでガスや便をスムーズに動かす
-
トイレに行く時間を“毎朝同じタイミング”に固定する
👉 毎朝のルーティン化がカギ。1〜2週間で腸のリズムが整い始めます。
発酵食品・食物繊維で腸内環境を整える
腸内環境の改善には、「腸内細菌のエサ」になる食材をとることが不可欠です。
発酵食品は善玉菌を直接補い、食物繊維はそのエサとなって腸内フローラを整えてくれます。
この2つを組み合わせると、腸が元気に動き出し、ガスや便の滞りが軽減します。
💡対策ポイント
-
【発酵食品】ヨーグルト、納豆、味噌汁、キムチ、甘酒などを毎日少しずつ
-
【食物繊維】
-
水溶性(善玉菌を育てる)…オートミール、海藻、果物
-
不溶性(便のかさを増やす)…野菜、豆類、きのこ
-
-
両方を“朝食または昼食”に取り入れるとより効果的
👉 例:
・朝食=ヨーグルト+バナナ+オートミール
・昼食=味噌汁+サラダ+玄米
※注意:不溶性繊維ばかり摂ると逆にお腹が張る場合もあるため、バランスが大切です。
スマホを見ながら食事しない・早食いをやめる
意外ですが、「ながら食べ」や「早食い」も腸の働きを鈍らせる原因です。
スマホやテレビを見ながら食事をすると、“食べている感覚”が鈍り、咀嚼回数が減少。
その結果、消化が追いつかずガスが溜まりやすくなり、「ゴロゴロするのに出ない」状態につながります。
また、早食いは交感神経を刺激して腸の動きを止めてしまうため、“ゆっくり食べる”ことも立派な腸活です。
💡対策ポイント
-
食事中はスマホを手放し、「食べること」に集中
-
1口につき20〜30回は噛む(唾液と混ざることで消化促進)
-
“ながら食べ”をやめるだけでも、腹部の張りが軽減されることも
👉 食事を「味わう」ことで、副交感神経が優位になり、腸の動きが自然と整います。
まとめ
腸を整えるために必要なのは、特別なサプリや薬ではなく「毎日の小さな習慣」。
・朝の一杯の水
・腸が喜ぶ食事
・“ながら食べ”をしない丁寧な食事時間
この3つを意識するだけで、腸は確実に変わっていきます。
次の章では、ストレスを和らげて腸をさらに元気にする「心の整え方」について見ていきましょう。
ストレス対策で“腸”も変わる!

ストレスは腸の動きやガスの発生、便通に大きく影響します。
心をほぐすことは、同時に“腸を整える第一歩”。
ここでは、日常の中でできるストレスケアの具体的な方法を紹介します。
リラックスできる時間を意識的に作る
ストレスを感じたとき、腸は「緊張モード」に入り、動きが鈍くなります。
意識的に“何もしない時間”を持つことが、腸にとっての休息になります。
・お気に入りの音楽を聴く
・ゆっくりお茶を飲む
・自然の中を散歩する
といった「ほっとできる時間」を1日10分でも取り入れてみましょう。
短時間でも、自律神経のバランスが整いやすくなります。
深呼吸・入浴・軽い運動で自律神経を整える
浅い呼吸は、体を常に“緊張状態”にします。
ゆっくりと深呼吸をするだけでも、副交感神経が優位になり、腸がリラックスして動きやすくなります。
また、ぬるめのお風呂に10〜15分つかる、軽く体を動かすことも効果的。
特にウォーキングやヨガは、腸のぜん動を促すサポートにもなります。
「頑張らない運動」が“ゆる腸活”のポイントです。
完璧を目指さない“ゆる腸ケア”が長続きのコツ
「毎日腸活しなきゃ」と思うほど、プレッシャーになって逆効果です。
ストレスを減らすためには、“できる範囲でゆるく続ける”ことが大切。
・できる日はヨーグルトを食べる
・無理のない時間に寝る
・疲れた日は何もしない勇気を持つ
といった“ゆるい積み重ね”で、腸の調子はじわじわと安定していきます。
腸にとっての理想は「頑張らないこと」。
気持ちを緩めることで、自然とお腹も落ち着いていきます。
💡 まとめ
ストレスケアは、腸ケアそのもの。
「心をゆるめる=腸が動く」と意識して、
今日から“リラックス時間”を少しだけ増やしてみましょう。
まとめ|「ゴロゴロするのに出ない」は腸と心のSOSかも

お腹がゴロゴロするのに便が出ない――。
それは「腸の不調」だけでなく、「心の緊張」が影響しているサインかもしれません。
腸と心は密接に繋がっており、どちらかが乱れるともう一方にも不調が表れやすくなります。
腸内環境が乱れると、ガスが過剰に発生したり、便がスムーズに動かなくなったりします。
同時に、ストレスによる自律神経の乱れも腸の働きを抑えてしまい、「出したいのに出ない」状態に。
つまり、腸と心の両方をいたわることが、根本的な改善のカギです。
たとえば、
・朝一杯の水で腸を“起こす”
・発酵食品や食物繊維を意識する
・ゆっくり深呼吸して心を落ち着ける
そんな小さな行動の積み重ねが、腸のリズムを取り戻す助けになります。
「今日は出ないな」と感じた日は、焦らずに“体からのメッセージ”を受け取る日。
無理に出そうとせず、腸を休ませ、心をほぐす時間を持ってみましょう。
腸も心もゆるんだとき、自然と“すっきり”は訪れます。


