
小説やイラストなどの創作活動をしていると、SNSや同人界隈でよく耳にする独特の言葉=「創作クラスタ語」。
「供養」「地雷」「解釈違い」など、一見すると意味が分かりにくい用語も多いですが、実は創作仲間と交流するうえで欠かせない共通言語です。
この記事では、作品制作・交流・二次創作・スラング といったジャンル別に、よく使われる創作クラスタ語をまとめました。
初心者からベテランまで、「創作語」を理解して使いこなせば、あなたの創作ライフがもっと楽しく、広がりのあるものになります。
そもそも「創作クラスタ語」って何?
創作クラスタとは?小説・イラスト好きが集まるコミュニティ
「創作クラスタ」とは、Twitter(現X)やPixivなどのSNS・創作投稿サイトに集まる 小説・イラストを中心に創作活動をしている人たちのグループ を指します。
同じ趣味やジャンルを共有する仲間同士で交流し、作品を公開したり感想を伝え合ったりすることで、独自の文化が形成されてきました。
特にSNS上では「#創作クラスタ」などのタグを使って自分の作品や活動を発信する人も多く、広義では 創作好きが集まる“界隈”全体 を意味します。
ネット発の独自言語=クラスタ語の特徴
創作クラスタ内では、やり取りの中で自然に生まれた 独特の言葉(スラングや略語) が数多く使われています。
これがいわゆる「創作クラスタ語」です。
-
例:
-
「ネタ帳」=アイデアをストックしておくメモ
-
「供養」=ボツ案や未完成のアイデアを公開すること
-
「地雷」=自分が苦手とする表現や設定
-
こうした言葉は、外の人にはわかりにくい場合もありますが、クラスタ内では 一言で状況や感情を共有できる便利な合言葉 になっています。
また、SNSでの短文投稿に適した 省略表現や比喩的な言い回し が多いのも特徴です。
なぜ創作界隈で用語が生まれるのか?
創作クラスタ語が多く生まれる背景には、いくつかの理由があります。
-
共感を共有する文化
小説・イラストを制作する過程や苦労は、一般的な日常では理解されにくい部分があります。用語を作ることで、同じ体験を持つ人同士が共感しやすくなります。 -
効率的なコミュニケーション
「プロット」「キャラ崩壊」「供養」などの言葉は、説明を省いて一言で状況を伝えられるため、SNSの短文文化と相性が抜群です。 -
コミュニティの一体感
専門用語を共有することで「同じ仲間」という認識が強まり、創作仲間とのつながりや居心地の良さを感じられるのも大きな要因です。
つまり創作クラスタ語は、 作品を作る人たちのリアルな体験や感情から自然に生まれ、コミュニティの絆を強める役割 を果たしていると言えます。
創作クラスタ語・用語集【ジャンル別まとめ】

創作クラスタ語にはさまざまな種類があり、使われる場面によってニュアンスも異なります。ここでは 「作品制作系」「交流系」「二次創作系」「スラング系」 の4つに分けて代表的な用語を解説します。
【作品制作系】小説・イラスト執筆で使う用語
小説やイラストを実際に「作る」過程で生まれた用語です。制作の苦労や進行状況を共有する時によく使われます。
-
プロット:作品のあらすじや骨組みをまとめた設計図。
-
設定厨(せっていちゅう):細かい設定を作り込みすぎる人、あるいはその傾向。
-
キャラ崩壊:本来の性格から外れた言動をキャラクターにさせてしまうこと。
-
供養:完成に至らなかったアイデアや没ネタを公開すること。
-
筆が乗る/筆が止まる:制作がスムーズに進む、あるいは全く進まない状態を表す比喩。
👉 創作活動の“あるある”を共有する言葉が多いのが特徴です。
【交流系】SNSやイベントで使われるクラスタ語
創作クラスタはSNSでの交流が中心のため、発信やコメントのやり取りに関連する用語も豊富です。
-
反応:いいね・リプライ・ブクマなど作品に対するアクション全般。
-
感想ツリー:SNSで作品感想を連続投稿すること。
-
拡散希望:作品や告知をより多くの人に見てもらうための表現。
-
地雷:自分が苦手とする要素や設定。事前に共有されることもある。
-
壁打ち:交流よりも作品投稿を中心に活動するスタイル。
👉 「見てもらいたい」「伝えたい」気持ちがこもった言葉が多く、SNS文化と直結しています。
【二次創作系】同人文化や推し活に関する用語
二次創作や同人界隈で生まれた言葉も、創作クラスタ語として広く使われています。
-
カプ(CP):キャラクター同士の関係性(カップリング)。
-
推し:最も応援しているキャラクターや作者。
-
尊い:推しや作品に強く心を動かされた時の表現。
-
解釈違い:自分のイメージと異なる表現・描写。
-
沼:ハマり込んで抜け出せない作品やキャラへの熱中状態。
👉 ファン活動の熱量を示す用語が多く、仲間同士で盛り上がるときによく使われます。
【スラング系】ネタ・ジョークとして広まった用語
ユーモアや共感を生む「ネタ」系のクラスタ語も人気です。
-
筆圧が強い:感情のこもった表現や激しい筆致を称える言葉。
-
死んだ(尊死):推しや作品に感情が追いつかず言葉を失う状態。
-
供給過多:公式やファンからの新情報・作品が多すぎて追えないこと。
-
エアプ:プレイや体験をしていないのに語る人(主にゲーム系)。
-
無限に読める/見れる:作品やキャラへの愛情を誇張する表現。
👉 ネタとして笑い合うことで、クラスタ内の一体感がさらに深まります。
ポイント
創作クラスタ語はジャンルごとに役割が異なりますが、どれも 「仲間同士で効率よく共感し合う」ために生まれた言葉 です。
正しく理解して使うことで、創作活動や交流がもっとスムーズになり、界隈の楽しさを倍増させてくれます。
創作クラスタ語を使うときの注意点
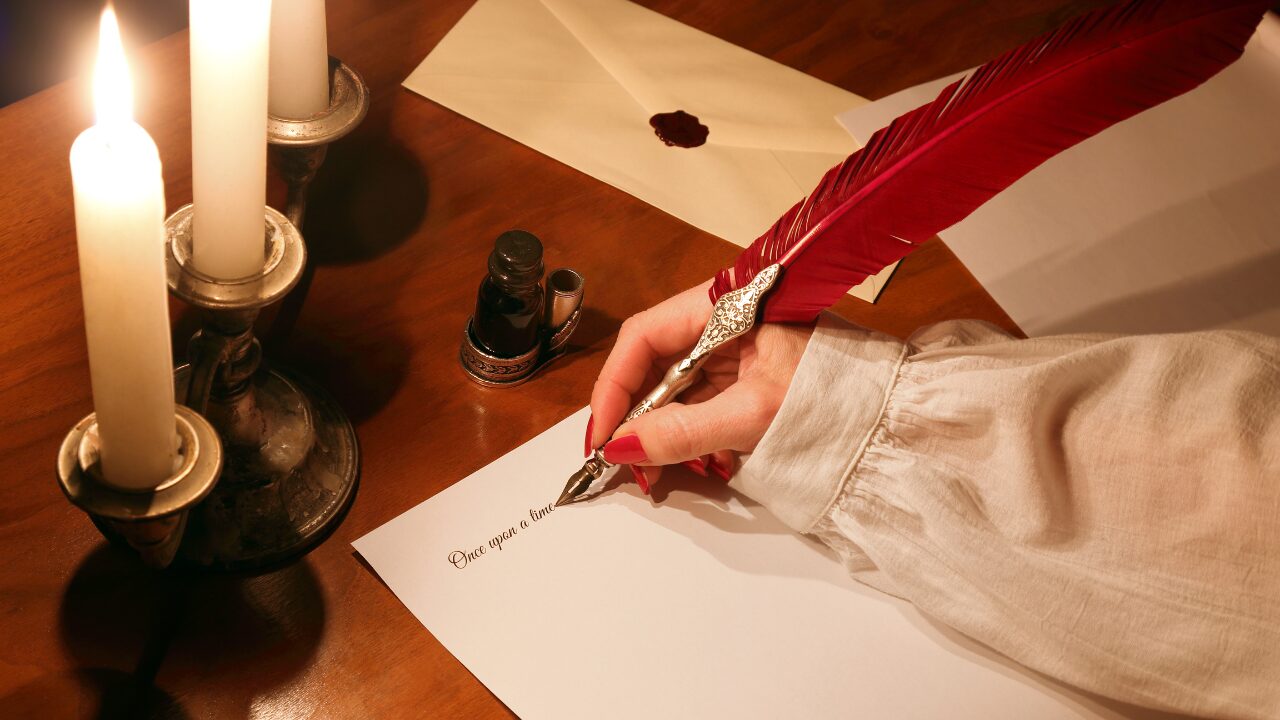
創作クラスタ語は仲間内での共通言語として便利ですが、使い方を誤ると相手に伝わらなかったり、思わぬ誤解を生むこともあります。ここでは、知っておきたい注意点をまとめました。
用語を知らない人には通じないことも
創作クラスタ語はあくまで 界隈内のスラング です。そのため、
-
一般的な友人や家族
-
創作活動に馴染みのない人
-
初めて交流する相手
には伝わらない可能性があります。
たとえば「供養」や「地雷」などは、創作クラスタ内では定着している言葉ですが、知らない人には全く違う意味に受け取られることも。
👉 初対面の相手や広い層に向けて発信する場合は、 専門用語を避けるか補足説明を添える のが安心です。
誤用・解釈違いでトラブルになるケース
創作クラスタ語は感覚的に使われることが多いため、人によって解釈が異なる場合があります。
-
「地雷」 → 「絶対に避けたいもの」と強く捉える人もいれば、「ちょっと苦手」程度の意味で使う人も。
-
「解釈違い」 → 批判ではなく「自分とは違う」というニュアンスで使う人もいれば、否定的に受け取る人も。
こうした言葉を不用意に使うと、相手を傷つけたり、炎上につながるリスクもあります。
👉 特にセンシティブな用語は、 相手の使い方を観察してから合わせる のが安全です。
場面に応じた使い分けのコツ
創作クラスタ語は、場面に応じて上手に使い分けることで便利なツールになります。
-
仲間内やSNS限定:略語やスラングを積極的に活用して親近感を深める
-
公式の場や初対面の人との交流:誤解を避けるために一般的な表現に置き換える
-
ブログや創作紹介文など外向けの文章:用語を使う場合は「(=意味)」と補足を入れる
👉 つまり「誰に向けて発信しているか」を意識すれば、クラスタ語はトラブル防止どころか 交流を円滑にする武器 になります。
💡まとめると:
-
クラスタ語は便利だが 通じる相手を選ぶ
-
人によってニュアンスが違うので 誤用に注意
-
場面ごとに使い分け ることで安全かつ楽しく活用できる
創作活動がもっと楽しくなる!用語を活かすコツ

創作クラスタ語は単なるスラングではなく、うまく活用すれば創作活動をより楽しく、仲間との交流をスムーズにしてくれる“潤滑油”のような存在です。ここでは、クラスタ語を上手に活かすためのコツを紹介します。
クラスタ語で交流がスムーズに
創作クラスタ語は、同じ趣味を持つ人同士の距離を一気に縮めてくれる効果があります。
-
共通の用語を使うことで「同じ界隈の人」だとすぐに分かる
-
コメントや感想にクラスタ語を交えると、親近感や共感を伝えやすい
-
「供養しました」「解釈違いかも」など、一言で状況や気持ちを簡潔に共有できる
👉 言葉の“省略”ではなく“共感の合図”として使うことで、自然に交流が広がります。
SNSでの発信力アップに繋がる
SNSでは短文でのやり取りが基本のため、クラスタ語は発信力を高める強い味方になります。
-
検索タグやハッシュタグと相性が良い:「#創作クラスタ」「#供養」など
-
トレンド感のある言葉を取り入れると拡散されやすい
-
投稿のタイトルや一言コメントにクラスタ語を使うと、同好の士が見つけやすい
👉 ただし、外向け発信では知らない人への配慮も必要。 クラスタ語+補足説明 を意識すれば、幅広い読者にも届きやすくなります。
仲間との共感・一体感を深める
クラスタ語は、仲間との「あるある」を共有できる魔法のツールです。
-
「筆が止まった…」「供給過多で死んだ」 などの言葉で制作の悩みや喜びを共有
-
用語をきっかけに会話が広がり、創作のモチベーションも上がる
-
専門用語を理解していることで「自分はこのコミュニティの一員」という安心感を得られる
👉 言葉を共有することで、ただ作品を作るだけでなく 仲間と創作を楽しむ“場”が広がる のがクラスタ語の大きな魅力です。
💡まとめると:
-
クラスタ語は「交流のきっかけ」になる
-
SNSでの発信に役立ち、ファンや仲間を見つけやすくなる
-
共通言語を通じて仲間意識が深まり、創作活動がもっと楽しくなる
まとめ|創作クラスタ語を理解して創作ライフをもっと楽しもう
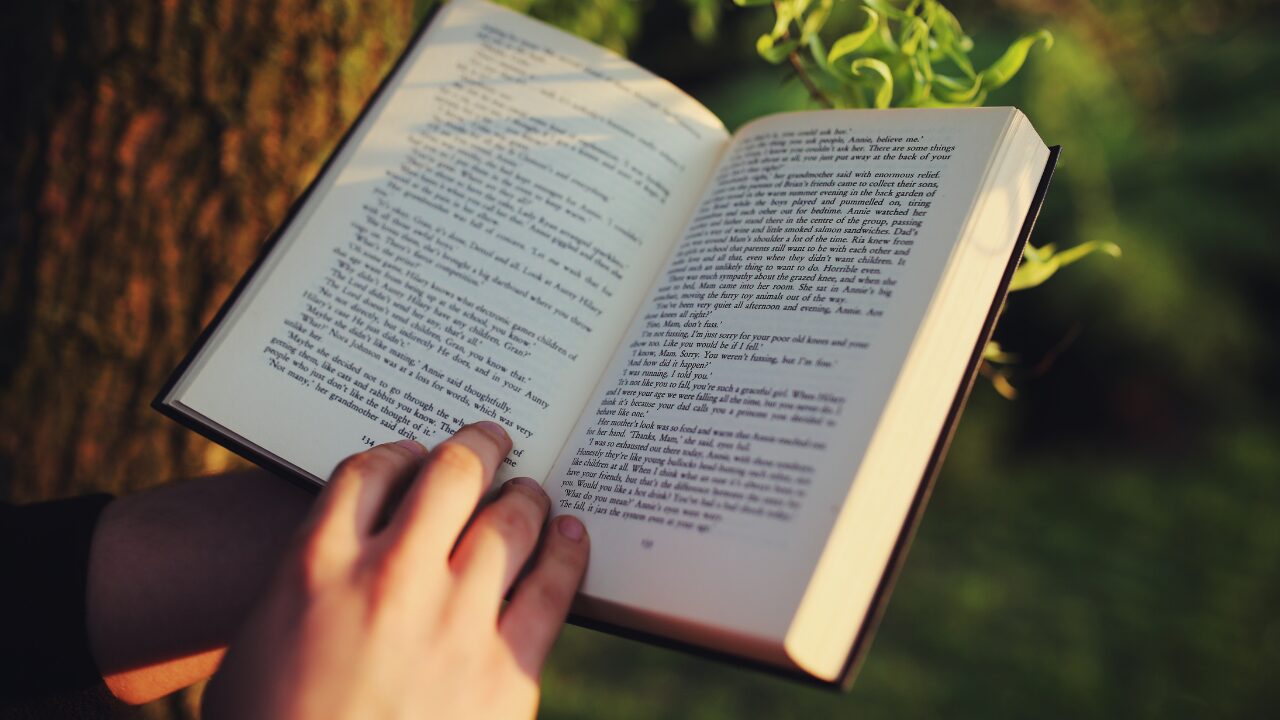
創作クラスタ語は、ただのスラングや略語ではなく、創作界隈で活動する人たちが作品を語り合い、仲間とつながるために自然と生まれた文化の一部です。正しく理解して使うことで、創作活動はさらに豊かで楽しいものになります。
言葉を知れば界隈の文化がもっとわかる
クラスタ語を理解することは、創作界隈の文化を深く知ることにつながります。
-
用語の背景には、創作の悩み・喜び・情熱 が詰まっている
-
言葉を知ることで、SNSやイベントでの会話もスムーズになる
-
「あ、これはあの気持ちを表してるんだ」と理解できることで、作品や仲間への共感も広がる
👉 言葉を知ることは、単なる知識以上に 「創作をもっと楽しむためのパスポート」 になります。
無理に使わず「楽しむ」気持ちが大事
ただし、クラスタ語は「必ず使わなければならない」ものではありません。
-
知らなくても創作はできるし、楽しめる
-
無理に背伸びして使うと誤解やトラブルの原因になることも
-
大切なのは「言葉を通じて創作を楽しむ」気持ち
👉 クラスタ語はあくまで 仲間と楽しむための“遊び心”。自分に合う言葉を選んで、自然に取り入れるのが一番です。
💡最終的に:
-
クラスタ語を知れば、創作界隈の文化や空気感がぐっとわかる
-
使う・使わないは自由。大事なのは 創作を楽しみ続けること
-
言葉を味方にして、自分らしい創作ライフを楽しもう!


