
高校・大学受験の世界では、受験生同士や予備校、SNSなどで使われる“受験語”が数多く存在します。
「A判定」「ボーダー」「赤本」「滑り止め」など、一見わかりにくい言葉も、受験を有利に進めるためには理解しておきたい重要なキーワードです。
この記事では、受験語の意味や使い方をわかりやすく整理し、効率的な覚え方や親・先生が知っておくべきポイントまで徹底解説します。
受験語とは?
受験生の間で使われる“独特の言葉”
受験シーズンになると、受験生の間では独特の「受験語」が飛び交います。これは、試験の形式や学習方法を表すだけでなく、仲間内のスラングとして使われるものも多いのが特徴です。たとえば「滑り止め」(第一志望に落ちた場合を想定して受ける安全校)や「浪人」(一度受験に失敗して翌年に再挑戦すること)といった言葉は、日常会話ではあまり使われませんが、受験生にとっては当たり前のように通じる言葉です。
こうした受験語は、短い言葉で状況を表現できるため、効率的に情報交換をするうえで便利です。しかし初めて聞く人にとっては意味が分かりにくく、誤解を招くこともあります。受験語を正しく理解しておくことで、情報収集や受験生同士のコミュニケーションがスムーズになります。
入試情報サイト・SNSでよく目にする用語
受験語は、受験生同士の会話だけでなく、入試関連サイトやSNSでも頻繁に登場します。特にTwitter(現X)やInstagramでは「#受験垢」と呼ばれるアカウントがあり、そこでのやり取りには専門的な略語が多く使われています。
たとえば:
-
「共テ」 … 大学入学共通テストの略。
-
「赤本」 … 過去問題集(教学社の赤表紙シリーズ)。
-
「ボーダー」 … 合格可能性が高いとされる最低ライン。
-
「併願校」 … 第一志望以外に同時に受験する学校。
これらは受験に関する記事やブログでも普通に使われるため、受験情報を調べる際には理解しておくことが大切です。知らないまま読むと内容が正しく伝わらず、誤った解釈をしてしまう可能性もあります。
つまり、受験語を知ることは単に“受験生の会話に追いつく”ためだけでなく、入試情報を正しく理解するためにも欠かせないスキルなのです。
高校・大学受験でよく使われる受験用語一覧
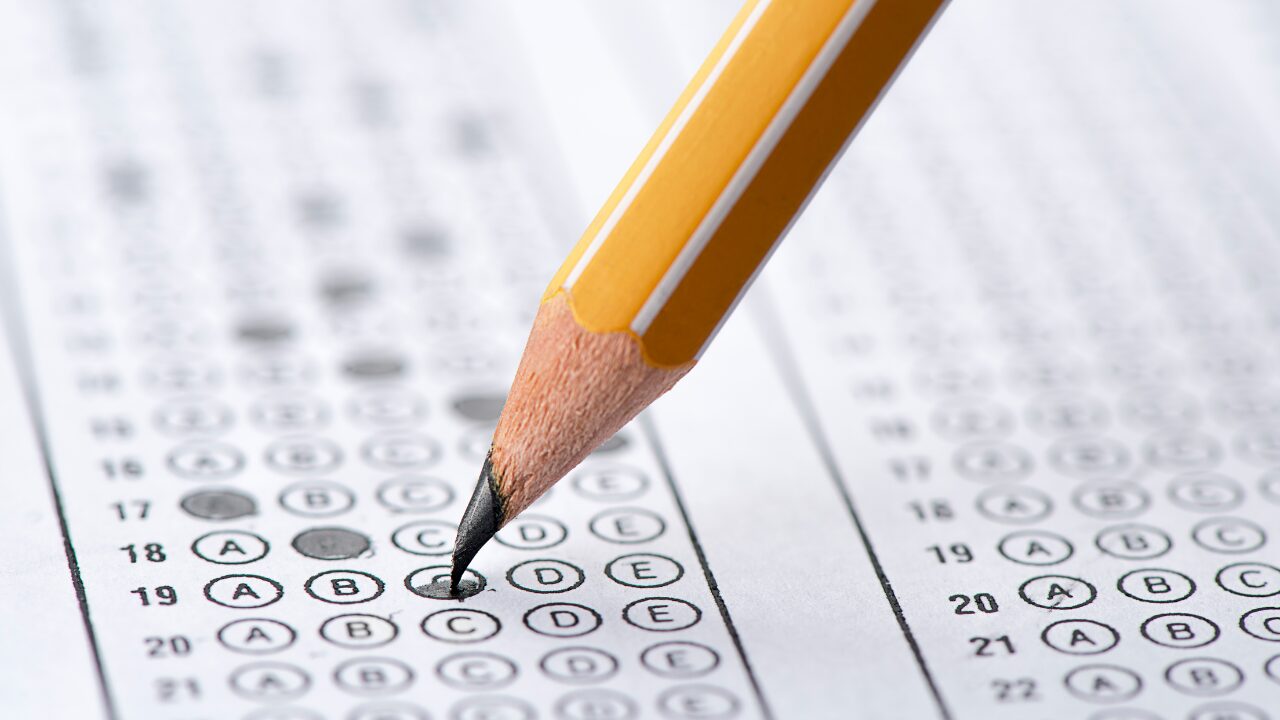
試験形式・日程に関する用語(例:前期・後期、共通テスト)
受験には独特のスケジュールや形式があり、それを示す用語が多く存在します。
-
共通テスト:大学入学共通テスト。国公立大学の受験に必須、私立大学でも利用される。
-
前期・後期:国公立大学の入試日程区分。前期は合格者が多く、後期は狭き門。
-
指定校推薦/総合型選抜(AO):学力試験以外の要素(学校推薦・面接・小論文など)で合否を決める方式。
-
一般入試:もっとも標準的な筆記試験形式。
日程や方式を理解しておくことで、無駄なく受験計画を立てられます。
合否判定・偏差値に関する用語(例:ボーダーライン、A判定)
模試や予備校の情報では、合否の可能性を示すための専門用語が使われます。
-
ボーダーライン:合格可能性が高いとされる最低点ライン。
-
A判定/B判定:模試の合格可能性を示す指標。A判定=合格可能性80%以上、B判定=60%程度とされることが多い。
-
偏差値:模試や学校レベルを数値化した指標。受験校選びの目安になる。
-
安全圏/チャレンジ校:合格可能性が高い志望校/合格は難しいが挑戦する志望校。
これらの用語を理解しておくと、模試結果の解釈や志望校選びがぐっと分かりやすくなります。
受験勉強に関する用語(例:赤本、過去問演習、共テ対策)
勉強法や教材を指す受験語も多くあります。
-
赤本:教学社が出版する大学別過去問題集。表紙が赤いことからの俗称。
-
過去問演習:志望校の過去問題を解き、出題傾向に慣れる勉強法。
-
共テ対策:大学入学共通テストを想定した学習方法。時間配分や形式に慣れることが重要。
-
基礎固め/仕上げ:勉強の進行度を表す言葉。基礎知識の定着から、試験直前の総合演習までの段階を指す。
受験生同士の会話でも「赤本やった?」「今は仕上げ中」といった形で自然に使われます。
受験生のスラングやネット用語(例:滑り止め、浪人、併願校)
正式な入試用語ではなく、受験生の間で生まれたスラングも数多く存在します。
-
滑り止め:第一志望が不合格でも合格できるように受けておく学校。
-
浪人:高校卒業後に合格できず、翌年に再挑戦すること。
-
併願校:第一志望と並行して受ける大学や高校。安全校からチャレンジ校まで幅広い。
-
受験垢:SNS上で受験勉強の進捗や悩みを共有する専用アカウント。
これらは非公式ながら受験生のリアルな感情を反映しており、仲間内でのコミュニケーションに欠かせません。
受験語はどうやって覚える?効率的な覚え方
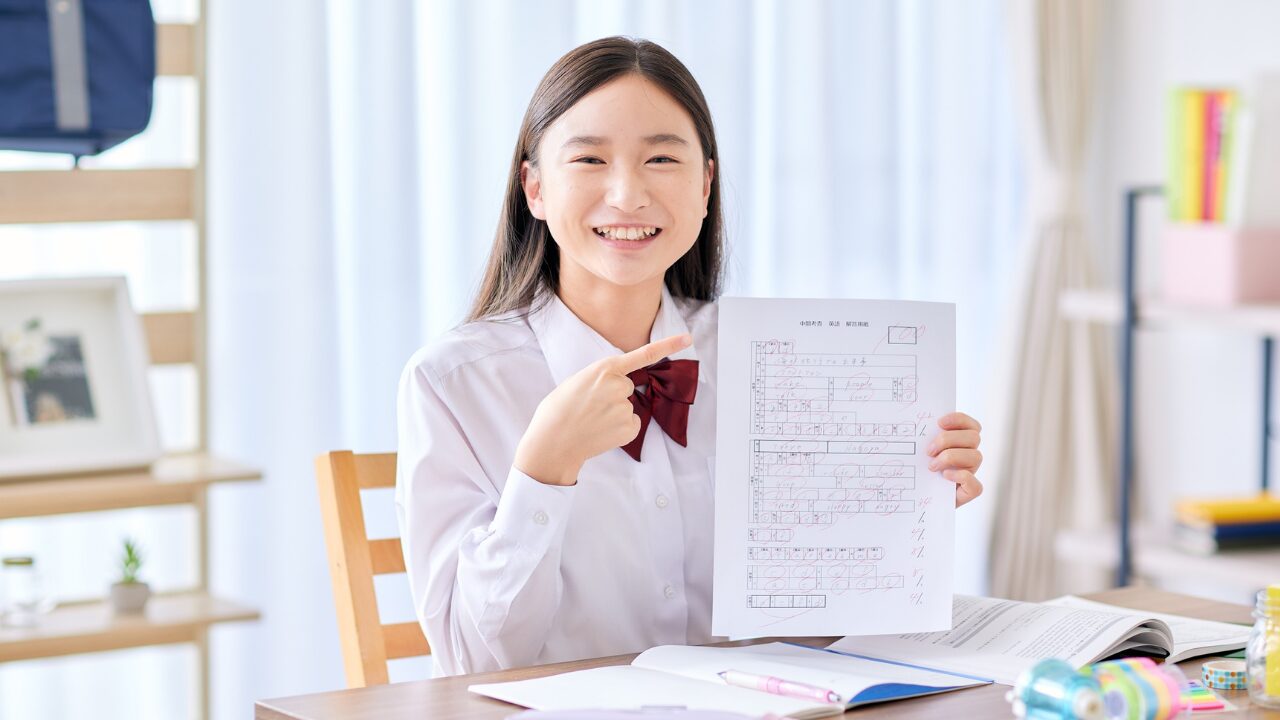
カテゴリーごとにまとめて覚える
受験語は数が多いため、バラバラに覚えると混乱しやすいもの。効率よく覚えるには「カテゴリー分け」が効果的です。
たとえば、
-
試験形式に関する用語(共通テスト、前期・後期、推薦入試)
-
合否判定に関する用語(A判定、ボーダー、偏差値)
-
勉強・教材に関する用語(赤本、過去問、模試)
-
スラング系用語(滑り止め、浪人、併願校)
といった具合にジャンルごとに整理して覚えると、知識が関連付けられ、記憶に定着しやすくなります。
SNSや予備校サイトを活用する
受験語は参考書だけでなく、SNSや予備校の公式サイトで触れることができます。特にTwitter(現X)の「受験垢」やYouTubeの勉強系チャンネルでは、最新の受験語が日常的に使われています。
また、駿台や河合塾などの予備校サイトでは「用語解説」ページや模試関連の説明が充実しており、信頼できる情報源としておすすめです。公式サイトで意味を確認しつつ、SNSで実際の使われ方をチェックすると、自然と覚えられます。
友達同士でクイズ形式にしてみる
暗記を「遊び感覚」に変えると、ストレスなく学べます。たとえば、友達と一緒に「受験語クイズ」を作ってみましょう。
-
例:「A判定って合格可能性は何%くらい?」「滑り止めの意味は?」
-
例:「共テって正式名称は?」
こうしたやり取りを通じて、言葉の意味を確認し合えば自然と記憶に残ります。また、勉強仲間との会話の中で繰り返し出てくることで、定着率がさらにアップします。
親や先生も知っておきたい受験語

受験生との会話をスムーズにするために
受験語は、受験生にとって日常的な言葉ですが、大人には馴染みが薄いものも多くあります。たとえば「赤本」「共テ」「ボーダー」といった言葉を理解していないと、受験生の話を聞いても意味が伝わらず、会話がすれ違ってしまうことも。
親や先生が受験語を知っておけば、受験生が抱えている不安や悩みをスムーズに共有できるようになります。
-
「模試でB判定だったんだ」と言われても意味を理解できれば、適切に励ますことができる。
-
「併願校を決めなきゃ」と言われても、進路相談に具体的に乗れる。
つまり、受験語を知ることは“受験生との共通言語を持つこと”につながり、安心感を与える効果もあります。
誤解を防ぎ、正しく情報をサポートする
受験語は便利な一方で、誤解されやすい表現も多いです。例えば「滑り止め」という言葉は受験生の間では普通に使われますが、親が聞くと「失礼な表現では?」と感じることもあります。また「A判定だから安心」と思い込みすぎると、実際には合格を保証するものではないため危険です。
親や先生が用語の正しい意味を理解していれば、こうした誤解を防ぎ、冷静にサポートすることができます。
-
誤った情報に惑わされず、正しい受験計画を立てやすくなる。
-
子どもの焦りやプレッシャーに対して、客観的なアドバイスができる。
-
必要な情報源(予備校サイト・大学公式情報)に誘導してあげられる。
受験は家族や学校全体で取り組む大きなイベントです。親や先生も「受験語」を理解することで、受験生をより安心して支えられる環境が整います。
まとめ|受験語を知れば、情報収集・対策もスムーズに!

用語理解は“受験のリテラシー”
受験語は単なる専門用語ではなく、受験を効率よく進めるための“情報リテラシー”です。模試の判定や入試方式、勉強法に関する言葉を正しく理解できれば、志望校の情報をスムーズに読み取り、自分に必要な対策を素早く選択できます。
逆に、用語を知らないと情報収集のスピードが落ちたり、誤解して不安を抱えたりする原因にもなります。つまり「受験語を理解すること=受験を有利に進める力を持つこと」と言えます。
無理なく自然に覚えていこう
受験語を一度にすべて暗記しようとする必要はありません。日常の勉強や会話、SNSのやり取りの中で少しずつ触れ、自然に覚えていけば十分です。
-
カテゴリーごとに整理する
-
SNSや予備校サイトで実際の使い方をチェックする
-
友達や先生との会話で繰り返し使ってみる
こうした工夫を重ねることで、無理なく身についていきます。用語が理解できるようになれば、受験に向けた行動がよりスムーズになり、精神的な余裕にもつながります。
受験戦略・勉強法の体系書はこちら🔻


