
会話の中でつい「ちなみに」を多用していませんか?
便利なつなぎ言葉ではありますが、使いすぎると「話が脱線してる」「知識をひけらかしてる」といった印象を与えてしまうこともあります。
この記事では、「ちなみに」を自然に使いこなすためのコツや、言い換え表現、実践トレーニング方法までをやさしく解説。
今日から“脱・ちなみに依存”で、伝わる&心地いい会話を目指しましょう。
なぜ「ちなみに」を使いすぎてしまうのか?
「ちなみに」という言葉は、話をつなげるときにとても便利な表現です。
だからこそ、意識せず何度も口から出てしまうことがあります。
けれど使いすぎると、話の流れが散らかって聞き手が疲れてしまうことも。
ここでは、「つい“ちなみに”が増えてしまう」理由をやさしく整理してみましょう。
「つなぎ言葉」として便利だからこそ多用しがち
「ちなみに」は、前の話題に軽く関連づけながら別の情報を足すときに使える便利な言葉。
たとえば「ちなみに昨日〜」や「ちなみに〇〇って知ってる?」のように、自然に会話をつなげられます。
ただし、その“便利さ”が落とし穴でもあります。
話す内容を整理する前に、反射的に「ちなみに」と言ってしまうと、話題が散らかりやすくなります。
つまり、「つなぎの言葉」として頼りすぎてしまうことで、会話全体が“寄り道だらけ”に感じられてしまうのです。
話の構成を整える前に「ちなみに」でつなげるクセがある人は、
一度「この話題、本当に前の内容とつながってるかな?」と立ち止まってみるとよいでしょう。
沈黙が怖くて、つい埋め合わせに使ってしまう
会話の途中で沈黙が生まれると、「何か話さなきゃ」と焦ってしまう人も多いでしょう。
そんなとき、「ちなみに〜」で新しい話題を出すことで“間”を埋めようとすることがあります。
でも、沈黙は決して悪いものではありません。
聞き手が考えていたり、話を整理している時間であることも多いのです。
それを「気まずい沈黙」と感じて急いで言葉を継ぎ足すと、
結果的に会話が浅くなったり、相手の集中が途切れてしまうことも。
“間を怖がらない”という意識を持つだけで、自然なテンポが戻ります。
焦らず一呼吸おく習慣をつけることで、「ちなみに」が減り、言葉に落ち着きが生まれます。
「丁寧に話そう」という意識が裏目に出ることも
「会話を丁寧に続けよう」「相手に気を遣おう」という思いから、
話をつなげるために「ちなみに」を多く使ってしまう人もいます。
たとえば、相手の関心を広げようとして「ちなみに〇〇もありますよ」と補足を続けるケース。
その気遣い自体はとても素晴らしいことですが、
“補足が多すぎる=情報量が多くてまとまりがない”と感じられることもあります。
大切なのは、「相手が今、何を求めているか」を感じ取ること。
丁寧さは「情報量」ではなく、「わかりやすさ」で伝わります。
「ちなみに」を使う代わりに、いったん話を区切ってから「もし興味があれば〜」と添えるだけでも、
より自然で思いやりのある印象に変わります。
✏️まとめ
-
「ちなみに」は便利だからこそ、無意識に増えやすい
-
沈黙を怖がるほど「つなぎ言葉」に頼りやすくなる
-
“丁寧さ”を伝えるには、量よりも整理と間が大切
「ちなみに」の使いすぎがもたらす印象とは?

「ちなみに」は、情報を補足したり話を広げたりするときに便利な言葉です。
しかし、あまりに頻繁に使うと、聞き手には“意図しない印象”を与えてしまうことがあります。
自分では丁寧に説明しているつもりでも、相手には「話がまとまっていない」「何が言いたいのか分からない」と感じられることも。
ここでは、「ちなみに」を多用したときに起こりやすい印象のズレを見ていきましょう。
話が脱線しているように感じられる
「ちなみに」は、本来“話題を少し外して補足する”ための言葉です。
そのため、1つの会話の中で何度も使うと、話がどんどん脇道にそれていくように聞こえてしまいます。
たとえば、
「ちなみに昨日〜」「ちなみにそれで思い出したんだけど〜」「ちなみに〜もあるよ」
と続くと、聞き手はどこがメインの話題だったか分からなくなってしまうのです。
結果、「この人の話はまとまりがないな」「結局何を言いたいんだろう?」と感じられてしまうことも。
対策ポイント:
話す前に「この話題で一番伝えたいことは何か?」を一度整理しておきましょう。
補足を入れるときは、「ちなみに」ではなく「補足すると」「もう少し詳しく言うと」など、
“本題の延長線上”を示す言葉に置き換えると、流れが途切れにくくなります。
話の流れが途切れ、聞き手が混乱する
「ちなみに」は、話の“接続”をゆるやかに変える言葉です。
つまり、ひとつ間違えると「会話の方向転換」と受け取られやすいのが特徴。
そのため多用すると、聞き手は「今の話は終わったの?」「別の話に変わったの?」と混乱してしまいます。
会話の流れが途切れると、聞き手は集中力を失いがちになります。
それは「興味がない」からではなく、脳が“次の流れをつかめない”からです。
対策ポイント:
話をつなげたいときは、
-
「そういえば」「一方で」「話を戻すと」
など、“今の話と関係があることを明示する言葉”を使うとスムーズです。
また、無理に言葉でつなげようとせず、
短い間(ま)を入れるだけでも、聞き手が流れを理解する時間を取れます。
“つなぐよりも、整理する”意識が、自然な会話づくりの鍵です。
知識を披露しているように誤解されることも
「ちなみに」は、“ちょっとした豆知識を添える”ような響きを持っています。
そのため、話の中で何度も出てくると、
聞き手によっては「知識を披露している」「少し上から話している」と感じてしまう場合があります。
もちろん、意図は全くそんなことではないでしょう。
けれど、人によっては「へえ、そうなんだ…(少し距離を感じる)」と受け取られてしまうこともあるのです。
対策ポイント:
「ちなみに〜」の代わりに、
-
「そういえば前に聞いたんだけど…」
-
「ちょっと余談だけど…」
-
「もし参考になれば…」
など、相手の関心を尊重するクッション言葉に置き換えると柔らかい印象になります。
また、知識を補足するときは、“教える”よりも“共有する”意識で。
たとえば「私も最近知ったんだけど〜」と添えるだけで、グッと親しみが増します。
✏️まとめ
-
「ちなみに」を多用すると、話が“脇道”に見える
-
接続が曖昧になり、聞き手の集中が途切れやすくなる
-
意図せず「上から目線」に誤解されることもある
言葉でつなぐより、“流れを整える”意識を。
それだけで、会話の自然さと印象がぐっと良くなります。
自然な会話にするためのコツ

「ちなみに」を減らそうと思っても、いざ会話になるとつい口から出てしまう——。
そんな人は多いものです。
大切なのは、“言葉を減らす”ことではなく、“自然に伝える流れを作る”こと。
ここでは、「ちなみに」に頼らず、聞きやすく伝わる話し方をつくる3つのコツをご紹介します。
「ちなみに」を“言い換える”意識を持つ
「ちなみに」は便利な一方で、使いすぎると話が単調になりやすい言葉。
まずは、“別の言葉でもつなげる”という意識を持つだけで、会話がグッと自然になります。
たとえばこんな言い換えができます:
| シーン | 「ちなみに」を使わない言い換え例 |
|---|---|
| 軽く話題を変えるとき | 「そういえば」「ところで」 |
| 比較・補足をしたいとき | 「一方で」「反対に」「もう少し言うと」 |
| 話題をやわらかく切り替えるとき | 「少し話が変わるけど」「余談だけど」 |
これらの言葉は、「ちなみに」と同じように話をつなげながらも、
“どんな方向に話が動くのか”を明確に伝えられるのがポイントです。
また、文章にする際は「ちなみに」を一度削って読んでみると、
意外とスムーズに流れることもあります。
“なくても通じる言葉”であることに気づけるでしょう。
文と文の“つながり”を意識して話す
自然な会話の鍵は、“言葉”ではなく“流れ”にあります。
「ちなみに」を使いすぎてしまう人の多くは、
実は話の内容を整理する前に口を開いていることが多いのです。
たとえば、
「Aについて話していたのに、いきなりBの話になってしまった」
という場面では、聞き手が“話の橋渡し”を見失ってしまいます。
対策ポイント:
話す前に「今の話題 → 次の話題」の“関係性”を一瞬だけ意識しましょう。
頭の中で「なぜそれを話すのか?」を確認するだけで、自然なつながりが生まれます。
具体的には、こんな一文を加えるのがおすすめです:
-
「それで思い出したんだけど〜」
-
「少し関連する話なんだけど〜」
-
「同じようなことで言うと〜」
このひと手間で、聞き手は「話が続いている」と感じ、スムーズに受け取ることができます。
“言葉の橋”を意識して架けることで、「ちなみに」に頼らずとも流れるような会話ができます。
「間(ま)」を怖がらず、沈黙も味方にする
多くの人が「ちなみに」を多用してしまう背景には、
沈黙を埋めなければいけないという焦りがあります。
けれど、会話の“間(ま)”は悪いものではありません。
むしろ、聞き手が内容を整理したり、あなたの言葉を咀嚼する大切な時間です。
無理に話を継ぎ足すよりも、
一呼吸おいてから話すほうが、落ち着いた印象を与え、聞き手も安心して耳を傾けられます。
実践法:
-
話の途中で「ちなみに」と言いそうになったら、2秒だけ黙ってみる
-
深呼吸をして“次に何を話すか”を頭の中で整える
-
沈黙を「空白」ではなく「余韻」として受け取る
会話はキャッチボール。
投げ続けるより、相手の反応を待つ時間があるほうが、心地よいテンポになります。
“間を味方にする”ことで、「ちなみに」がなくても自然に話がつながっていくはずです。
✏️まとめ
-
「ちなみに」は他の表現でも十分代用できる
-
話の“つながり”を意識すると、自然な流れが生まれる
-
沈黙を怖がらず、会話に“余白”を作ることで印象がよくなる
「言葉でつなぐ」より、「間と流れでつなぐ」。
それが、“脱・ちなみに依存”の第一歩です。
「ちなみに」の上手な使い方とは?
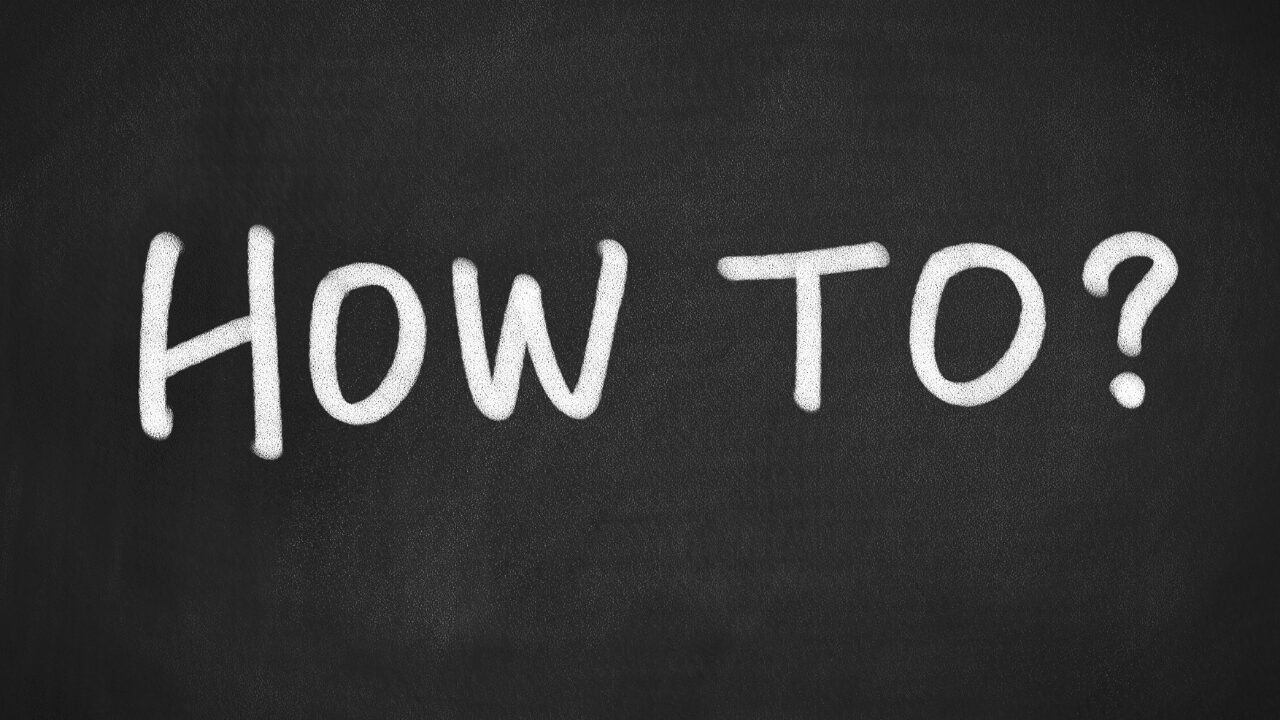
「ちなみに」は、決して悪い言葉ではありません。
むしろ、使いどころさえ見極めれば、会話をやわらかく、親しみやすくしてくれる表現です。
大切なのは、「いつ・どんな目的で使うか」。
ここでは、“自然に聞こえる『ちなみに』の使い方”を3つのポイントで見ていきましょう。
話題を“やわらかく切り替える”ときに使う
会話の中で、「今の話題を少し変えたい」と思う場面はありますよね。
そんなとき、「ちなみに」はとても便利な“クッション言葉”になります。
たとえば:
「この前の映画、すごくよかったね。ちなみに、次の作品も同じ監督らしいよ。」
このように、“関連性はあるけれど新しい話題”へ移るときに使うと、
聞き手はスムーズに流れを受け取ることができます。
逆に、全く関係のない話に使うと、唐突さが強まり「え、急に?」と感じられることも。
「前の話題から自然に切り替える」ためのやわらかな橋渡しとして使うのがコツです。
使い方のコツ:
-
「Aの話 → Aに関連するBの話」へ移るときに使う
-
本題を終えたあと、“会話を軽く続けたい”ときに使う
-
相手の集中を途切れさせないよう、声のトーンをやや落として入れる
“話題転換の合図”として上手に使えば、会話が穏やかでテンポよく感じられます。
「前の話題と軽くつながっている」ときにだけ使う
「ちなみに」は、本来“補足”や“関連情報”を示す接続詞です。
つまり、前の話と少しでも関係があるときにこそ、本来の力を発揮します。
たとえば:
「旅行の話」で「ちなみに、その地域って〇〇も有名だよね」
→ OK:テーマが同じ「旅行・地域情報」の延長線上。
一方で、
「仕事の話」をしていて「ちなみに、昨日映画見たんだけど〜」
→ NG:つながりが薄く、話が急に飛んで聞き手が置いてけぼりになります。
対策ポイント:
-
「前の話題と関係ある?」と一瞬確認してから使う
-
無理に“ちなみに”でつなげず、「少し話は変わるけど」と正直に言っても◎
-
「ちなみに」を使う=“まだ本題の延長”という意識を持つ
つまり、「ちなみに」は“関連性のある寄り道”には最適ですが、“突然の方向転換”には不向きなのです。
話題が軽くつながっているときだけ、やさしく添えるように使うと自然に聞こえます。
多用せず“1会話につき1回程度”を目安に
「ちなみに」は万能に見えますが、あまりに何度も出てくると、会話が単調に感じられてしまいます。
“1会話につき1回”を目安にするだけで、言葉にメリハリが生まれ、聞き手の印象も格段に良くなります。
こんな意識を持つと◎:
-
まずは1回使ったら、「次は別の言い方でつなごう」と意識する
-
同じ相手との会話の中で「ちなみに」が2回以上出たら、一度リセット
-
「ちなみに」を入れたくなったら、“一呼吸おく”
「ちなみに」はスパイスのようなもの。
少し加えると味が深まりますが、入れすぎると風味がぼやけてしまいます。
“ここぞというときに1回”——それが、自然で印象のいい使い方です。
✏️まとめ
-
「ちなみに」は、話題をやわらかく切り替えるときに使う
-
前の話題との関連性があるときだけ活かす
-
多用せず1会話1回を目安に、“スパイス”として添える
「ちなみに」は、減らすのではなく、“選んで使う”言葉。
上手に使えば、会話に知的さと親しみが加わります。
日常で実践できる!「ちなみに」対策トレーニング
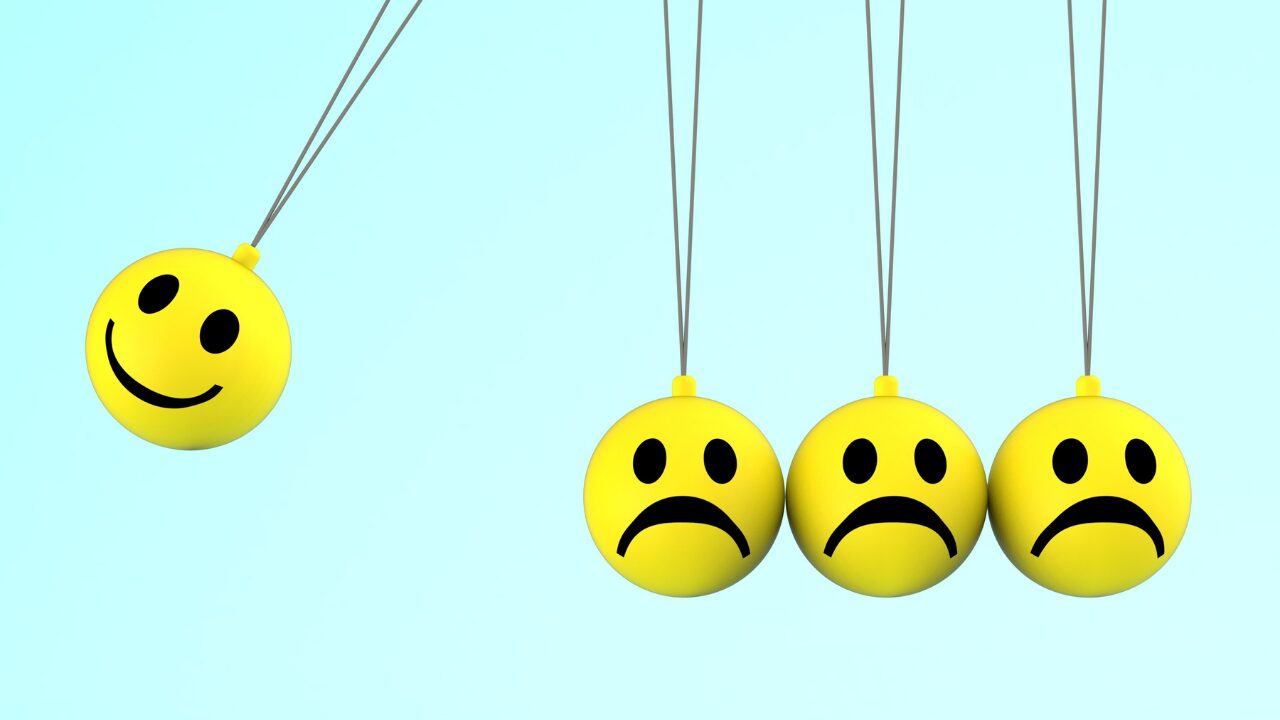
自分の会話を録音して「ちなみに率」をチェック
まずは“気づくこと”からがスタートです。
普段の会話を録音して聞き返すと、「思っていたより『ちなみに』を使っていた…」という発見があるはず。
自分の話し方のクセを客観的に知ることで、意識的に減らす第一歩になります。
ポイントは、「何回使っているか」だけでなく、どんな場面で出ているかを観察すること。
・沈黙を埋めたいとき
・話題を変えたいとき
・知識を補足したいとき
――その“使用パターン”がわかると、改善ポイントも見えてきます。
「要するに」「一方で」「そういえば」などの“代替フレーズ”をストック
「ちなみに」を減らすには、言い換えの引き出しを持っておくのが効果的。
似たニュアンスでも、使いどころによって印象が変わります。
たとえば:
-
「そういえば」→思い出したことを伝えるとき
-
「一方で」→対比を示したいとき
-
「要するに」→まとめや結論を伝えるとき
-
「ところで」→話題を切り替えるとき
このように、シーンに合った接続表現を選べるようになると、自然に「ちなみに」への依存が減っていきます。
1日1回、「ちなみに」を使わないトーク練習をしてみる
日常で意識的に練習することで、“無意識のクセ”が整っていきます。
たとえば、
-
同僚や友人との雑談
-
SNSでの投稿
-
家族との会話
どんな場面でも構いません。
「今日は“ちなみに禁止デー”にしてみよう」と意識するだけで、言葉の選び方が変わります。
はじめは少し不自然に感じるかもしれませんが、言葉を選ぶ力が磨かれていくと、
「伝わる話し方」や「流れのある会話」が自然に身についていきます。
💡まとめ
「ちなみに」は悪い言葉ではありません。
大切なのは、“便利だからといって頼りすぎないこと”。
自分の会話を振り返り、少しずつバリエーションを増やしていけば、
あなたの話し方はぐっと自然で、印象の良いものになります。
まとめ:脱・「ちなみに」依存で、伝わる&自然な会話を

「ちなみに」は、会話をやわらかくつなぐ便利な言葉。
けれど、使いすぎると話の軸がぼやけたり、聞き手が迷子になったりすることもあります。
“言葉のつなぎ”が目的になってしまうと、肝心の「伝えたい内容」が弱まってしまうのです。
「ちなみに」は便利だけど、使いすぎると伝わりにくくなる
どんなに良い話でも、「ちなみに」が何度も挟まると、聞き手は“脱線した印象”を受けやすくなります。
また、情報が多く感じられて整理しづらくなるため、主旨が伝わりにくいというデメリットも。
まずは、「この一言は本当に必要?」と一呼吸おいて考えるだけで、会話の流れがスッキリ整います。
“話の流れ”を意識するだけで、自然で心地いい会話に変わる
言葉の選び方よりも大切なのは、会話全体のリズムやつながりを意識すること。
たとえば、「前の話題とどう関係しているか」を意識して話すだけで、
「ちなみに」を使わなくても自然な切り替えができるようになります。
沈黙があっても大丈夫。
間をとることで、聞き手に“考える余白”が生まれ、より安心感のある会話になります。
無理に封印せず、“使いどころ”を見極めて上手に活かそう
「ちなみに」を完全に禁止する必要はありません。
むしろ、“場を和ませる一言”として上手に使えば、会話の印象を柔らかくできます。
たとえば、
-
話題を軽く変えたいとき
-
雑談に自然な流れを作りたいとき
-
少し付け足したい情報があるとき
――そんな場面で使うと、控えめで感じの良い印象に。
🌿まとめのひとこと
「ちなみに」を減らすことは、言葉を減らすことではなく、
“相手に伝わる会話”を増やすことにつながります。
話の流れを意識しながら、自分のペースで“脱・ちなみに依存”をめざしましょう。
その小さな意識が、あなたの話し方をより自然で魅力的に変えていきます。


