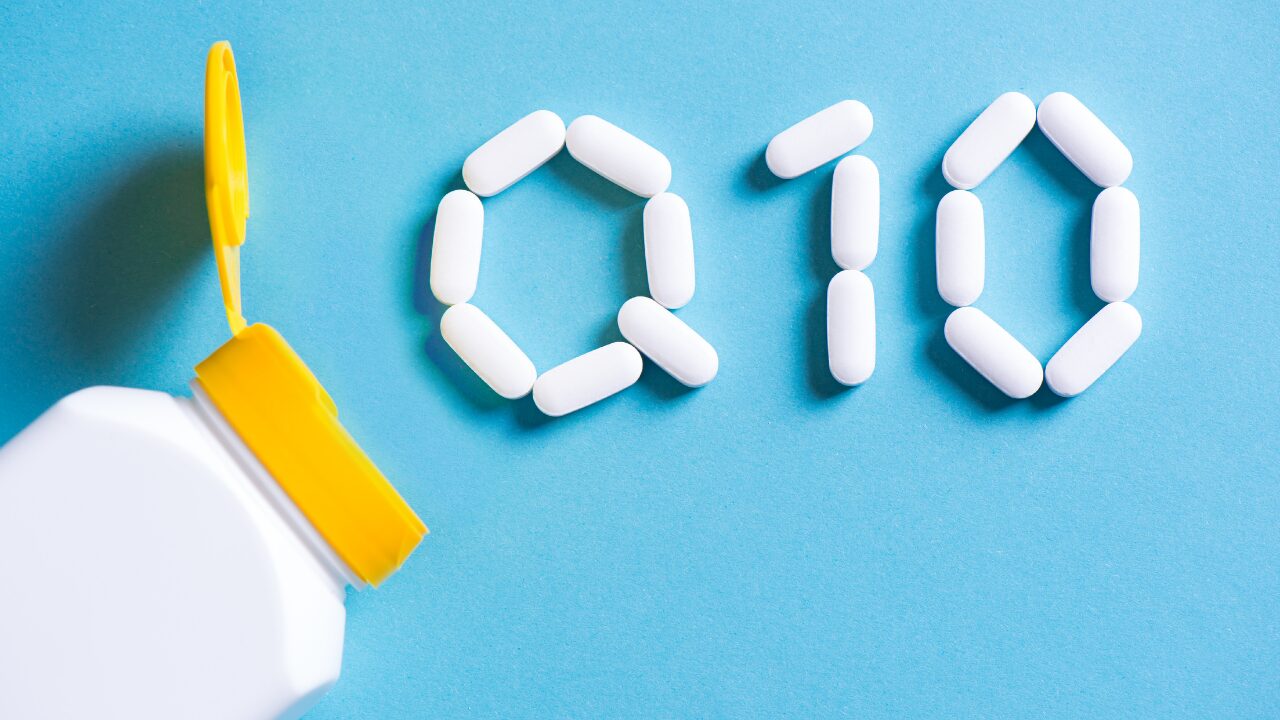
「若返り成分」とも呼ばれるコエンザイムQ10は、エネルギーを生み出すサポートや強力な抗酸化作用によって、私たちの健康と美容を守る重要な成分です。年齢とともに体内で減少してしまうため、食品やサプリメントからの補給が欠かせません。
本記事では、コエンザイムQ10の基礎知識から期待できる効果、豊富に含まれる食品、摂取の目安量や注意点、さらにおすすめサプリまでをわかりやすく解説します。若々しさと健康を保つために、ぜひ参考にしてください。
コエンザイムQ10とは?基礎知識をわかりやすく解説
コエンザイムQ10はどんな成分?
コエンザイムQ10(CoQ10)は、私たちの体内に存在するビタミン様物質のひとつで、「ユビキノン」とも呼ばれます。脂溶性の補酵素として細胞内のエネルギー産生に欠かせない役割を担っており、特に心臓や肝臓、腎臓といったエネルギー消費の多い臓器に多く含まれています。食品から摂取できるほか、体内でも合成されるため、本来は不足しにくい成分ですが、年齢や生活習慣によって減少することが知られています。
体内での働き(エネルギー産生・抗酸化作用)
コエンザイムQ10の代表的な働きは、次の2つです。
-
エネルギー産生をサポート
細胞内にある「ミトコンドリア」で、食べ物から得た栄養素をエネルギー(ATP)に変える際に必要不可欠な補酵素です。CoQ10が不足するとエネルギー効率が低下し、疲労感や持久力の低下につながる可能性があります。 -
強力な抗酸化作用
活性酸素を除去し、細胞の酸化ストレスを防ぐ働きがあります。酸化は老化や生活習慣病の原因のひとつとされており、コエンザイムQ10は「若返り成分」と呼ばれるゆえんにもなっています。
年齢とともに減少する理由
コエンザイムQ10は体内で合成されますが、20歳前後をピークに徐々に減少していきます。40代ではピーク時の約70%、60代では約50%程度にまで低下するといわれており、加齢による疲れやすさや肌の衰えの一因と考えられています。また、ストレスや過度な運動、生活習慣の乱れも減少を加速させる要因です。そのため、食品やサプリメントを通じて外から補うことが健康維持やアンチエイジングのサポートにつながります。
「若返り成分」と言われる理由!コエンザイムQ10の効果とは

アンチエイジング効果(抗酸化による細胞保護)
コエンザイムQ10は、体内で発生する「活性酸素」を除去する強力な抗酸化作用を持っています。活性酸素は細胞を酸化させ、シワ・たるみ・老化現象の原因のひとつとされます。CoQ10はこの酸化ストレスを抑え、細胞を守ることで、加齢に伴う機能低下を緩やかにし、若々しさを維持するサポートをしてくれるのです。
疲労回復や持久力向上への働き
エネルギーの生産工場といわれる「ミトコンドリア」で働くコエンザイムQ10は、ATP(エネルギー物質)を効率よく作るために欠かせません。CoQ10が十分にあることで疲労感の軽減や運動時の持久力向上が期待できます。スポーツ選手やアクティブに過ごしたい人にとっても、心強い成分です。
生活習慣病予防(心臓・血管のサポート)
心臓は全身に血液を送り出すため、常に大量のエネルギーを必要としています。コエンザイムQ10は心筋に豊富に存在し、心臓の働きをサポートするとともに、血管内の酸化ストレスを軽減する効果が期待されています。そのため、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病予防に役立つ可能性があると考えられています。
美肌やエイジングケアにも期待できる理由
紫外線やストレスによって発生する活性酸素は、肌のコラーゲンやエラスチンを破壊し、シミやたるみの原因になります。抗酸化作用を持つコエンザイムQ10は、肌細胞を守り、ターンオーバーを整えることで美肌効果やエイジングケアに役立つと注目されています。化粧品やサプリメントに配合されている理由もここにあります。
コエンザイムQ10が多く含まれる食品一覧

動物性食品(肉類・魚介類)
コエンザイムQ10は特に 臓器系や魚介類 に豊富に含まれています。代表的なものは以下の通りです。
-
牛肉(特に心臓・レバーなどの内臓部分)
-
豚肉(ヒレやレバーに多い)
-
鶏肉(特に心臓やもも肉)
-
サバ、イワシ、サンマ、マグロなどの青魚
-
イカ、エビなどの魚介類
動物性食品は吸収効率がよく、効率的にコエンザイムQ10を摂取したい人におすすめです。特に青魚はDHA・EPAも同時に摂れるため、心血管の健康維持にも役立ちます。
植物性食品(大豆・野菜など)
動物性食品ほど含有量は多くありませんが、植物性食品からも摂取可能です。
-
大豆製品(納豆、豆腐、味噌など)
-
ブロッコリー、ほうれん草、カリフラワーなどの緑黄色野菜
-
ピーナッツ、ゴマ、菜種油などのナッツ・植物油
植物性食品は健康志向やベジタリアンの人にとって貴重な供給源。食物繊維や他の抗酸化成分(ビタミンE・C)も同時に摂れるのがメリットです。
日常で取り入れやすい食材ランキング
「毎日の食事に取り入れやすい」という視点で選ぶと、次のような食材がおすすめです。
-
サバ・イワシ(焼き魚や缶詰で手軽)
-
牛肉や豚肉の赤身(メイン料理にしやすい)
-
大豆製品(味噌汁・納豆・豆腐で毎日摂取可能)
-
鶏もも肉(家庭料理で登場回数が多い)
-
ブロッコリー・ほうれん草(付け合わせやおひたしで簡単)
これらをバランスよく取り入れることで、無理なくコエンザイムQ10を摂取できます。特に魚の缶詰や冷凍野菜を活用すれば、忙しい人でも手軽に続けられます。
摂取の目安量と注意点【副作用・相互作用にも注意】

1日の摂取目安量
健康な人の場合、食品から摂れるコエンザイムQ10は 3〜5mg程度 とされています。サプリメントとして利用する際は、一般的に 1日30〜100mg が目安とされ、エイジングケアや疲労回復を目的とする場合には 100〜300mg 程度が研究でも使われています。
ただし、年齢・体調・目的によって必要量は異なるため、自己判断で大量に摂るのではなく、ガイドラインや専門家のアドバイスを参考にしましょう。
サプリメントで摂る場合のポイント
コエンザイムQ10は 脂溶性 のため、食後や油を含む食事と一緒に摂ることで吸収率が高まります。最近では、水溶性加工されたタイプや、吸収性を高めたサプリメントも販売されているので、利用目的やライフスタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
また、効果を実感するには 継続的な摂取 が大切です。短期間で劇的な変化を期待するのではなく、数週間〜数か月単位で続けることがポイントです。
副作用や薬との相互作用(スタチン系薬剤など)
基本的に安全性が高い成分とされていますが、まれに 胃の不快感、下痢、食欲不振 などの軽い副作用が報告されています。
特に注意が必要なのは、コレステロール低下薬(スタチン系) を服用している方です。スタチンは体内でのコエンザイムQ10の合成も抑制してしまうため、不足しやすくなります。そのため、医師の判断でサプリ併用を勧められる場合もありますが、必ず自己判断せずに医療従事者に相談してください。
また、ワルファリン(抗凝固薬)など一部の薬との相互作用が指摘されているため、持病で薬を服用している方は注意が必要です。
安全に摂取するための工夫
-
医師や薬剤師に相談してからサプリを始める
-
初めて摂る場合は少量からスタートし、体調の変化を観察する
-
食事からもバランスよく摂ることで、サプリに頼りすぎない
-
継続する際は、体調の変化や疲労感・肌の調子などを記録してみる
これらを心がけることで、安全かつ効果的にコエンザイムQ10を生活に取り入れることができます。
コエンザイムQ10おすすめのサプリTOP5

コエンザイムQ10のおすすめサプリTOP5を、効果・品質・吸収性などを考えてピックアップしました。日本で手に入りやすいものや信頼性が高いブランドを中心に紹介します。
1. 還元型CoQ10(Kaneka Ubiquinol)100mg
-
特徴:還元型(ユビキノール)CoQ10で、吸収性が高いタイプ。Kanekaの原料を使用しており、品質に定評があります。100mg/2カプセル。(※製品説明によれば60カプセル入り。日本国内で流通しているKaneka Ubiquinol製品の仕様です)
-
メリット:高い吸収率 → 少量で効率を期待できる。疲れやすさや加齢によるCoQ10低下を補いたい人に適しています。
-
注意点:価格がやや高め。脂溶性なので油分を含む食事と一緒に摂取するのが望ましい。
2. ネイチャーメイド Coenzyme Q10 50粒
-
特徴:ネイチャーメイドはネームバリューと信頼度が高いブランド。50粒入り。1粒あたりきちんとCoQ10を配合。
-
メリット:コスパが良い。リーズナブルながら品質が一定で安心感あり。サプリ初心者にも取り入れやすい。
-
注意点:用量が高吸収タイプ・還元型タイプと比べると普通のユビキノン型で、吸収率はやや劣ることも。用法を守り、続けて摂ることが重要。
3. DHC コエンザイムQ10 還元型 60粒
-
特徴:FDHC コエンザイムQ10 還元型で、1日あたりの数粒で十分な量を取れる設計。保存料・添加物を抑えたタイプも多い。
-
メリット:国内ブランドで安心。国内の品質管理・法規制に則って製造されており、信頼度が高い。ソフトカプセルなので飲みやすい。
-
注意点:コストが少し高めになる可能性。特に多量に摂りたい場合は割高感があるため、1回量・1日量をしっかり確認を。
4. ディアナチュラ コエンザイムQ10 60粒
-
特徴:アサヒグループ食品が手がけるディアナチュラシリーズの製品。60粒入りで日常的に摂りやすい。機能性表示食品などで手軽に使われることもある。
-
メリット:ドラッグストアやネットショップで入手しやすい。1回あたりの価格も比較的手頃。継続しやすい構成。
-
注意点:含有量・吸収率が製品によって異なるため、自分の目的(疲れ/美容/体力維持など)に見合う量か確認すること。
5. NOW Foods CoQ10 100mg ベジカプセル
-
特徴:海外ブランド、NOW Foods の植物由来ベジタブルカプセルタイプ。100mgの比較的しっかりした用量。30日分。
-
メリット:ベジタリアンや素材にこだわりたい人に向いている。添加物が少ないタイプを選びたい人には良い選択肢。用量もしっかりあるので疲れ・持久力サポート用として使える。
-
注意点:輸入品ゆえ輸送コスト・関税等で価格が変動することがある。ソフトジェルタイプに比べて吸収に多少時間がかかる可能性。
選び方のアドバイス
おすすめサプリを選ぶ際のポイントを以下にまとめます:
-
還元型(ユビキノール) vs 通常型(ユビキノン)
還元型は体内での活性形への変換が少ない分、体への利用効率が高いとされる。ただしコストは通常型より高くなることが多い。 -
吸収率を高める配合
ソフトジェル・脂質含有・オイル・包接体・微粉化など、吸収補助処理を行っている製品を選ぶと効果を得やすい。 -
信頼できるブランド・製造元
GMP認証・原材料の由来・国内外どちらで製造か・成分分析が公開されているかなど、品質管理がしっかりしているもの。 -
目的に合わせた用量
疲労感ケア・生活習慣病予防・アンチエイジングなど、目的によって必要量が変わる。最小限で始めて、効果を見ながら調整するのが無難。 -
価格対コスパ
1日あたりのコスト・含有量・粒数などを比較して続けやすいものを選ぶ。安くても含量が低ければ効果が薄くなることもある。
まとめ|コエンザイムQ10を上手に取り入れて若々しく健康に!
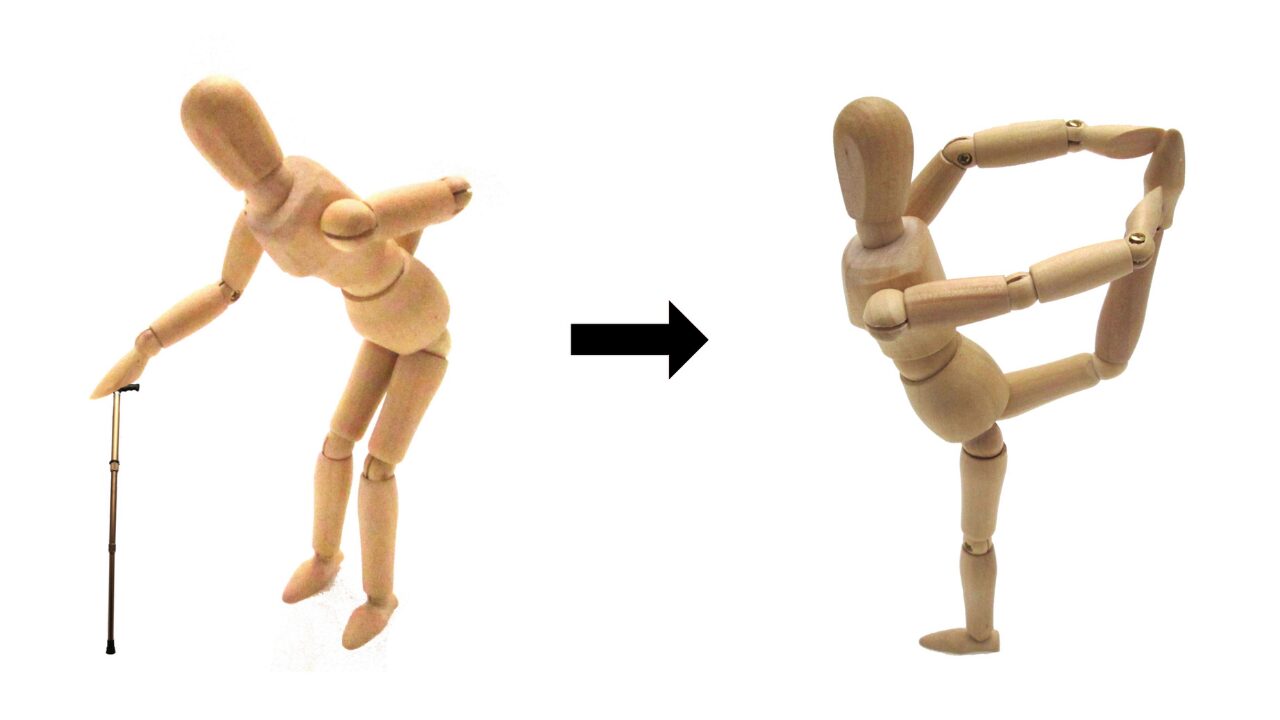
食品とサプリを組み合わせるのが理想
コエンザイムQ10は、肉や魚、大豆製品など普段の食事からも摂取できますが、加齢とともに体内の合成量が減少してしまいます。そのため「食品で自然に摂りつつ、足りない分はサプリメントで補う」というのが理想的な取り入れ方です。特に疲労感が強い方や美容・エイジングケアを意識している方は、サプリを活用することで効率的にコエンザイムQ10を体内に届けられます。
継続することで効果を実感しやすい
コエンザイムQ10は薬のように即効性があるわけではなく、継続して摂取することで少しずつ効果を実感できる栄養素です。毎日の食事や習慣に取り入れることで、エネルギー代謝や抗酸化作用が体をサポートし、若々しさや健康維持につながります。無理のない範囲で続けていくことが、アンチエイジングや生活習慣病予防において最も大切なポイントです。


