
「チョベリバ」「マジ卍」「キタコレ」——。
思い出した瞬間、ちょっと顔が熱くなる…でも、なんだか懐かしい!
かつてSNSやプリクラで量産された“黒歴史ワード”たちは、
私たちの青春を彩った“時代の象徴”でもあります。
この記事では、アラサー・アラフォー世代が使っていた懐かしのワードを
ジャンル別に一挙紹介!
「うわ、それ使ってた!」と思わず笑ってしまうあの頃のテンション、
一緒に振り返ってみませんか?
思い出すだけで顔から火が出る!? “黒歴史ワード”とは
「マジ卍」「チョベリバ」「キタコレ」「chu☆」……。
思い出した瞬間に「うわぁ〜!」と声が漏れる、懐かしの“黒歴史ワード”。当時はみんなが使っていたのに、今思うとちょっと痛々しい。でもそれこそが、青春の証でもあります。
SNSがまだ普及しきっていなかった時代、言葉は“仲間の合言葉”であり、“流行のバロメーター”。
誰もが「今っぽく見られたい」「共通のノリでつながりたい」と思っていたあの頃。
そんな純粋な気持ちが、数々の“黒歴史ワード”を生み出していったのです。
誰にでもある“中二感”たっぷりな時代
黒歴史ワードの根っこには、「自分らしさを出したい」願望があります。
思春期〜20代前半にかけての“中二感”は、誰にでも訪れるもの。
「普通じゃつまらない」「他とは違う私を見て!」という気持ちから、
どこか背伸びした表現や、謎のポエム口調、独特の語尾(例:〜ぴょん/〜的な?)が生まれたのです。
あの頃の私たちは、SNSもまだ黎明期。
「自己演出」や「キャラ作り」の練習を、まさにリアルタイムでしていた時代でした。
その結果、黒歴史ワードは“思春期のクリエイティビティ”の結晶とも言えるのです。
“黒歴史ワード”が生まれた背景(SNS・ギャル文化・ネットスラング)
“黒歴史ワード”の流行には、時代ごとのカルチャー背景があります。
💄 ギャル文化全盛期(1990年代後半〜2000年代)
プリクラ・デコメ・109系ファッションがブーム。
「チョベリバ」「ヤバみ」「ウケるんですけど〜」など、テンション高めのギャル語が日常会話に浸透。
文字装飾(☆・♪・〜)や顔文字文化もこの時期に爆発しました。
💻 ネットスラング黎明期(2ちゃんねる・mixi時代)
匿名掲示板から「キタコレ」「orz」「乙」「ワロタ」などのスラングが拡散。
オンライン特有の“ノリ”が若者の会話に入り込み、リアルでも使われるように。
📱 初期SNS&ガラケー文化(デコメ・プロフ帳・写メ)
当時は、メールの文面が「自分の世界観」を表現する場所。
「chu☆」「らぶ②」「〜にゃん」「マイメン」など、甘くて独特な表現が多発しました。
まさに“黒歴史ワードの温床”とも言える時代です。
当時はかっこよかったのに…!時代の移り変わりを感じる瞬間
黒歴史ワードの面白さは、「当時は本気でイケてると思っていた」というギャップ。
流行の最前線にいた言葉も、時が経てば笑い話になる——それがカルチャーの面白さです。
たとえば、「チョベリグ」は平成初期では最先端。
「マジ卍」もSNS黎明期には若者の象徴。
でも今使うと、一周回って“ネタ枠”扱い。
言葉はその時代の“空気”を映す鏡。
流行が過ぎれば色あせるけれど、そこに込められた「勢い」や「ノリ」は、今の若者スラングにも確実に受け継がれています。
つまり、黒歴史ワードも立派な時代の文化遺産なのです。
黒歴史ワード【ジャンル別まとめ】
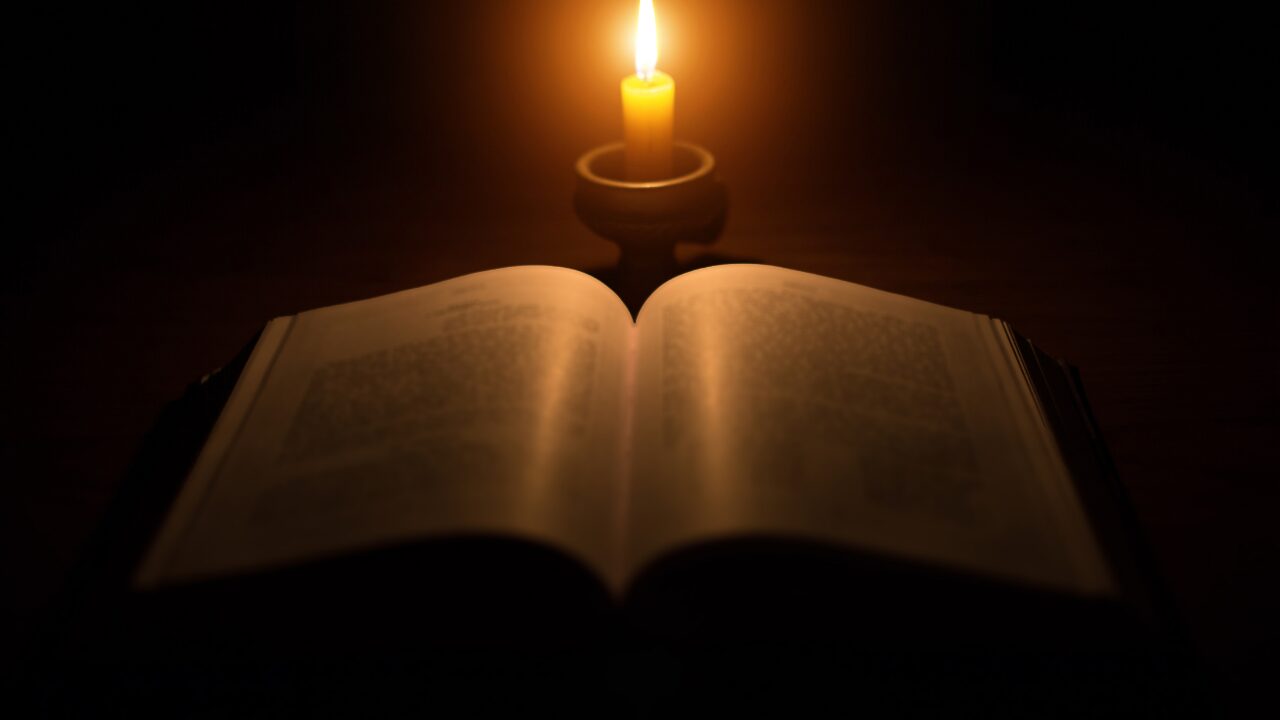
あの頃、誰もが“何かしらの黒歴史ワード”を使っていました。
学校でも、プリクラでも、SNSでも。
「今考えるとちょっと痛いけど、当時は全力で楽しかった」——そんな懐かしワードを、ジャンル別に振り返ってみましょう!
ギャル語・若者スラング編(例:マジ卍/チョベリバ/ウケるんですけど〜)
平成初期〜中期を席巻したのが、ギャル語&若者スラング。
109カルチャー、プリクラ、ケータイ小説が盛り上がった時代。
会話のテンションも「テンアゲ↑↑」がデフォルトでした。
💬 代表的な黒歴史ワード
-
チョベリバ/チョベリグ …「超ベリーバッド」「超ベリーグッド」の略。英語力ゼロの謎ノリ。
-
ウケるんですけど〜! …もはや笑ってなくても使ってた万能ワード。
-
マジ卍 …意味はないのにノリで言ってた“謎スラング界の王”。
-
ヤバみ/それな〜/ガチで …言葉の意味より“テンション”重視。
📸 当時の背景
ギャル雑誌やプリクラ落書きが情報源。
言葉がファッションの一部だった時代で、「しゃべり方」もトレンドの一種でした。
ネット掲示板&初期SNS編(例:orz/キタコレ/乙/ワロタ)
2ちゃんねる・mixi・前略プロフィールが盛り上がった、ネットスラング黄金期。
チャットや掲示板で使ってた言葉を、リアルでも口に出してた人…いましたよね?(笑)
💬 代表的な黒歴史ワード
-
orz …人が土下座してるAA(アスキーアート)。当時は落ち込みの定番表現。
-
キタコレ! …テンションが上がる瞬間に使う「来たこれ!」。
-
乙!/乙でした! …「おつかれ」の略。語尾が“乙”のコメント欄は青春。
-
ワロタwww/草生える …笑いの表現が進化する過程。
-
神!/ネ申! …何かすごいとすぐ“神扱い”。
📱 mixi世代あるある
日記のコメントに「コメ返」文化があり、
顔文字((゜∀゜)ノ)やAA(><)が飛び交っていた時代。
文章が個性だったあの頃、黒歴史ワードは“ネット人格”の象徴でした。
恋愛・プリクラ・メール文化編(例:らぶ②/彼ぴっぴ/chu☆)
恋愛系ワードこそ、黒歴史ワードの宝庫。
特にプリクラやガラケーのメール時代は、“恋愛テンション”が文面に全力で出ていました。
💬 代表的な黒歴史ワード
-
らぶ②(LOVE×2) …カップルの常套句。プリクラの落書きはこれ一択。
-
chu☆/chu〜/chuU〜 …語尾にキス音を入れる謎文化。
-
彼ぴっぴ/ダーリン/王子/姫 …照れずに呼んでた自分が信じられない…。
-
ずっと一緒にいようね(はぁと) …絵文字多用、デコメ多用、語尾に“☆”。
📞 ガラケー時代の思い出
メールの最後に「おやすみ☆ミ」「またねぇ〜♪」を付けるのが礼儀。
デコメやハートマークが“愛情表現”のツールでした。
いま読み返すと…文字だけで全身が熱くなるレベルの甘酸っぱさ。
ファッション&ビジュアル系編(例:病みかわいい/〜様信者/†漆黒†)
V系・ゴスロリ・中二ワード全開の闇系・病みかわいい文化も忘れちゃいけません。
黒と赤の背景に白文字、そして“†(ダガー)”が飛び交っていたあの時代——。
💬 代表的な黒歴史ワード
-
†漆黒の堕天使† …厨二界のレジェンドネーム。
-
〜様信者/○○命/推ししか勝たん(先駆け) …崇拝レベルの推し文化。
-
病みかわいい/闇属性/魂の叫び …日記のポエムに多発。
-
†Requiem†/††† …中二テンションが頂点に達した瞬間。
🎸 当時の背景
「シド」「ナイトメア」「アヤビエ」などV系バンドブームが全盛期。
黒歴史ワードは、ファッションやメイクと一体化した“世界観”でした。
自分の中に“物語”を持っていた、あの時代ならではの美学です。
日記・ブログ・プロフィール文化編(例:†堕天使系女子†/相方/マイメン)
「前略プロフ」「デコログ」「アメブロ」…
プロフィールや日記文化の中にも、黒歴史ワードは満載でした。
💬 代表的な黒歴史ワード
-
相方/相棒/マイメン …友情アピールの定番。
-
†堕天使系女子†/姫系女子/小悪魔系 …自己紹介テンプレの代表格。
-
mixiネーム:◯◯☆Love/××@病み期 …ハンドルネームがすでに黒歴史。
-
プロフ帳:好きな言葉→一期一会/感謝/運命 …ポエム率高め。
📝 当時の背景
ブログは「自分を見せる場所」だったからこそ、
“痛いけど全力で書いてた”あの感じが、今思えば愛おしい。
「写メ」「デコメ」「絵文字乱舞」も全部、私たちの青春の記録です。
なぜ私たちは、あの頃“痛い言葉”を使いたくなったのか?

思い返せば、あの「黒歴史ワード」を使っていた頃、
私たちは誰かに笑われたいわけでも、バズりたいわけでもなかった。
ただ——
「仲間と同じ言葉でつながりたかった」
「自分らしさを表現したかった」
それだけなんですよね。
あの“痛い”言葉たちは、実は私たちの心のピュアな部分から生まれていたのです。
承認欲求の原点は「仲間との共通語」だった
「ウケる〜!」「チョベリバ!」「マジ卍!」
どんな言葉も、“仲間の輪の中”でこそ輝いていました。
あの頃の若者文化は、いわば**「共通語でつながる時代」**。
みんなが同じワードを使うことで、仲間意識を確認し合っていたのです。
クラスメイト、部活仲間、SNSの友達…。
同じ言葉を使えば、
「自分もこのグループの一員だ」
「私もちゃんと“今”を生きてる」
そんな安心感がありました。
つまり、“黒歴史ワード”は承認欲求の最初の形。
いいね!ボタンがなかった時代、言葉そのものが“つながるサイン”だったのです。
時代を映す鏡——黒歴史ワードは“青春の表現”
黒歴史ワードを集めてみると、そこには当時の時代背景がまるごと詰まっていることに気づきます。
たとえば、
-
「チョベリバ」「バリサイ」→ギャル文化・テレビバラエティの影響
-
「orz」「乙」「キタコレ」→ネット文化の拡大と匿名コミュニティの誕生
-
「らぶ②」「chu☆」→プリクラ・メール文化と恋愛至上主義の象徴
つまり、黒歴史ワードは「若者文化の年表」でもあるのです。
その時代に生きる私たちが、流行やメディア、社会の空気に影響を受けながら、
**“言葉で時代を表現していた”**とも言えます。
あの頃のワードを見返すことは、
「私たちはどんな時代を生き、何を大事にしていたのか」を振り返る小さな旅なのです。
“黒歴史”は、実は「自己表現の第一歩」だった説
今となっては恥ずかしいあの言葉も、
実は**「自分を表現する練習」**だったのかもしれません。
SNSが普及しはじめ、
「誰かに見られる」「共感される」ことが新しいコミュニケーションになった時代。
その中で、みんなが“痛い言葉”を使いながら、
少しずつ「自分らしさの出し方」を模索していたのです。
あの頃の「†堕天使系女子†」も、「マジ卍」も、
今の“ストーリーズ投稿”や“推し活ハッシュタグ”と本質は同じ。
ただ方法が違うだけで、どちらも**「自分を見てほしい」「誰かと共感したい」**という
人間らしい願いの表れです。
だからこそ、黒歴史ワードを笑って振り返れる今、
私たちはあの頃より少しだけ成熟した証拠なのかもしれません。
今ならどう言い換える?黒歴史ワードの現代アレンジ

かつて一世を風靡した“黒歴史スラング”たち。
当時はキラーワードでも、今使うとちょっと照れくさい……。
でも実は、現代のスラングに言い換えると自然に通じるんです。
ここでは、懐かしの言葉を“令和風”にアレンジして紹介します!
「マジ卍」→「ガチでヤバい」
かつては「マジ卍(まじまんじ)」が“テンション最高潮”を表す定番ワードでした。
いま風に言うなら、**「ガチでヤバい」や「普通に神」**が近いニュアンス。
「卍」はもはや形容しがたい“ノリ”の象徴でしたが、今も“勢いで伝える文化”は健在です。
「チョベリバ」→「テンション下がる〜」
90年代ギャル語の代表「チョベリバ(超ベリー・バッド)」は、
いまなら「テンション下がる〜」「ガチ無理」がピッタリ。
当時はポップでキュートな響きでしたが、現代ではよりナチュラルな口語に変化しています。
「キタコレ」→「それ最高!」
「キタコレ!」は“待ってました!”の気持ちを表す歓喜ワード。
現代では「それ最高!」「きたーーー!」が使われることが多く、
SNSでは🔥や👏などの絵文字で感情を表すスタイルに進化しています。
「chu☆」→「好きすぎる🥺」
「chu☆」は、いわゆる“ネット恋愛時代”の甘め表現。
令和では「好きすぎる🥺」「尊い」「ぎゅってしたい」など、
絵文字+感情ワードで可愛く想いを伝えるのが主流です。
言葉がシンプルになったぶん、表現はより感情的に。
現代スラングとの比較(例:それな/ぴえん/えぐい/草)
令和の若者スラングを見てみると、
「それな(共感)」「ぴえん(悲しい)」「えぐい(すごい)」「草(笑う)」など、
短く・テンポよく・感覚で伝える言葉が主流。
言葉の形は変わっても、
「テンション」「共感」「ノリ」で盛り上がる文化は昔とまったく同じなんです。
🌀 時代は変わっても、“言葉で盛り上がる”ノリは普遍。
黒歴史スラングも、令和流にアップデートすればまた輝くかも!
まとめ|“黒歴史ワード”も、全部あなたの青春だった

かつて夢中で使っていたスラングや言葉たち。
今振り返ると「よくこんなの言ってたな…」と恥ずかしくなるかもしれません。
でも、それこそがその時代を全力で生きていた証。
“黒歴史”という言葉の裏には、確かにあった青春の熱量が詰まっています。
黒歴史=恥ずかしいではなく“思い出の証”
誰にでも、振り返ると赤面するような時期があります。
けれど、それは「その瞬間を本気で楽しんでいた」からこそ。
当時の言葉づかいやノリには、その時代の空気や感情が凝縮されています。
黒歴史は、決して消すべき過去ではなく、あなたらしさの一部なんです。
あの頃の言葉にこそ、世代のカルチャーが詰まっている
スラングは単なる言葉遊びではなく、
音楽・ファッション・SNSなど、カルチャーそのものを映す鏡。
「チョベリバ」や「マジ卍」といった言葉の背景には、
その時代の価値観や“流行の熱”がしっかり刻まれています。
だからこそ、当時のスラングを語ることは、世代を超えた共感のきっかけにもなるのです。
次の世代もきっと“黒歴史ワード”を作っていく
時代が変われば、言葉も変わる。
今の若者たちが使う「ぴえん」や「えぐい」も、
10年後にはきっと「懐かしい!」と笑われる日が来るでしょう。
でもそれでいいんです。
どの時代にも“言葉で盛り上がる文化”があり、
それがまた次の世代の青春の証になるのだから。
💬 黒歴史も、時代を超えたカルチャーの一部。
恥ずかしさよりも、その頃の自分をちょっと誇らしく思ってみませんか?


