
「しっかり寝たのに疲れが取れない」「ずっと体がだるい」「やる気が出ない」——そんな不調が続いていませんか?
実はその“慢性的な疲労感”、ストレスや睡眠不足ではなく「栄養不足」が原因かもしれません。
現代人の多くは、食事の偏りや忙しさから知らず知らずのうちに必要な栄養が不足し、エネルギーを生み出す力が低下しています。
この記事では、疲れやすさを招く栄養素の不足サインから、今日から実践できる改善法・おすすめサプリまでを徹底解説。
「休んでも回復しない疲れ」を根本からリセットし、内側から元気を取り戻すヒントをお届けします。
「疲れが取れない…」それ、ただの疲労じゃないかも?
仕事や家事を終えてしっかり休んだはずなのに、「まだだるい」「朝起きても疲れが抜けない」と感じることはありませんか?
その疲労感、実は“休んでも回復しないタイプ”の慢性疲労かもしれません。
一時的な疲れは、睡眠や休養で体内のエネルギーが回復すれば自然に取れます。
しかし、体がエネルギーをうまく作り出せていない状態になると、どれだけ寝ても疲れが取れなくなるのです。
その背景には、ストレスや生活リズムの乱れに加え、体を動かすための栄養素が不足していることが関係しています。
睡眠や休養を取っても回復しない“慢性疲労”の正体
慢性疲労とは、エネルギー産生がうまくいかない状態が続き、体が常にエネルギー不足になっていることを指します。
体の中では、摂取した糖や脂質をエネルギーに変換するために、ビタミンB群やミネラルなど多くの栄養素が使われています。
ところが、食生活の乱れや偏りによってこれらの栄養素が不足すると、
エネルギーを作る“工場”がうまく働かず、エンジン不調のような状態に。
結果として、
-
睡眠を取っても疲れが抜けない
-
集中力が続かない
-
体が重く、朝からだるい
といった状態が続くようになります。
つまり、「寝ても疲れが取れない」人は、単なる休養不足ではなく、体内の栄養バランスが崩れている可能性を疑う必要があります。
ストレスや生活習慣の乱れだけじゃない、“隠れ栄養不足”に注意
疲れが取れない原因として「ストレス」「運動不足」「睡眠不足」などがよく挙げられますが、
実は見落とされがちなのが「隠れ栄養不足」です。
現代の食生活では、コンビニ食や外食中心になりやすく、カロリーは足りていても“栄養素”が不足しやすい傾向にあります。
とくに、ビタミンB群・鉄・亜鉛・マグネシウムなどのエネルギー代謝に欠かせない栄養素が不足すると、
体は十分なエネルギーを作り出せず、疲れが慢性化していきます。
さらに、ストレスや過労が続くと、これらの栄養素は体内で大量に消費されるため、
「頑張っている人ほど栄養不足になりやすい」という悪循環に陥ることも。
見た目や食欲に変化がなくても、
-
朝起きられない
-
やる気が出ない
-
肌や髪の調子が悪い
といったサインが出ている場合は、体が「栄養足りてないよ」と訴えているサインかもしれません。
疲労感につながる「栄養不足」にはこんなサインが

栄養不足は、すぐに体調不良として現れるわけではありません。
最初は「なんとなくだるい」「集中できない」「肌の調子が悪い」といった小さなサインから始まります。
しかし、そのまま放置してしまうと、慢性的な疲労感やメンタルの不調にまで発展することも。
ここでは、体が発している“栄養不足のサイン”を3つの視点から見ていきましょう。
朝起きてもだるい・集中力が続かない
しっかり寝たはずなのに朝から体が重い、仕事中に集中力が切れやすい…。
それは「睡眠の質」だけでなく、エネルギーを作る栄養素が不足しているサインです。
特に不足しやすいのが、
-
ビタミンB群(B1・B2・B6・B12など):糖質をエネルギーに変える
-
鉄:酸素を運んで脳や筋肉の働きをサポート
-
マグネシウム:神経伝達や筋肉のリラックスに関与
これらが足りないと、体内でエネルギーがうまく作られず、
「燃料切れ」のように頭も体も働かなくなります。
食事で補うなら、
👉 玄米、豚肉、卵、納豆、ほうれん草、ナッツ類 などを意識的に取り入れましょう。
また、食後にだるさを感じる人は、糖質過多でビタミンB群が消費されている可能性もあるため、
糖質控えめ+ビタミン豊富な食事を心がけるのがポイントです。
肌荒れ・口内炎・抜け毛が増える
肌や髪、口の中の状態は、体の栄養状態を映す鏡です。
見た目のトラブルが続くときは、体の内側で栄養不足が進行している可能性があります。
特に関係が深いのは以下の栄養素です:
-
たんぱく質:肌・髪・爪の主成分。不足するとハリやツヤが失われる
-
ビタミンB2・B6:皮膚や粘膜の再生に不可欠
-
鉄・亜鉛:細胞の新陳代謝や髪の成長をサポート
これらが不足すると、肌荒れや口内炎、抜け毛といった形でサインが現れます。
改善には、
👉 鶏むね肉、豆腐、魚、卵、レバー、ナッツ類 などの高たんぱく+ミネラル食を意識。
特に、鉄分はビタミンCと一緒に摂ることで吸収率が高まるため、
レバー+ブロッコリーやほうれん草+柑橘類の組み合わせがおすすめです。
イライラ・気分の落ち込みなど“心の不調”もサイン
「なんとなく気分が沈む」「小さなことでイライラする」
こうした“心の疲れ”も、実は栄養不足が関係していることがあります。
脳の神経伝達物質(セロトニン・ドーパミンなど)を作るためには、
-
トリプトファン(アミノ酸)
-
ビタミンB6・葉酸・鉄
-
オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)
といった栄養素が必要不可欠。
これらが不足すると、脳内のバランスが崩れ、気分の安定が難しくなります。
心の栄養を補うには、
👉 鮭・サバ・アーモンド・バナナ・豆製品・緑黄色野菜 などを意識的に摂るのが効果的。
また、ストレスが強い人ほどビタミンCやB群を多く消費するため、
疲れた日ほど栄養を意識的に“プラス補給”する習慣を持つことが大切です。
「最近なんか疲れやすい」「肌や気分も不調続き…」
そんなときこそ、体が出している“栄養サイン”を見逃さず、
早めに食生活を見直すことが、疲労回復への第一歩です。
疲れやすさを引き起こす、足りていない栄養素とは?

慢性的な疲労感の原因の多くは、「エネルギーが足りていない」状態にあります。
しかし、それは食事量が少ないからではなく、体がエネルギーを作るために必要な栄養素が不足しているため。
ここでは、現代人が特に不足しやすく、疲れやすさに直結する4つの栄養素を詳しく見ていきましょう。
エネルギー代謝に欠かせない「ビタミンB群」
「なんとなく疲れが抜けない」「集中力が続かない」――
そんな時にまず見直したいのが、ビタミンB群の不足です。
ビタミンB群は、糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変えるための“触媒”のような役割を果たします。
つまり、食事をしてもB群が足りないと、体内で燃料がうまく使われず、エネルギーが枯渇してしまうのです。
主な働き:
-
ビタミンB1:糖質をエネルギーに変換(疲労回復に直結)
-
ビタミンB2:脂質の代謝や細胞再生をサポート
-
ビタミンB6・B12:神経や血液の健康維持
補給におすすめの食品:
👉 豚肉、玄米、卵、納豆、まぐろ、バナナ、レバー、にんにく など
特に、デスクワークや頭を使う仕事が多い人はビタミンB1の消費が増えるため、
毎日少しずつ継続的に摂ることがポイントです。
酸素を運ぶ「鉄分」不足がだるさの原因に
「寝ても疲れが抜けない」「立ちくらみや息切れがする」
そんな症状がある人は、鉄分不足(鉄欠乏性貧血)の可能性があります。
鉄は、血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。
鉄が足りなくなると、筋肉や脳に十分な酸素が行き渡らず、
エネルギーを作る働きが低下して、だるさや集中力の低下を引き起こします。
主な鉄の種類と特徴:
-
ヘム鉄(吸収率が高い):レバー、赤身肉、まぐろ、カツオなど
-
非ヘム鉄(植物性):ほうれん草、小松菜、大豆製品、ひじき など
吸収率を高めるポイントは、ビタミンCと一緒に摂ること。
例えば、「牛肉+ブロッコリー」「ほうれん草+レモン汁」といった組み合わせが効果的です。
女性やダイエット中の人は特に鉄が不足しやすいため、意識的な補給を心がけましょう。
抗酸化力を支える「亜鉛」「マグネシウム」
「体が重い」「気分が上がらない」と感じる人は、ミネラル不足にも要注意。
特に「亜鉛」と「マグネシウム」は、体の抗酸化力と代謝のバランスを保つうえで欠かせない存在です。
-
亜鉛:細胞の修復・免疫機能・ホルモン分泌をサポート
不足すると、味覚障害・肌荒れ・集中力低下などが起こりやすくなります。
👉 含まれる食品:牡蠣、牛肉、卵、チーズ、ナッツ、豆類 -
マグネシウム:エネルギーを作る酵素の働きを助け、筋肉や神経の安定に関与
不足すると、こむら返り・不眠・イライラ・疲れが取れにくいといった不調が出やすくなります。
👉 含まれる食品:アーモンド、海藻、玄米、豆腐、ほうれん草
これらは汗やストレスでも失われやすいため、
運動をする人・仕事でストレスを感じやすい人は特に意識的な補給が必要です。
免疫力と回復力を高める「たんぱく質」
たんぱく質は、体の材料であり、回復力の源。
筋肉・臓器・皮膚・髪・ホルモン・酵素など、ほとんどすべてがたんぱく質からできています。
不足すると、疲れやすさだけでなく、免疫力の低下や肌・髪の不調、集中力の低下など、全身に影響が出ます。
たんぱく質の質とバランスが大切で、
-
動物性たんぱく質:肉、魚、卵、乳製品
-
植物性たんぱく質:大豆、豆腐、納豆、レンズ豆 など
を1日2〜3食の中で組み合わせるのが理想です。
特に忙しい人や食事が偏りがちな人は、
プロテインや高たんぱくスナックを上手に取り入れるのも効果的。
また、たんぱく質の吸収を助けるために、
ビタミンB6(鶏肉、バナナ、にんにく)も一緒に摂ると、回復力がさらにアップします。
栄養不足による疲労は、「努力不足」ではなく「体のSOS」です。
バランスよく栄養を補い、体の内側からエネルギーが湧く“疲れにくい体”をつくっていきましょう。
今日から始められる!栄養不足の改善法

「栄養不足」と聞くと、特別なサプリや食事法が必要だと思われがちですが、
実は、毎日の食生活を少し整えるだけで体の調子は大きく変わります。
大切なのは、体に“エネルギーをつくる材料”をバランスよく与えること。
ここでは、今日から実践できるシンプルな栄養改善のステップを紹介します。
まずは“3食バランス”を意識する
疲れやすい人の多くに共通しているのが、「朝食抜き」や「偏った食事パターン」。
しかし、体は常にエネルギーを使い続けているため、3食のリズムを崩すとすぐに栄養不足を招いてしまいます。
理想のバランスは、
-
主食(エネルギー源):ごはん、パン、麺など
-
主菜(たんぱく質源):肉、魚、卵、大豆製品
-
副菜(ビタミン・ミネラル・食物繊維):野菜、海藻、きのこ類
この3つを「1食の中にそろえる」ことが基本です。
特に朝は、エネルギーを生み出すビタミンB群とたんぱく質を摂ることで、
1日の代謝スイッチが入りやすくなります。
👉 例:
・ごはん+味噌汁+卵焼き+納豆
・全粒トースト+ヨーグルト+ナッツ+フルーツ
完璧を目指すより、“抜かない食事”を意識することが疲れない体づくりの第一歩です。
“食材選び”で疲れにくい体をつくる
(例:赤身肉・卵・納豆・ナッツなど)
同じ量を食べても、選ぶ食材によって「疲れにくさ」は大きく変わります。
特に疲労回復やエネルギー代謝を支える栄養素が多い“高栄養食材”を選ぶことがポイントです。
おすすめの疲労対策食材:
-
赤身肉・豚肉:ビタミンB群と鉄が豊富で、エネルギー産生をサポート
-
卵:良質なたんぱく質+ビタミン・ミネラルがバランス良く含まれる“完全栄養食”
-
納豆・豆腐・味噌:植物性たんぱく質+ビタミンK、マグネシウムを含む
-
ナッツ類:抗酸化ビタミンE、亜鉛、マグネシウムを補給
-
魚(特に青魚):DHA・EPAなどのオメガ3脂肪酸で、脳と血流をサポート
-
緑黄色野菜・海藻:ビタミンCや鉄の吸収を助け、抗酸化力を高める
また、コンビニでも意識すれば選べます。
👉 例:「おにぎり+サラダチキン+ゆで卵」「豆腐サラダ+ナッツ入りヨーグルト」など。
“何を食べないか”よりも、“何をプラスするか”を意識するのがポイントです。
調理法と食べ合わせで栄養吸収をUPするコツ
せっかく栄養を摂っても、吸収されなければ意味がありません。
同じ食材でも、調理法や食べ合わせ次第で栄養吸収率は大きく変わります。
✅ 吸収を高めるポイント
-
脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は油と一緒に
例:にんじんやブロッコリーをオリーブオイルで炒める -
鉄+ビタミンCで吸収率UP
例:レバー+ブロッコリー、ほうれん草+柑橘系ドレッシング -
たんぱく質+ビタミンB6で代謝促進
例:鶏むね肉+バナナ、まぐろ+にんにく -
加熱しすぎ注意!
ビタミンCやB群は熱に弱いので、蒸す・軽く炒める調理法がおすすめ
✅ 吸収を妨げるNG習慣
-
コーヒー・紅茶を食後すぐ飲む(鉄の吸収を妨げる)
-
過度な糖質・脂質の摂りすぎ(代謝に必要なビタミンを浪費)
-
夜遅い食事(代謝リズムを乱す)
“何を食べるか”だけでなく、“どう食べるか”まで意識すると、
栄養はしっかりと体のエネルギーに変わり、疲れにくい体質へと整っていきます。
食事は「栄養を摂るための習慣」であり、「体を回復させる時間」。
今日からできる小さな工夫が、明日の疲れにくい体づくりにつながります。
おすすめの栄養サプリ紹介|足りない栄養を手軽にチャージ!

栄養不足を食事だけで完全にカバーするのはなかなか難しいもの。
そんなとき、“食事の補助”としてサプリを選ぶことで、不足を手軽に補えます。
ただし、「万能」ではないため、選び方と使い方にポイントがあります。以下におすすめ系統と商品名、選び方をまとめました。
マルチビタミン・ミネラル系で“底上げ”
補助の役割
まず定番として、ビタミン・ミネラルを広く網羅しているマルチ系サプリがあります。偏食・外食が多かったり、毎日の食事バランスが崩れがちな人には特に有効です。
例えば、
-
ネイチャーメイド「マルチビタミン&ミネラル」:ビタミン12種+ミネラル7種をバランスよく配合。
リンク -
ディアナチュラ「マルチビタミン&ミネラル」:12種ビタミン+9種ミネラルを含む、栄養バランスを気にしている人向け。
リンク -
DHC「マルチビタミン/ミネラル+Q10」:リーズナブルにマルチ補給したい人に。
リンク
使い方のポイント
-
朝食時や昼食時など食事と一緒に摂ることで、吸収もスムーズ。
-
“毎日継続”が鍵。1回だけでは効果を感じづらいため、習慣化することが大切です。
-
食事で補えない分を“底上げ”として使うイメージで。基本は3食バランス+良質な食材です。
鉄・ビタミンB群など、疲労回復系に特化したアイテム
なぜこの組み合わせが有効?
前章で「疲れやすさ」に直結する栄養素として、鉄・ビタミンB群を挙げました。
これらを集中的に補給できるサプリを併用することで、疲労感・だるさ・集中力低下といった“疲れのサイン”にアプローチできます。
商品例
-
ディアナチュラ「ヘム鉄×葉酸+ビタミンB6・B12・C」:ヘム鉄が鉄の中でも吸収率が高いタイプで、ビタミンB6・B12・Cも同時配合。
リンク -
ディアナチュラ「鉄×マルチビタミン」:鉄+14種類のビタミンを1粒でまとめて補えるタイプ。
リンク
活用ポイント
-
鉄は吸収が難しい栄養素なので、食後・空腹を避けて摂取するのがおすすめ。
-
鉄・ビタミンB群は、ストレス・睡眠不足・重労働などで消費が増えるため、そのような状況が続いている人は特に意識的に。
-
サプリだけに頼らず、鉄分を含む食材(赤身肉、魚、豆製品、ほうれん草など)+ビタミンCを添える食べ合わせも併用しましょう。
続けやすさ&安全性で選ぶポイント
続けやすさの観点
-
飲む“回数/粒数”が少ない(1日1〜2粒程度)が望ましい。
-
錠剤が小さめ、ニオイ・味が気にならないタイプ。
-
定期購入やまとめ買いによるコスト安があると習慣化しやすい。
例:ネイチャーメイドやディアナチュラでは定期割引やまとめ割が紹介されています。
安全性・安心感の観点
-
国内工場・GMP認定など、製造環境が明記されているもの。
例:ディアナチュラ「国内工場で生産」表記あり。 -
栄養機能食品など、法的な枠組みで表示義務を満たしているもの。
-
自分の体調や持病、薬の服用有無を確認し、医師・薬剤師に相談してから使うこと。特に鉄・亜鉛・マグネシウムなどのミネラル過剰摂取は逆効果になることもあります。
-
継続期間を決めて、“様子を見ながら”使うこと。体の変化(疲れの取れ具合・肌・気分など)をメモしておくと、自分に合ったものが見えてきます。
✨まとめ
サプリは「食事で十分に補いきれない栄養を手軽に補うための補助ツール」です。
-
まずはマルチビタミン・ミネラル系で栄養バランスを整え、
-
疲れが強い・鉄・ビタミンB群が気になる場合は特化型を併用して、
-
続けやすさ&安心製造を基準に選ぶことで、効果を最大限に引き出せます。
ただし、サプリだけで「栄養不足を全部解決!」というわけではないため、食事・睡眠・運動・ストレスケアなどの基本生活習慣が土台となることを忘れずに。
まとめ|「疲れが取れない」は体からのSOS
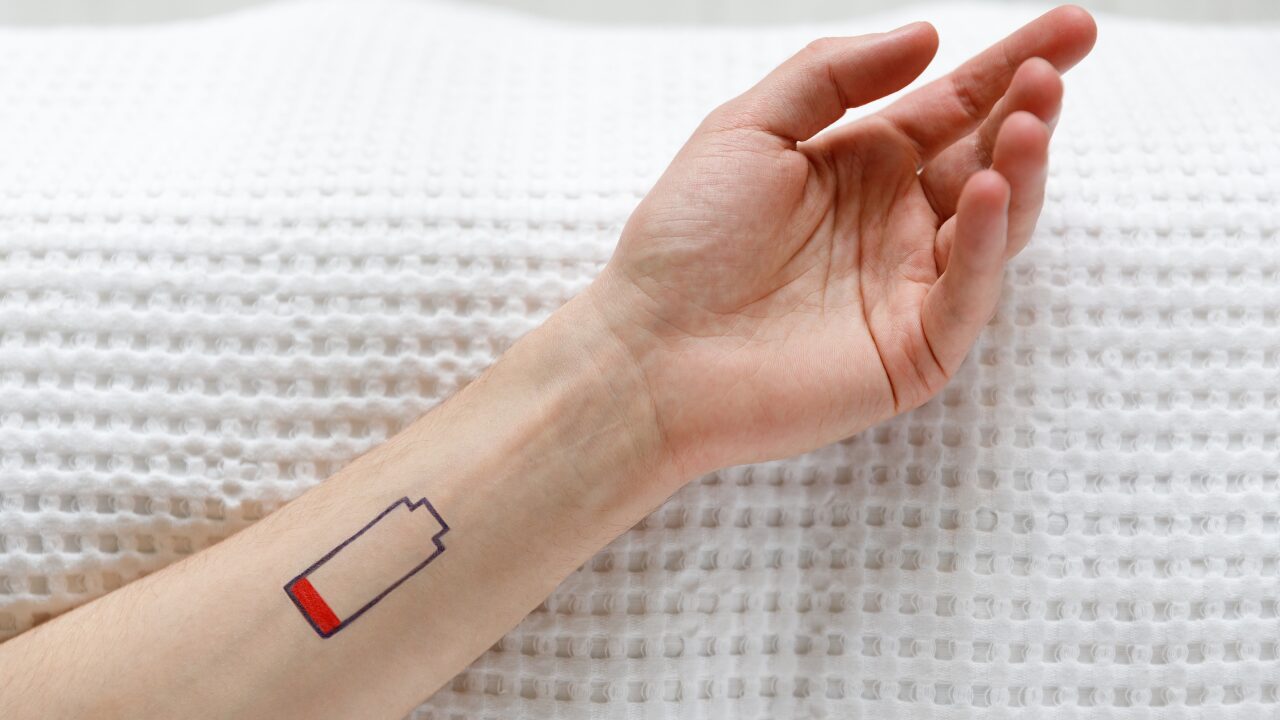
「しっかり寝たのに疲れが抜けない」「何をしてもだるい」――そんなとき、あなたの体は“もう限界”というサインを出しているのかもしれません。
それは単なる一時的な疲れではなく、栄養・休養・生活リズムのバランスが崩れている証拠です。
無理に我慢したり、カフェインや気合いで乗り切ろうとせず、“体の声”に耳を傾けることが、回復の第一歩になります。
一時的な疲れではなく、体が「助けて」と言っているサイン
疲労は、体内でエネルギーが足りなくなったり、細胞の修復が追いつかないときに生じる“生理的な防御反応”です。
つまり「もう休んで」「何かが足りていない」と体が訴えているサイン。
そのまま放置すると、以下のような悪循環に陥るリスクがあります。
-
だるさ・眠気 → 集中力低下 → パフォーマンスの悪化
-
食欲不振や肌荒れ → 栄養吸収の低下 → さらなる疲労感
-
気分の落ち込み・イライラ → 睡眠の質低下 → 慢性疲労へ
これらの状態を「年齢のせい」「仕事が忙しいから」と片付けず、体からの“ヘルプ信号”として受け止めることが大切です。
小さなサインを見逃さず、早めにリセットする意識を持ちましょう。
栄養バランスを整えることが、最も確実な“疲労回復の近道”
慢性的な疲れを本質的に回復させるには、「休むこと」だけでは不十分です。
土台となるのは、体がエネルギーを生み出せる状態=栄養が満たされていること。
-
エネルギーを作る「ビタミンB群」
-
酸素を全身に運ぶ「鉄分」
-
抗酸化と代謝を助ける「マグネシウム・亜鉛」
-
細胞修復に欠かせない「たんぱく質」
これらの栄養素がバランスよく揃うことで、ようやく“疲労が取れる体”になります。
逆にどれかが欠けると、体は「回復したくてもできない」状態に。
今日からできることは、
-
コンビニでもたんぱく質・野菜・炭水化物を意識して選ぶ
-
疲労を感じたらビタミンB群・鉄・マグネシウムを意識的に摂る
-
食事で難しい場合は、サプリで補助する
という3つのシンプルなステップです。
「疲れが取れない」と感じたら、まずは体の中の“栄養タンク”を満たすこと。
それが、薬やエナジードリンクに頼らず、自分の力で回復できるいちばん確実な近道です。
💡まとめの一文
「疲れ」は、体があなたを守るためのメッセージ。
栄養と休養を見直して、“頑張れる体”から“ちゃんと回復できる体”へシフトしていきましょう。


