
「ねぇママ、“ガチ勢”ってなに?」「パパ、“エモい”ってどういう意味?」――ある日突然、子どもが放つ“謎ワード”に戸惑ったことはありませんか?
SNSやYouTube、学校などを通じて、子どもたちの言葉は驚くほど早く変化しています。中には大人には意味不明なワードも多く、思わず「どういうこと!?」と聞き返してしまうことも。
この記事では、子どもがよく使う最新の「謎ワード」を一覧で紹介し、その意味・使われ方・背景をわかりやすく解説します。親も知っておくことで、子どもの言葉の世界を理解し、より楽しいコミュニケーションにつなげることができます。
突然の「謎ワード」、どう受け止めればいい?
意味がわからなくても慌てないでOK
子どもが突然、「それな」「エモい」「ガチ勢」など、大人には聞き慣れない“謎ワード”を使い始めることがあります。
思わず「何それ!?」「そんな言葉使っちゃダメ!」と反応してしまいそうですが、実は多くの“謎ワード”は子ども同士の流行語や軽いノリの表現。深刻にとらえる必要はありません。
まずは落ち着いて、「最近そういう言葉が流行ってるんだな」と一歩引いて受け止めましょう。
言葉の背景を知ることで、むしろ子どものコミュニティや流行を理解するヒントにもなります。
「世代ギャップ」よりも「コミュニケーションのチャンス」
親世代からすると、意味のわからない言葉を使う子どもを見ると「言葉づかいが乱れているのでは?」と感じることもあります。
でも、そこで一番大切なのは**“否定ではなく会話”を選ぶこと**です。
たとえば、
「最近その言葉よく使うね。どういう意味なの?」
と軽く聞くだけで、子どもは嬉しそうに説明してくれることがあります。
「知らない=世代ギャップ」ではなく、「知ろうとする=信頼のきっかけ」。
子どもにとって“自分の世界を理解してくれる親”はとても安心できる存在です。
「どこで覚えたの?」とやさしく聞くのがポイント
もし少し気になる言葉や強い表現が出てきたときは、「どこで覚えたの?」と穏やかに質問してみましょう。
多くの場合、「YouTubeで見た」「友だちが言ってた」といった軽い経路で覚えているだけです。
このとき注意したいのは、
-
「そんな言葉、やめなさい!」と頭ごなしに否定しない
-
「意味を教えて」と好奇心をもって聞く
という2つの姿勢。
言葉の意味を一緒に調べることで、子どもの情報リテラシーを育てるきっかけにもなります。
「知らない言葉を調べてみる」――この習慣は、成長するうえでとても大切な力です。
💡まとめポイント
-
“謎ワード”は多くが流行語。焦らず観察する
-
世代差よりも会話のチャンスととらえる
-
否定ではなく、「教えて」と寄り添う姿勢が大切
よく使われる「謎ワード」一覧|意味と使い方をチェック!
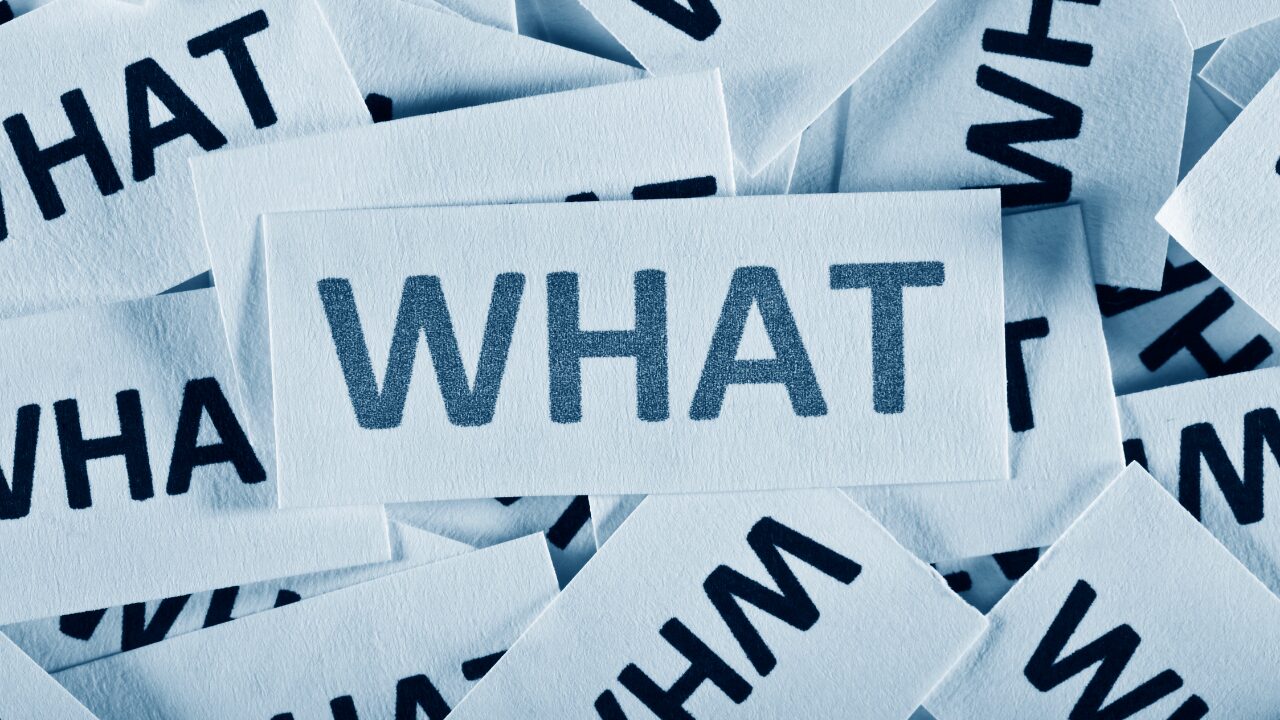
子どもたちの間では、テレビや本よりもSNSやYouTubeなどのネット文化から新しい言葉がどんどん生まれています。
ここでは、親が知っておくと安心できる代表的な“謎ワード”をカテゴリー別に紹介します。
「聞いたことあるけど意味がわからない…」という方は、ぜひここで整理してみましょう。
SNS・YouTube発のワード(例:それな〜/ガチ勢/バズる)
SNSや動画配信で生まれた言葉は、ノリの良さと短さが特徴。
YouTuberやインフルエンサーの口ぐせが、そのまま学校でも流行ることがあります。
-
それな〜:=「本当にそう思う」「共感!」という意味。相づち代わりに使う。
-
ガチ勢:=「本気で取り組んでいる人」「真剣なファン」。例:「あの子、推しのガチ勢だよね」
-
バズる:=「SNSなどで急に話題になる」「拡散される」。例:「その動画、バズってるよ!」
👉 どれも“軽いノリ”で使われる表現が多く、深刻な意味はない場合がほとんどです。
学校や友だち間で流行るワード(例:きもかわ/エモい/やばたにえん)
学校やクラスで自然発生的に流行るのがこのタイプ。
友だち同士の“共通のノリ”として使われ、感情を簡単に伝えられる言葉が多いのが特徴です。
-
きもかわ:=「気持ち悪いけどかわいい」。ぬいぐるみやキャラによく使う。
-
エモい:=「なんか心にくる」「切ない・懐かしい・感動的」など幅広い感情を表す。
-
やばたにえん:=「やばい!」をさらに面白く言うギャグ系ワード。
これらは「かわいい・面白い」をポジティブに言い換える表現で、感情のニュアンスを楽しむ文化から生まれています。
アニメ・ゲーム発ワード(例:チート/神回/無理ゲー)
アニメやゲームの世界で使われていた言葉が、日常会話にも広がったタイプ。
オタク文化や配信文化の影響で、小学生〜中学生にも浸透しています。
-
チート:=「ずるいほど強い・反則級」。例:「あのキャラ、チートすぎ!」
-
神回:=「最高の回・完璧な内容」。例:「今日のアニメ神回だった!」
-
無理ゲー:=「クリア不可能なゲーム」→転じて「難しすぎて無理」という意味。
これらは楽しさや感動を共有するための表現であり、ネガティブな意味合いは少ないのが特徴です。
「短縮語」「造語」系(例:マ?=本当?/それな=同意)
子どもたちは、日常会話をできるだけ短く・テンポよくするために言葉を省略する傾向があります。
文字やチャット文化の影響で、「略す」「くっつける」ことで独自の言葉を作るのが得意です。
-
マ?:=「マジ?」の略。驚きや確認のリアクションに使う。
-
それな:=「同感!」の意味。友だちの意見に共感するときに使う。
-
りょ:=「了解」の略。LINEやチャットで使われる定番。
短縮語は悪意ではなく、**「テンポよく会話する遊び」**として定着している場合が多いです。
地域・クラス内限定のローカル“謎ワード”もある!
実は、“謎ワード”の中には特定の地域やクラス限定の言葉も多く存在します。
「同じ学校でも学年が違えば通じない」「そのクラスだけの内輪ノリ」なども珍しくありません。
こうした言葉は、子どもたちの間で生まれる小さなコミュニティの“合言葉”。
無理に理解しようとするより、「楽しそうだね」「それってどんな意味なの?」と聞くことで、
子どもの世界を尊重する姿勢を見せることができます。
💡まとめポイント
-
謎ワードの多くは「SNS・友だち・ゲーム」発
-
意味を知れば安心できる言葉がほとんど
-
会話のきっかけとして使えば、親子関係がもっと近づく
なぜ流行る?子どもが「謎ワード」を使う理由

子どもたちはなぜ、突然聞いたこともないような“謎ワード”を使い始めるのでしょうか?
そこには、単なる流行やノリだけでなく、子どもの人間関係・心理的な背景が関係しています。
ここでは、その4つの理由を詳しく見ていきましょう。
仲間意識を強める“合言葉”として使われる
子どもにとって「同じ言葉を使うこと」は、**“仲間である証拠”**のようなもの。
「それな」「ガチで」「マジ無理」などの短いフレーズは、同年代の子たちが自然に共有する“合言葉”のように使われます。
言葉の意味そのものよりも、
「同じ言葉を使っている=同じ世界にいる」
という安心感や一体感が大きな目的です。
つまり“謎ワード”は、友だちとの絆を深めるコミュニケーションツール。
親が理解していなくても、子どもにとっては社会性を育むひとつのステップなのです。
SNSやYouTubeの影響で言葉が瞬時に拡散
現代の子どもたちは、テレビよりもSNSやYouTubeから新しい言葉を吸収しています。
人気のYouTuberやショート動画の中でよく聞く言葉が、数日で学校中に広がることも。
たとえば、ある動画で使われた「バズる」「チート」「神回」などが、
翌日には友だちとの会話で普通に登場する――そんなスピード感が当たり前になっています。
SNSは今や、“言葉の発信源”であり“拡散装置”。
子どもたちは無意識のうちに、ネット文化の波を日常会話に取り入れているのです。
「面白い」「ノリがいい」から広まりやすい
子どもたちの“謎ワード”は、意味よりも**「言ってて楽しい」「ノリがいい」**ことが大事。
テンポがよく、リズム感のある言葉は、まるで口ぐせやギャグのようにクラス全体に広がります。
たとえば「やばたにえん」「ぴえん」「チートすぎ」などは、
内容よりも“響きの面白さ”で広まった代表例です。
つまり、“謎ワード”は遊び心の延長線上。
大人から見ると意味不明でも、子どもにとっては“楽しいことば遊び”なのです。
「大人にはわからない」秘密のコード感が人気
もうひとつの大きな理由は、「大人には通じない」ことが楽しいという心理です。
子どもたちは成長とともに、「自分たちの世界」を持ちたくなるもの。
“謎ワード”は、その象徴ともいえる存在です。
「先生や親が知らない言葉を自分たちは知っている」という感覚が、
ちょっとした優越感や“自立心”の表れにもつながっています。
これは反抗ではなく、自然な成長のステップ。
秘密の言葉を共有することで、子どもたちは「自分たちの居場所」を感じているのです。
💡まとめポイント
-
“謎ワード”は仲間意識を深める「言葉の合言葉」
-
SNSの拡散力で流行が一瞬で全国に広がる
-
ノリの良さ・面白さが広まりやすさのカギ
-
“大人に通じない言葉”=子どもの世界を持つ喜び
親が知っておくと安心な「謎ワード」5つのチェックポイント

子どもが突然使い始めた“謎ワード”。
「ちょっと下品?」「その言葉、大丈夫?」と不安になる瞬間もありますよね。
でも、焦って注意する前に――5つのチェックポイントを押さえておくと安心です。
子どもの言葉づかいを“禁止”ではなく“理解”の方向で見守ることで、親子の関係もぐっと良くなります。
① 意味を決めつけずにまず調べる
まず大切なのは、「知らない=悪い言葉」と決めつけないこと。
“謎ワード”の多くは、ただの流行語やネットスラングで、特に悪意がないケースがほとんどです。
GoogleやSNSで検索したり、「〇〇 意味」で調べたりするだけでも、意外とすぐに理解できます。
もし不安な言葉が出てきたら、
「その言葉ってどういう意味で使ってるの?」
と穏やかに聞いてみましょう。
子ども自身も深い意味を知らずに使っている場合が多いです。
② ネガティブな意味かどうか確認する
中には、「人をバカにする」「悪口っぽい」といった言葉も存在します。
でも、それも意味を理解すれば誤解が防げることが多いです。
たとえば「草」=「笑う」というネットスラングや、「ざつ」と言う若者語など、
一見変に聞こえても実は軽い冗談だったりします。
ポイントは、
-
使われ方(文脈)を見る
-
相手を傷つけていないか確認する
この2点。
言葉単体ではなく、どう使っているかをチェックするのが正しい見守り方です。
③ 悪意ではなく“流行り”として使っている場合も多い
子どもたちは“流行に乗る”ことで仲間意識を感じます。
つまり、流行語を使うのは「周りに合わせたい」「楽しみたい」気持ちの表れ。
悪意や反抗心ではないことがほとんどです。
たとえば「チート」「神」「無理ゲー」なども、
大人が聞くと強い言葉に感じますが、子どもにとっては「すごい!」「難しい!」という
単なるテンション表現です。
親としては、「使い方が適切かどうか」を見守りながら、
「その言葉、どんなときに使うの?」
と会話のきっかけにしてみましょう。
④ SNS由来の言葉は出どころもチェック
SNSやYouTubeで生まれたワードの中には、元ネタや動画の内容が過激なものもあります。
言葉そのものよりも、**「どこで覚えたか」**に注目するのが大切です。
-
YouTuberの決めゼリフ
-
TikTokのトレンド音源
-
ゲーム実況のコメント文化
など、出どころを知ることで、言葉の使われ方や意図がわかります。
親が「どこで聞いたの?」と穏やかに聞くだけで、
安全なコンテンツ選びにもつながります。
⑤ 会話を止めずに“共有”のきっかけにする
一番大切なのは、「その言葉、使っちゃダメ!」と会話を止めないこと。
子どもが新しい言葉を使うのは、**「話したい」「聞いてほしい」**というサインでもあります。
もしよくわからないワードが出てきたら、
「面白い言葉だね!どんな意味?」
「ママ(パパ)も使ってみようかな(笑)」
といった“共有”のリアクションがおすすめ。
言葉を通して笑い合うことで、
子どもは「自分を理解してくれている」と感じ、家庭での会話も豊かになります。
💡まとめポイント
-
まずは意味を調べて冷静に理解する
-
文脈を見て“悪意”があるかを判断
-
多くは流行語。禁止より理解を
-
SNS発のワードは出どころを確認
-
否定せず、親子の会話チャンスに変える
子どもの言葉づかいにどう向き合えばいい?

子どもが使う「謎ワード」や流行語は、親世代には理解しづらいものもありますが、実は成長やコミュニケーションの一部として自然な現象です。大切なのは、言葉を頭ごなしに否定するのではなく、「なぜその言葉を使うのか?」を一緒に考える姿勢です。
「禁止」よりも「理解と対話」を大切に
「そんな言葉使わないの!」と否定すると、子どもは心を閉ざしてしまうことも。まずは「それってどういう意味?」と興味を持って聞く姿勢を示しましょう。親が理解しようとすることで、子どもも安心して言葉の背景を話してくれるようになります。
正しい日本語を学ぶバランス感覚を身につけよう
流行語を使うのは悪いことではありません。ただし、場面によって言葉を使い分ける力は必要です。家庭や学校など、場に応じて「丁寧な言葉」や「正式な表現」を学ぶ機会を大切にしましょう。
「流行語→定着語」になるケースも多い(例:マジ・ウケる など)
昔は若者言葉だった「マジ」「ウケる」も、今では一般的に使われる言葉になりました。言葉は時代とともに変化するもの。今の“謎ワード”も、数年後には普通の日本語として定着しているかもしれません。
「言葉の変化」も時代の成長の一部
新しい言葉は、子どもたちが社会や文化を反映して作り出したものです。無理に止めるよりも、「言葉の進化を一緒に観察する」というスタンスで見守ると、親子の会話も豊かになります。
💡 ポイント:
言葉づかいの変化は、子どもが社会と関わり、成長している証拠。
「理解 → 対話 → 指導」の順で、柔軟にコミュニケーションをとることが大切です。
まとめ|「謎ワード」も子どもの成長の一部

子どもが使う「謎ワード」は、単なる流行ではなく、成長や人間関係の広がりを映す鏡でもあります。親が理解を示すことで、子どもの世界を尊重しながら、より深い信頼関係を築くことができます。
言葉の変化を通して子どもの世界を理解しよう
「最近の言葉はわからない」と感じても、それは子どもが新しい文化や情報に触れている証拠です。意味を調べたり、実際に使われる場面を観察したりすることで、子どもがどんなコミュニティに関わっているのかが見えてきます。
言葉を知ることは、子どもの今を知る手がかりになるのです。
親子の会話が増えるチャンスに変えていこう
「それ、どういう意味?」「誰が言い出したの?」と興味を持って聞くことで、自然と会話のきっかけが生まれます。
「謎ワード」は親子の距離を縮めるきっかけにもなり得ます。笑いながら言葉の由来を話したり、一緒に調べたりする時間が、子どもの自己表現力や言葉への興味を育てていきます。
💬 まとめポイント:
子どもの「謎ワード」を否定せず、理解と共有のチャンスとして受け止めよう。
言葉の変化を一緒に楽しむことが、親子の信頼とコミュニケーションを深める第一歩です。
子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉はこちら🔻


