
「会話中に言葉が出てこない…」「あれ、名前が思い出せない…」そんな経験はありませんか?実は、これは40代以降だけでなく、20代・30代の若い世代にも起こり得る“脳のサイン”です。仕事やプライベートでスムーズに会話できないと、自信を失ったり人間関係に影響することも。
本記事では、言葉が出てこない原因と、その改善につながる脳トレ・生活習慣の見直し方法を分かりやすく解説します。
なぜ会話中に言葉が出てこなくなるのか?
会話の最中に「あれ?言葉が出てこない…」という経験は、20代・30代でも珍しくありません。実はこの現象には、脳の働き方や生活習慣、さらには体調や病気のサインなど、さまざまな要因が関わっています。ここでは主な原因と、それぞれに応じた対策を解説します。
脳の処理速度と記憶力の低下が影響
20代後半から30代にかけて、脳の処理速度やワーキングメモリ(作業記憶)は少しずつ変化していきます。情報を一時的に保持しながら処理する力が落ちると、「知っているのに出てこない」という現象が起きやすくなります。
対策
-
読書や新聞を声に出して読む(音読で言語中枢を活性化)
-
新しい趣味や学習で脳に刺激を与える
-
適度な運動で血流を良くし、脳の働きをサポートする
スマホ依存やストレスが関係していることも
スマホを長時間使う生活は「情報を探す力」ばかりが働き、自分の頭で思い出す機会が減ってしまいます。また、強いストレスや睡眠不足は脳の前頭葉機能を低下させ、言葉の切り替えや記憶の呼び出しがスムーズにできなくなります。
対策
-
スマホで調べる前に「少し思い出す」習慣をつける
-
睡眠の質を高める(就寝前のブルーライトを避ける)
-
軽い運動や深呼吸でストレスを和らげる
一時的なもの?それとも隠れた病気のサイン?
言葉が出てこないのは一時的な疲労や集中力低下によることもありますが、頻度が多くなったり、日常生活に支障をきたすほどになると注意が必要です。脳梗塞の前触れや、若年性認知症などが背景にあるケースも報告されています。
対策・チェックポイント
-
「物忘れ」だけでなく「言葉が出ない状態」が頻発していないか確認
-
記憶障害や注意力低下など、他の症状も伴う場合は医師に相談
-
不安を感じたら早めに脳神経内科や心療内科でチェックを受ける
20代・30代の「言葉が出てこない」状態を放置するとどうなる?

若い世代でも「言葉が出てこない」状態をそのままにしておくと、日常生活や将来に大きな影響を与える可能性があります。ここでは、放置した場合に起こりやすい問題と、それに対処するための方法を紹介します。
仕事のコミュニケーションに悪影響
会議やプレゼン中に言葉が出てこないと、自信がないように見られたり、誤解を招いて評価に響くことがあります。特に20代・30代はキャリア形成の重要な時期なので、伝達力の低下は大きなマイナスになりかねません。
対策
-
会議前に話す内容をメモにまとめておく(準備で安心感が増す)
-
専門用語や表現は「言い換えリスト」を作っておく
-
音読やアウトプット習慣で瞬発的に言葉を出すトレーニングをする
人間関係で誤解やストレスを生みやすい
友人や恋人との会話で言葉が出てこないと、「話を聞いていないのでは?」と誤解されたり、沈黙が気まずさや距離感を生むこともあります。自分自身も「うまく話せない」と落ち込み、会話を避けるようになり、孤立感が強まるケースもあります。
対策
-
無理に完璧な言葉を探すのではなく、「今ちょっと思い出せないけど…」と伝える
-
語彙力を増やすために日常的に本や記事を読む
-
友人と軽い雑談やしりとりなどで「言葉遊び」を楽しむ
将来的な認知機能低下のリスクにつながる可能性
言葉がスムーズに出てこない状態は、脳の言語中枢が十分に働いていないサインでもあります。若い世代で頻発する場合、長期的には集中力や記憶力の低下につながり、認知症リスクを高める要因になるともいわれています。
対策
-
有酸素運動(ウォーキング・ジョギング)で脳の血流を改善
-
食生活を見直し、魚やナッツなど脳に良い食材を取り入れる
-
脳トレ(クロスワード・暗記・音読)で日常的に刺激を与える
-
頻繁に症状が出る場合は、早めに医療機関で相談する
改善の第一歩!日常生活でできる簡単な対策

「会話中に言葉が出てこない」状態を改善するためには、特別なトレーニングよりも、まずは日常生活を整えることが第一歩です。脳の働きをサポートし、自然に言葉を引き出せる環境を作ることで、スムーズな会話がしやすくなります。
睡眠・食生活を整えて脳の働きをサポート
脳は、睡眠と栄養によって大きくパフォーマンスが変わります。睡眠不足や偏った食生活は、集中力や記憶力の低下を招きやすく、「言葉が出ない」状態を悪化させる原因になります。
対策
-
7時間前後の質の良い睡眠を確保する(就寝前のスマホは避ける)
-
魚(DHA・EPA)やナッツ類、野菜をバランス良く摂る
-
コーヒーやエナジードリンクの過剰摂取は控え、適度な水分補給を意識する
読書や人との会話で「言葉の引き出し」を増やす
普段から新しい言葉や表現に触れておくことは、会話力アップに直結します。読書や人との対話を通じて、語彙を自然に増やすことができ、必要な場面でスッと取り出せるようになります。
対策
-
毎日10分だけでも本や新聞を読む習慣をつける
-
「面白いと思った表現」をメモしておく
-
人との会話では、相手の言葉を繰り返したり要約して返す(記憶+アウトプット練習になる)
ながらスマホを減らして集中力を取り戻す
スマホを触りながらの食事や会話は、脳の注意力を分散させ、言葉を思い出す力を弱めます。「ながらスマホ」を減らすだけで、集中力が戻り、会話中に言葉を思い出しやすくなります。
対策
-
食事中や会話中はスマホを手元から離す
-
情報をすぐ検索せず、まずは自分で思い出す習慣をつける
-
1日の中で「スマホを見ない時間」を意識的に作る
おすすめの脳トレ法|言葉を引き出す力を鍛える
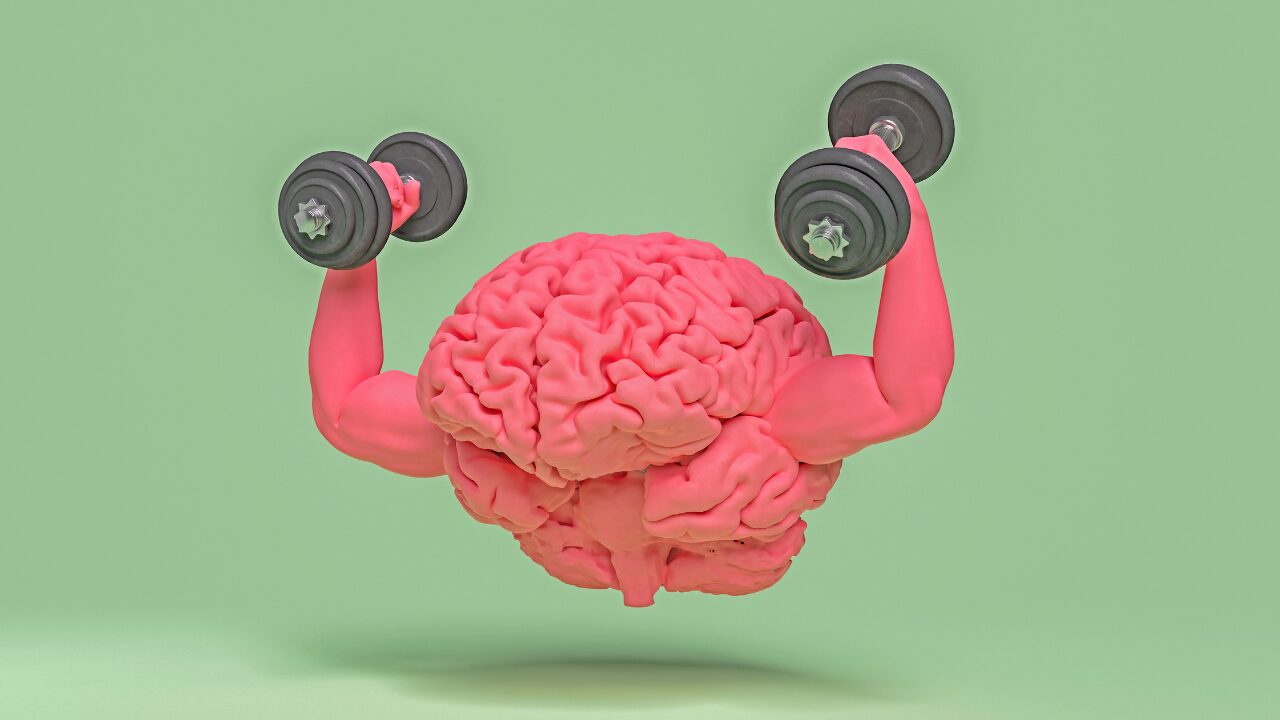
「言葉が出てこない」状態を改善するには、脳の言語中枢に適度な刺激を与えることが効果的です。ここでは、楽しみながら続けられて、会話力アップにもつながる脳トレ方法を紹介します。
しりとり・早口言葉・暗唱で言語中枢を刺激
子どもの遊びのように思える「しりとり」や「早口言葉」も、実は脳の言語処理を鍛える優秀なトレーニングです。また、短い詩や名言を暗唱することで、記憶力と瞬発的な言葉のアウトプット力が高まります。
具体的なやり方
-
家族や友人としりとりをする(制限時間をつけると効果UP)
-
早口言葉を毎日1分チャレンジ
-
好きな歌詞や名言を覚えて、声に出して暗唱する
クロスワードや漢字パズルで語彙力を強化
語彙力不足が「言葉が出てこない」原因の一つです。クロスワードや漢字パズルは、新しい言葉や熟語に触れるきっかけになり、自然に語彙が増えていきます。
具体的なやり方
-
新聞や雑誌のクロスワードを定期的に解く
-
漢字パズルや四字熟語クイズをスマホアプリで取り入れる
-
わからない言葉が出てきたら、その場で調べて「自分の言葉帳」にメモする
音読・アウトプット習慣で会話力アップ
言葉を「頭で理解するだけ」でなく「口に出して使う」ことで、記憶に定着しやすくなります。特に音読やアウトプット習慣は、会話での言葉選びをスムーズにする効果が期待できます。
具体的なやり方
-
毎日5分、新聞や本を音読する
-
読んだ内容をSNSや日記に要約して書く
-
一日の出来事を人に話すとき、「3つのポイント」でまとめて伝える練習をする
改善が感じられないときは?|受診の目安とチェックリスト

日常的な工夫や脳トレをしても「言葉が出てこない」状態が改善しない場合、放置せず医療機関に相談することも大切です。特に20代・30代であっても、隠れた病気が関わっているケースもあるため、早めに見極めましょう。
単なる物忘れか、注意すべき症状かを見極める
誰にでも「ど忘れ」はありますが、問題はその頻度と影響の度合いです。
-
一時的に思い出せないだけで後から出てくる → 生活習慣や疲労が原因の可能性が高い
-
何度も同じことを忘れる、会話に支障をきたす → 注意が必要
ポイント
-
「言葉が出ない」が日常生活や仕事に影響していないかチェック
-
頻度が増えている、悪化している場合は早めに相談
受診を考えるべきサイン一覧
次のようなサインがある場合は、脳神経内科や心療内科などの受診を検討しましょう。
-
知っている人や物の名前が頻繁に出てこない
-
同じ話を何度も繰り返してしまう
-
言葉が出ないだけでなく、注意力・判断力の低下もある
-
突然のしびれ・めまい・ろれつが回らないなどの症状を伴う
-
不安感やうつ症状とセットで現れている
医師に相談する前に整理しておきたいこと
受診する際は、医師にできるだけ正確に伝えることが診断の助けになります。事前に以下を整理しておきましょう。
チェックリスト
-
言葉が出てこない頻度(週に何回・どんな場面で)
-
その状態がどのくらい続いているか(期間)
-
他に気になる症状(頭痛・めまい・気分の落ち込みなど)
-
睡眠・食生活・ストレス状況
-
家族に同様の症状があるかどうか
こうした情報をまとめておくことで、医師が原因を絞り込みやすくなり、適切な対応につながります。
まとめ|言葉が出てこないのは、20代・30代でも起こり得る“脳のSOS”

「会話中に言葉が出てこない」という悩みは、年配者だけの問題ではなく、20代・30代の若い世代にも起こり得ます。これは一時的な疲労やストレスのサインであることもあれば、脳が「ちょっと休ませて」と訴えているSOSであることもあります。大切なのは、「まだ若いから大丈夫」と放置せず、日常生活の中で小さな改善を積み重ねることです。
早めの対策で会話力と脳の健康を守ろう
言葉が出にくい状態を放置すると、仕事や人間関係に影響を与えるだけでなく、将来的な認知機能低下のリスクにもつながります。早めに気づいて対策をとれば、会話力を守るだけでなく、脳の健康そのものを維持することができます。
ポイント
-
「最近ちょっとおかしいな」と思ったら小さな生活改善からスタート
-
深刻な場合は早めに医師へ相談し、安心材料を得る
脳トレと生活習慣の改善で変化は実感できる
睡眠・食事・運動を整えつつ、しりとりや音読、クロスワードなどの脳トレを取り入れると、言葉の引き出しが少しずつ増えていきます。継続することで「前よりスムーズに話せる」「会話が楽しい」と変化を実感できるはずです。
行動のヒント
-
1日10分の読書や音読を続けてみる
-
会話中にスマホ検索せず、自分の記憶を使う習慣をつける
-
「脳に良い生活リズム」を整えることを第一歩にする
👉 言葉が出てこないのは“脳の衰え”ではなく“改善のチャンス”と考えて、今日からできる小さな工夫を始めてみましょう。
言葉がなかなか出てこない人の思い出しドリル大全🔻


