
「なぜ“油を売る”がサボる意味になるの?」「“猫の手も借りたい”って、なぜ猫?」──
日常でよく使う日本語の言い回し、よく考えるとちょっと不思議ですよね。
実はその多くには、昔の人の暮らしや感覚、時代背景が隠されています。
この記事では、思わずツッコミたくなる日本語表現20選をピックアップし、
それぞれの意味・由来・使い方をわかりやすく解説します。
読み終えたころには、「言葉ってこんなに面白いんだ!」と感じるはずです。
なぜそう言うの?思わずツッコミたくなる表現20選
① 「油を売る」──サボることと油に何の関係が?
意味: 仕事中にこっそりサボる、無駄話をすること。
由来: 江戸時代、油売りの商人が油を量る際、時間がかかるために世間話で客をつないでいたことから、「油を売る=長話をして時間をつぶす」になったと言われています。
使い方: 「あの子、仕事中に油売ってないで手を動かして!」
② 「二の舞を演じる」──“舞”が失敗の象徴になった理由
意味: 他人と同じ失敗を繰り返すこと。
由来: 平安時代の能楽で、ある舞手が失敗した舞(“一の舞”)を、次の舞手も同じように間違えたことから「二の舞」と呼ばれるようになりました。
使い方: 「彼の二の舞を演じないよう、しっかり準備しよう。」
③ 「猫の手も借りたい」──なぜ“猫”なの?
意味: 非常に忙しく、誰でもいいから手伝ってほしい状態。
由来: 猫は普段役に立たない存在として見られていたため、「そんな猫の手でもいいからほしい」という比喩になりました。
使い方: 「年度末は猫の手も借りたいほど忙しい!」
④ 「馬が合う」──“馬”で相性を表すのはなぜ?
意味: 気が合う、相性がよい。
由来: 馬はペアで走るとき、テンポやリズムが合わないと転倒することから、人間関係の相性を「馬が合う」と表すようになったとされています。
使い方: 「彼とは初対面なのに馬が合った。」
⑤ 「棚からぼたもち」──なぜ“棚”と“ぼたもち”?
意味: 思いがけず幸運が舞い込むこと。
由来: 棚の上に置いたぼたもちが、偶然落ちてきて口に入る──そんな都合のよさを表したもの。江戸時代のことわざです。
使い方: 「応募したら当たった!棚からぼたもちだね。」
⑥ 「のれんに腕押し」──“のれん”が比喩に使われる理由
意味: 手応えがない、反応が薄い。
由来: のれん(布のれん)は押しても力が伝わらないことから、「努力しても反応がない」状態を指すようになりました。
使い方: 「何を言ってものれんに腕押しって感じだ。」
⑦ 「尻に火がつく」──なぜ“尻”?その由来は意外な日常動作
意味: 物事が切羽詰まる、追い込まれること。
由来: 昔の囲炉裏の近くで座っていて、火の粉が飛んで尻が熱くなり、慌てて動き出す様子から。
使い方: 「締切が明日?尻に火がついた!」
⑧ 「雲行きが怪しい」──天気じゃなく“状況”に使うのはなぜ?
意味: 物事の進行が不穏な方向に向かっている。
由来: 本来は空模様が悪くなる様子を表していましたが、そこから転じて「状況の悪化」に使われるようになりました。
使い方: 「会議の雲行きが怪しいな…」
⑨ 「腹を割る」──正直に話すことと“腹”の関係
意味: 本音をさらけ出して話すこと。
由来: 「腹」は心情を象徴する場所とされ、腹の中を見せる=本心を明かすという意味が生まれました。
使い方: 「そろそろ腹を割って話そうか。」
⑩ 「口が滑る」──どうして“口”が動く表現に?
意味: うっかり言ってはいけないことを話してしまうこと。
由来: 口がなめらかに動く=余計なことまで話してしまう様子をたとえたもの。
使い方: 「しまった、つい口が滑った!」
⑪ 「耳にタコができる」──なぜ“タコ”?実際にできるの?
意味: 同じことを何度も聞かされてうんざりすること。
由来: 同じ場所を何度も刺激してできる“たこ”を、比喩的に耳に置き換えた表現です。
使い方: 「その話、もう耳にタコができるほど聞いた!」
⑫ 「水に流す」──なぜ“水”で許すことになる?
意味: 過去のいざこざを忘れて、なかったことにする。
由来: 流れる水が汚れを洗い流す様子から、「過去のことを清める・忘れる」という意味になりました。
使い方: 「もう過去のことだし、水に流そう。」
⑬ 「手を焼く」──なぜ“手”で“困る”を表す?
意味: 扱いに困る、どうにもできない。
由来: 直訳的には「火傷するほど扱いが難しい」という比喩。子どもや問題に「手を焼く」と言います。
使い方: 「うちの息子にはほんと手を焼くよ。」
⑭ 「顔が広い」──なぜ“顔”で交友関係を言うの?
意味: 知り合いが多く、人脈が広いこと。
由来: 「顔」はその人を象徴するもの。多くの人に顔を知られている=交際範囲が広いとされました。
使い方: 「彼はこの業界で顔が広い。」
⑮ 「猫をかぶる」──かわいいけど、実は計算高い表現?
意味: 本性を隠しておとなしく装うこと。
由来: 猫が一見おとなしく見えて、実は俊敏で気まぐれな動物であることから、人間の偽りの態度をたとえました。
使い方: 「最初は猫をかぶってたけど、今は本性がバレた。」
⑯ 「虫の居所が悪い」──なぜ“虫”が感情の比喩に?
意味: 機嫌が悪い、気分がすぐれない。
由来: 古来、人の体には“感情を司る虫”がいると信じられており、その虫の位置が悪いと怒りっぽくなると考えられました。
使い方: 「今日は虫の居所が悪いみたいだからそっとしとこう。」
⑰ 「足を引っ張る」──物理的に?それとも心理的に?
意味: 他人の成功や進行を妨げること。
由来: 競技や戦で、前に進もうとする相手の足を引く=邪魔することから。
使い方: 「足を引っ張るようなことはしたくない。」
⑱ 「青二才」──なぜ“青”と“二才”?若者を表す謎
意味: 未熟な若者。
由来: 「青」は未熟、「二才(にさい)」は年若い人を指す言葉。つまり“未熟な若者”という二重表現。
使い方: 「あの頃は青二才で何も知らなかった。」
⑲ 「骨が折れる」──“苦労する”と“骨”の意外な関係
意味: 労力がかかる、たいへん苦労すること。
由来: 骨を折るほど力を入れる=大変な努力をするという比喩。実際に折るわけではありません。
使い方: 「ここまで仕上げるのに骨が折れたよ。」
⑳ 「一肌脱ぐ」──助けることと“脱ぐ”の意外なつながり
意味: 力を貸す、協力する。
由来: 江戸時代、男性が本気で助けようとするとき、上着を脱いで仕事に取りかかったことから生まれた言葉。
使い方: 「困ってるなら、一肌脱ぐしかないな!」
意味や由来を知ると、日本語がもっと面白くなる

私たちが日常で何気なく使っている言葉の多くは、昔の人々の生活や風習、信仰、仕事の様子から生まれたものです。
「油を売る」や「棚からぼたもち」など、一見不思議な言い回しも、当時の暮らしを知ると「なるほど」と納得できます。
たとえば、江戸時代の商人や職人の動作、農村での生活習慣、自然を神聖視する日本古来の考え方など──。
そうした背景が、今も私たちの言葉の中に息づいているのです。
言葉の由来を知ることは、単なる雑学ではなく、日本人の感性や文化を知る手がかりにもなります。
「なぜそう言うの?」と調べてみると、昔の人のユーモアや観察力に思わず感心することも。
また、こうした知識は、子どもや外国人に日本語を教えるときにも役立ちます。
単語の背景を一緒に説明することで、言葉の面白さや日本文化の奥深さをより伝えやすくなります。
意味や由来を知ることで、
普段の会話も、文章も、ちょっとした表現の“味わい”が増す。
──そんなところに、日本語の魅力が隠れているのです。
まとめ|“言われてみれば不思議”が、日本語の面白さ
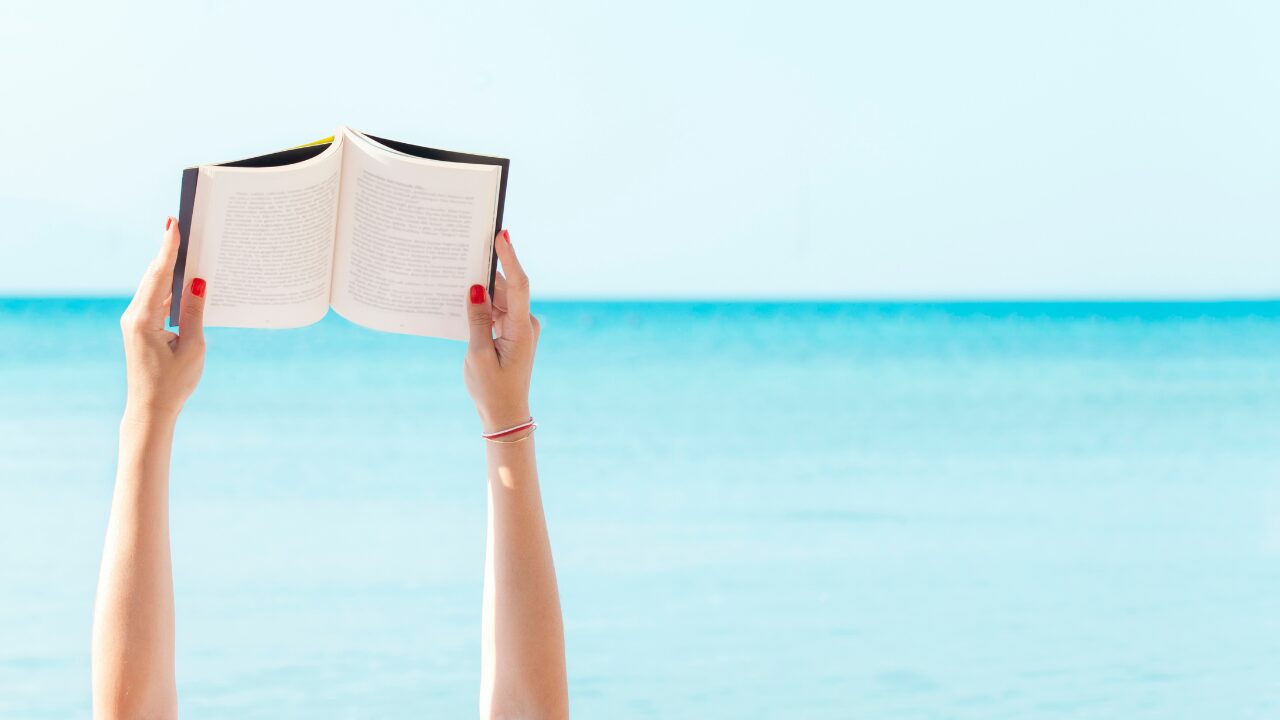
日々使っている日本語には、その時代を生きた人々の知恵や文化、感情がぎゅっと詰まっています。
「なぜそう言うの?」と感じる表現ほど、実は昔の暮らしや価値観が色濃く映し出されているものです。
たとえば「馬が合う」には動物との共生の歴史が、「水に流す」には自然とともに生きてきた感性が隠れています。
そんな背景を知ることで、言葉が単なる“記号”ではなく、“文化の物語”として感じられるようになります。
言葉の由来を調べることは、知識を増やすだけでなく、自分の世界を少し広げる行為です。
そしてその発見は、日常の会話にも豊かな彩りを添えてくれます。
これから使う一つひとつの言葉にも、「どうしてこう言うんだろう?」という小さな好奇心を持ってみましょう。
きっと、当たり前に使っていた日本語が、ぐっと面白く、愛おしく感じられるはずです。
よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑🔻


