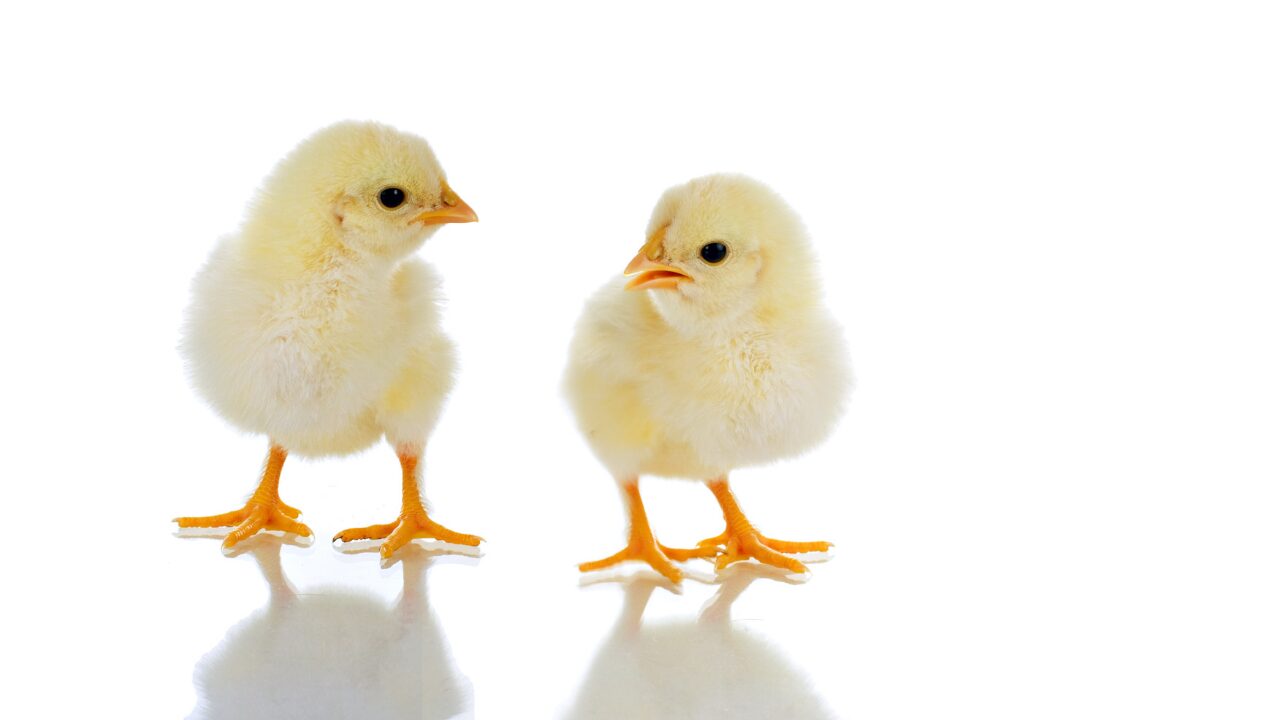
「自分って平均より上?それとも下?」そんな素朴な疑問をデータで徹底解説!
この記事では、日本人の平均身長・体重・睡眠時間・年収・貯金額・生活習慣まで幅広くまとめました。信頼できる統計データをもとに、男女・年代・世界比較なども紹介。「平均」を知ることで、自分の立ち位置やライフスタイルを考えるヒントが見つかります。
そもそも「平均」ってどうやって出してる?信頼できるデータの見分け方
「日本人の平均身長」や「平均年収」といった数値は、ニュースやネット記事でよく目にしますよね。ですが、一口に“平均”といっても算出方法や参照するデータの出どころによって、意味が大きく変わることがあります。正しく理解していないと、実際の感覚とズレていたり、誤解したまま比較してしまうことも…。ここでは、「平均」を理解するための基本ポイントと、信頼できるデータの見分け方を解説します。
平均値と中央値の違いとは?
-
平均値(算術平均)
集団全体の数値を合計し、人数で割ったもの。もっとも一般的に使われますが、極端に大きな数値や小さな数値があると、全体の実態を正しく反映しないことがあります。
例:年収の平均値は、一部の高収入層によって大きく引き上げられがち。 -
中央値
データを小さい順に並べて、ちょうど真ん中に位置する数値。外れ値の影響を受けにくく、実際の「真ん中の人」を示すため、生活実感に近い数字として使われることが多いです。
例:平均年収の中央値を確認すると、「一般的な水準」がよりリアルに見えてきます。
👉 つまり、「平均」という言葉を見たときには、それが 平均値なのか中央値なのか を意識することが大切です。
国が出す統計と民間調査の使い分け
平均データを調べる際は、どの機関が出している調査なのかも重要なポイントです。
-
国の統計(信頼度が高い)
総務省統計局や厚生労働省、文部科学省などが行う大規模調査。サンプル数が多く、長年の推移も追えるため信頼性が高いのが特徴です。
例:国勢調査、国民健康・栄養調査、労働力調査など。 -
民間調査(身近で具体的)
就職・転職サイトや調査会社などが独自に集めたアンケート結果。対象が限定されるぶん、国の統計よりも偏りが出ることがありますが、最新トレンドや実際の体感を反映しているケースもあります。
例:「転職サイトが発表する平均年収ランキング」など。
👉 平均を知るときは、「国の統計で長期的な傾向を見る」「民間調査で直近の動きを知る」といった使い分けをすると、より正確に理解できます。
最新版!日本人の平均身長・体重【男女・年代別データ】

日本人の身長や体重は、年齢や性別、さらに時代によって少しずつ変化しています。成長期の子どもから大人世代までの平均値を知ることで、自分や家族の健康チェックの目安にもなります。ここでは、小学生から高校生の成長データ、成人世代の男女別データ、そして世界と比較した日本人の体格の特徴を見ていきましょう。
小学生〜高校生の平均身長・体重の推移
文部科学省の「学校保健統計調査」によると、子どもの身長や体重は年齢ごとに大きく変化します。
-
小学生低学年(6〜8歳)
男子:身長115〜125cm前後、体重20〜25kg前後
女子:身長115〜124cm前後、体重19〜24kg前後 -
小学生高学年(10〜12歳)
男子:身長135〜145cm、体重30〜40kg
女子:身長135〜147cm、体重30〜42kg
→ この時期は女子の方が早く成長する傾向があり、男子を一時的に上回ることも多いです。 -
中学生〜高校生(13〜17歳)
男子:中学〜高校にかけて一気に伸び、最終的に170cm前後まで成長
女子:中学初期に成長がピークを迎え、高校生では155〜160cm前後に落ち着く
👉 成長期は個人差が大きいため、平均値と多少違っても心配はいりません。むしろ「成長のリズムが人それぞれ」であることを理解しておくことが大切です。
20代〜60代の男女別平均身長・体重
成人の身長・体重は加齢とともに微妙に変化します。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、以下のような傾向が見られます。
-
20代〜30代
男性:身長171cm前後、体重68kg前後
女性:身長158cm前後、体重52kg前後 -
40代〜50代
男性:身長170cm前後、体重70kg前後
女性:身長157cm前後、体重54kg前後
→ 生活習慣や代謝の変化により、40代以降は体重がやや増加する傾向があります。 -
60代以降
男性:身長168cm前後、体重67kg前後
女性:身長154cm前後、体重52kg前後
→ 加齢に伴う骨密度や筋肉量の減少で、身長がやや縮むこともあります。
👉 年代ごとの数値を見ることで、自分が「同世代と比べてどうか」が分かりやすくなります。
世界と比べた日本人の体格の特徴
日本人の平均身長は世界的に見ると 中程度からやや低め に位置します。
-
男性:日本は170cm前後で、オランダ(183cm前後)やアメリカ(177cm前後)と比べると低め。
-
女性:日本は157cm前後で、世界的には平均的な高さ。ただし北欧諸国(170cm前後)と比べると差が大きいです。
体重に関しては、日本人は欧米諸国と比べて 肥満率が低く、体格がスリム なのが特徴。これは食習慣や生活スタイルの違いが影響しています。
👉 世界と比較すると、日本人は「小柄だけれど健康的でバランスの取れた体格」といわれることも多いです。
✅ まとめると:
-
子どもの成長は女子が早め、男子は中高生で一気に伸びる
-
成人の身長は20代でピーク、体重は40代以降で増えやすい
-
世界と比べると日本人はやや小柄だがスリムな体型が特徴
平均睡眠時間はどれくらい?年齢・性別での違いも解説

「なんとなく寝不足…」と感じる日本人は多いですが、実際に私たちがどのくらい眠っているのか知っていますか?睡眠時間は年齢や性別、さらに国ごとでも大きく違います。ここでは、日本人の平均睡眠時間と世界比較、さらに年代や男女による違い、理想の睡眠時間とのギャップを詳しく見ていきましょう。
日本人の平均睡眠時間と世界比較
OECD(経済協力開発機構)の国際調査によると、日本人の平均睡眠時間は 約7時間22分。これは加盟国の中でも最も短い水準です。
-
日本:7時間22分
-
アメリカ:約8時間30分
-
フランス:約8時間50分
-
韓国:約7時間41分
👉 世界的に見ると、日本人は「睡眠時間が短い国」として知られています。働き方や生活リズムの影響が大きく、慢性的な睡眠不足が社会問題として指摘されているのです。
年代別・性別の睡眠時間の違い
厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、日本人の睡眠時間は 年齢が上がるにつれて短くなる傾向 があります。
-
20代〜30代
男性:約7時間弱 / 女性:約7時間前後
→ 仕事や子育てで生活リズムが乱れやすく、不眠や寝不足の自覚が多い世代。 -
40代〜50代
男性:約6時間半前後 / 女性:約6時間40分前後
→ 睡眠時間が最も短い年代。仕事の忙しさや家庭の責任により、質の良い睡眠を確保しにくい。 -
60代以降
男性:約6時間半前後 / 女性:約6時間50分前後
→ 睡眠時間そのものは長くならないが、早寝早起きの生活パターンに移行しやすい。
👉 男女差でみると、女性の方がやや長く眠る傾向があります。ただし、妊娠や更年期などライフイベントで睡眠の質が下がりやすいのも特徴です。
理想の睡眠時間とのギャップ
専門家によれば、成人に必要な睡眠時間は 7〜9時間 が目安とされています。
しかし、日本人の平均睡眠は多くの年代で7時間を切っており、理想より短いのが現状です。
-
推奨:7〜9時間
-
日本の現実:6〜7時間前後
👉 この差が積み重なると、集中力の低下や生活習慣病リスク、メンタル不調につながる可能性があります。
「自分は平均よりも少ないかも?」と思ったら、就寝時間を30分だけ早める、寝る前のスマホを控えるといった小さな工夫から始めてみましょう。
✅ ポイントまとめ:
-
日本人の睡眠は世界的に見ても短め
-
40〜50代が最も睡眠時間が少ない
-
理想の7〜9時間に届かず、慢性的な睡眠不足が課題
平均年収・貯金額もチェック!あなたは上?下?

「自分の年収や貯金は平均と比べてどうなんだろう?」と気になる人は多いはず。
ただし、平均には“見せかけの高さ”があるため、正しく理解することが大切です。ここでは、日本人の平均年収と貯金額を年代・性別・世帯別に整理し、さらに“中央値”と比べたリアルな状況を解説します。
日本人の平均年収【年代・性別・業界別】
国税庁「民間給与実態統計調査」によると、日本人の 平均年収は約443万円(最新データ)。
-
年代別の傾向
-
20代前半:250〜300万円前後
-
30代:400万円前後
-
40代:500万円前後(ピーク)
-
50代以降:やや下がり400万円台へ
-
-
男女別の違い
-
男性:約540万円
-
女性:約300万円
→ 男女差は依然として大きく、働き方の違い(正社員か非正規か)も影響しています。
-
-
業界別の特徴
-
金融・保険業:高め(平均600万円超)
-
IT・通信業:年収上昇中(平均550万円前後)
-
サービス・小売業:低め(平均300〜350万円前後)
-
👉 年収は「年代」「性別」「業界」で大きく変わるため、同世代や同業種で比較することが大切です。
平均貯金額と世帯ごとの違い
金融広報中央委員会の調査によると、世帯ごとの平均貯金額は以下の通りです。
-
単身世帯:平均653万円
-
二人以上の世帯:平均1,500万円超
ただし、この平均値は一部の「資産を多く持つ世帯」によって大きく引き上げられています。実際には「貯金ゼロ」という人も約2割程度存在します。
👉 平均だけを見て「全然足りない!」と焦るのではなく、世帯状況やライフステージに応じた目安としてとらえることが大切です。
中央値と比べると見えてくるリアル
平均値は極端に高額な層に引っ張られるため、「実際の感覚」とはズレることがあります。そこで参考になるのが 中央値。
-
年収の中央値:約373万円
-
貯金額の中央値:単身世帯 約50万円、二人以上世帯 約1,000万円
👉 平均と比べると「ずいぶん低い」と感じるかもしれませんが、これが“真ん中の人”のリアル。
つまり、「平均より下だからダメ」というわけではなく、中央値に近いかどうかで自分の位置を把握した方が現実的です。
✅ ポイントまとめ:
-
日本人の平均年収は約443万円だが、中央値は約373万円
-
貯金は平均より中央値を参考にした方が現実に近い
-
年代・性別・業界・世帯状況ごとに大きな差がある
食生活・運動習慣などの生活リズムの平均って?

「健康的な生活を送りたい」と思っていても、実際に自分の生活習慣が平均と比べてどうなのかは意外と知らないものです。ここでは、日本人の平均的な運動量や食生活、そして健康診断から見える生活習慣の実態を整理してみましょう。
1日の平均歩数と運動習慣
厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、日本人の 1日の平均歩数 は次の通りです。
-
男性:約7,000歩
-
女性:約6,000歩
推奨される1日の目標歩数は 8,000〜10,000歩 とされており、実際の数値は少し足りないのが現状です。
また、週に1回以上運動をしている人の割合は約3割程度。特に20〜40代は仕事や生活の忙しさから運動習慣を持つ人が少なく、40代以降になると健康意識が高まって徐々に増える傾向があります。
👉 「歩数は足りてる?」「週1回でも運動できてる?」と見直すことが、自分の健康リズムのチェックになります。
食事の回数・外食の頻度
-
食事の回数
日本人の大半は「1日3食」を基本にしているものの、20〜30代では「朝食を抜く」人が2〜3割程度存在します。特に単身世帯や働き盛りの世代に多い傾向です。 -
外食の頻度
-
週1〜2回程度が平均
-
男性単身世帯や20代〜30代では「週3回以上」が目立つ
-
50代以降や家族世帯は外食頻度が少なく、家庭料理中心
-
👉 平均と比べて自分の食生活がどうかを振り返ることで、「栄養バランスの改善点」が見えてきます。
健康診断データから見る生活習慣の実態
健康診断の統計からは、日本人の生活習慣に関する特徴も見えてきます。
-
BMI(体格指数)の平均
-
男性:23前後
-
女性:22前後
→ 基準値(18.5〜24.9)の範囲にあるものの、30代以降は「肥満傾向」が増加。
-
-
生活習慣病の予備群
高血圧や高コレステロール、血糖値の異常は40代以降で急増。特に男性は「飲酒・喫煙・運動不足」が複合してリスクを高めています。 -
検診受診率
国の目標は80%ですが、実際の受診率は約60%前後にとどまっています。
👉 健康診断の結果は「生活習慣の平均点表」のようなもの。受診していない人はまず“平均のライン”に参加することが健康維持の第一歩です。
✅ ポイントまとめ
-
日本人の平均歩数は男性7,000歩、女性6,000歩とやや不足気味
-
食生活は「朝食を抜く若年層」と「外食が多い単身世帯」が目立つ
-
健康診断では40代以降に生活習慣病のリスクが増加
日本人の「結婚」「子ども」「恋愛」の平均事情

平均初婚年齢と結婚率の推移
近年、日本人の初婚年齢は右肩上がりで上昇しています。厚生労働省の統計によると、男性は平均約31歳、女性は約29歳で初婚を迎えるのが一般的です。昭和時代は20代前半での結婚が主流でしたが、学業の延長や就労環境の変化、ライフスタイルの多様化により晩婚化が進行。加えて、結婚そのものを選択しない人も増え、婚姻件数は長期的に減少傾向にあります。
平均子ども人数と出生率の変化
日本の合計特殊出生率は1.2前後で推移しており、平均子ども人数は「2人未満」が一般的になっています。高度経済成長期には「子ども2〜3人」が標準的でしたが、現在は経済的負担やキャリアとの両立、育児環境の課題から、子どもを持たない選択や一人っ子家庭が増加しています。政府の少子化対策にもかかわらず、出生数は年々減少し、社会的な大きな課題となっています。
恋愛事情・交際期間の平均って?
恋愛観も大きく変化しています。調査によると、結婚前の平均交際期間は約3〜4年とされ、過去に比べて「じっくり相手を見極める傾向」が強まっています。一方で「恋人がいない人」の割合も増加し、特に若い世代では恋愛よりも趣味や仕事に時間を使う人が目立ちます。恋愛・結婚が「必須」ではなく「選択肢」のひとつとなり、平均データだけでは測れない多様なライフスタイルが広がっているのが現代日本の特徴です。
【まとめ】平均を知ることで見える「自分らしい選択」

「平均」と「自分」に差があっても大丈夫
統計データの「平均」は、あくまで大勢の人をならした数字です。必ずしも自分がそこに当てはまる必要はありません。例えば平均年収や平均結婚年齢より早い・遅い、身長や体重が標準値と違う…そんな差があっても「異常」ではなく「個性」と捉えることが大切です。平均と違うからといって不安になるのではなく、自分にとって快適で納得できる選択をすることが最も重要です。
統計を暮らしやキャリアにどう活かすか
平均の数字は「自分の位置を知る目安」として役立ちます。たとえば健康診断の平均値と比べることで生活習慣を見直したり、年収や貯金額の中央値を知ることでライフプランを考える参考にできます。ただし、平均に無理やり合わせる必要はありません。「社会全体の傾向を知ったうえで、自分に合った最適な行動を選ぶ」ことが統計を上手に使うポイントです。
教養としての「日本人論」はこちら🔻


