
ビタミンB12は、神経や血液の健康を守るうえで欠かせない栄養素です。脳や神経の正常な働きをサポートし、赤血球の生成にも関わるため、疲労感や貧血、記憶力の低下を防ぐ役割を果たします。しかし、体内では作り出せないため、食事やサプリからの摂取が必要です。
この記事では、ビタミンB12の効果や不足によるリスク、効率よく摂れる食べ物やサプリの選び方まで徹底解説します。
ビタミンB12とは?基礎知識をチェック
水溶性ビタミンのひとつで“赤いビタミン”とも呼ばれる
ビタミンB12は、ビタミンB群に分類される水溶性ビタミンのひとつです。特徴的なのは、その化学構造にコバルトという金属を含む点で、分子自体が赤色をしていることから「赤いビタミン」とも呼ばれています。体内では主に神経機能の維持や赤血球の生成に関わる働きをしており、健康に欠かせない栄養素です。
体内で合成できないため食事から摂取が必要
ビタミンB12は、他のビタミンと同様に人間の体内では合成できません。一部の細菌によって生成されますが、人間はそのまま利用できないため、基本的には食品からの摂取が必須です。特に肉や魚介類などの動物性食品に多く含まれるため、ベジタリアンやヴィーガンの人は不足しやすい栄養素として知られています。不足すると貧血や神経障害の原因になるため、日常的に意識して取り入れることが大切です。
葉酸・鉄との関係も重要なポイント
ビタミンB12は単独で働くだけでなく、葉酸や鉄と一緒に赤血球の生成を助けるという大きな役割を持っています。この3つの栄養素が不足すると「巨赤芽球性貧血」と呼ばれる特有の貧血が起こりやすくなります。
また、葉酸とともにDNAの合成にも関与しており、細胞分裂や成長の過程において重要な栄養素です。そのため、妊娠中や成長期には特に十分な摂取が推奨されています。
ビタミンB12の主な効果と働き

神経細胞を保護し、脳や精神の健康を守る
ビタミンB12は、神経を包む**ミエリン鞘(しょう)**という膜の生成に深く関わっています。ミエリンは電気信号をスムーズに伝える絶縁体のような役割を果たし、神経細胞を保護する働きがあります。これが不足すると、手足のしびれや感覚異常、記憶力の低下など、神経系のトラブルを招くことがあります。十分なビタミンB12を摂取することで、脳の働きや精神の安定をサポートできるのです。
赤血球をつくり、貧血を予防する
ビタミンB12は、赤血球の形成に欠かせない栄養素です。DNAの合成を助け、正常な赤血球を作るために働きます。不足すると赤血球がうまく成熟できず、「巨赤芽球性貧血」という特有の貧血が起こります。この貧血は鉄分不足による鉄欠乏性貧血とは異なり、ビタミンB12や葉酸の不足が原因です。酸素を運ぶ赤血球が十分に作られることで、全身のエネルギー供給がスムーズになり、だるさやめまいの予防にもつながります。
エネルギー代謝を助け、疲労回復にも役立つ
ビタミンB12は、体内でたんぱく質や脂質、炭水化物の代謝をサポートする働きがあります。これにより、摂取した栄養を効率よくエネルギーへと変換でき、日常生活でのスタミナ維持に役立ちます。また、神経や脳に栄養をスムーズに届けることで、集中力や持久力の低下を防ぎ、疲労回復を助ける効果も期待できます。
うつ症状や記憶力低下との関連性
近年の研究では、ビタミンB12が精神面や認知機能の健康に関与していることも注目されています。B12が不足すると神経伝達物質の合成が乱れ、うつ症状や不安感が出やすくなるといわれています。また、高齢者で不足すると、記憶力や認知機能の低下が進むリスクも報告されています。逆に十分に摂取することで、メンタルの安定や脳の老化予防に役立つ可能性があると考えられています。
ビタミンB12が不足するとどうなる?

悪性貧血やしびれ・神経障害のリスク
ビタミンB12が不足すると、赤血球が正常に作られなくなり、悪性貧血(巨赤芽球性貧血)を引き起こす可能性があります。この貧血は鉄分不足によるものとは異なり、血液中の赤血球が大きく未熟なまま増えるのが特徴です。さらに、B12は神経を保護する「ミエリン鞘」の形成に関与しているため、不足すると手足のしびれ・歩行障害・感覚異常などの神経症状も出やすくなります。進行すると回復に時間がかかるため、早めの対策が重要です。
記憶力・集中力の低下、うつ症状
ビタミンB12が不足すると、脳の神経伝達がスムーズに行えなくなり、記憶力や集中力の低下につながることがあります。また、神経伝達物質の合成が乱れることで、うつ症状や気分の落ち込みが現れるケースもあります。特に高齢者では、B12不足が進行すると認知症に似た症状を示すことがあり、精神面・認知機能の両面で注意が必要です。
特に不足しやすい人(高齢者・ベジタリアン・胃切除後の人など)
ビタミンB12は動物性食品に多く含まれるため、ベジタリアンやヴィーガンの人は不足しやすい栄養素です。また、高齢者は胃酸の分泌が低下してB12の吸収がうまくいかず、不足しやすい傾向にあります。さらに、胃切除や消化器系の手術を受けた人、慢性的に胃薬(制酸薬)を服用している人も吸収不良を起こしやすいとされています。こうした人は、食品だけでなくサプリメントや注射による補給を検討することが望ましいでしょう。
ビタミンB12が豊富な食品一覧

肉類(レバー、牛肉、豚肉など)
肉類はビタミンB12の代表的な供給源です。特に**レバー(牛・豚・鶏)**には非常に多く含まれており、少量でも効率よく摂取できます。また、牛肉や豚肉にも比較的豊富に含まれているため、日常的な食事で不足を防ぎやすいのが特徴です。普段からバランスよく肉を取り入れることで、神経や血液の健康維持に役立ちます。
魚介類(さんま、しじみ、牡蠣、サケなど)
魚介類はビタミンB12の宝庫といわれるほど豊富な食品群です。特にしじみやあさりなどの貝類はトップクラスの含有量を誇ります。また、牡蠣、サケ、サンマ、イワシといった魚にも多く含まれ、和食の定番メニューから摂りやすいのがメリットです。魚介類は良質なたんぱく質やDHA・EPAなども同時に摂れるため、健康全般にプラス効果があります。
卵や乳製品にも含まれるが量は少なめ
卵やチーズ、牛乳などの乳製品にもビタミンB12は含まれていますが、その量は肉や魚に比べて少なめです。卵1個あたりの含有量はごくわずかなため、卵や乳製品だけで必要量を満たすのは難しいでしょう。ただし、ベジタリアンの方にとっては数少ない供給源になるため、毎日の食事に取り入れることが推奨されます。
植物性食品にはほとんど含まれないので注意
ビタミンB12は植物性食品にはほとんど含まれていません。海苔や発酵食品にごく微量含まれるケースもありますが、体内で有効に利用できる量ではないと考えられています。そのため、ヴィーガンや厳格なベジタリアンの方は特に不足リスクが高く、サプリメントや強化食品による補給が必須といえるでしょう。
ビタミンB12サプリの選び方とおすすめ商品

吸収率の良い形態(メチルコバラミン・シアノコバラミン)
ビタミンB12サプリにはいくつかの形態があります。代表的なのはメチルコバラミンとシアノコバラミンです。
-
メチルコバラミン:体内でそのまま働ける形態。吸収率が高く、神経や脳の健康サポートに向いています。
-
シアノコバラミン:安定性が高く、一般的なサプリに広く使われる形態。コスパが良く、初心者におすすめです。
目的や予算に合わせて選ぶのがポイントです。
ビタミンB群や葉酸と一緒に摂れるマルチサプリも便利
ビタミンB12は単体で摂るよりも、葉酸やビタミンB6、他のビタミンB群と一緒に働くことで効果を発揮します。
-
葉酸とセットで摂ると赤血球の生成を強力にサポート
-
ビタミンB6と一緒でホモシステイン代謝を助け、動脈硬化の予防に期待
そのため、マルチビタミンサプリやBコンプレックスサプリを選ぶのも効率的です。
タブレット・ドリンク・注射など摂取方法の違い
-
タブレット(錠剤)・カプセル:最も手軽で持ち運びやすい。毎日続けたい人向け。
-
ドリンク・ゼリータイプ:即効性が欲しい時や、錠剤が苦手な人に便利。
-
注射(医療機関のみ):吸収障害がある人や重度の不足に用いられる方法。自己判断ではなく医師の管理下で行われます。
普段の生活スタイルに合った形態を選びましょう。
おすすめサプリの紹介(人気・口コミ・コスパ)
ここでは日本で人気があり、口コミやコスパの面で評価の高いビタミンB12サプリをピックアップしました。
-
DHC ビタミンBミックス
手軽にB群をまとめて補えるロングセラー。コスパ重視派に人気。
リンク -
ネイチャーメイド ビタミンB12
シンプルにB12だけを補いたい人におすすめ。大手ブランドで安心感あり。
リンク -
NOW Foods メチルB12
高吸収型のメチルコバラミンを配合。海外サプリの中でもコスパ◎。
リンク -
ディアナチュラスタイル マルチビタミン&ミネラル
B12だけでなく葉酸・鉄・亜鉛なども摂れるマルチタイプ。栄養バランスを気にする人に。
リンク -
Solgar Methylcobalamin(海外)
高品質サプリで支持されるブランド。舌下で溶かすタイプで吸収性に優れる。
リンク
👉 まとめると、「吸収率重視ならメチルコバラミン」「手軽さならマルチビタミン」という選び方が基本です。
ビタミンB12の摂取でよくある疑問Q&A

1日に必要な摂取量はどれくらい?
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、成人の推奨摂取量は1日2.4μgとされています。妊娠中は+0.4μg、授乳中は+0.8μgが目安です。通常の食事をしていれば不足しにくい栄養素ですが、高齢者や菜食中心の方は不足しやすいため意識的に摂ることが大切です。
サプリと食品、どちらで摂るのが良い?
理想は食品から自然に摂取することです。肉類・魚介類・乳製品をバランスよく食べていれば必要量を満たせます。ただし、
-
ベジタリアンやヴィーガン
-
高齢者(胃酸分泌の低下で吸収が悪くなる)
-
胃の手術を受けた人
などは不足リスクが高いため、サプリメントを利用するのが有効です。特に「メチルコバラミン型」のサプリは吸収率が高くおすすめです。
飲みすぎても大丈夫?過剰摂取のリスクは?
ビタミンB12は水溶性ビタミンのため、余分に摂取しても尿から排出されるため、通常の食品や一般的なサプリの範囲で過剰症の心配はほとんどありません。
ただし、医師の処方で高用量を注射やサプリで摂取している場合は、自己判断で量を増やさないことが大切です。
子どもや妊娠中でも摂取していい?
ビタミンB12は胎児の神経や血液の発達に不可欠な栄養素で、妊娠中・授乳中の女性に特に重要です。推奨量の範囲であれば安全で、食事から自然に摂るのが基本です。
子どもにとっても必要な栄養素ですが、サプリを与える場合は年齢に合わせた製品を選び、量を守ることがポイント。心配な場合は小児科や産婦人科に相談すると安心です。
まとめ|ビタミンB12で神経と血液の健康を守ろう
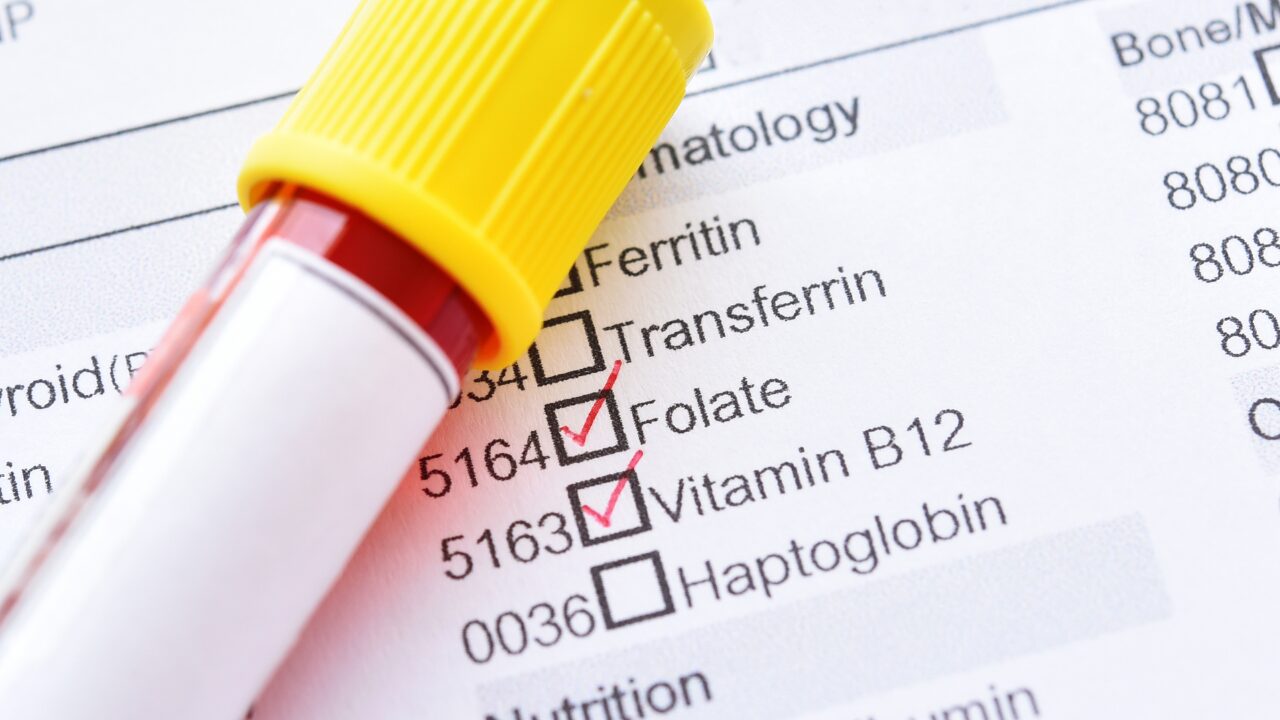
神経と血液を支える欠かせない栄養素
ビタミンB12は、体内で神経の働きを正常に保ち、赤血球の生成をサポートする重要な役割を担っています。不足すると「手足のしびれ」「記憶力の低下」「貧血」といった不調につながることも。エネルギー代謝や集中力にも関わるため、日々の元気を支える栄養素といえます。
不足リスクを理解して、食事+サプリでバランスよく補う
特に高齢者やベジタリアン、胃腸の弱い方はビタミンB12不足のリスクが高いといわれています。魚介類や肉類を中心に食事から意識して摂ることが基本ですが、必要に応じてサプリを組み合わせることで効率よく補給できます。無理のない方法で続けることが大切です。
健康維持・疲労回復・メンタルケアに役立つ
ビタミンB12は、貧血予防だけでなく、疲労回復やストレス対策にも有効とされる栄養素。仕事や学習に集中したい時、心身のパフォーマンスを高めたい時にも役立ちます。毎日の食生活に意識して取り入れ、健康な神経と血液を守ることで、年齢を重ねてもイキイキと過ごせる土台をつくりましょう。


