
夕方になると足がパンパンにむくむ、顔がぼんやり腫れぼったい…そんな不快な「むくみ」に悩む人は多いのではないでしょうか。実は、その原因のひとつが体内の 水分と塩分(ナトリウム)のバランス にあります。ここで役立つのが、余分なナトリウムを排出し、水分調整をサポートする「カリウム」です。
本記事では、カリウムがむくみに効果的な理由から、多く含む食品ランキング、さらに効率よく摂取する食べ方のコツまで徹底解説します。毎日の食事に取り入れて、“むくみ知らずの体”を目指しましょう。
そもそも「むくみ」の原因とは?
むくみは医学的には「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれ、体内の水分が必要以上にたまり、血管やリンパの流れが滞ることで起こります。特に顔や脚に出やすく、「夕方になると靴がきつい」「朝起きると顔が腫れぼったい」など、日常生活の中で多くの人が経験する身近な症状です。では、その原因を詳しく見ていきましょう。
体内の水分バランスが崩れるとむくみが起こる
人間の体は約60%が水分でできており、その水分は「細胞の中」と「細胞の外(血管・リンパなど)」でバランスを保っています。
しかし、このバランスが崩れると、余分な水分が細胞の外にたまり、むくみとして現れます。特に、長時間の立ち仕事やデスクワークで同じ姿勢を続けると、血流が滞りやすく水分が下半身にたまってしまいます。
💡対策ポイント
-
1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチをする
-
足首を回したり、ふくらはぎを動かすことで血流を改善
-
水分を我慢せず、こまめに飲むことで循環をスムーズにする
塩分(ナトリウム)の摂りすぎが大きな要因
塩分に含まれるナトリウムは、水分を体内に引き込み保持する性質があります。ラーメンや加工食品、スナック菓子などを食べ過ぎると、体は余分なナトリウムを薄めようとして水分をため込み、結果的にむくみが起こりやすくなります。
💡対策ポイント
-
塩分控えめの調味料を選ぶ(減塩しょうゆ、だしを活用)
-
漬物や加工食品は食べ過ぎない
-
カリウムを含む食品(バナナ、ほうれん草、アボカドなど)を一緒に摂ることでナトリウムを排出しやすくする
生活習慣やホルモンの影響も見逃せない
むくみは、単に食生活だけでなく、生活習慣やホルモンの変化にも左右されます。睡眠不足や運動不足、アルコールの飲みすぎは血流やリンパの流れを滞らせ、むくみを悪化させる原因に。さらに女性の場合、月経前や妊娠中はホルモンの影響で水分をため込みやすくなります。
💡対策ポイント
-
睡眠はしっかり7時間前後を目安に
-
軽い運動やマッサージで巡りをよくする
-
アルコールは控えめにし、飲んだあとは水をしっかり補給する
-
女性はホルモン周期を意識し、特に月経前はむくみやすいと理解して生活リズムを整える
カリウムがむくみ解消に効果的な理由

むくみ対策に欠かせない栄養素のひとつが カリウム です。カリウムはミネラルの一種で、体の水分調整や老廃物の排出に深く関わっています。普段の食生活に意識的に取り入れることで、余分な水分をため込みにくい体をつくるサポートをしてくれます。
余分なナトリウムを体外に排出する働き
カリウムの最大の特徴は、体内のナトリウム(塩分)を排出する力です。
塩分を摂りすぎると、ナトリウムが体内にたまり、それを薄めようとして水分が余分に保持され、むくみが起こります。ここでカリウムを十分に摂ると、腎臓の働きを助けてナトリウムを尿と一緒に排出してくれるため、自然と水分バランスが整いやすくなります。
💡対策ポイント
-
食塩を多く含む外食や加工食品には、野菜・果物を合わせる
-
バナナやほうれん草、トマトなどを日常的に取り入れる
細胞内の水分バランスを整えるサポート
体内の水分は「細胞の中」と「細胞の外」の2か所でバランスを取りながら存在しています。カリウムは細胞の中に多く存在し、ナトリウムと対になって水分の出入りをコントロールしています。
カリウム不足になると細胞内の水分が外に漏れやすくなり、体の一部に水がたまってむくみが悪化しやすくなります。逆にカリウムを十分に摂取すれば、細胞レベルで水分の流れをスムーズに保てます。
💡対策ポイント
-
毎食に野菜や果物を1品プラスする習慣をつける
-
ジュースではなく、できるだけ“そのまま”食べて栄養を丸ごと摂る
血圧の安定や疲労回復にもつながる
カリウムはむくみ解消だけでなく、血圧の安定にも役立つ栄養素です。ナトリウムを排出してくれることで高血圧のリスクを下げるほか、筋肉の収縮や神経の働きを正常に保つ作用もあります。そのため、足のだるさや全身の疲労感をやわらげる効果も期待できます。
💡対策ポイント
-
疲れを感じたときはカリウム豊富な果物(キウイ、メロンなど)を補給
-
運動後や汗をかいたときは、カリウムと水分を一緒に取ると回復が早まる
👉 このようにカリウムは「余分な塩分を出す」「細胞内の水分を整える」「血圧や疲労にアプローチする」と、むくみ対策に直結する働きを持っています。
カリウムを多く含む食品ランキング【TOP10】

むくみ対策には、毎日の食事でカリウムをバランスよく取り入れることが大切です。ここでは、手軽に取り入れやすい「カリウム豊富な食品」をランキング形式で紹介します。
1位:バナナ|手軽に食べられる代表食品
バナナは1本で約350mgのカリウムを含み、忙しい朝や間食に最適。さらに糖質や食物繊維も豊富で、エネルギー補給や便通改善にも役立ちます。
💡ポイント:皮をむくだけで食べられるので、むくみが気になるときの即効対策におすすめ。
2位:アボカド|美容と健康にうれしい栄養豊富食材
アボカドは「森のバター」と呼ばれ、1個あたり約700mg以上のカリウムを含みます。さらに良質な脂質やビタミンEも豊富で、美肌や老化予防にも効果的。
💡ポイント:サラダやトーストにのせるだけで、手軽に摂取可能。
3位:ほうれん草|野菜の中でもトップクラスのカリウム量
ゆでたほうれん草100gには約490mgのカリウムが含まれています。鉄分や葉酸も豊富で、貧血予防や疲労回復にもぴったり。
💡ポイント:スープやお浸しで“煮汁ごと”食べると効率よく摂取できる。
4位:さつまいも|食物繊維も豊富で腸活にも◎
さつまいもは100gで約470mgのカリウムを含み、さらに食物繊維とビタミンCも補給できます。腹持ちが良く、ダイエット中のおやつにも最適。
💡ポイント:蒸したり焼いたりして、そのまま食べるのがおすすめ。
5位:大豆・枝豆|植物性たんぱく質と一緒に摂れる
枝豆100gで約490mg、大豆製品(納豆・豆腐など)にも豊富にカリウムが含まれます。筋肉維持に欠かせないたんぱく質と一緒に摂れるのも魅力。
💡ポイント:おつまみ感覚で手軽に食べられ、夜のむくみ防止にも◎。
6位:キウイフルーツ|ビタミンCとカリウムを同時に補給
キウイ1個で約290mgのカリウムを含みます。さらにビタミンCが豊富で、疲労回復や美肌効果も期待できます。
💡ポイント:朝食やデザートとして取り入れると、むくみ解消+美容ケアに。
7位:ひじき・わかめなどの海藻類|低カロリーで効率よく補給
乾燥ひじきやわかめにはカリウムが凝縮されています。水で戻すと量が増えるので、低カロリーで効率よく摂取できるのも魅力。
💡ポイント:味噌汁やサラダに加えるだけで手軽にプラス。
8位:じゃがいも|和洋中どんな料理にも使いやすい
じゃがいも100gには約410mgのカリウムが含まれています。調理のバリエーションが豊富で、日常的に取り入れやすい食材です。
💡ポイント:スープや煮物にして、煮汁ごと食べるのがベスト。
9位:トマト|水分&抗酸化成分も一緒に摂れる
トマト100gで約210mgのカリウムを含みます。さらにリコピンによる抗酸化作用で、血流改善や美肌にも効果的。
💡ポイント:生のままサラダで、またはトマトジュースで手軽に補給。
10位:メロン|水分補給とセットでむくみ対策におすすめ
メロン100gには約350mgのカリウムが含まれています。水分もたっぷりで、夏場の水分補給+むくみケアにぴったり。
💡ポイント:食後のデザートや朝のフルーツに取り入れるのがおすすめ。
👉 このランキングを活用すれば、日常の食事にカリウムを無理なく取り入れられます。むくみ対策には「いろいろな食品をバランスよく組み合わせること」が大切です。
カリウムを効率よく摂る食べ方のコツ

カリウムは水に溶けやすく、熱にも弱い性質があるため、調理や食べ方に工夫をしないと摂取量が減ってしまいます。むくみ解消効果をしっかり得るためには、できるだけロスを減らして摂ることがポイントです。
加熱や水にさらしすぎない調理法を選ぶ
カリウムは“水溶性ミネラル”のため、長時間ゆでたり、水にさらしすぎたりすると流れ出してしまいます。
💡対策ポイント
-
野菜は「蒸す・炒める・電子レンジ加熱」を優先
-
ゆでる場合は短時間にして、すぐに冷ます
-
切る大きさを大きめにして、流出を最小限にする
果物や野菜は“生”で食べるのも効果的
生で食べられる果物や野菜は、そのまま摂ることでカリウムを余すことなく取り入れられます。熱や水を加えないので栄養の損失が少ないのが魅力。
💡対策ポイント
-
サラダやスムージーにする
-
バナナやキウイ、トマトなどはそのままカットして手軽に摂取
-
果物は間食に取り入れると無理なく習慣化できる
スープや煮物で“煮汁ごと”いただく工夫
どうしてもゆでたり煮たりする場合は、煮汁ごといただける料理にするのがおすすめです。スープや煮物なら、溶け出したカリウムも余さず摂れます。
💡対策ポイント
-
野菜スープや味噌汁にする
-
ポトフやカレーなど、汁ごと食べられる料理に活用
-
煮汁を冷まして保存し、翌日の料理に再利用するのも◎
1日の食事にバランスよく分散させて摂取する
カリウムは一度に大量に摂るよりも、1日の中でバランスよく取り入れるほうが効率的です。食事のたびに少しずつ摂取することで、体内で安定した水分バランスを保てます。
💡対策ポイント
-
朝:フルーツ(バナナやキウイ)でカリウム補給
-
昼:サラダや野菜スープでプラス
-
夜:煮物や味噌汁でしっかり摂取
-
間食:ナッツや枝豆を活用
👉 調理法と食べ方を工夫するだけで、同じ食材でもカリウムの摂取効率が大きく変わります。むくみ対策には「調理+分散摂取」がカギです。
摂りすぎには注意!カリウムの適切な摂取量と注意点
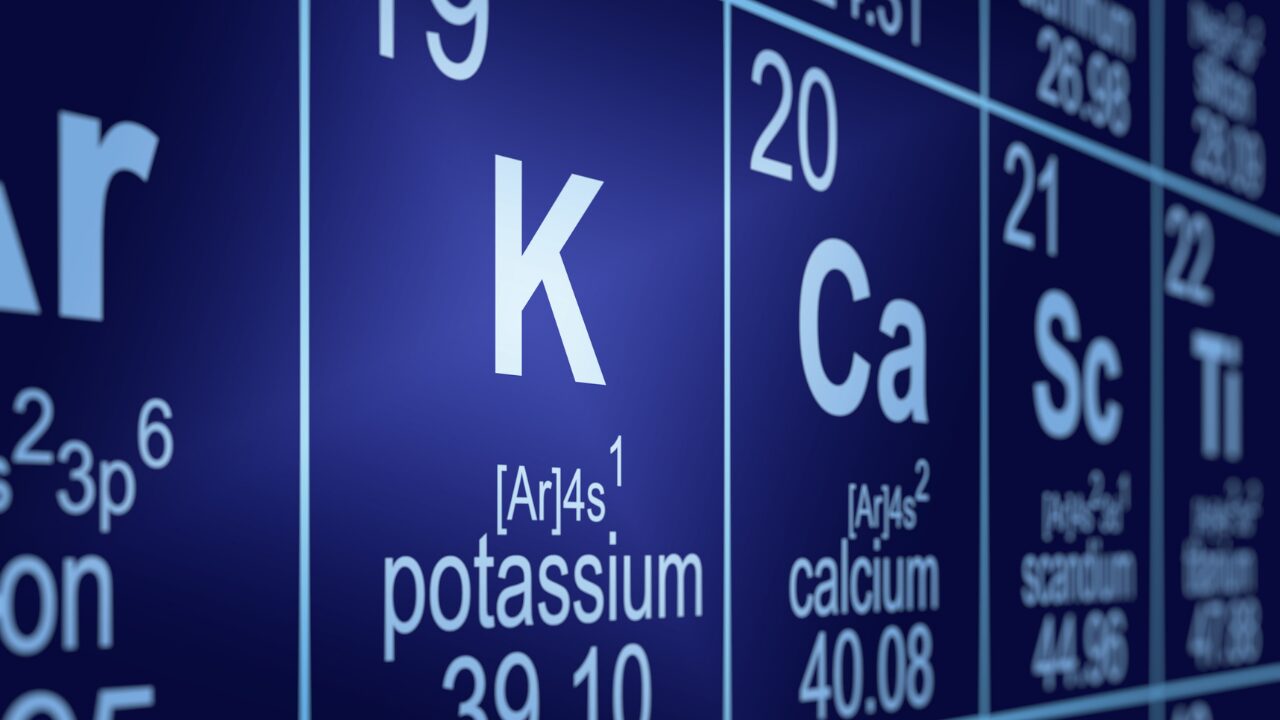
むくみ対策としてカリウムを積極的に取りたいところですが、“過剰摂取”にも注意が必要です。特にサプリメントや既往症がある方は慎重に扱いましょう。
成人が目安にしたい1日の摂取量
日本における基準値や目安量は以下のように設定されています:
-
日本人の食事摂取基準(2025年版)では、成人男性で 約2,500 mg/日、成人女性で 約2,000 mg/日 程度を目安量として挙げているという情報があります。
-
また、生活習慣病予防の観点からは、男性3,000 mg/日、女性2,600 mg/日を目標量とするという文献もあります。
-
ただし、通常の食事であれば過剰症になるリスクは低く、耐容上限量(上限値)は定められていないとの見解もあります。
-
ちなみに、厚生労働省の過去のデータでは、国民健康・栄養調査における成人の中央値摂取量は、男性で約2,384 mg、女性で約2,215 mgと報告されています。
実務的な目安としては、まずは “目安量レベル” を日常食で目指し、それ以上を摂る場合はサプリなどを使うにしても上限リスクを理解しておくことが重要です。
サプリや過剰摂取によるリスク
サプリメントでカリウムを補うことは手軽ですが、次のようなリスクが考えられます:
-
高カリウム血症:血液中のカリウム濃度が高くなりすぎると、不整脈、筋力低下、麻痺、心停止など重大な症状を引き起こす可能性があります。特に腎機能が低下している人では、排泄が追いつかずリスクが高まります。
-
薬との相互作用:利尿剤や降圧薬、ACE阻害薬、カリウム保持性利尿薬などを飲んでいる方は、カリウム濃度がさらに上がる可能性があるため注意が必要です。
-
サプリの品質リスク:成分表記が曖昧、過剰含有、添加物過多、品質管理の不十分な製品もあるため、信頼できる製造元・販売元を選ぶ必要があります。
-
胃腸への負担:濃度の高いミネラル類は胃腸に刺激を与えることがあり、胃痛・下痢などを引き起こすことがあります。
このようなリスクを避けるため、サプリを使う場合は 医師・薬剤師と相談 し、目安を超えないように用量・用法を守ることが重要です。
腎臓に不安がある人は医師に相談を
腎臓は体内のカリウムバランスを調整する主要な臓器です。腎機能に問題がある方や腎臓病の診断を受けている方は、通常よりカリウムを制限する必要が出ることがあります。
-
腎機能が低下していると、カリウムの尿中排泄が不十分になり、高カリウム血症リスクが高まります。
-
糖尿病や高血圧など、腎臓に影響を与える疾患を持つ方も注意が必要です。
-
腎臓病の段階(腎機能指標、クレアチニン、GFRなど)に応じて、1日あたりの許容量が個別に設定されることがあります。
-
したがって、腎臓に不安、または検査で腎機能が低めと指摘された方は、 必ず主治医と相談してからカリウム多めの食事やサプリ使用を検討する 必要があります。
製品例(国産/信頼性を重視したもの)
以下は、国産または信頼性の高いカリウム関連サプリの例ですが、あくまで参考として挙げます(使用・購入の際には必ず成分表示・医師相談を):
-
カリウムの力(栄養機能食品/日本製):日本製・モンドセレクションの受賞実績あり。
リンク -
カリウム 生活:日本製タブレットタイプ
リンク -
PURELAB 塩化カリウム サプリ:ビタミンB類との複合配合タイプ
リンク -
NOW Foods クエン酸カリウム 99 mg:海外製だが成分明示タイプ
リンク
まとめ|むくみ対策にはカリウム摂取がカギ!

カリウムは「余分な水分&塩分」を調整してくれる
カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、細胞内の水分バランスを整える働きがあります。塩分過多や立ち仕事・長時間の座り姿勢で起こりやすいむくみに対して、自然にサポートしてくれる心強いミネラルです。
食品からバランスよく取り入れるのがベスト
サプリに頼る前に、まずは食事からの摂取が基本。バナナ・キウイ・ほうれん草・アボカド・いも類など、身近な食材に多く含まれています。組み合わせ次第で無理なくカリウムを取り入れられるので、毎日の献立に少し意識して加えてみましょう。
毎日の食事習慣で“むくみ知らず”の体を目指そう
むくみ対策は一度きりの工夫ではなく、日々の食習慣の積み重ねが大切です。塩分控えめを心がけながら、カリウムをしっかり摂ることで、体の水分循環がスムーズになり、むくみにくいすっきりした体を維持できます。毎日の食事にちょっとした工夫を取り入れて、“むくみ知らず”の快適な生活を目指しましょう。


