
朝方、突然ふくらはぎが「ピキッ」とつって目が覚めた——そんな経験、ありませんか?
実は、寝ている間に起こるふくらはぎの“つり”は、血流やミネラルバランスの乱れ、体の冷え、筋肉の疲労など、さまざまな体の変化が関係しています。
一過性のものなら心配いりませんが、頻繁に起こる場合は体からのSOSかもしれません。
この記事では、医師の解説のもと、朝方にふくらはぎがつる主な原因と、毎日できる“体にやさしい予防習慣”をわかりやすく紹介します。
朝の痛みを繰り返さないために、今日からできるケアを始めましょう。
朝方にふくらはぎがつる…それ、体からのサインかも
朝方や寝ている最中に突然「ふくらはぎがつる」経験は、多くの人に起こります。
これは単なる筋肉のトラブルではなく、体のバランスが崩れているサインであることも。
特に、睡眠中は体温・血流・水分量が下がりやすく、筋肉が収縮しやすい状態になります。
また、加齢や運動不足、冷えなどの小さな要因が積み重なることで、“こむら返りが起きやすい体”に傾いてしまうのです。
「朝方によくつる」「最近頻度が増えた」と感じる人は、日常の体調変化や生活習慣を見直すタイミングかもしれません。
寝ているときにつるのは「血流」や「ミネラル不足」が関係
睡眠中のふくらはぎのつり(こむら返り)は、血流の低下とミネラルバランスの乱れが主な原因といわれています。
-
血流が滞ると…
長時間同じ姿勢で寝ていると、ふくらはぎの筋肉に血液が行き渡りにくくなります。
酸素や栄養が不足すると筋肉が異常収縮し、「つる」現象が起こりやすくなります。 -
ミネラル不足(特にマグネシウム・カルシウム・カリウム)
これらのミネラルは、筋肉の収縮と弛緩をコントロールしています。
水分不足や偏った食事、発汗量が多い人では、ミネラルバランスが崩れやすくなります。
対策ポイント
・寝る前にコップ1杯の常温水を飲む
・バナナ・豆腐・海藻類など、マグネシウム・カリウムを含む食品を積極的に摂る
・就寝前にふくらはぎを軽くマッサージして血流を促す
「加齢」「冷え」「水分不足」など、体の小さな変化が背景に
ふくらはぎのつりは、年齢や体質の変化とも深く関係しています。
-
加齢による筋肉量・代謝の低下
年を重ねると筋肉の水分保持力が下がり、筋肉の反応が過敏になりやすくなります。 -
冷えによる筋肉の緊張
足先の冷えは血流を悪化させ、筋肉の柔軟性を奪います。エアコンの効いた部屋や冷えやすい夜間は特に注意。 -
軽い脱水状態
寝ている間にも汗や呼吸で水分が失われ、朝方は体が“軽い脱水”状態に。筋肉が収縮しやすくなります。
対策ポイント
・就寝前にぬるめ(38〜40℃)の湯船に浸かり、体を芯から温める
・靴下やレッグウォーマーで下半身の冷えを防ぐ
・寝室の湿度を保ち、喉や体が乾かないようにする
一時的なこむら返りと、注意すべき慢性的なサインの違い
一度きりの「つり」であれば、体調や姿勢などの一時的な要因が多いですが、
頻繁に起こる場合や、激しい痛みを伴う場合は注意が必要です。
-
注意すべきサイン
・週に何度もつる
・痛みが数分以上続く
・足のしびれやむくみを伴う
・こむら返り以外にも疲れ・冷え・しびれを感じる
これらの症状がある場合、糖尿病・動脈硬化・神経疾患・甲状腺の異常など、血液や神経のトラブルが隠れていることもあります。
対策ポイント
・まずは生活習慣を整え、それでも改善しない場合は内科や整形外科を受診
・痛みが強いときは無理に伸ばさず、温タオルで温めながらゆっくりストレッチ
ふくらはぎがつる主な原因5つ|生活習慣や体の状態をチェック
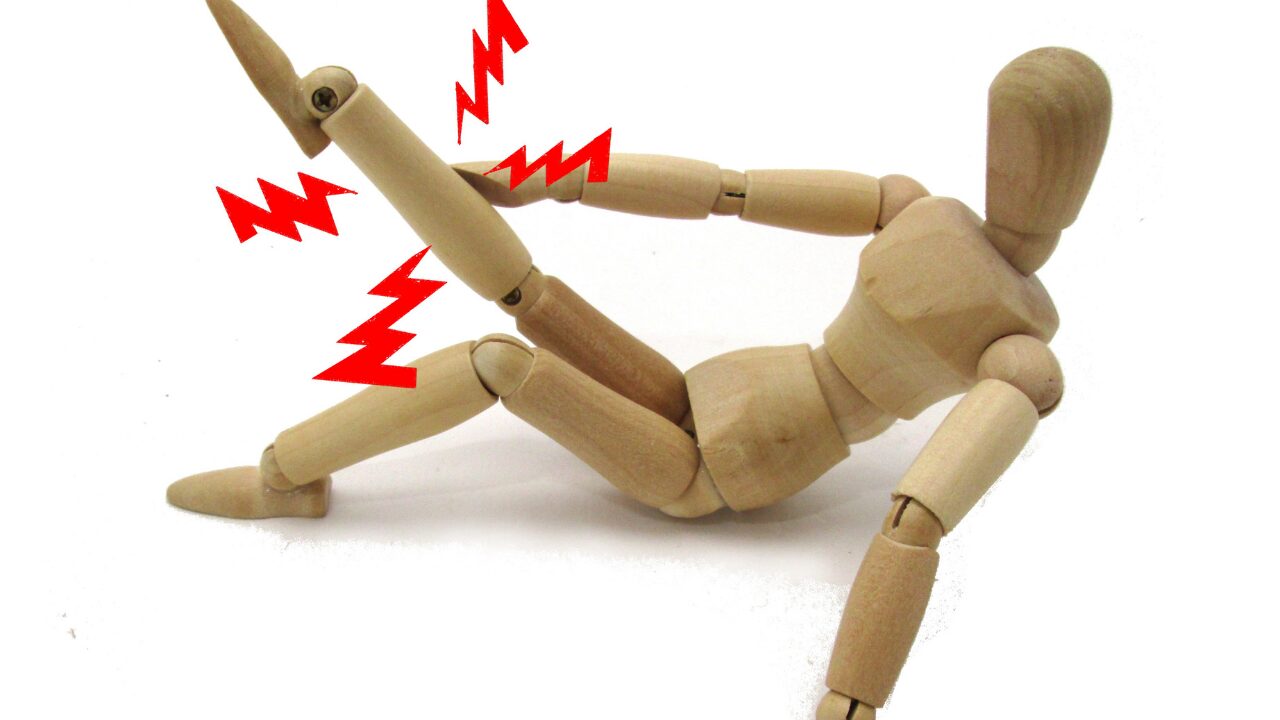
朝方にふくらはぎがつるとき、その背景にはいくつかの共通した要因があります。
代表的なのは、水分・ミネラル不足、冷え、血行不良、筋力低下、そして病気や薬の影響です。
一見ささいなことに見えても、体の内側では筋肉や神経、血流バランスが崩れていることも。
ここでは、考えられる主な5つの原因と対策をくわしく見ていきましょう。
① 水分・ミネラル(特にマグネシウム・カルシウム)の不足
筋肉が収縮・弛緩するには、マグネシウムやカルシウム、カリウムなどのミネラルが欠かせません。
これらが不足すると、筋肉が異常に収縮しやすくなり、こむら返りが起こりやすくなります。
特に、寝ている間は発汗や呼吸で水分が失われるため、朝方は軽い脱水状態になりがちです。
対策ポイント
-
寝る前にコップ1杯の常温水を飲む
-
汗をかきやすい季節は電解質飲料を少量とる
-
食事では、豆腐・海藻・ナッツ・バナナなどを意識して取り入れる
-
カフェインやアルコールの摂りすぎに注意(利尿作用でミネラルが排出されやすくなる)
② 冷えや血行不良による筋肉の緊張
足先やふくらはぎが冷えると、血管が収縮して筋肉への酸素供給が低下します。
その結果、筋肉が過度に緊張し、「つる」状態になりやすくなるのです。
特に、エアコンの風や冷たい床、薄着で寝るなどの環境が原因になることもあります。
対策ポイント
-
寝る前に**ぬるめの入浴(38〜40℃)**で血流を促す
-
冷えやすい人は、靴下やレッグウォーマーで足を保温
-
就寝前に足首を回す・ふくらはぎを軽くもむなどのストレッチを取り入れる
-
日中も長時間同じ姿勢を避け、1時間に1回は軽く動く習慣を
③ 長時間の立ち仕事・運動・睡眠中の姿勢
長時間の立ち仕事や激しい運動は、ふくらはぎの筋肉を酷使します。
その疲労が抜けきらないまま眠ると、**筋肉が硬直して夜中や朝方に“つる”**ことがあります。
また、寝ているときの姿勢にも注意が必要です。足首を下に伸ばした状態(つま先が下向き)で寝ると、ふくらはぎの筋肉が縮んだままになり、つりやすくなります。
対策ポイント
-
運動後は軽いストレッチやマッサージで筋肉を緩める
-
立ち仕事の人は着圧ソックスやふくらはぎポンプ運動を取り入れる
-
寝るときは**足首をやや上げる姿勢(バスタオルを足元に敷く)**を試す
-
過度な運動や長風呂での脱水にも注意
④ 加齢や筋力低下による循環機能の変化
年齢を重ねるとともに、筋肉量や血管の弾力が低下し、血液循環が悪くなりやすい傾向にあります。
また、筋力が衰えると「ふくらはぎポンプ」と呼ばれる下半身の血流補助機能が弱まり、代謝が落ち、つりやすい状態に。
対策ポイント
-
毎日のウォーキングやストレッチでふくらはぎの筋肉を維持
-
しゃがむ・つま先立ちするなどの軽い筋トレを習慣化
-
寝る前に足を上げる姿勢(壁に足を立てかけるなど)で血流をサポート
-
栄養・水分・睡眠をバランスよく整えることで筋肉の回復力を保つ
⑤ 病気や薬の影響(糖尿病・甲状腺・利尿薬など)
頻繁にふくらはぎがつる人は、体の疾患や服用中の薬が関係していることもあります。
特に以下のようなケースでは、医師に相談が必要です。
-
糖尿病や動脈硬化による血流障害
-
甲状腺機能低下症による代謝異常
-
利尿薬や降圧薬などでミネラルが過剰に排出されている
-
妊娠中や慢性的な脱水状態
対策ポイント
-
原因が病気や薬にある場合は自己判断せず医師に相談
-
症状や薬の影響を記録して伝えるとスムーズに診察できる
-
市販のミネラルサプリを使う際も、医師・薬剤師に確認を
脚ツランベルトはこちら🔻
朝のふくらはぎのつりを防ぐために、できること

ふくらはぎのつりは、「血流」「水分・ミネラルバランス」「筋肉の柔軟性」の3つを整えることで予防できます。
ポイントは、“夜の過ごし方”と“日中の体の使い方”を見直すこと。
ここでは、体にやさしく、無理なく続けられる5つの習慣を紹介します。
寝る前に「ぬるめの入浴」で血流を整える
夜の入浴は、ふくらはぎのこむら返り対策にとても効果的です。
38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かることで、血流が全身に巡り、筋肉の緊張がほぐれます。
熱すぎるお湯は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、リラックスできる温度が理想です。
入浴後に急に冷やさないよう、バスタオルで足元を包むと温かさが持続します。
ポイント
-
お湯にエプソムソルト(硫酸マグネシウム)を入れると筋肉の緊張緩和に◎
-
シャワーだけの日は、ふくらはぎを中心に温かいお湯をかけるだけでもOK
「水分+ミネラル補給」を意識してバランスよく
こむら返りの多くは、体内の水分とミネラルのアンバランスが引き金です。
とくに寝ている間は、汗や呼吸でコップ1杯以上の水分を失っているといわれています。
寝る前に常温水をコップ1杯飲むだけでも、朝方のつりを防ぎやすくなります。
また、日中は水だけでなく、マグネシウム・カリウムを含む食事を意識的に取りましょう。
おすすめの摂り方
-
朝:バナナや豆乳スムージーでカリウム補給
-
夜:豆腐・納豆・海藻類・ナッツ類でマグネシウム補給
-
激しい運動をする人は、ミネラル入りの水や経口補水液を少量ずつこまめに摂取
ふくらはぎを軽く伸ばす「寝る前ストレッチ」習慣
筋肉が硬いままだと、睡眠中に縮んで“つる”原因になります。
寝る前の軽いストレッチでふくらはぎの緊張をやわらげましょう。
簡単ストレッチ例(布団の上でOK)
-
仰向けになり、片足をまっすぐ伸ばす
-
つま先を自分のほうにゆっくり引き寄せる(ふくらはぎが伸びる感覚を意識)
-
10秒キープしてゆるめる × 3回
-
反対の足も同様に行う
無理に引っ張らず、「気持ちいい」と感じる程度で十分です。
続けることで、筋肉が柔らかくなり、つりにくい体を維持できます。
冷えやすい人は「レッグウォーマー」も効果的
ふくらはぎは体の中でも冷えやすい部位。
冷え=血流低下=筋肉のこわばりにつながるため、保温も立派な予防策です。
特に冬場や冷房の効いた寝室では、就寝時にレッグウォーマーを着けるのがおすすめ。
足首からふくらはぎまでをやさしく温めることで、夜間の血流が安定します。
ポイント
-
締めつけすぎない、コットンやシルク素材を選ぶ
-
電気毛布の使用時は低温やけどに注意
-
足先まで覆う靴下タイプより、足首〜ふくらはぎ中心のタイプが快適
日中の歩行やマッサージで“循環力”をキープ
日中の動きが少ないと、ふくらはぎの「筋ポンプ作用」が衰え、血液やリンパの流れが滞ります。
結果として、夜間に筋肉が硬くなり、つりやすい状態になります。
対策ポイント
-
通勤や買い物時に意識して歩く(1日15〜30分程度)
-
デスクワーク中は、つま先上げ・かかと上げを交互に行う
-
就寝前に足首を回す・ふくらはぎを軽くもむことで筋肉をリセット
日中の「軽い運動」が夜のこむら返り防止に直結します。
血流が良くなることで、冷え・むくみ・疲れも改善し、脚全体のコンディションもアップします。
繰り返す・激しい痛みには注意!受診を考えるタイミング

朝方にふくらはぎがつるのは、多くの場合「一時的な筋肉疲労」や「水分・ミネラル不足」が原因です。
しかし、頻繁に起こる・強い痛みを伴う・しびれを伴うといった場合は、
体の中で血流や神経に関わる異常が起きている可能性があります。
こむら返りは、体が発している“小さなSOSサイン”。
見逃さず、早めに医療機関を受診することが、長期的な健康維持につながります。
週に何度もつる・強い痛みが続くときは要注意
一般的なこむら返りは、数十秒〜数分で治まり、その後に軽い筋肉痛が残る程度です。
ところが、週に何度もつる・痛みが数時間続く・翌日も歩きづらいという場合は要注意。
このようなケースでは、単なる筋肉のこわばりではなく、
神経や血流のトラブル、慢性的な栄養バランスの崩れが関係していることがあります。
こんなときは医療機関へ
-
寝ている間に毎晩つる、または朝起きるたびに痛む
-
痛みのほかに、足のしびれ・むくみ・冷感がある
-
つった後に、筋肉の張りや腫れが長く残る
こうした状態が続くと、慢性の循環不全や神経障害の可能性もあるため、早めの受診が安心です。
糖尿病・動脈硬化・神経疾患などの可能性も
頻繁なこむら返りの背景には、次のような持病や疾患が潜んでいることがあります。
-
糖尿病:血糖コントロール不良により末梢神経がダメージを受け、筋肉が誤作動を起こす
-
動脈硬化・下肢静脈瘤:血流障害で筋肉への酸素供給が低下し、こむら返りを誘発
-
甲状腺機能低下症:代謝の低下で筋肉のエネルギー供給が乱れる
-
神経疾患・脊椎トラブル:神経の伝達異常によって足の筋肉が不意に収縮する
-
利尿薬・降圧薬の副作用:体内のカリウム・マグネシウムが排出され、バランスが崩れる
これらの疾患が原因の場合、セルフケアだけでは改善しにくいのが特徴です。
頻度や症状をメモしておき、医師に伝えると診断がスムーズになります。
病院では血液検査や神経・循環チェックで原因を特定
受診する際は、まず内科・整形外科・循環器内科などで相談しましょう。
医療機関では、以下のような検査を行い、原因を特定します。
🩺 主な検査内容
-
血液検査:電解質(ナトリウム・カリウム・マグネシウムなど)や血糖・腎機能をチェック
-
神経・筋肉検査:末梢神経障害や筋疾患の有無を確認
-
血流検査(ABI・エコーなど):下肢の動脈・静脈の詰まりや逆流を調べる
-
服薬確認:利尿薬や降圧薬などの影響を把握
原因が特定できれば、ミネラル補充・血流改善薬・生活習慣改善など、適切な治療方針が立てられます。
放置せず、医師と一緒に“つりにくい体づくり”を目指すことが大切です。
まとめ|朝方のふくらはぎのつりは「体の声」。見逃さず、整えていこう

まずは生活習慣を整えて“つらない体”を目指す
朝方のふくらはぎのつり(こむら返り)は、単なる筋肉の痙攣ではなく、「体のバランスが崩れているサイン」です。
水分・ミネラル不足、血行不良、筋肉疲労、冷え、睡眠中の姿勢など、日常の小さな習慣が重なることで起こります。
まずは、ぬるめのお風呂で血流を促す・就寝前のストレッチ・水分+マグネシウムの補給など、基本のケアを習慣にしましょう。
特に「寝る前のリラックスタイム」を意識的に取ることで、自律神経が整い、筋肉の緊張を和らげる効果も期待できます。
日中もこまめに歩いたり、軽く足首を回したりすることで、自然と“つりにくい脚”を維持できます。
体の小さなサインを見逃さないことが、健康の第一歩
朝方のこむら返りが増えた・痛みが強くなったという変化は、体が「負担がかかっている」と知らせている証拠です。
特に、週に何度もつる・夜中に何度も目が覚めるような場合は、糖代謝や血行に関わる疾患が隠れている可能性もあります。
「年齢のせい」「疲れのせい」と片づけず、自分の体調を見直すきっかけにすることが大切です。
ふくらはぎは「第2の心臓」と呼ばれるほど、全身の健康に関わる重要な部位。
日々の小さなケアを積み重ねて、体の声に耳を傾けながら、健やかな朝を迎えられる体づくりを心がけましょう。
💡ポイント:
ふくらはぎのつりは、体調・血流・筋肉バランスの“ミニサイン”。
見逃さずにケアを続けることで、将来的な血行不良や慢性疲労の予防にもつながります。
アクセス ツラナイトバンドはこちら🔻


