
「よくよく考えると」という言葉、日常会話でもよく耳にしますよね。
なんとなく使っているけれど、「“よく”を重ねるのは正しいの?」「少しくどい印象にならない?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、「よくよく考えると」は正しい日本語であり、深く考えた末に気づいたことを表す表現です。
この記事では、「よくよく考えると」の正確な意味や使い方、誤用しやすいポイント、そして場面別の例文までわかりやすく解説します。
正しい日本語として自然に使いこなせるよう、ぜひ最後までチェックしてみてください。
そもそも「よくよく考えると」ってどういう意味?
「よくよく考えると」という言葉は、日常会話や文章でよく耳にしますが、
「よく」と「よくよく」の違いや、正しい意味をきちんと理解している人は意外と少ないものです。
まずはこの表現の基本的な意味から見ていきましょう。
「よくよく」は“よく”を強めた表現
「よくよく」は、同じ言葉を重ねることで意味を強調する“畳語(じょうご)”と呼ばれる日本語表現です。
「よく(=十分に・慎重に)」という意味をさらに強め、「非常に丁寧に」「念入りに」「しっかりと」というニュアンスになります。
たとえば、
-
「よく考える」→ 普通にじっくり考える
-
「よくよく考える」→ 何度も頭の中で整理して、深く掘り下げて考える
というように、“より慎重で丁寧な思考”を表すのがポイントです。
そのため、「よくよく」は「何度も考え直す」「冷静に見直す」といった心理的な過程を含んでいます。
「よくよく考えると」は“じっくり考えた結果”という意味
「よくよく考えると」は、「じっくり考えた結果」「深く考え直してみると」といった意味で使われます。
つまり、何かに気づいたり、最初の印象とは違う結論にたどり着いたときに使う表現です。
たとえば、こんな使い方が自然です。
-
「よくよく考えると、あのときの彼の行動には理由があったんだね」
-
「よくよく考えると、最初の判断は少し早計だったかもしれない」
このように、「よくよく考えると」は“改めて冷静に考え直した結果、見えてきた真実や気づき”を伝えるときに使うのが基本です。
日常会話では「改めて考えると」というニュアンスでも使われる
会話の中では、「よくよく考えると」はもっと柔らかい意味で使われることもあります。
「改めて考えてみると」「今になって振り返ると」といった、“気づき”や“再確認”のニュアンスを含む表現です。
たとえば、
-
「よくよく考えると、あのとき私も悪かったかも」
-
「よくよく考えると、あの選択が今の自分を作ってるんだよね」
といったように、感情的な気づきや反省、振り返りの場面でよく使われます。
つまり、「よくよく考えると」はフォーマルにもカジュアルにも使える便利な日本語表現なのです。
✅ ポイントまとめ
-
「よくよく」は「よく」を強調した言葉(=より丁寧・慎重に)
-
「よくよく考えると」=“深く考えた結果、気づいたことを述べる”表現
-
日常会話では「改めて考えると」「今になって思えば」と同じように使える
「よく考える」と「よくよく考える」の違いとは?
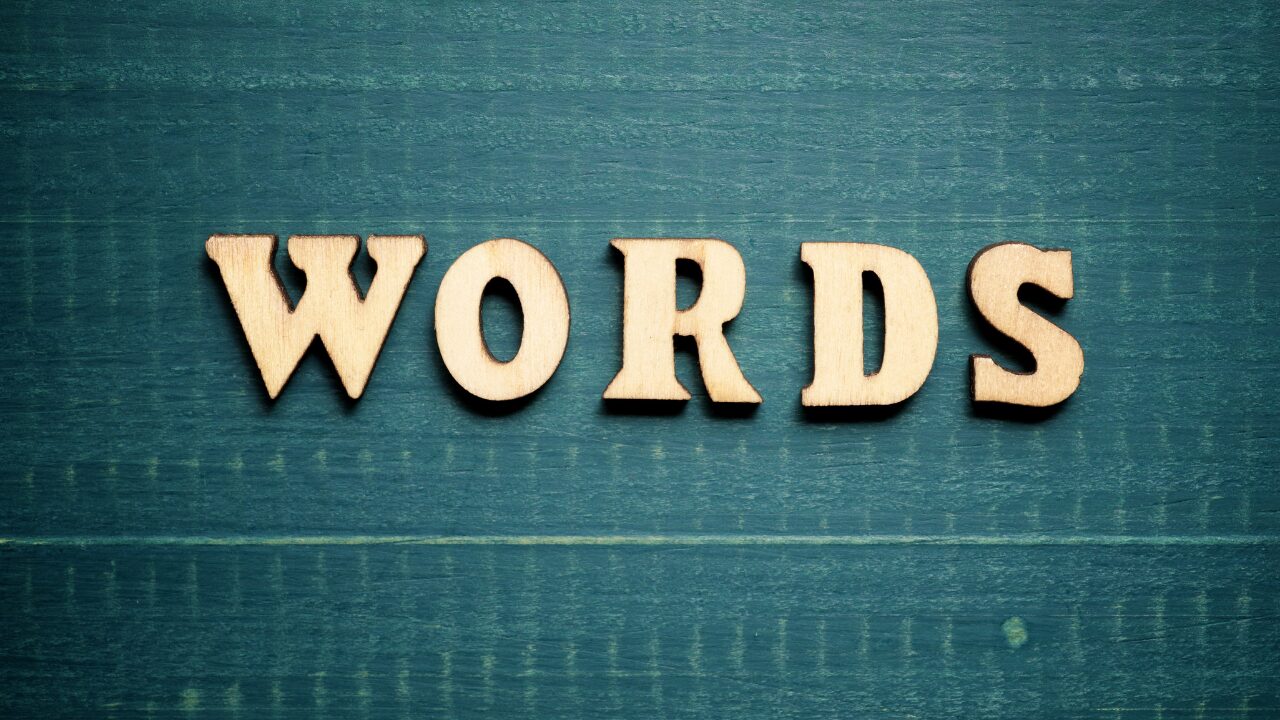
「よく考える」と「よくよく考える」は、どちらも“考える”という行為を丁寧に表す言葉ですが、
その深さと強調の度合いには明確な違いがあります。
一見似ていても、使う場面によって印象が変わる表現です。
ここでは、それぞれの意味の違いや使い分け方を具体的に見ていきましょう。
「よく考える」=丁寧・慎重に考える
「よく考える」は、「軽はずみに行動せず、しっかり考える」という意味で使われます。
“よく”には「十分に」「慎重に」「注意深く」といった意味があり、
物事を一度じっくり検討するというイメージを持つ表現です。
例文:
-
「その提案について、もう少しよく考えてみよう」
-
「よく考えたうえで決めることが大切です」
このように、「よく考える」は冷静・理性的に考えることを表し、
ビジネスでも日常でも幅広く使えるスタンダードな言い回しです。
つまり「よく考える」は、行動前に一度立ち止まって検討する、
いわば「慎重な判断」を促す言葉といえます。
「よくよく考える」=さらに深く掘り下げて考える(より強調)
一方で「よくよく考える」は、同じ「よく」を重ねることで意味を強めた表現です。
単に「注意深く考える」だけでなく、
“何度も頭の中で整理して、深く掘り下げる”という強い意識を含みます。
つまり、「よく考える」が“慎重な思考”なら、
「よくよく考える」は“熟慮を重ねた結果、何かに気づく”というニュアンスです。
例文:
-
「よくよく考えると、あの判断は少し早まっていたかもしれない」
-
「よくよく考えると、彼の言葉には優しさがあった」
このように、「よくよく考える」は時間をかけて深く考えた結果の気づきや結論を表す表現です。
少し感情や思いを込めた“人間らしい言葉”でもあります。
ビジネス・スピーチ・文章での使い分け例
ビジネスや公式な文章では、場面に応じて使い分けることで印象を大きく変えることができます。
| 用語 | 主なニュアンス | 適した場面 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| よく考える | 慎重・冷静・分析的 | 会議・提案・検討時 | 「よく考えたうえでご判断ください。」 |
| よくよく考える | 熟慮・洞察・再認識 | スピーチ・文章表現・反省的場面 | 「よくよく考えると、私たちの目指すべき方向は明確です。」 |
💡 使い分けのポイント
-
ビジネス文書や会議では「よく考える」を使うと、冷静で論理的な印象に。
-
スピーチやコラムでは「よくよく考える」を使うと、感情や気づきを自然に伝えられます。
たとえばプレゼンの締めで、
「よくよく考えると、私たちが本当に大切にすべきものは“信頼”ではないでしょうか」
と使えば、聴き手に“気づき”や“共感”を促す効果があります。
✅ まとめポイント
-
「よく考える」=慎重・冷静に考える(標準的)
-
「よくよく考える」=深く掘り下げて考えた結果の気づきを表す(強調)
-
ビジネスでは使い分けが重要。感情を伝えたいときは「よくよく考える」を活用
「よくよく考えると」のよくある誤用パターン

「よくよく考えると」は正しい日本語表現ですが、
使い方やニュアンスを誤解している人も少なくありません。
特に、“くどく聞こえる”“二重表現では?”といった誤った認識を持たれがちです。
ここでは、代表的な誤用パターンや注意点をわかりやすく整理して解説します。
「よくよく」を“くどい”“くり返し”と誤解しているケース
「よくよく」は同じ言葉を重ねているため、「くどい」「しつこい」という印象を持つ人もいます。
しかし、本来の「よくよく」は“よく”を強めるための畳語(じょうご)であり、
「くどい」という意味ではありません。
✅ 正しい理解:「よくよく」= よく(慎重に)+ よく(さらに丁寧に)= “念入りに・深く”
つまり、「よくよく考える」は「しつこく考える」ではなく、
“時間をかけて丁寧に考える” というポジティブな意味を持っています。
❌ よくある誤解例
-
「よくよく考える」は“くどい言い回し”だから使わない方がいい
→ 誤り。意味の重複ではなく、強調表現として自然な日本語です。
✅ 正しい使い方
-
「よくよく考えると、彼の意見にも一理ある」
→ “何度も頭の中で整理して出した結論”という意味で適切。
「よくよく考えると」は二重表現ではない
「“よく”が二回あるから、二重表現(重複表現)では?」と思う人も多いですが、
実はこれは 誤り です。
日本語では、「じっくり」「いろいろ」「どきどき」「そろそろ」など、
同じ語を繰り返して強調や柔らかさを出す表現が多くあります。
「よくよく」もその一つであり、文法的にも意味的にも正しい重ね言葉です。
✅ 二重表現ではない理由:
「よくよく」は“同じ意味を不必要に重ねた”ものではなく、
意味を強めるための強調表現に分類されるからです。
例:
-
「よく考える」→ 普通に慎重に考える
-
「よくよく考える」→ さらに深く・繰り返し考える
つまり、「よくよく考える」は強調表現であり、誤りではないということを覚えておきましょう。
感情的に使いすぎると“しつこい印象”になることも
一方で、「よくよく考えると」は便利な表現である反面、
使う頻度や文脈によっては“くどく”感じられる場合があります。
特に、感情的な文章やスピーチで繰り返し使いすぎると、
「また同じことを言っている」「しつこい」といった印象を与えることがあります。
❌ 悪い例:
「よくよく考えると、やっぱり彼が悪い。でもよくよく考えると、私も悪いのかもしれない。」
→ 「よくよく考える」が連発され、文章全体が冗長に。
✅ 改善例:
「改めて考えると、彼にも理由があったのかもしれない。」
→ 言い換えを使うことで、すっきりと自然な印象に。
💡 ポイント
-
同じ文章内で何度も使うとくどく聞こえる
-
会話では1回、文章では文末や結論部分での使用がベスト
-
言い換え表現「改めて考えると」「冷静に考えると」とのバランスを意識する
✅ まとめポイント
-
「よくよく」は“くどい”ではなく、“念入り・丁寧”を意味する強調語
-
「よくよく考えると」は二重表現ではなく、正しい日本語
-
ただし、感情的な文脈での多用は避け、言い換えで自然に整えるのがコツ
実際に使ってみよう!正しい使用例・誤用例

「よくよく考えると」という表現は、正しく使えば知的で落ち着いた印象を与えられますが、
使い方を誤ると“くどい”あるいは“不自然”に聞こえることもあります。
ここでは、フォーマルから日常会話までの使い方や誤用例、さらに便利な言い換え表現を紹介します。
正しい使い方の例文(フォーマル/日常/会話)
💼 フォーマルな場面での例
ビジネスメールや会議、スピーチなどでは、「よくよく考えると」は冷静な再評価や洞察を伝えるときに最適です。
-
「よくよく考えると、この方針にはリスクが多いことがわかりました。」
-
「よくよく考えると、今回の決断は早計だったかもしれません。」
-
「よくよく考えると、チームの努力が成果につながったのだと実感します。」
➡ フォーマルでは、“深く検討した結果”という意味で使うと、誠実で慎重な印象を与えられます。
🏠 日常生活での例
家庭や友人との会話など、少し柔らかい表現で「よくよく考えると」を使うと、
“気づき”や“反省”のニュアンスを自然に伝えられます。
-
「よくよく考えると、あのとき私も言いすぎたかもね。」
-
「よくよく考えると、こっちの道を選んで正解だったと思う。」
-
「よくよく考えると、やっぱり彼のアドバイスが的確だったな。」
➡ “今になって気づく”という気持ちを込めたいときに使うと◎。
💬 カジュアルな会話での例
軽いトーンでも、「よくよく考えると」は使えます。
ただし、口語ではやや堅く聞こえるため、「改めて考えると」「振り返ってみると」と交互に使うと自然です。
-
「よくよく考えると、この映画めっちゃ深い話だよね。」
-
「よくよく考えると、旅行の準備まだ何もしてないわ!」
➡ “軽い気づき”にも使える万能表現ですが、使いすぎは避けましょう。
🟩 誤用例と、その理由の解説
❌ 誤用①:「よくよく考えることをよく考える」
「よくよく考えることをよく考えるようにしています」
→ 同じ語の連続で不自然。意味が曖昧になります。
✅ 改善例:
「大事なことは、よくよく考えるようにしています」
→ 1回の使用で十分伝わります。
❌ 誤用②:「よくよく考えるように行動する」
→ 「考えるように行動する」は論理的に不自然な表現。
「行動する」=「考えた後の結果」なので、同時に使うと矛盾します。
✅ 改善例:
「行動する前に、よくよく考えるようにしています」
→ 因果関係が明確で自然な言い回しに。
❌ 誤用③:「よくよく考えると楽しかった!」
→ この場合、“考える”より“感じる”が正しい文脈。
“考えた結果”ではなく“体感的な気づき”を表したいときは、別の表現が適切です。
✅ 改善例:
「改めて振り返ると楽しかった!」
→ 「よくよく考えると」ではなく、「振り返ると」に置き換えるのが自然。
「よくよく考えると」の類語・言い換え(例:「改めて考えると」「冷静に考えると」など)
「よくよく考えると」は便利な言葉ですが、文の連続使用はくどく感じられることがあります。
そんなときは、文脈に合わせて言い換え表現を取り入れるのがおすすめです。
| 言い換え表現 | ニュアンス | 使用例 |
|---|---|---|
| 改めて考えると | 再確認・振り返り | 「改めて考えると、あの経験が今につながっている」 |
| 冷静に考えると | 客観的・分析的 | 「冷静に考えると、今回は引き下がるのが得策だ」 |
| 深く考えると | 理屈・本質を掘り下げる | 「深く考えると、問題の原因は別のところにある」 |
| よくよく思い返すと | 感情を込めて振り返る | 「よくよく思い返すと、あの時間はかけがえのないものだった」 |
| じっくり考えると | ゆっくり丁寧に考える | 「じっくり考えると、今の道が自分に合っている気がする」 |
💡ポイント
-
フォーマルな文書では「冷静に考えると」「改めて考えると」
-
日常会話では「じっくり考えると」「思い返すと」が自然
-
「よくよく考えると」は“深い気づき”を伝えたいときに絞って使うと効果的
✅ まとめポイント
-
「よくよく考えると」は“深く考えた結果の気づき”を伝える表現
-
文脈に合わない使い方(体感や行動系動詞との併用)は不自然
-
言い換えをうまく使えば、文章にリズムと説得力が生まれる
まとめ:「よくよく考えると」を正しく使いこなそう

「よくよく考えると」という表現は、深く・丁寧に考えた結果、何かに気づくという意味を持つ便利な言葉です。
日常会話からビジネス文まで幅広く使える一方で、誤用や勘違いも多い表現のひとつ。ここではその使い方をしっかり整理しておきましょう。
「よくよく考えると」は“深く考えた末の気づき”を表す
「よくよく考えると」は、単に「考える」というよりも、冷静に・時間をかけて考えた結果、何かに気づいた時に使うのが基本です。
例:
-
よくよく考えると、彼の言葉には優しさがあった。
-
よくよく考えると、最初の判断が正しかったようだ。
つまり、熟考の末に新しい視点や理解にたどり着いたときにぴったりの表現です。
二重表現ではなく、正しい日本語表現
「よくよく」は「よく」を重ねて強調しているだけで、二重表現ではありません。
同じような例として「少しずつ」「たびたび」「じっくりと」などのように、意味を深めるための重ね言葉は多く存在します。
つまり「よくよく考える」は、“くどい”のではなく“丁寧で意味のある強調”。
正しく理解して使えば、表現力がぐっと広がります。
意味を理解して使えば、文章も印象もぐっと良くなる
「よくよく考えると」は、感情的にならず、一歩引いて冷静に考えた結果を伝える言葉。
そのため、使い方を誤らなければ、知的で落ち着いた印象を与えることができます。
✅ 正しい使い方のポイント:
-
感情的なシーンよりも、落ち着いて振り返る場面に使う
-
“気づき”や“発見”を伴う文脈で使う
-
重ね言葉としての強調を自然に活かす
🔎 まとめると
-
「よくよく考えると」=深く考えた末の気づきを表す
-
二重表現ではなく、意味を強める自然な日本語
-
正しく使えば、文章全体が知的で柔らかい印象に
💬 ワンポイントアドバイス
文章や会話で「よくよく考えると」を適切に使うことで、
“思慮深さ”や“冷静さ”を伝えることができます。
感情的な語り口よりも、「一度立ち止まって考えた」ような場面に取り入れてみましょう。


