
近年、SNSやカジュアルな言葉が主流になる中で、「正しい言葉遣い」や「丁寧な日本語」の価値が改めて見直されています。
言葉は、相手を思いやる“こころの形”であり、時代を超えて人と人とをつなぐ力を持つもの。
この記事では、大人が身につけておきたい言葉遣いの基本から、子どもにも伝えたい日本語の美しさまでをやさしく解説します。
“きれいな言葉”を学ぶことは、マナーだけでなく、人との関係をあたたかくする第一歩です。
なぜ今、「言葉遣い」が注目されているのか
かつては「言葉遣い」といえば、ビジネスマナーや学校教育の一部として学ぶものでした。
しかし近年、SNSやチャットなどのカジュアルな表現が主流になるにつれ、
改めて“丁寧な言葉”の価値が見直されています。
たとえば、SNSでは短い言葉や絵文字で気軽に気持ちを伝えられる一方で、
“言葉足らず”による誤解や、意図しない冷たさを感じさせてしまう場面も増えました。
そんな中で、相手を思いやる言葉遣いができる人は、より信頼され、印象に残ります。
言葉遣いは、単なる「言い方」ではなく、
その人の人柄・価値観・思いやりを映す“心の鏡”のようなもの。
どんなに内容が正しくても、伝える言葉が乱暴だったり、
無意識に相手を下げる表現になっていたりすると、
その瞬間に“信頼”が揺らいでしまうこともあります。
現代は、情報よりも“共感”が重視される時代。
だからこそ求められているのは、
知識としての「伝える力」よりも、心で寄り添う「伝わる力」です。
やさしい言葉、思いやりのある言い回し、
そして相手に“安心”を与えるトーン——
それが、今の時代に注目されている「言葉遣いの本質」といえます。
丁寧な言葉を使うことは、堅苦しい作法ではなく、
“相手を大切に思う”という気持ちの表れ。
その意識を持つだけで、日常の会話も、子どもへの言葉かけも、
ぐっとあたたかく、豊かなものになります。
大人が身につけておきたい日本語の基本マナー

社会人になってからも、「この言い方で合っているのかな?」と悩む瞬間は少なくありません。
それほど日本語は奥深く、使う場面や相手によって“正解”が変わる言語です。
ここでは、大人として知っておきたい日本語の基本マナーを見直してみましょう。
敬語・謙譲語・丁寧語のバランスを見直そう
敬語は「相手を敬う言葉」ですが、使い方を間違えると、かえって不自然に聞こえることもあります。
たとえば、「おっしゃられる」「ご覧になられる」などの二重敬語は、つい使ってしまいがちな代表例。
大切なのは、「相手を立てながらも、自然に話す」ことです。
相手を過剰に持ち上げるよりも、状況に合わせてシンプルな敬語を選ぶほうが、
言葉に“やさしさ”と“信頼感”が生まれます。
-
正しい例:「おっしゃっていました」「ご覧になってください」
-
不自然な例:「おっしゃられていました」「ご覧になられました」
丁寧さを追求しすぎず、「伝わりやすく」「心地よく」話せる言葉が理想です。
「すみません」と「ありがとうございます」の使い分け
私たちは日常の中で、つい「すみません」を多用しがちです。
しかし、場面によっては「ありがとう」に言い換えるだけで、
印象がぐっと明るく、前向きになります。
-
✕:「すみません、手伝ってもらって」
-
○:「ありがとうございます、助かりました」
「すみません」は相手に“申し訳なさ”を伝える言葉、
「ありがとうございます」は“感謝”を伝える言葉。
どちらも丁寧ですが、感謝の言葉は関係を育てる力があります。
ちょっとした言い換えが、相手の心にやさしく届くコミュニケーションになります。
相手を立てながら自然に話す“やわらか表現”のコツ
敬語を意識しすぎると、堅苦しくなったり、距離を感じさせたりすることもあります。
そんなときに役立つのが、“やわらか敬語”です。
たとえば——
-
「〜してください」→「〜していただけますか?」
-
「〜ですか?」→「〜でしょうか?」
-
「〜だと思います」→「〜のように感じます」
ほんの少し語尾をやわらかくするだけで、
相手を尊重しながら、自分の気持ちも丁寧に伝えられます。
やわらかい言葉づかいは、マナーというより思いやりの表現。
「相手がどう感じるか」を想像できる人こそ、本当の意味で“言葉上手な大人”と言えるでしょう。
丁寧すぎず、カジュアルすぎず。
その中間にある“心地よい日本語”こそ、大人が目指したい言葉遣いのかたちです。
日常で活きる!場面別・丁寧な言葉遣いの例

私たちは様々な場面で言葉を使い分けています。
普段あまり意識しないうちに、つい“雑な言葉遣い”になってしまうことも。
ここでは、職場・プライベート・オンラインの3つの場面それぞれで、丁寧さと自然さを兼ね備えた言葉遣いのポイントと具体例を挙げていきます。
【職場】上司・同僚・取引先との会話で気をつけたい言葉
職場では、「適切な敬語・配慮ある表現・語調のバランス」が求められます。
間違いやすい表現、注意すべき言い回しを押さえておきましょう。
✔ 注意ポイント
-
「了解」「わかりました」など、軽すぎる表現を使わない
→ ビジネス現場では「承知しました」「かしこまりました」などを使うべき。 -
二重敬語・過剰表現にならないよう慎重に
-
「~のほう」「~になります」といった曖昧な表現は避け、正確で丁寧な文にする
→ 例:「こちらが資料になります」→「こちらが資料でございます」など -
上司や目上の人には「お疲れ様です」などの言葉遣いにも注意(「ご苦労様」は基本的に使わない)
-
クッション言葉(枕詞)を使って柔らかさを出す
例:「恐れ入りますが」「お手数ですが」「もしよろしければ」などを添える
✔ 具体例
| 相手 | 普通な言い方 | 丁寧で好印象な言い方 |
|---|---|---|
| 上司への報告 | 「課長、終わりました」 | 「課長、完了しました。ご確認いただけますでしょうか」 |
| 同僚への依頼 | 「これやっといて」 | 「すみませんが、こちらをお願いできますか」 |
| 取引先 | 「資料を送ります」 | 「本日、資料をお送りいたします。ご査収くださいませ」 |
| 断る場面 | 「それは無理です」 | 「申し訳ございませんが、難しいかと存じます」 |
これらの言い回しをストックしておくことで、急な場面でも落ち着いて丁寧な対応ができるようになります。
【プライベート】親しい人との“やさしい敬語”
親しい相手だからこそ、気を抜くと乱暴な言葉遣いになりがちです。
ただし、親しさと礼儀は両立できます。適度な敬語・やわらか表現を意識しましょう。
✔ ポイント
-
「〜してくれる?」→「〜してくれますか?」と語尾を少し丁寧に
-
「〜だよ」「〜ね」などの語尾に“〜ですね”“〜でしょうか”などを加える
-
相手をねぎらう言葉を忘れない:ありがとう・お疲れさま等
-
親しさを出すなら、丁寧さの中に“あなたらしさ”を混ぜ込む
-
あまり堅苦しくない範囲で、子どもや家族にも使いやすい敬語表現を使う
✔ 具体例
| シチュエーション | 普通な言い方 | やわらか敬語での言い方 |
|---|---|---|
| 友人にお願い | 「これ貸して」 | 「これ、貸してもらえますか?」 |
| 家族への声かけ | 「ご飯できたよ」 | 「ご飯ができました。食べますか?」 |
| お礼 | 「ありがとうね」 | 「ありがとう、助かったよ」 |
| 気遣い | 「無理しないで」 | 「無理なさらないでくださいね」 |
「親しい間柄だから気を抜く」のではなく、“親しさを壊さず、礼儀を保つ”意識が大人の言葉遣いには大切です。
【オンライン】メール・SNSでの言葉遣いが印象を左右する
オンラインの表現は、顔が見えず“言葉だけ”で印象が決まるため、特に丁寧さと配慮が問われます。
誤解を避けるため、表現の選び方・推敲・文体の統一に気を配りましょう。
✔ 注意ポイント
-
投稿・コメントは読み直し・推敲を行い、誤字・語調の乱れを防ぐ
-
軽い言い回し(「了解」「〜だよね」「〜かな」など)はビジネス関係相手や目上の人には使わない
-
SNSではあいまいな表現・断定を避け、「〜と思います」「〜ではないでしょうか」など柔らか表現を使う
-
クッション言葉や枕詞を使って、投稿・返信の印象を和らげる
-
顔文字や絵文字を使う際も“TPOを意識”:フランクすぎる表現は控える
-
キャッチーさよりも誠実さを重視:短文でも丁寧に伝えることで信頼を得られる
✔ 具体例(メール・SNS)
| 媒体 | 普通な書き方 | 丁寧表現の例 |
|---|---|---|
| メール | 件名:報告 本文:資料を送ります |
件名:◯◯に関する資料送付のご連絡 本文:いつもお世話になっております。◯◯でございます。資料を送付いたしましたので、ご査収くださいませ。 |
| SNS(コメント返信) | 「いいね、ありがとう!」 | 「いいねありがとうございます。とても嬉しいです」 |
| チャット・DM | 「今つかえる?」 | 「お疲れ様です。今、お時間よろしいでしょうか?」 |
| 投稿文 | 「新商品出たよ~」 | 「このたび、新商品を発売いたしました。ぜひご覧くださいませ」 |
オンライン表現では、「短くても丁寧」「思いやりが伝わる文」がたとえ小さな投稿でも印象を左右します。
子どもにも伝えたい、日本語の美しさと表現力

私たちが日々使っている日本語には、
単なる“伝達手段”を超えた心のぬくもりや思いやりが息づいています。
便利でスピード重視の時代だからこそ、
次の世代にも伝えていきたいのが、「言葉の美しさ」や「表現の豊かさ」です。
「いただきます」「おかげさま」など、感謝を伝える言葉の深さ
日本語の中には、目に見えない“つながり”や“感謝”を表す美しい言葉がたくさんあります。
たとえば「いただきます」は、食べ物だけでなく、
自然の恵み・作ってくれた人・命そのものへの感謝を込めた言葉。
また、「おかげさま」という表現も特徴的です。
“誰かのおかげで、今の自分がある”という、
謙虚さと感謝を一言で伝える日本語独特の表現です。
このような言葉を日常の中で自然に使うことは、
「ありがとう」を口にする習慣を超えて、
“感謝して生きる姿勢”を子どもに伝えることにつながります。
子どもたちが「ごちそうさま」「おつかれさま」「おかげさまで」と言えるようになると、
それは単なるマナーではなく、
人との関係を大切にする心が育っている証拠です。
四季の言葉・あいさつ言葉が育てる“思いやりの心”
日本語には、四季折々の自然や情景を繊細に表す言葉が豊富にあります。
「花冷え」「木漏れ日」「秋風がしみる」など、
季節と心を結びつける表現が多いのは、日本語の大きな魅力です。
こうした“季節の言葉”を知ることで、
子どもたちは自然への感受性を育み、
「感じ取る力」や「思いやりの心」が豊かになります。
また、あいさつの言葉も、単なる形式ではなく相手を思いやる文化のひとつ。
-
「いってらっしゃい」「おかえりなさい」には、“無事を願う気持ち”
-
「お疲れさま」には、“相手をねぎらう気持ち”
-
「おはようございます」には、“新しい一日を共に始める喜び”
こうした言葉を家庭や学校で自然に交わすことで、
言葉が人をつなぐ温かい循環が生まれます。
“美しい言葉”を通して、心の豊かさを育む
日本語の美しさは、難しい文法や古典にあるのではなく、
日常の中のさりげない言葉づかいにこそ宿っています。
たとえば、
-
「ありがとう」ではなく「ありがとうございます」と言う
-
「どういたしまして」ではなく「お役に立ててうれしいです」と返す
-
「またね」ではなく「また会えるのを楽しみにしています」と伝える
たった一言の違いで、言葉の印象も、受け取る心の温度も変わります。
それは、相手を思う気持ちが“言葉”という形になって現れる瞬間です。
美しい日本語を子どもに伝えることは、
正しい言葉を教えることではなく、
「人を大切にする心」を教えること。
親や大人がていねいな言葉を選ぶ姿を見せるだけで、
子どもたちは自然と“言葉の美しさ”を感じ取り、
やがてそれを、誰かにやさしく返せるようになります。
“美しい言葉づかい”は、マナーではなく心の習慣。
その積み重ねが、子どもにも伝わる「思いやりの連鎖」をつくっていくのです。
家庭や学校でできる“言葉の教育”とは
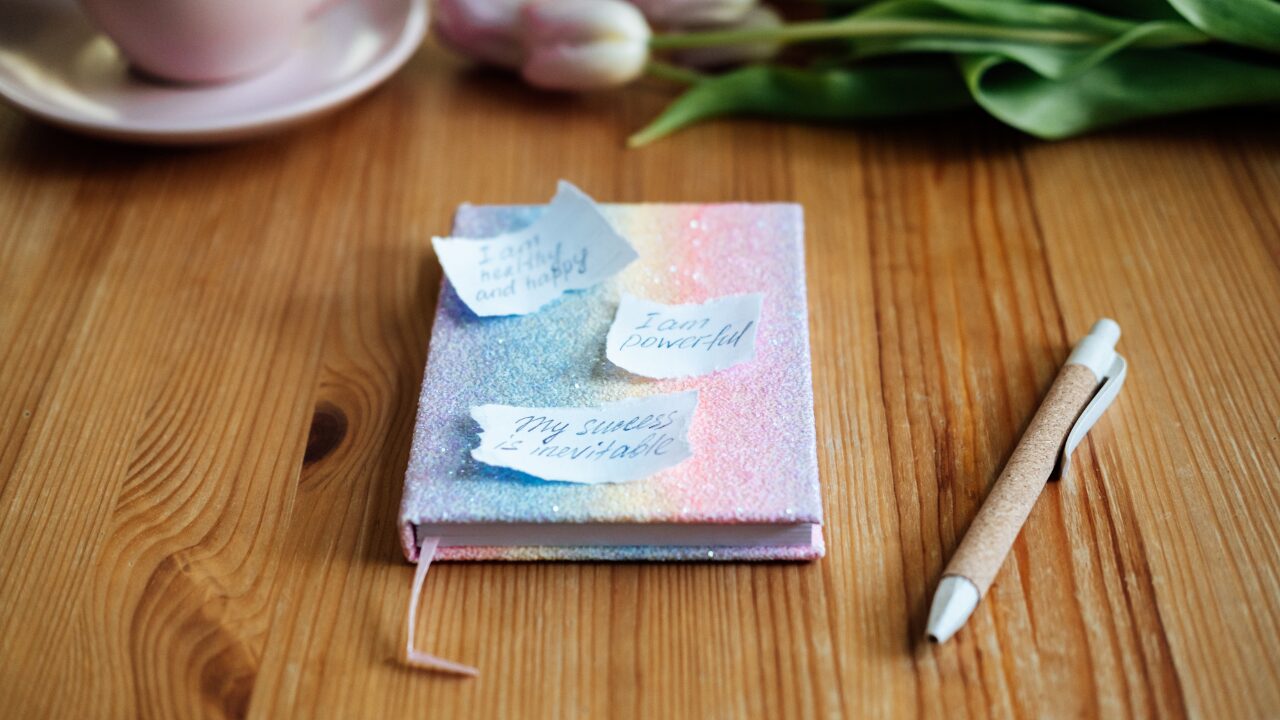
日常の会話が“言葉の土台”をつくる
子どもの言葉遣いは、特別な教材ではなく日々の会話の中で育まれます。
「おはよう」「ありがとう」「どうぞ」といった、何気ないやりとりこそが“言葉の教育”の第一歩。
親や教師が使う言葉を通して、「人との距離感」や「心の向け方」を自然に学んでいきます。
たとえば、誰かに物を渡すときに「はい」ではなく「どうぞ」と言うだけで、受け取る側の気持ちはやわらかくなります。
子どもは耳で聞いた言葉をそのまま真似るため、大人が日常的に使う言葉こそ、最も大きな教材なのです。
読み聞かせ・手紙・挨拶で自然に身につく言葉遣い
本の読み聞かせや手紙のやり取りは、語彙を豊かにし、感情表現を磨く最高の機会です。
絵本の中の美しい日本語や、手紙に込めた一言から、子どもは「丁寧な言葉のあたたかさ」を学びます。
また、「おはよう」「行ってらっしゃい」「おかえり」といったあいさつの積み重ねは、礼儀だけでなく人との関係を大切にする心を育てます。
言葉の教育は、“教える”よりも“交わす”ことで自然に身につくもの。家庭や学校で会話の温度を少し上げるだけでも、子どもの日本語力は確実に変わっていきます。
叱るより「伝える」姿勢が、子どもの言葉を育てる
子どもが言葉遣いを間違えたとき、叱るよりも「なぜその言葉がふさわしくないか」を伝えることが大切です。
「その言い方だと、相手が悲しいかもね」と、相手の気持ちを想像させることで、“使いたくなる言葉”へと自然に変わっていきます。
「丁寧な言葉を使いなさい」ではなく、“丁寧な心を持とう”と教えることが本質的な言葉の教育。
家庭でも学校でも、子どもが「自分の言葉で人を大切にできる」ような環境づくりこそが、これからの時代に求められる教育です。
まとめ|言葉遣いは「思いやり」のかたち

言葉は、人と人とをつなぐ“見えない橋”です。
どんなに短い一言でも、その中には相手を思う気持ちや自分の在り方が表れます。
「ありがとう」「お疲れさま」「おかげさま」──これらの言葉は、誰かを大切にする小さな行動そのものです。
正しい言葉遣いとは、単にルールを守ることではなく、相手を尊重する姿勢を伝える手段。
そして同時に、自分自身を丁寧に扱う誇りでもあります。
思いやりを込めて話す習慣は、人間関係を豊かにし、社会の中で信頼を築く力へとつながります。
また、子どもは大人の言葉を鏡のように映します。
大人が日常で言葉を楽しみ、丁寧に使う姿を見せることこそ、何よりの教育。
「言葉って素敵だな」と思える体験を重ねることで、次の世代にも日本語の美しさと温かさが自然と受け継がれていきます。
丁寧な言葉は、人を遠ざけるためではなく、心を近づけるためのもの。
あなたの「ひとこと」が、誰かの一日をやさしく変えるかもしれません。
心理学的に正しい! 人に必ず好かれる言葉づかいの図鑑🔻


