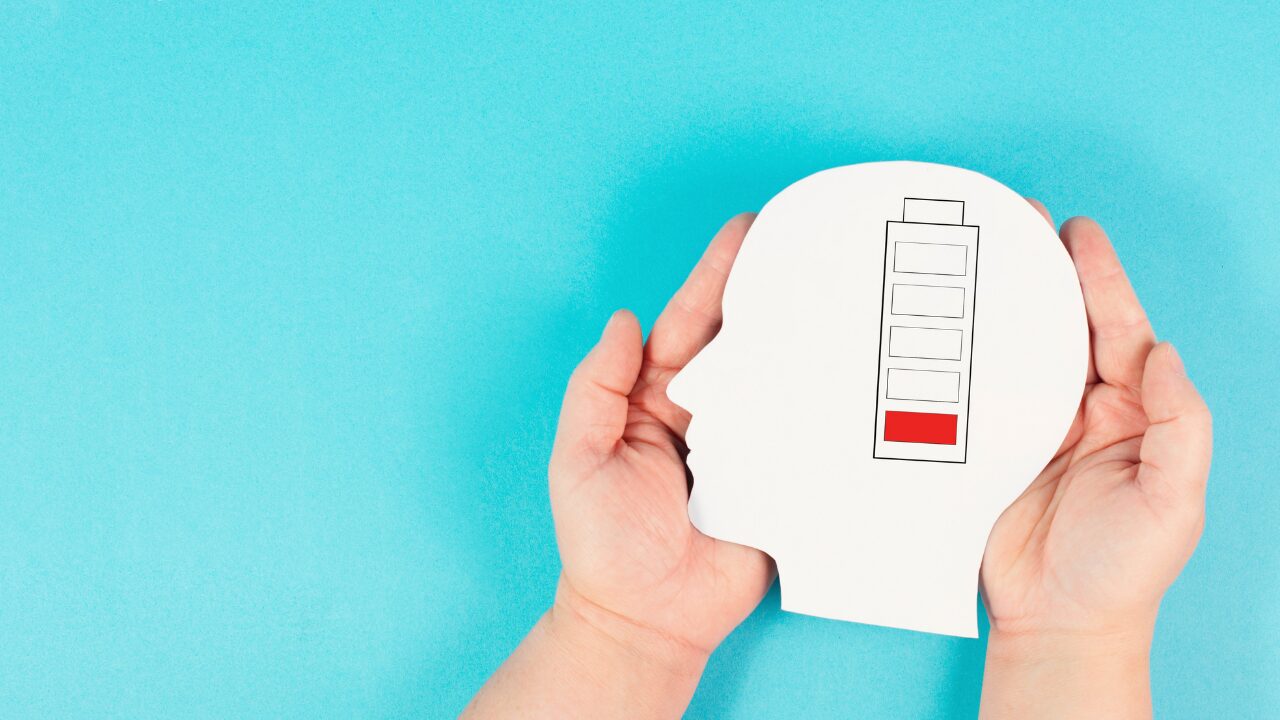
しっかり休んだはずなのに、なぜか疲れが取れない――。
そんなとき、原因は「体」ではなく「心の疲れ」にあるかもしれません。
近年、ストレス・情報過多・責任感の強さなどによって、知らず知らずのうちに“心のエネルギー”が消耗している人が増えています。
本記事では、心理カウンセラー監修のもと、「休んでも疲れが抜けない」状態の原因と、心をリセットする具体的な方法をわかりやすく解説します。
何もできない日があっても大丈夫。
焦らず、自分のペースで“本当の休息”を取り戻していきましょう。
休んでも疲れが取れない…その原因は「心の疲労」かも
「ちゃんと寝たのに、なんだかスッキリしない」「休みの日なのに気分が重い」——
そんなとき、体ではなく“心が疲れている”可能性があります。
現代人の多くは、仕事や人間関係、SNSなどを通して、常に情報と感情を処理し続けています。
そのため、身体を休めても、心のエネルギーが回復していないことが多いのです。
心の疲れは目に見えませんが、放っておくと集中力の低下や無気力、自己否定感などにつながります。
まずは、自分が「どんな疲れ」を感じているのかを見つめることから始めましょう。
肉体よりも“心のエネルギー”が消耗しているサイン
心のエネルギーが消耗しているとき、人は次のような状態になりやすくなります。
-
休んでも「やる気」や「楽しさ」を感じにくい
-
何をしても満たされない、虚しさを感じる
-
小さなことでイライラしたり、涙が出る
-
人に会うのがしんどい、何もしたくない
これらは、心がエネルギー切れを起こしているサインです。
心の疲れは、頑張り屋の人ほど気づきにくいもの。
「疲れているのは気のせい」と無理を続けると、やがて感情が動かなくなる“燃え尽き”状態に陥ることもあります。
対策ポイント:
体を休めるだけでなく、「考えない」「比べない」「頑張らない」時間を意識的に作りましょう。
静かな音楽を聴いたり、ぼーっと空を眺めたりするだけでも、心の回復に効果的です。
「しっかり寝てもスッキリしない」は、脳や感情の疲れ
十分に睡眠を取っているのにスッキリしないのは、脳の疲労が回復していないサインです。
スマホやパソコンを長時間使う生活では、脳が常に情報処理を続けており、
休んでいるつもりでも脳が“起きっぱなし”の状態になっていることがあります。
また、感情の我慢やストレスの抑圧も、脳の過活動を引き起こします。
「本音を言えない」「いつも気を使ってしまう」など、
心の中で常に何かを“抱えている”状態が続くと、脳がオーバーヒートしてしまうのです。
対策ポイント:
-
寝る前1時間はスマホやSNSを見ない「情報オフ時間」を作る
-
寝る前に日記やメモで“今日のモヤモヤ”を書き出す
-
深呼吸やストレッチで脳と体に「休んでいいよ」と伝える
“しっかり寝たのに疲れが取れない”という人ほど、脳を静める習慣が鍵になります。
ストレス・人間関係・情報過多が“心の回復”を妨げる
現代では、心を休める時間が自然と奪われています。
SNSでの比較、職場での気遣い、絶えず入る通知や情報……。
気づかないうちに「心のノイズ」がたまり続けているのです。
とくに、人間関係のストレスは大きな要因。
「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と我慢を重ねることで、
自分の感情を押し殺し、心の自然治癒力を弱めてしまいます。
対策ポイント:
-
一人の時間を意識的に取り、「人の声」から離れる
-
SNSやニュースを“見ない日”をつくる
-
「自分のためだけの予定」(好きなカフェ、散歩、香りの時間など)を入れる
情報と人から少し距離を取ることで、心は静かに回復し始めます。
休んでも疲れが取れないときほど、“刺激の少ない1日”を自分にプレゼントしてみましょう。
休んだはずなのに疲れている人の“よくある特徴”
「しっかり休んだはずなのに、なぜか疲れが抜けない」——
それは、体は休んでも“心”がまだ働き続けている状態かもしれません。
心が休まらない人には、いくつかの共通点があります。
どれも“真面目で頑張り屋な人”ほど陥りやすい傾向です。
まずは、自分の中に当てはまるものがないか、そっと確認してみましょう。
休んでいるつもりでも「思考」が止まっていない
たとえ体を休めていても、頭の中で「明日の準備」「人間関係の悩み」「過去の反省」など、
考えごとが止まらないと、脳はずっと働き続けたままです。
“何もしていないのに疲れる”という人は、
「体」ではなく「思考」が動き続けていることが原因の場合が多いです。
対策ポイント:
-
「今考えても仕方ないことリスト」を作って、頭の外に出す
-
寝る前に“今日考えたいことはここまで”と自分に区切りをつける
-
1日10分、思考を手放す「何もしない時間」をスケジュールに入れる
️ 意識のスイッチを切ることも“休む力”の一つです。
「考えない勇気」を持つことで、脳も心も少しずつ緩んでいきます。
責任感が強く「休むことに罪悪感」を持っている
真面目で優しい人ほど、「自分だけ休んでいいのかな」「怠けている気がする」と
休むことに罪悪感を抱きやすい傾向があります。
しかし、“頑張るために休む”のは本来とても大切なこと。
休息は「怠け」ではなく、「次に進むための準備時間」です。
対策ポイント:
-
「休む=リセットの時間」と言葉の意味を置き換える
-
頑張った自分を労う言葉を意識的にかける(例:「よくやったね」「今日はここまでで十分」)
-
「人の期待」よりも「自分の心の声」を優先する練習をする
罪悪感より“回復感”を優先することで、
心は次第に「休んでもいい」と感じられるようになります。
「何かしなきゃ」と焦る“常にON状態”の脳
「せっかくの休日なのに、何かしなきゃもったいない」
「生産的なことをしないと落ち着かない」
このように、いつも“何かしていないと不安”な状態は、
脳が常にONのままで、エネルギーを消耗し続けているサインです。
現代では、効率や成果が重視されすぎて、「何もしない」ことが苦手な人が増えています。
でも、本当に疲れを取るには、“立ち止まる時間”こそが必要です。
対策ポイント:
-
「今日は何もしない日」を予定表に入れておく
-
「やることリスト」ではなく「やめることリスト」を作る
-
“何もしていない時間”を「自分を整える時間」と意識的に呼び替える
“止まる勇気”が、心を守る第一歩。
焦りを手放すことで、心は自然とエネルギーを取り戻します。
SNSやスマホで、無意識に心を刺激し続けている
ベッドの中や休憩時間にSNSを見ていると、
気づかないうちに他人の情報や感情に引きずられ、心が休まらない状態になります。
特に、「自分と他人を比べる」「ネガティブな投稿に反応する」などは、
脳が常に“緊張状態”を保ってしまう原因です。
対策ポイント:
-
SNSやニュースを“見ない時間帯”を決める(例:寝る1時間前、朝起きてすぐ)
-
通知をオフにして“受け身”の刺激を減らす
-
スマホを置いて散歩・読書・音楽など“心に優しい刺激”に切り替える
情報の断捨離は、心のデトックス。
画面から離れるだけで、驚くほど心が静まり、エネルギーが戻ってくるのを感じられるはずです。
心をリセットする方法|“本当の休息”を取り戻すコツ
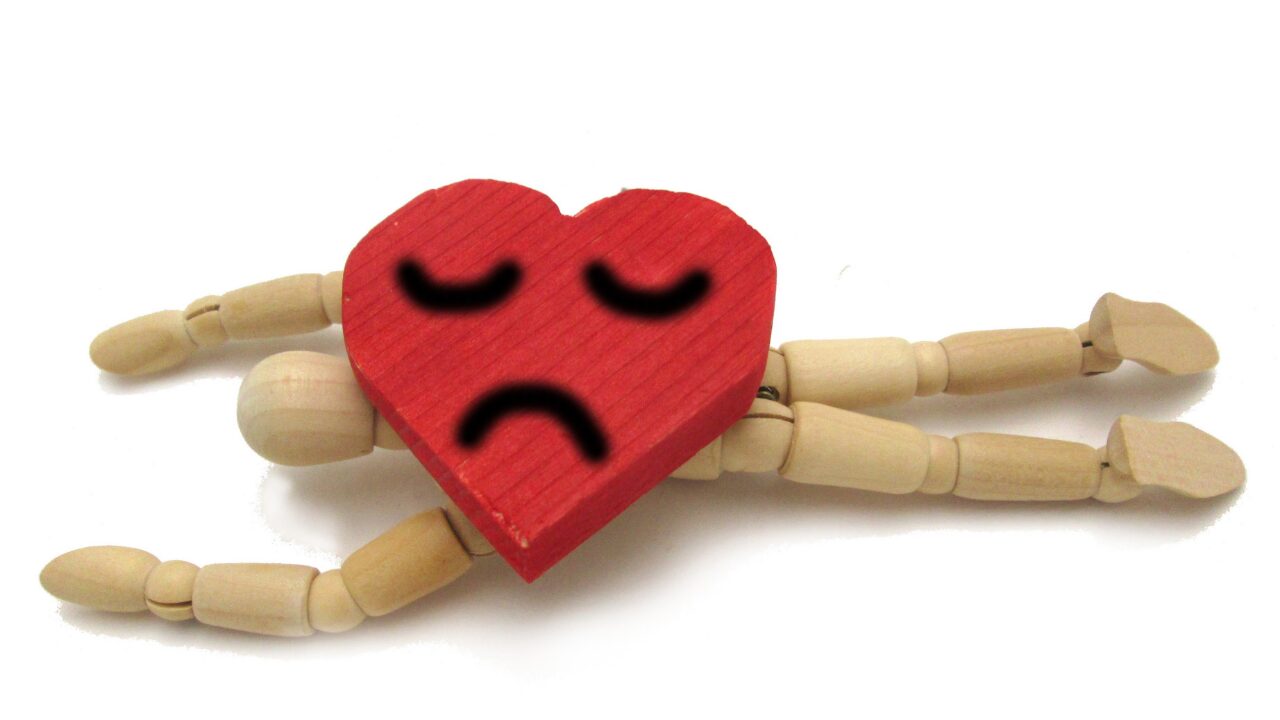
「しっかり休んだはずなのに疲れが抜けない」ときは、
“休息の方向”が少しズレているのかもしれません。
多くの人は「体を休める」ことには意識を向けますが、
実は、“心を休める”方法を知らないまま頑張り続けてしまうことが多いのです。
ここでは、心のエネルギーをリセットし、
内側から穏やかさを取り戻すための具体的なステップを紹介します。
何もしない時間を「意識的に」つくる
心が疲れているときこそ、“何もしない時間”を意識してつくることが大切です。
ただソファに座ってぼーっとする、湯船にゆっくり浸かる、窓の外を眺める。
一見「何もしていないように見える時間」にこそ、脳と心は静かに回復しています。
しかし、真面目な人ほど「何もしない=ムダ」と感じてしまいがち。
でも実は、それが本当の休息のはじまりです。
対策ポイント:
-
1日15分だけ「何もしない」時間をタイマーで確保する
-
その間、スマホ・音・人から完全に離れる
-
「何もしていない自分」を責めず、ただ“いるだけ”を許す
️ “空白の時間”は、心が再び動き出すための充電タイム。
勇気をもって“止まること”を自分に許しましょう。
自分の気持ちを言葉にして“感情の整理”をする
疲れが抜けない理由のひとつは、感情が溜まっているから。
悲しみや怒り、不安を「感じないように」してしまうと、
心の中に“未処理の感情”が残り、エネルギーを奪い続けます。
言葉にすることで、感情は形を持ち、整理されていきます。
ノートや日記、スマホのメモでも構いません。
「今の気持ち」「今日一番しんどかったこと」をただ書き出すだけで、
心の中が少しずつ整っていきます。
対策ポイント:
-
「疲れた」「悲しい」「本当はこうしたかった」と正直に書く
-
無理にポジティブに変換しない(そのままでOK)
-
書いたあとは「よく頑張ってるね」と自分に一言添える
感情を押さえ込むのではなく、“見つめてあげる”ことで癒しが始まります。
五感を使って「今ここ」に集中する(自然・香り・音など)
心が疲れているとき、人は「過去の後悔」や「未来の不安」に意識を向けがちです。
そんなときこそ、“今この瞬間”に意識を戻すことが大切です。
そのために役立つのが、五感(見る・聴く・触れる・香る・味わう)を使うこと。
自然の景色や心地よい香り、静かな音などを通して、
思考ではなく感覚に意識を向けることで、心はスッと落ち着きを取り戻します。
対策ポイント:
-
外の空気を感じながら深呼吸する
-
お気に入りのアロマやコーヒーの香りをゆっくり味わう
-
静かな音楽や自然音を流して、耳を休ませる
五感に意識を戻すことは、「今ここにいる自分」を取り戻すセルフケア。
それは心を未来や過去の雑音から守る“優しい瞑想”でもあります。
完璧を手放して「できない日」を許す
「ちゃんと休まなきゃ」「明日は頑張らなきゃ」と思うほど、
休むことがプレッシャーになり、心はさらに疲れてしまいます。
疲れている日には、何もできなくていい日もあっていいんです。
ベッドから出られない日、予定をキャンセルする日、泣いて過ごす日——
それも立派な“回復のプロセス”です。
対策ポイント:
-
「今日は50%の自分で十分」と考える
-
「できたこと」よりも「無理しなかったこと」を褒める
-
SNSや他人のペースと比べない
休む=弱さではなく、再生の準備。
完璧を手放したとき、心はようやく本来のペースで息をし始めます。
心のリセットは、頑張ることではなく“緩めること”から始まります。
「何かをしなきゃ」と思う気持ちを少し横に置いて、
“何もしない勇気”を、自分にプレゼントしてあげてください。
生活を見直す|心と体を整えるための小さな習慣
心の疲れは、特別な出来事よりも「毎日の積み重ね」で少しずつ溜まっていきます。
そのため、“生活のリズムを整えること”こそが、最も効果的なリセット法です。
ここでは、心と体のバランスを取り戻すために役立つ、
“今日からできる小さな習慣”を紹介します。
朝の光を浴びて“体内時計”をリセット
朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びる。
たったそれだけで、体内時計が整い、心と体が自然と“朝モード”に切り替わります。
光には、幸せホルモン「セロトニン」を活性化させる効果があります。
このホルモンが増えることで、気分の安定や集中力の回復につながり、
「何となく元気が出ない朝」も少しずつ軽くなっていきます。
対策ポイント:
-
起きてすぐ5分でもいいので、窓辺やベランダで朝日を浴びる
-
朝の深呼吸をセットにすると、脳がすっきり目覚める
-
雨の日や冬場は、明るい照明やライトを代用してもOK
「朝の光を浴びる=心のスイッチを入れる」習慣に。
一日のはじまりを丁寧に整えるだけで、心の安定感がぐっと高まります。
軽い運動で「脳のリラックスホルモン」を活性化
運動は、体だけでなく心にも直接的な癒やし効果があります。
特に、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、
脳内のリラックスホルモン「セロトニン」「エンドルフィン」を分泌させ、
ストレスを和らげる働きがあります。
運動というと「続けなきゃ」と構えてしまいがちですが、
5〜10分の“軽い動き”で十分効果があります。
対策ポイント:
-
朝や夕方に5分だけでも散歩をする
-
デスクワークの合間に肩回し・首ほぐしを取り入れる
-
スマホを置いて、音楽に合わせて体を揺らすだけでもOK
動くことで「心の流れ」も動き出す。
体を少し動かすたびに、心もほんの少し軽くなっていきます。
寝る前1時間は“情報断食”の時間にする
寝る直前までスマホやSNSを見ていると、
脳が常に情報を処理し続け、“休む準備”ができなくなってしまいます。
人間の脳は、光や情報の刺激で覚醒モードになります。
特に夜は、情報の取りすぎが“疲れを翌日に持ち越す”大きな原因になります。
対策ポイント:
-
寝る1時間前はスマホ・ニュース・SNSをシャットアウト
-
代わりに、読書・音楽・深呼吸などの“静かな時間”を過ごす
-
「夜のルーティン」を決めると、体が自然と眠る準備に入る
情報を断つ時間=心を鎮める時間。
デジタルから離れることで、頭の中が静まり、
眠りの質もぐっと上がっていきます。
日記やノートで“モヤモヤ”を外に出す
「なんとなく疲れてる」「理由はわからないけど気分が重い」
そんなときこそ、頭の中を“書き出して整理する”ことが大切です。
書くことで、曖昧な不安が“言葉”になり、
自分の心の状態を客観的に見つめ直すことができます。
これは心理療法でも用いられる、感情のデトックス法です。
対策ポイント:
-
ノートに「今日感じたこと」「印象に残ったこと」を3行だけ書く
-
感情を評価せず、そのまま書く(例:「悲しかった」「焦った」など)
-
書いたら「よくやってるね」と自分をねぎらう一言を添える
書くことは、自分と対話する時間。
モヤモヤを外に出すことで、心のスペースに“新しいエネルギー”が入ってきます。
どれも特別なことではなく、日常の中に取り入れられる小さな工夫です。
“完璧に整える”より、“少し整える”を続けることが、
心の安定とエネルギー回復への近道になります。
まとめ|“心の疲れ”を癒すのに、時間がかかってもいい

「何もしたくない自分」も受け入れることが回復の第一歩
「何もしたくない」「頑張れない」と感じるとき、私たちはつい自分を責めてしまいます。
でも、それは“怠け”ではなく、心が「これ以上無理をしないで」とSOSを出しているサインです。
疲れ切った心を回復させるためには、まず“今の自分をそのまま認める”ことが大切。
何かをしようと無理に奮い立たせるよりも、
「今日は何もできない日でもいい」と、静かに受け入れる勇気を持ちましょう。
自分を責めないことで、少しずつ心に“安心のスペース”が戻ってきます。
焦らず、少しずつ“自分のペース”を取り戻そう
心の疲れが癒えるスピードは、人それぞれ。
「早く元気にならなきゃ」と焦るほど、かえって回復は遠のいてしまいます。
回復のプロセスは、“直線”ではなく“波”のようにゆらぎながら進むもの。
少し元気な日もあれば、また動けない日もある。
そのすべてが「癒しの途中」です。
大切なのは、周囲と比べず、自分のペースを尊重すること。
「今日はこれだけできた」と小さな前進を認めていくうちに、
いつのまにか心が軽くなり、自然と笑顔が戻ってくるでしょう。
心の疲れは、“頑張りすぎた証”です。
休んでも疲れが取れないときこそ、自分にやさしく、時間をかけて心を整えていきましょう。
焦らず、少しずつ、あなたのペースで大丈夫です。


