
「ふわふわ」「ドキドキ」「キラキラ」——日本語には、同じ言葉を重ねることで“感情の揺れ”や“心の温かさ”を表す言葉がたくさんあります。
それが「重ね言葉」。響きの心地よさやリズムの美しさで、気持ちをやさしく伝える表現です。
この記事では、恋愛や喜び・動作・情景などを描く「重ね言葉」の意味と使い方を一覧で紹介。
“言葉の響き”で想いを伝える、日本語の奥深い魅力を感じてみましょう。
日本語の「重ね言葉」ってなに?
「ふわふわ」「ワクワク」「きらきら」など、同じ言葉を繰り返す“重ね言葉”は、
日本語の中でもとくに音の響きが心地よく、感情や情景をやわらかく伝える表現です。
たとえば「ふわふわ」には、軽やかで柔らかい感触だけでなく、
“安心感”や“優しさ”といった感情まで感じられます。
また「ドキドキ」は心臓の鼓動を表す音から生まれた言葉で、
“緊張”や“ときめき”など、心の動きをリアルに表現します。
このように、重ね言葉は「音」から感情や雰囲気を伝える、日本語ならではの感性表現。
一語で説明するよりも直感的に伝わるため、
日常会話・文学・広告コピーなど、幅広い場面で使われています。
また、「ふわふわ」「ぽかぽか」「キラキラ」などのように
やさしい母音が繰り返されることで、
言葉全体に“やわらかさ”や“親しみ”を感じさせるのも特徴です。
コラム:「万葉集」にも登場していた!? 古典にも見られる重ね言葉の歴史
実は、重ね言葉は現代に限った表現ではありません。
そのルーツは、なんと奈良時代の『万葉集』にまでさかのぼります。
当時の和歌では、「ときどき」「はるはる」「しずしず」など、
感情や情景を強調するために言葉を重ねる表現が多く使われていました。
これは、“リズム”や“響き”を大切にする日本語の美意識のあらわれです。
たとえば、季節の移ろいや恋の切なさを表すとき、
単語を重ねることで**「言葉に余韻を生む」**効果があったのです。
現代の「ドキドキ」「ワクワク」も、
その伝統を受け継いでいるといえるでしょう。
✨まとめポイント
-
重ね言葉=同じ音を繰り返して意味を強調する日本語表現
-
感情・音・情景を一度に伝えられるのが魅力
-
万葉集など古典文学にも登場する、日本語文化の象徴的な言葉づかい
気持ちを伝える「感情系の重ね言葉」一覧

人の“心の動き”を表すとき、日本語では重ね言葉がよく使われます。
「ドキドキ」「ワクワク」「イライラ」「ウキウキ」など、
どれも感情のリズムや高まりを音の響きで直接伝える表現です。
たとえば、
-
「ドキドキ」…緊張やときめきで心臓が高鳴る様子
-
「ワクワク」…期待で胸が弾む気持ち
-
「イライラ」…思い通りにならず気持ちが乱れる
-
「ホッと」…緊張や不安が解けて安心する瞬間
-
「ニコニコ」…穏やかに笑顔が続く状態
-
「ウキウキ」…軽やかで楽しい気分が続く
これらの言葉は、単に感情を説明するだけでなく、心のテンポや強さを音で表現しているのが特徴です。
たとえば「ドキドキ」は一瞬の高鳴りではなく、“しばらく続く鼓動”を感じさせます。
つまり、重ね言葉によって「感情の持続」や「余韻」まで伝わるのです。
使う場面で変わるニュアンス
-
「ドキドキ」:恋のときめき/試験前の緊張/サプライズの瞬間など
-
「ワクワク」:旅行前/プレゼントを開ける前など、未来への期待感
-
「ウキウキ」:気分が明るく弾むとき
-
「ホッと」:緊張がほぐれた安堵感を表す
このように、一語でその人の心の中まで伝わるのが重ね言葉の魅力です。
絵文字のように、話し手の“気持ちのトーン”を言葉だけで表現できるため、SNSや会話でもよく使われます。
豆知識:「ドキドキ」と「キュンキュン」はどう違う?
似た意味に感じる「ドキドキ」と「キュンキュン」。
どちらも“ときめき”を表す言葉ですが、実はニュアンスが少し違います。
-
ドキドキ:心臓の鼓動そのものを表す言葉。
→ 緊張・驚き・恐れなど、ポジティブにもネガティブにも使える。
(例)「告白の瞬間、心がドキドキした」 -
キュンキュン:胸が“締めつけられるように”ときめく感覚。
→ 恋愛・感動など、より甘く切ない感情に限定して使われることが多い。
(例)「優しくされた瞬間、胸がキュンキュンした」
つまり、「ドキドキ」は身体的な反応、「キュンキュン」は感情の揺れに焦点があるんです。
🌷まとめポイント
-
「ドキドキ」「ワクワク」などの重ね言葉は、感情の高まりを音で表す
-
繰り返すことで“感情の強さ・持続”を感じさせる
-
「ドキドキ」=鼓動、「キュンキュン」=胸の痛みを伴うときめき
動作を伝える「身体的な重ね言葉」一覧

「ヨチヨチ」「テクテク」「ゴロゴロ」「バタバタ」「モジモジ」など、
人や動物の“動き”や“仕草”を描くときにも、重ね言葉は大活躍します。
これらは、見る人の頭の中に自然と動きが浮かぶのが特徴。
たとえば――
-
「ヨチヨチ」:赤ちゃんがまだ不安定に歩く様子
-
「テクテク」:小さな歩幅で一歩ずつ進む穏やかな歩き方
-
「ゴロゴロ」:転がる動作や、のんびりくつろぐ様子
-
「バタバタ」:慌ただしく動く様子、走り回る音
-
「モジモジ」:恥ずかしそうに体をくねらせるしぐさ
どの言葉も、“音”を聞くだけで情景や感情まで浮かぶのが魅力です。
つまり、重ね言葉は単なる動作描写にとどまらず、
キャラクターの心の状態や空気感まで伝える表現なんです。
「動き+感情」を一緒に描く日本語の魔法
日本語の重ね言葉は、動作の描写に感情のニュアンスを含ませることができます。
たとえば、
「ヨチヨチ」は“がんばる姿の愛おしさ”、
「モジモジ」は“恥ずかしさ”や“かわいらしさ”を添えます。
このように、音のやさしさと繰り返しのリズムが、
動作のリアルさに“親しみ”や“温度”を与えてくれるのです。
絵本やアニメ、日常会話などでよく使われるのも、
「聞いているだけで情景が伝わる」からこそ。
赤ちゃん言葉やペットのしぐさの描写に使われることも多く、
人の心をほっと和ませる力を持っています。
ポイント:擬音語・擬態語として、会話や物語で情景をふくらませる
「テクテク」「バタバタ」「ゴロゴロ」などは、
音の響きで“動作”を再現する擬音語や擬態語の一種です。
これらを使うことで――
-
会話が自然でやわらかくなる
-
文章にリズムや臨場感が生まれる
-
映像的なイメージを簡単に伝えられる
たとえば、
「猫がゴロゴロしている」
と書くだけで、“のんびりくつろぐ情景”がすぐに浮かびます。
重ね言葉は、話し手と聞き手の間にイメージを共有するための日本語的リズム。
会話や物語に取り入れることで、
セリフが生き生きとし、描写に奥行きが生まれるのです。
🌷まとめポイント
-
「ヨチヨチ」「テクテク」などは“動き+感情”を伝える重ね言葉
-
擬音語・擬態語として、臨場感や可愛らしさを演出
-
会話・絵本・物語に使うと、情景や雰囲気がぐっと豊かになる
重ね言葉が持つ「やわらかさ」と「親しみ」

「ふわふわ」「ぽかぽか」「キラキラ」――
これらの重ね言葉を口にすると、どこかやさしい気持ちになりませんか?
重ね言葉には、音の響きそのものに“ぬくもり”や“安心感”を生む力があります。
たとえば「ふわふわ」なら、柔らかい布や雲を思い浮かべるような“軽やかさ”。
「ぽかぽか」なら、春の日差しや温もりのある人との時間を連想させます。
このように、音のリズムと響きだけで感触・温度・感情を伝えられるのが、
日本語の重ね言葉の大きな魅力です。
やさしい響きが「距離を縮める」言葉に
重ね言葉は、使うだけで相手との心理的な距離をやわらげる効果があります。
たとえば、
-
「お茶でもポカポカしよう」
-
「そのぬいぐるみ、ふわふわだね」
といった言葉は、どちらも柔らかく、温かい印象を与えます。
広告コピーや商品名にもよく使われるのは、
“やさしさ”や“親しみ”を自然に伝えられるからです。
たとえば「ふわふわパンケーキ」「ぽかぽか湯たんぽ」「キラキラ女子」など、
音の響きがそのままイメージ訴求力になっています。
子ども言葉・恋愛表現・癒し系にも人気
重ね言葉は、子ども向けの絵本や会話表現でも定番です。
赤ちゃん言葉のようなやわらかくリズミカルな響きが、
自然と温かさや親しみを感じさせます。
また恋愛シーンでは、
「ドキドキ」「キュンキュン」「ホッとする」など、
心の温度を伝える“癒し系ワード”として使われます。
このように、重ね言葉は年齢や性別を問わず、
人の心に“やさしく触れる”コミュニケーションツールなのです。
例文で感じる“響きのぬくもり”
「今日は心がぽかぽかするね」
「この服、ふわふわで気持ちいい!」
どちらの文も、音の響きがそのまま感情のトーンになっています。
“ぽかぽか”には穏やかな幸福感、“ふわふわ”には柔らかな触感と安心感。
単なる形容ではなく、「気持ちを共有する言葉」として働いているのです。
🌷まとめポイント
-
重ね言葉は「音の響き」で優しさ・ぬくもりを伝える表現
-
会話・広告・恋愛などで“親しみ”や“癒し”を生む
-
「ふわふわ」「ぽかぽか」などは感情と情景を同時に伝える
英語にない?「日本語らしさ」としての重ね言葉
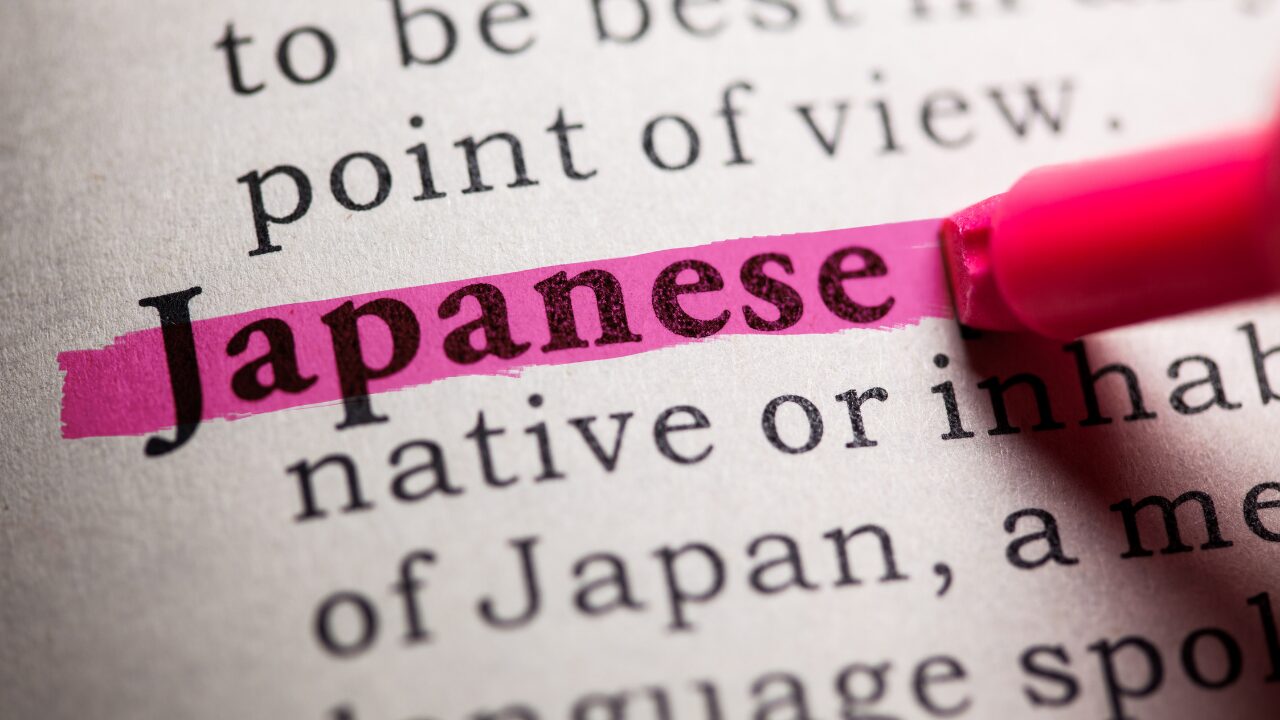
「ドキドキ」「ワクワク」「キラキラ」などの“重ね言葉”は、
日本語の中でもとくに音と感情が一体化した表現です。
一方で、英語には同じような「音の繰り返し」で感情や情景を伝える表現はほとんどありません。
英語では “My heart is pounding.”(心臓がドキドキしている) のように、
動詞+名詞で意味を説明するのが一般的。
それに比べて日本語の重ね言葉は、説明を超えて“感覚そのもの”を響きで伝えるのです。
たとえば「ふわふわ」は“soft”や“fluffy”で訳されますが、
“音の軽やかさ”や“触れたときの安心感”までは再現できません。
つまり、重ね言葉は単なる擬態語ではなく、
「感情のリズム」を持つ日本語の美しい特徴といえます。
音・感情・リズムが一体化する日本語の魅力
日本語の重ね言葉は、音・感情・リズムが三位一体になっているのが魅力です。
発音したときの響きが、そのまま感情の高まりややさしさを表します。
たとえば――
-
「ドキドキ」:高鳴る鼓動(緊張・ときめき)
-
「ワクワク」:弾むリズム(期待・楽しみ)
-
「ホッと」:息を抜く音(安心・安堵)
このように、発音の“リズム”と“意味”が一致している言語は、世界でも珍しい存在。
だからこそ、重ね言葉は**「日本語らしさ」を象徴する表現形式**として、
日本語学習者にも非常に人気があります。
日本語学習者が魅了される理由
海外の学習者からは、「日本語のオノマトペ(擬音・擬態語)が美しい」との声が多く聞かれます。
「ドキドキ」「ニコニコ」「ザワザワ」などの言葉は、
一度聞くだけで音から情景が浮かぶため、直感的に理解できるのが魅力です。
また、日本語の重ね言葉は感情表現が豊かで、
“直接的に言わなくても気持ちが伝わる”という、
日本文化特有の“やわらかな伝え方”を体現しています。
コラム:翻訳できない日本語表現 ― “ドキドキ”を英語で言うと?
「ドキドキ」は英語に直訳できない日本語表現の代表格です。
英語であえて言い換えるなら、状況によって次のように分かれます。
| 状況 | 英語表現 | ニュアンス |
|---|---|---|
| 緊張・不安 | My heart is pounding. / I’m nervous. | 物理的な鼓動や緊張を説明 |
| 恋のときめき | My heart skipped a beat. / I feel butterflies. | 感情的な高揚を詩的に表現 |
| 驚き・恐怖 | My heart was racing. | 急な動揺や恐れを強調 |
どの表現も意味は伝わりますが、「ドキドキ」という音のリズムと温度感までは表せません。
この“翻訳できなさ”こそが、重ね言葉の持つ日本語の繊細な感性を象徴しているのです。
🌷まとめポイント
-
英語には少ない“音の繰り返し”による情緒表現が日本語の魅力
-
重ね言葉は音・感情・リズムが一体化した文化的表現
-
「ドキドキ」「ワクワク」などは翻訳しづらい、“日本語らしさ”の象徴
まとめ|重ね言葉で、心に残る表現を

言葉のくり返しが、感情のくっきりした輪郭になる
「ふわふわ」「ドキドキ」「キラキラ」——日本語の重ね言葉は、単なる言葉の繰り返しではありません。
音のリズムと響きによって、言葉に“感情の温度”や“心の動き”を宿らせる表現です。
たとえば「ワクワク」には“未来への期待”が、「ホッと」には“安心”が込められています。
言葉の響きがやわらかく、相手の心にスッと届く——そんな“心地よい伝わり方”ができるのが、重ね言葉の魅力です。
SNSの投稿や日常会話のひと言にも取り入れるだけで、ぐっと印象が優しくなり、感情が伝わりやすくなります。
小説や詩、キャッチコピーなど、表現の幅を広げたいときにもおすすめです。
🟣 締めの一文案:
「言葉を重ねる」ことは、「気持ちを重ねる」こと。
あなたの中の“ドキドキ”を、言葉で表してみませんか?


